スポーツ界の覇者が語る仕事哲学に学ぶ
プロフェッショナルの条件 |
| 常に最高のパフォーマンスが求められるスポーツ界のプロフェッショナルたち。自己研さんに励み、勝利にこだわり続ける彼らのストイックで柔軟な独自の“仕事哲学”に迫る。《2008年10月号より抜粋》 取材・文/槙野仁子、市谷 美香子(編集部)、撮影/池田真理 |

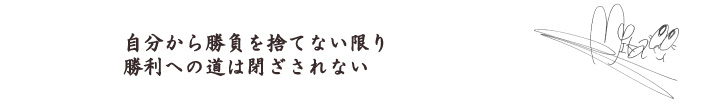
「レース中、カーブの場面で車体と服が摩擦を起こして、やけどするんです(笑)」。両肩の痛々しい傷跡とは対照的な笑顔で話すのは、レーシングドライバーの神子島みか選手。小学2年生からカーレースの世界に興味を抱き、17歳でA級ライセンスを取得。国内外問わず数々のレースに参戦し、活躍を見せる22歳だ。しかし、骨身を削る世界に常に身を置きながらも、彼女が醸し出す雰囲気は独特だ。手入れの行き届いた巻髪に、愛らしく描かれたアイライナー。ファッションやお洒落に敏感な年ごろの顔も持ち合わせる。どこにいても、自分らしさ≠失わないスタイルの持ち主に、プロフェッショナルの条件を聞いてみた。
スポーツにもさまざまなジャンルがありますが、なぜレーシングカーを選択し、生きていく上での軸と決断したのですか?
「レーシングカート(18歳以降はレーシングカー)との出会いは、小学生の時。元レーサーだった父の影響で始めました。小学校4年生の時には、本格的なプロのドライバーになりたいと考え、専門的なチームに入って真剣に取り組むようになったんです。でも、15歳の時に迷いが出てきました。レーシングカート以外に、もっと自分に向いていることがあるんじゃないかと思って。そのころは、レースに全然集中できませんでしたね。この世界は常に危険と背中合わせ、中途半端な気持ちでやってはいけない。だから、思い切って車の世界から離れました。これまでできなかったことをいろいろとやってみたんですが、どれも違うと思った。離れてみて、改めて『レースが一番面白い』と実感したんです。というのも、私は自分が納得できないと次に進めないタイプ(笑)。レースって、誰かが採点して勝敗が決まるものじゃない。一番でチェッカーを受ける人が、一番強い。勝ち負けがはっきりしているから、心の底から納得して次に向かって走れる。『もう一度、やってみよう』と17歳で復帰することにしたんです。復帰後、初めてのシーズンで2回優勝し、シリーズチャンピオンになったことも自信につながり、この道で生きて行く、と決めたんです」
ビジネスの世界では、組織に属すると、その組織の色に染まらざるを得ない場面に遭遇することがあります。しかし、神子島選手は過酷な世界で戦う雰囲気を感じさせない、自分の色を持って競技に取り組まれています。そのスタイルを貫くに当たっての苦労や葛藤などはありましたか?
「周りからは、『話題性を狙っているのか』とか『いつまでそんな格好をしているんだ』と言われることもありますよ(笑)。でも苦労や葛藤などは、感じたりしません。自分らしさを大切にすることは個性だと思うから。逆に自分のスタイルを持ち続けることがモチベーションになっています」
自分の流儀を持って、好きなことを追求し続けている神子島選手ですが、そんな神子島選手が思うプロフェッショナルの条件とは?
「どんなときもあきらめないでやり切ることだと思っています。過去の経験で言えば、今の監督の指導を受けることになったのも、勝つことをあきらめなかったから。あるレースに臨んだ時、予選が2回あって、1回目はトップで通過したんですが、2回目でスピンをしてしまって。決勝は30番手くらいからのスタートで臨むことになったんです。『もう勝てないかもしれない』と弱気な気持ちがもたげてきたんですが、『最後まで何があるか分からない、やり切ろう』と気持ちを立て直したんです。自分の中で切り替えができたことで、10周レースで1周に付き2台を抜くペースで走り抜け、9位まで追い上げることができたんです。その様子を今の監督が見てくれていて、『一台一台抜いていく姿にハングリーさを感じた』と言って、指導してもらえることになったんです。投げ出して終わりにすることは簡単だけど、あきらめずにやれば必ず自分が納得できる発見がある。その姿勢が大事だと思います」
夏場ともなれば、車内温度は60度を超え、生傷が絶えないレーシングカーの世界。気持ちの持ち方一つで大事故を招く危険と紙一重の競技に生きる神子島選手だが、勝つ感覚は何物にも代え難いという。「人生でうれし泣きしたことは2回ですが、両方ともレースでした。その感覚をもう一度経験したいから、やり続けていきたいですね。いつの日か、フォーミュラニッポンに出たい。それが夢なんです」と話すその目は力強く、愛らしさと勇ましで輝いていた。
スポーツにもさまざまなジャンルがありますが、なぜレーシングカーを選択し、生きていく上での軸と決断したのですか?
「レーシングカート(18歳以降はレーシングカー)との出会いは、小学生の時。元レーサーだった父の影響で始めました。小学校4年生の時には、本格的なプロのドライバーになりたいと考え、専門的なチームに入って真剣に取り組むようになったんです。でも、15歳の時に迷いが出てきました。レーシングカート以外に、もっと自分に向いていることがあるんじゃないかと思って。そのころは、レースに全然集中できませんでしたね。この世界は常に危険と背中合わせ、中途半端な気持ちでやってはいけない。だから、思い切って車の世界から離れました。これまでできなかったことをいろいろとやってみたんですが、どれも違うと思った。離れてみて、改めて『レースが一番面白い』と実感したんです。というのも、私は自分が納得できないと次に進めないタイプ(笑)。レースって、誰かが採点して勝敗が決まるものじゃない。一番でチェッカーを受ける人が、一番強い。勝ち負けがはっきりしているから、心の底から納得して次に向かって走れる。『もう一度、やってみよう』と17歳で復帰することにしたんです。復帰後、初めてのシーズンで2回優勝し、シリーズチャンピオンになったことも自信につながり、この道で生きて行く、と決めたんです」
ビジネスの世界では、組織に属すると、その組織の色に染まらざるを得ない場面に遭遇することがあります。しかし、神子島選手は過酷な世界で戦う雰囲気を感じさせない、自分の色を持って競技に取り組まれています。そのスタイルを貫くに当たっての苦労や葛藤などはありましたか?
「周りからは、『話題性を狙っているのか』とか『いつまでそんな格好をしているんだ』と言われることもありますよ(笑)。でも苦労や葛藤などは、感じたりしません。自分らしさを大切にすることは個性だと思うから。逆に自分のスタイルを持ち続けることがモチベーションになっています」
自分の流儀を持って、好きなことを追求し続けている神子島選手ですが、そんな神子島選手が思うプロフェッショナルの条件とは?
「どんなときもあきらめないでやり切ることだと思っています。過去の経験で言えば、今の監督の指導を受けることになったのも、勝つことをあきらめなかったから。あるレースに臨んだ時、予選が2回あって、1回目はトップで通過したんですが、2回目でスピンをしてしまって。決勝は30番手くらいからのスタートで臨むことになったんです。『もう勝てないかもしれない』と弱気な気持ちがもたげてきたんですが、『最後まで何があるか分からない、やり切ろう』と気持ちを立て直したんです。自分の中で切り替えができたことで、10周レースで1周に付き2台を抜くペースで走り抜け、9位まで追い上げることができたんです。その様子を今の監督が見てくれていて、『一台一台抜いていく姿にハングリーさを感じた』と言って、指導してもらえることになったんです。投げ出して終わりにすることは簡単だけど、あきらめずにやれば必ず自分が納得できる発見がある。その姿勢が大事だと思います」
夏場ともなれば、車内温度は60度を超え、生傷が絶えないレーシングカーの世界。気持ちの持ち方一つで大事故を招く危険と紙一重の競技に生きる神子島選手だが、勝つ感覚は何物にも代え難いという。「人生でうれし泣きしたことは2回ですが、両方ともレースでした。その感覚をもう一度経験したいから、やり続けていきたいですね。いつの日か、フォーミュラニッポンに出たい。それが夢なんです」と話すその目は力強く、愛らしさと勇ましで輝いていた。
