「まくら投げ大会で地方創生」に人生をかける20代の挑戦
今回話を伺ったのは、「全日本まくら投げ大会」を運営するtoiz(トイズ)の大塚眞氏。静岡県伊東市の町おこしプロジェクトとして始まった「まくら投げ大会」をスポーツ競技会として確立し、いまでは100チーム近くが応募する規模まで成長させました。地方創生にかける同氏のバイタリティはどこにあるのかを聞きました。

株式会社toiz 大塚眞(オオツカ・マコト)
2012年3月、株式会社toiz設立。ゲストハウス運営、全日本まくら投げ大会の企画・運営・PRを担当し、スポーツまくら投げインストラクターとしても活動。2015年に営業所を新潟県十日町市に開設。プロジェクトマネージャーとして着物ジャケット「織鶴」の企画、シェアアトリエ「アスト/asto」の運営、編集プロダクション「とかとこ」ディレクター、廃校利活用委員会代表等を務める。また、ローカルライフマガジン「TURNS」のファシリテーターとして自治体の移住定住促進・シティプロモーション分野で地方創生に携わる
東日本大震災のボランティア活動が人生の転機に
もともと“地方”に興味があり、大学では公共政策を専門に学んでいました。地方活性化を目的に活動するサークルにも所属しており、東京と地方を行ったり来たりしていました。
東日本大震災が起きたのはちょうどそのころです。当時、わたしは19歳でした。テレビや新聞の報道を見て、いても立ってもいられなくなり、サークルの仲間とともにボランティアバスツアーを企画しました。被災地のボランティアセンターと詳細を詰め、活動場所や宿泊場所を手配しました。集まったのは約40名の学生です。現地で津波による甚大な被害を目の当たりにし、これまで自分自身が持っていた価値観が大きく変わったことを覚えています。その光景は、一生忘れることはないでしょう。

その後も月1回のペースでボランティアバスツアーを実施し、朝から夕方まで、がれきの撤去や泥まみれになった家屋の清掃などを行いました。みんなで力を合わせることで徐々にきれいになり、被災者の方々からたくさんの感謝のことばをいただきました。
知識も経験もない大学生でも、力を合わせれば被災した町の景色を変えることができることを実感しました。それまでわたしの中にあった「地方を活性化させたい」という漠然とした思いが、「これを自分の生きる道にしよう」という強い意志に変わった瞬間でした。
それ以来、さらに本腰を入れて地方活性化について考えるようになりました。たどり着いた結論は、「単発で活動しても大きな成果は生み出せない。真の意味で地方を活性化させるには、事業化して活動を継続する必要がある」ということでした。そこで2012年3月、大学に通いながら仲間とともに起業しました。ちょうど20歳のときです。
まくら投げをスポーツ競技に
その後、活動地域の1つだった静岡県伊東市から、「若者を温泉街に呼び込むための企画づくりができないか」と相談を受けました。伊東市は、富士箱根伊豆国立公園の指定区域にあり、温暖な気候と豊かな自然、美しい景観に恵まれ、温泉保養地として全国に知られています。しかし、バブル崩壊後の長引く経済不況により、観光客数は1991年をピークに減少を続け、20数年もの間、低迷を続けていました。現地への人の流れを作るための新たなコンテンツが必要とされていたのです。
わたしたちは、「若者に関心を持ってもらえるものを企画しましょう」と提案し、伊東市および観光協会の方々とアイデアを出し合いました。メディアが興味を持つ内容で、なおかついままでにないインパクトのある企画を検討した結果、地元の高校生が提案した「まくら投げ」を新たにイベントとして開催するとともに、もともと伊東市で行われていた「タライ乗り競走」や「尻相撲大会」という奇祭をPRしていくことになりました。
まくら投げといえば、日本人ならほぼすべての人が知っている遊びです。ルールや規則はありません。わたしたちは、スポーツ競技と同じように、まくら投げにルールや規則を設けて勝敗を競い合うようにすれば、温泉街の町おこしのコンテンツにできるのではないかと考えました。
そうして2013年2月、伊東市で第1回全日本まくら投げ大会が開催されました。伊東市民だけでなく、首都圏からも参加チームを募り、1チーム8人の合計18チームが参加しました。
ただ、このときはまだ確立されたルールが存在しておらず、布団を盾がわりにしてガードしながらまくらを投げ合うという、いわゆる普通のまくら投げだったのですが、会場は大いに盛り上がりました。しかし、課題もたくさん見つかりました。ゲーム性を備えたルールを整備しなければ、単なるレクリエーションで終わってしまいます。また、大会を盛り上げるためには、プロモーションも必要になります。こうした課題を1つずつ洗い出して改善案を企画書にまとめて提案した結果、翌年2月に第2回大会を開催することになりました。
ルールがある、勝敗がある、だから楽しめる
まくらの数は10個でキャッチするのは禁止、2分1セットの3セットマッチ制など、A4用紙5枚にわたるルールが固まったのは、第3回大会になってからでした。ルールができたことで、各チームは戦略を練るようになり、練習する意義も生まれました。すると今度は、スポーツとしてまくら投げに熱中する若者が出てきたんです。そうした方々が練習会を企画し、そこで新たなコミュニティが生まれる。まくら投げが新たな人間関係を構築するためのコンテンツとなったのです。
同じ時期に、プロモーションの面でもターニングポイントを迎えました。新ルールの検証のために初めて都内で行われた練習会の様子が、消費・流通・マーケティングの専門紙「日経MJ」に取り上げられたのです。これがきっかけとなり、テレビの取材が次々と舞い込み、全日本まくら投げ大会の知名度が一気に上がりました。
第4回大会には東京キー局のほとんどが取材に訪れました。これまでの3回の開催でスポーツイベントとしての地盤がほぼできたので、第4回大会からは事業としての継続性に主眼を置き、“収益化”に注力するようになっていきました。現在は、スポーツまくら投げをコンテンツ化して一定の収益を上げられるようになり、公金依存の地方イベントから脱却しようとしています。
また、参加チームも年々増え、現在は100チーム近くが応募する規模まで成長しました。会場のキャパシティの関係で全チームを伊東市に招くことは難しいのですが、毎年2月にはまくら投げ大会に参加するために人口数万人の温泉街に600人以上が集まります。これが話題となって、旅行会社からまくら投げツアーの企画依頼の問い合わせが増えています。
最近は、海外からの問い合わせもありました。「まくら投げを日本文化の教育事業に取り入れたいので、大会を視察させてほしい」と、香港の教育機関から問い合わせがあったのです。
日本文化を象徴する畳と浴衣は不可欠
ここに至るまでには、膨大な議論がありました。まくら投げをスポーツ競技とすることに、どんな価値があるのだろうか。遊びだからこそ、まくら投げは楽しいのではないか。わざわざフィールドを畳にする必要があるのか。浴衣を着ないほうがスポーツとして成立するのではないかなどです。議論していくうちに、何が正解かわからなくなることもありました。
そんなときは、原点に立ち返ることが重要です。自分がまくら投げを町おこしのコンテンツにしたいと考えた理由は何だったのだろうかと。そのとき、“まくら投げは日本の文化である”ということに気づきました。畳も浴衣も日本を象徴する重要なアイテムです。海外の方にまくら投げに興味を持ってもらうためには、どちらも外せない要素であることが明確になりました。

はたから見たら、くだらないことに頭を使っていると思われるかもしれません。しかし、大会運営のために伊東市から拠出していただいた公金や、選手たちから集めた参加費で開催するイベントである以上、企画運営するわれわれは真剣に世界観を作り上げなければなりません。遊び心やゆるさを持ち合わせながら、事業として継続させていくための仕組みを、「伊東市の活性化」という本来の目的を置き去りにせずに作っていかなければならないのです。
地方経済の活性化のために人が流れる道筋を作る
なぜ楽しいのか、どうすれば楽しめるのかを徹底的に追求したことは、結果として正解だったと思います。レクリエーションのままのまくら投げ大会では、ここまで継続できなかったでしょう。
次の目標は、まくら投げ大会をいっしょに盛り上げてくれる地域を増やしていくことです。まずは、東京、千葉、大阪、福岡など、人口の多い都市で予選大会を開催し、伊東市に人がどんどん流れていく道筋を作っていきたいですね。
競技人口を増やすだけでなく、さらに地域経済を活性化することを考えていかなければなりません。やるべきことはたくさんあります。2019年2月の開催で第7回目となりますが、自分としてはまだスタートしたばかりという心境です。地方がこれからの時代を生きていくためには、継続的な事業が必要なのです。そのために、地方が秘めている価値をもっと多くの人に知ってもらえるようにすることが、自分の使命だと思っています。
※こちらの記事は『BRAND PRESS』より転載しています
RELATED POSTSあわせて読みたい

人事ジャーナリストが解説! 会社目線で見た「営業マンの年収」とは【営業の年収大解剖】

無職になった芦名佑介~高年収も地位も捨てて気付いた本当の“幸せ”

「全ての情熱を1社に注げ」大手コンサルからベンチャーに転職した男が語る、新規開拓営業の極意

若者がモノを買わない時代。“経済の流れ”はどこから生まれる? 【Makuake中山亮太郎ほか】
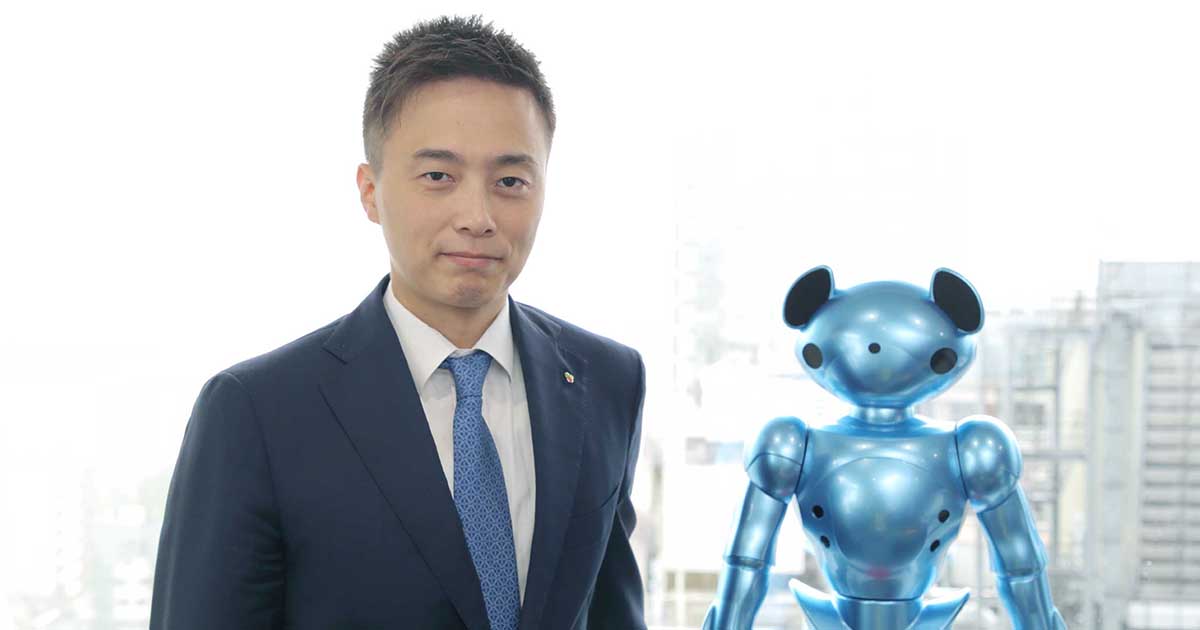
介護・保育業界の常識を変えた男の仕事哲学「歩く距離と出会いの数は比例する」
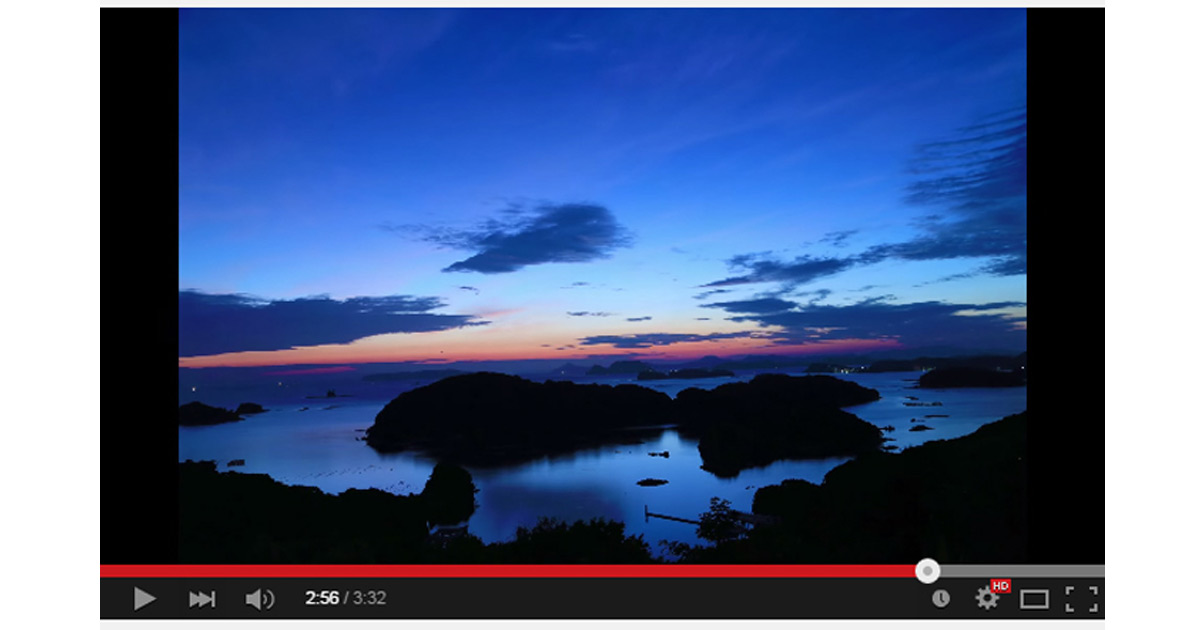





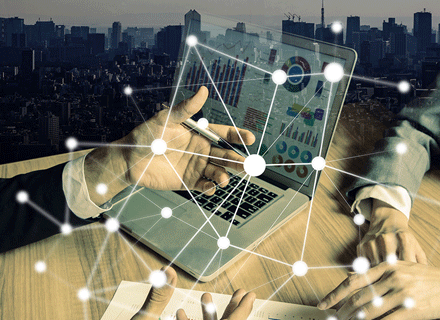
![市場規模拡大中!人材業界の営業求人特集 [東京都]](http://type.jp/st/feature/wp-content/uploads/2020/09/spid6258.png)


