孤独死現場に湧く大量の虫、周りの人間の醜さ…それでも「遺品整理人は辞めない」と語る28歳の信念
故人の遺品整理や、孤独死のあった現場などを片付ける特殊清掃に従事している小島美羽さん。20歳の頃に遺品整理人の仕事を知り、「やってみたい」と心から思ったという。
凄惨な現場を目にすることは、彼女にとっての日常。ゴミ屋敷の片付けで1000匹近いゴキブリに囲まれたこともあるそうだが、「辞めようと思ったことはない」と小島さんは微笑む。
なぜ小島さんは、現在の仕事を自ら選んだのか――。遺品整理人の知られざるやりがいと、小島さんの思いに迫った。

株式会社ToDo-Company:遺品整理クリーンサービス 遺品整理人
小島美羽さん(@E90Bn9fL1foVLn6)
1992年生まれ。高校卒業後、郵便局の配達員を3年経験。その後、テレビ番組のADや工場の検品・封入スタッフ、菓子の製造・販売スタッフなどのアルバイトをしながら遺品整理の仕事を目指す。2014年、遺品整理クリーンサービス(株式会社ToDo-Company)に入社。遺品整理やゴミ屋敷の清掃、孤独死の特殊清掃に従事する。16年より、孤独死の現場を再現したミニチュアを独学で制作。19年に自著『時が止まった部屋 遺品整理人がミニチュアで伝える孤独死のはなし』(原書房)も刊行
故人の親族や知人などから依頼を受け、2~5名のチームで遺品の整理・仕分け、部屋の片付け、搬出、明け渡し清掃までが主な作業。時には、遺族に受け渡す遺品以外の不要なものをリサイクル・寄付、供養する手配も行う。
孤独死の特殊清掃では、遺体の残存体液の清掃・消毒作業などを行い、部屋を明け渡せるようクリーニング。毎日1件程度の依頼に対応するが、室内の状態によって作業時間は変化する。ゴミ屋敷の遺品整理と清掃を行うケースもあり、虫が発生することが予想される現場では防護服を着用するそう。
朝9時半にスタートし、食事を取らずに作業を進め、14時~15時頃に終了するケースが多い。
月給制で、実働8時間、休日は週に1~2日程度。収入については、「一人暮らしをしながら自分の趣味にもお金が使えて、貯蓄もできる程度」だそう。
「郵便局で働いていた頃よりはいいですね。私はキャラクターグッズを集めるのが趣味なので、ぬいぐるみやいろんなグッズにお金を使うことが多いです」
父の死、業界の腐敗…「私が遺品整理の世界を変えてみせる」
小島さんが遺品整理の仕事について初めて知ったのは、高校卒業後、郵便局で働き始めてからのことだった。
「当時、同僚から遺品整理の仕事について教えてもらい、興味を持って調べていたら、悪徳業者がごろごろいることを知りました。家族を亡くして悲しんでいる遺族に対して高額請求を突き付けたり、物を投げつけたり、怒鳴りつけたりするケースもあるそうで……。遺族の悲しみを踏みにじるような悪徳業者は『許せない』と感じました」

特殊清掃・遺品整理の現場イメージ(写真は小島さん作成のミニチュア作品)
「許せない」という強い思いが込み上げてきた背景には、高校生の頃に父親を亡くした時の経験がある。
「当時は両親が別居したばかりだったのですが、自宅の廊下で倒れている父を母が偶然発見したんですよ。まだ息があって、すぐに救急車を呼びましたが、父は病院で息を引き取りました。危うく、孤独死になるところでした」
遺族の気持ちが分かる自分なら、何かできるんじゃないか――。「悪徳業者なんて、ぶっ潰してやりたい!」そんな正義感に駆られ、遺品整理の世界に飛び込んだ。
「『この業界を変えてやる』と意気込んでいましたが、実際にはそう簡単に務まる仕事じゃないことも分かっていました。安易に挑戦して、『やっぱりイメージと違ったから』と辞めることになれば、それこそ遺族や故人に対して失礼になってしまうのではないか。そういう懸念もありました」

そこで小島さんは郵便局を辞め、自分を試す期間を2年間設けた。「興味がある他の仕事に就き、遺品整理の仕事に就いても途中で目移りしないようにあらゆる気になる仕事をやりました」と小島さんは話す。ショッキングな現場を見ても動じない心を養うために、遺体の画像を検索して見るようにしたという。
「もともと残酷な描写は苦手なタイプなんですよ……。なので、この鍛錬期間は正直きつかったですね。また、遺品整理の現場は『臭いがすごい』という話も聞いていたので、臭いのイメージトレーニングもしていました」
家族も彼氏も大反対。それでも「やりたい」
約2年、自己鍛錬の期間を過ごした後、小島さんは「遺品整理クリーンサービス」に入社した。
同社の求人広告には、遺族の気持ちに寄り添うことを大事にする経営の姿勢や、死と向き合う仕事の過酷さ、そこで求められる誠実さが丁寧に書かれており、それが入社の決め手となった。
「他の遺品整理会社の求人もたくさん見ましたが、どこも『誰にでもできる簡単なお仕事です』って書いてあったんですよ。でも『それって本当?』って。今の会社は、遺品整理に対する私の考え方と、ぴったり合っていたので『ここしかない』と思いました」
当時、小島さんは22歳。転職を家族に告げると、母親からの猛反対にあった。
「『どうしてわざわざそんな大変な仕事に就くの?』と母には言われました。母なりに心配してくれていたんですが、私はどうしてもやりたかった。
でも、身内に認めてもらえないままでは全力を出せないので、この仕事の大切さや必要性を話し、ひたすら説得したんです。その結果、『そんなにやりたいなら頑張りなさい』と諦めてくれました(笑)」
また、当時付き合っていた彼氏には、「そんな仕事をしたら呪われるよ」と諭された。「さすがに頭にきた」と小島さんは本音をこぼす。
「『もし君が孤独死して、その部屋を片付けてくれる人がいたら、その人を呪うの? そんなわけないでしょ』と詰め寄ったら、彼も納得してくれました(笑)。
人が亡くなった現場に対し、心霊的なものを想像して恐怖心を抱く人もいますが、孤独死しても同じ人間。呪うだなんて、本当に失礼な話だと思いますね」

あっさり職場に馴染むも、ぶつかった壁は“人間のずるい心”
遺品整理人として働き始めた小島さんは、社長から指導を受けながら、現場経験を重ねていった。
「初めての特殊清掃の現場で、『あれ? 自分が想像していたよりも、全然臭くない!?』と拍子抜けしました。人によっては吐いてしまうほど強烈な臭いの時もありましたが、想像の方が勝っていたので、まさに2年間の自己鍛錬のおかげですね(笑)」
遺体があった家には、皮膚など人体の一部が残っていることもある。初めてそれを見た時も、鍛錬期間のおかげか「あ、これがそうか」と自然と受け止められたという。
「ただ、クロゴキブリだけは今も慣れないです。ゴミ屋敷の清掃に入って1000匹近いゴキブリに囲まれた時は、精神崩壊するかと思いました……!」
仕事のスキルは順調に習得。想像以上に“あっさり”と、職場に馴染むこともできた。
しかし、小島さんの正義感を揺さぶる事件が次々に起こっていく。人の死があるところには、人間の“ずるい心”が渦巻いていたのだ。
「遺品整理の見積もりをする際、依頼人の方に故人との関係や死因などをヒアリングするのですが、『正直に言うと作業をしてもらえないのではないか?』『高額請求をされてしまうのではないか?』という不安から嘘をつく方もいます。
例えば、亡くなった方が感染症などを患っていた場合は、清掃に入る側も通常とは違う装備や準備が必要になります。しかし、以前も故人の死因が結核だったことを伏せていらした方がいて、後から分かった時は不安が込み上げてくると同時に、悲しい気持ちになりました……」

また、不動産関連で人間のずるさを目にすることも多いという。清掃をすれば十分にきれいになる部屋を「フルリフォームが必要だ」として遺族に高額請求をする大家や不動産会社がある。
遺族には「迷惑を掛けた」という思いがあるため、法外な金額を請求されてもそのまま支払ってしまうケースも多いそうだ。
「以前、22歳くらいの男性がゴミ屋敷で亡くなり、その部屋を片付ける案件がありました。依頼人は彼のお父さん。悲しみのあまり部屋に入ることもできず、マンションの入り口で泣きながら待機されていました。
私たちが大家さんと話をしていると、けばけばしい服を着た男女がズカズカと近付いてきて、『部屋は全部リフォームしてもらう』と詰め寄ってきました。彼らは不動産会社の人間だったようで、遺族を気遣う様子など一切ありませんでした」
腐敗した業界の「当たり前」を変えたい、そう思っていたはずなのに、手も足も出せなかった。帰社する車の中では、「涙が止まらなかった」と小島さんはうつむく。
しかし、次の日に依頼人から「昨日は本当に助かった」という一本の電話が入った。感謝の言葉をもらったのに、込み上げてくるのは悔しさだけ。「自分には何もできなかったのに……。もっと何かできたはずなのに……」そんな気持ちに後押しされて、法律の勉強にも取り組んだ。
「これでやっと、前に進める」依頼人に安心を与えたい
小島さんが遺品整理の仕事をする上で、何より大事にしてきたのが、遺族の気持ちに寄り添うことだ。故人がどんな人だったのか、丁寧にヒアリングすることを心掛けている。
「依頼人の方とは、故人の方について詳しくお話を伺うことで、信頼関係を築いていきます。遺品整理の最中には、『山登りがお好きな方だったんですね』『海外によく行かれていたんですね』など、お写真を見ながら故人についてお話しすることも。
依頼人の方が『そうそう、この時はね』と楽しそうに思い出を語る姿を見ると、愛されていたことや、仲が良かったことが伝わってきます」
小島さんは、「この仕事のやりがいは、依頼人の方が“ホッとしてくれる瞬間”にある」と続ける。

「整理が終わってきれいに片付いた部屋でお線香をあげると、それまで暗かった依頼人の方の顔が、ほっとしたような、穏やかな顔に変わります。『これでやっと前に進める』そうおっしゃっているようでお役に立てたことを実感できますし、残された人たちが笑顔になれたら故人も安心して旅立てると思うんですよね」
小島さんの元には、依頼人からお礼の手紙やメッセージが届くことも多い。「何よりの瞬間です」と小島さんはうれしそうに微笑む。
肉体的・精神的にハードでも「仕事を辞めたい」と思ったことはない
小島さんは入社3年目の頃に、孤独死の現場のミニチュア制作を開始。作品をまとめた自著も出版した。

小島さんのミニチュア作品
「人がつながりの中で生きていくことの大切さや、暮らしの中に潜む生命を脅かすリスクなどを発信することを目的に、このミニチュア制作を始めました。
現在は、『二世帯住宅の孤独死』をテーマにした作品を製作中です。『孤独死は他人事ではない』という事実を、少しでも広められればと思っています」
小島さんに今後の目標について聞くと、「初心を忘れないこと」という謙虚な答えが返ってきた。
「入社した時から現在まで、自分の仕事に対する思いは全く変わりません。遺族を思いやる気持ちを大事にし、絶対悲しませないスタンスで遺品整理の仕事を続けていきたいと思います」
また、遺品整理は肉体的にも精神的にもハードな仕事だが、「辞めたいと思ったことは一度もない。これからもずっと続けたい」と小島さんは言い切る。
「やっぱり、自分で『これだ』と決めた仕事ですからね。心から『やりたい』と思ったことだからこそ、人からどう思われようと関係ない。自分自身がやりがいを実感できる仕事なら、それが一番です」
取材・文/上野真理子 撮影・編集/大室倫子・川松敬規(編集部)
RELATED POSTSあわせて読みたい

【おくりびと】20代で納棺師の世界へ。人の死を10年以上見続けた男が語った圧倒的な“誇り”

M-1芸人からゴミ清掃員に。マシンガンズ滝沢に学ぶ「どんな仕事でも楽しんじゃう」ための心掛け

パチスロ寺井一択の破天荒な人生論「モテたい、勝ちたい、一番だって言われたい!」

「批判も周囲の目も気にしない。将来の不安もない」“おごられる”が仕事のプロ奢ラレヤーがストレスフリーでいられる理由

“レンタルなんもしない人”の人生が、「中学生以来ずっとつらい」から「毎日がエンタメ」になるまで






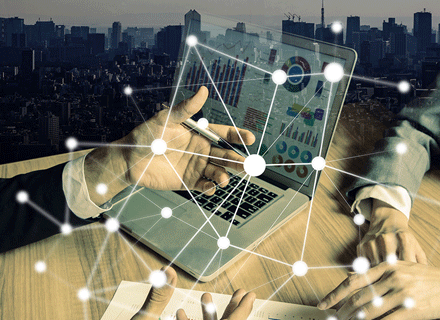
![市場規模拡大中!人材業界の営業求人特集 [東京都]](http://type.jp/st/feature/wp-content/uploads/2020/09/spid6258.png)


