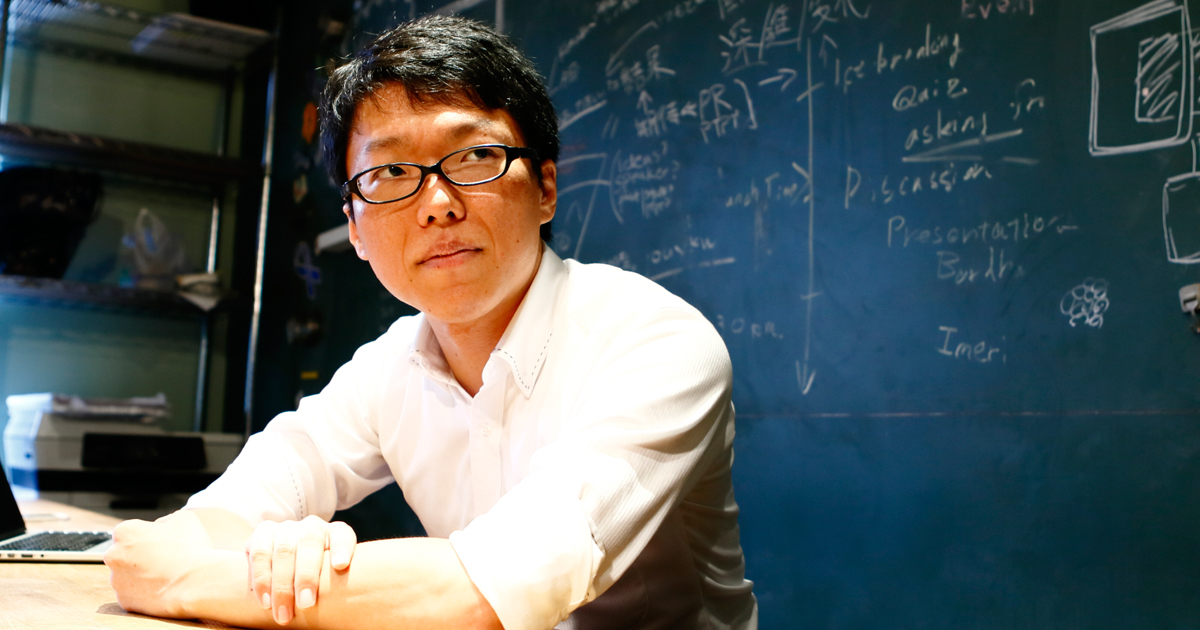2020年2月13日(木)に開催された、女性営業職の働き方を考えるイベント「新世代エイジョカレッジ・サミット2019」。本イベントで示された2014年のデータによると、「営業職として新卒入社した女性の9割が、10年以内に現場を離れている」という。
ここで問題なのは、「営業を続けたいのに続けられない」という人も含まれている点だ。働き方改革が進んだ今でも、こうした人が一定数いるという。
営業職の女性はなぜ、現場にい続けられないのか? 「営業職としてずっと働きたい」と考えている今の20代が、長く働いていくためには何が必要なのか?
その答えを探るべく、営業女子のための応援コミュニティ『営業部女子課』主宰の太田彩子さんらが登壇したトークセッションを紹介しよう。

中央大学大学院戦略経営研究科教授 佐藤博樹さん
雇用職業総合研究所 (現、労働政策研究・研修機構)研究員、法政大学経営学部教授、東京大学社会科学研究所教授を経て14年10月より現職、15年東京大学名誉教授。主な著書は『男性の育児休業』(共著、中公新書)、『職場のワーク・ライフ・バランス』(共著、日経文庫)、『結婚の壁』(共編著、勁草書房)など
相模女子大学客員教授 白河桃子さん(@shirakawatouko)
少子化ジャーナリスト、 作家、 相模女子大学客員教授、内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員、内閣官房「一億総活躍国民会議」民間議員、内閣府「新たな少子化社会対策大綱策定のための検討会」委員 などを務める。女性のライフキャリア、少子化問題、働き方改革、女性活躍、ダイバーシティーなどをテーマに、活動は多岐に渡る
一般社団法人 営業部女子課の会 代表理事 太田彩子さん(@belleffect)
早稲田大学卒業後、リクルート・ホットペッパーの企画営業として活躍後、独立しダイバーシティープロジェクトや女性活躍支援に携わる。これまで5万人以上の女性営業を支援してきた。2009年より営業女子のための応援コミュニティ『営業部女子課』を全国で展開し、営業女子の活躍を目的とした勉強会やイベントを開催している
佐藤:「営業現場のことが分かる女性管理職」がいないこと、そして「管理職になりたい」という若手女性もいないことが原因だと思います。営業職の女性管理職が増えたら、社内の営業スタイルが変わったり、支援体制が整ったりするので、現場でも「営業を続けたい」という女性がもっと増えてくるはずですから。
白河:働き方改革を、管理職に丸投げしてしまう企業が多いんですよ。だからただでさえ忙しい管理職が、より多忙になっているのが現状です。
佐藤:「今のマネジャーの働き方を見ていたら、とてもじゃないけど管理職になりたいなんて思えない」というメンバーも多いでしょう。
太田:働き方改革で残業時間などが改善しつつある一方で、精神的な疲弊感やプレッシャーを感じる方も増えてきたようにも思います。
白河:女性が将来的に家庭を持ったら、男性の5倍も家事や育児の時間を持つことになるというデータも出ています。このように家庭内ではまだ男女不均衡なのに、会社においては「男女平等だから活躍できるよね?」と言われるのは酷な話ですよ。
大田:営業職の女性とキャリア面談をする際によく出てくるキーワードは、「マンネリ化」と「行き詰まり感」です。営業職は「今月頑張って予算を達成しました」といっても、また次の月は一から積み上げないといけない。「この繰り返しをいつまで続けるんだろう」という精神的な疲弊感を何とかしないと、なかなか営業を続けたいという女性は増えてこないと思います。

佐藤:管理職に関しては問題がもう一つあります。今の時代、営業は「お客さまに新しい価値を提案する」ことが特に求められている。だからこそ営業の仕方を効率化するなどして、スタイルを変えなければなりませんが、時代についていけない管理職も多いのです。
佐藤:特に若手営業パーソンの上司にあたる世代は、OJTで「足を使って営業しよう」と教わって、仕事を覚えてきた人も少なくない。理論的に課題を説明して、データを分析して提案する、というスキルを持ち合わせていないことも多いのです。
白河:上司は経営トップの言うことを翻訳して現場に伝える役割がありますが、その翻訳をうまくできない人も少なくありません。
佐藤:はい。例えその上司がこれまで「仕事ができる人」だと評価を受けてきても、今はどんどん仕事の仕方や考え方が変わってきていきますから。今20代の営業パーソンは、スキルを自分で磨いていくことが大切になると思います。
佐藤:会社としても、今いる管理職をどう変えるかというよりも、これからどのような管理職を登用するのかに目を向け始めているのではないでしょうか。多様な部下をマネジメントして、営業職の働き方を根本から変えるような、これまで正しいとされてきたやり方を捨てられる人を企業は管理職として登用する必要があるでしょう。
太田:これまで企業はレベルの高い個人の営業パーソンを求めていましたが、これからは「チームで営業力を高めていく」ことが重要になってくると思います。お互いが補完し合って「あなたたちから買いたい」と言われるチームづくりが求められるので、それができる管理職が必要ですね。

佐藤:女性の営業職の皆さんには、何か世の中で大きな変化が訪れたときに慌てないでほしいと言いたいですね。そのためには、知的好奇心を持って世の中にアンテナを張り、人より早くその兆候に気付くことが大切です。そしてもう一つ、大切なのが学習習慣です。常に何かを学んでおく習慣が、この先新しいことを学ぶ必要性が出てきたときに役立ちますから。
白河:私は現場の方へのメッセージというよりも、上司の皆さんに言いたいです。営業職の女性に「期待している」と声を掛けて、と。今世界的にも、日本企業のジェンダーギャップはとても問題視されています。取締役会を見ても似た年代の男性ばかりで女性はいないことも多い。そのような企業は「持続可能な企業ではない」と判断されるようになってきました。そういう意味でも、ジェンダーにはぜひ注目していただきたいです。
太田:皆さんには、自分自身を信じる力を高めてほしいと強く思っています。「管理職になれる自信がありません」「営業を続けられる自信がありません」という方が多いですが、それは実力ではなく心理的なハードルですよね。まず自分を信じることでそのハードルは乗り越えられるので、「私達はできる」と信じて社会を変革していってほしいです。
文/安藤記子 編集・撮影/大室倫子(編集部)