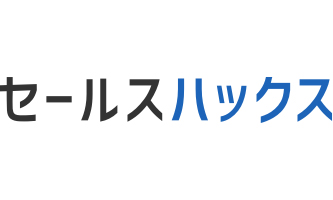From セールスハックス
※この記事は2017/10/26にセールスハックスに掲載された記事の転載です
営業マンにはプレゼンテーションは必須ですが、プレゼンテーションが得意という人は意外と少ないものです。
今回は次のプレゼンテーションからきっと役に立つ、営業マンのためのプレゼンテーションのコツを紹介します。
プレゼンテーションをすることが決まったら、資料の準備が必要です。
伝えたいことをすべて盛り込んだ資料を作ってしまいがちですが、まずは、お客様のご都合を考えて、プレゼンテーションにかけられる時間を決めましょう。
お約束が1時間であっても、プレゼンテーションに丸々1時間をかける必要はありません。
質問に答える時間なども想定して、プレゼンテーションは打ち合わせの1/2以内に納めるようにします。
プレゼンテーションの参加人数によって、話し方や伝え方も変わってきます。
何人、どのような立場の人が出席をするのか、事前に確認をしましょう。
見込み客が営業ステージのどの段階にあるのかを確認しましょう。
まだ購入を検討していない段階で、「弊社を選ぶ理由」というプレゼンテーションをされても、お客様は困ってしまいます。
既に商品紹介用のプレゼンテーションがある場合は、新たに資料を作成せずにそのままテンプレートを使ってしまいがちですが、必ず内容を見直し、見込み客の営業ステージにふさわしいかを吟味し、スライドの過不足を調整しましょう。
プレゼンテーションの後、見込み客に何をしてほしいか、つまり見込み客の次のアクションを念頭に、プレゼンテーションを組み立てましょう。
例えば、「競合よりも自社を選ぶのが最適であることを納得してもらう」、「意思決定者との商談につなげる」、「トライアルに申し込んでもらう」、「詳細な見積もり作成のための打ち合わせにつなげる」といった目的では、それぞれ盛り込む内容も異なってくるはずです。
見込み客が営業ステージのどの段階にあったとしても、見込み客がサービスや商品を利用している様子をイメージできるようにします。
見込み客の課題や利用シーンに合わせて、スライドの内容を変更しましょう。
利用の様子をイメージしていただくのに最適な方法が、具体例をいれることです。
同じような課題を持ったお客様の例、自社サービス導入後の成功事例などを適宜盛り込みましょう。
詳細についてすべて説明をする必要はありません。
見込み客に響く形で簡潔に紹介し、詳細は別資料にまとめます。
商品やサービスの効果や効能を、見込み客にとっての価値に翻訳をして、プレゼンテーションに盛り込みましょう。
例えば、自社商品の機能が競合商品より5%勝っていたとしても、見込み客にはピンと来ません。
その結果、お客様にとってどのような価値となるのか、利用にどのような違いが出るのかを伝えましょう。
プレゼンテーションを作り終わったら、本当に必要なスライドに絞ります。
資料が多い方が立派な資料と思いがちですが、簡潔にポイントを伝える、少ない枚数の方がよいプレゼンテーション資料といえます。
このスライドは本当に必要か、まだ減らせるスライドはないか、という目で資料をレビューしましょう。
価格について詳細を詰めるのが目的でない場合は、価格についての詳細は別資料に入れます。
まずは商品やサービスの価値を理解してもらってから、価格について議論をするようにしましょう。
思わぬ脱線や変更の場合に対応できるよう、短いバージョンも必ず用意をします。
特に経営層の意思決定者はせっかちでポイントだけを知りたがる人も少なくありません。
「ポイントは?」、「一言で言ったら?」などの質問に対応できるようにしましょう。
プレゼンテーションの練習をしたことがありますか?
資料作成には時間をかけても、プレゼンテーションの練習をしない人の方が多数派でしょう。
しかし、プレゼンテーションの練習をするかどうかが成功の明暗を分けるといっても過言ではありません。
最低でも2回は練習をしましょう。
営業活動においてトークスクリプトやコールスクリプトが効果的であるよう、プレゼンテーションにも台本(スクリプト)があると効果が全く違います。
プレゼンテーション資料同様、一度作れば応用ができるので、一度は台本を作成し、それをもとに練習をするのがお勧めです。
プレゼンテーションは「発表」であるという考え方は捨てましょう。
営業のプレゼンテーションの場合はお客様との会話、つまりコミュニケーションなのです。
自社製品やサービスのよさを一方的に伝えるのではなく、聞き手の反応も考えます。
発表側としては、質問はプレゼンテーション後にまとめて受け付ける方が楽に感じるかもしれません。
しかし、商談の手段である会話と考え、途中中断を恐れないでください。
不明点や質問がある場合は、いつでも質問や意見をいただけるよう、最初に宣言してしまいましょう。
質問がなくても、参加者の表情で気になることがあったら、見逃さず、こちらからフォローするようにします。
プレゼンテーションは質問をする機会でもあります。
例えば冒頭で、「今日確認したい、一番大切なポイントは何でしょうか?」と聞いてしまえば、強調すべきポイントがわかります。
万が一資料にそのポイントがない場合でも、急遽対応をすることができるでしょう。
要所要所で、聞き手の理解を確認し、最後には「ご質問や疑問にすべてお答えできたでしょうか?」と質問をすれば万全です。
チームから他にも参加者がいる場合は、ぜひ一部を話してもらいましょう。
プレゼンテーションにメリハリがつけられるだけでなく、チームの役割も伝えることができ、自社の価値を上げることができます。
ついつい行ってしまうのが、スライドに書いてあることをそのまま読んでしまうことですが、これは厳禁です。
スライドはあくまでも、プレゼンテーションの効果を高める、補助的なものです。
予防のためにも、スライドの文字は極力減らし、図や画像を多用した、視覚的効果の多いものにしましょう。
台本も効果的な予防策です。
緊張をすると誰でも話すスピードが速くなります。
話すスピードが早いと、内容も伝わりにくくなりますし、聞き手にも緊張が伝わってしまいます。
自分が話しやすい速度と聞き手にとってわかりやすいスピードは異なります。
練習の様子を録画し、自分で見直してみると、自分の話し方の癖も客観的に知ることができます。
プレゼンテーションでつい忘れてしまいがちなのが、次のステップを確認することです。
「ご検討ください」で終わらせず、必ず次のステップを確認しましょう。
プレゼンテーションは営業プロセスの通過点にすぎません。
成約につなげることが最も大切です。
プレゼンテーション後のフォローアップ・プログラムを組み、確実にフォローアップをするようにしましょう。
いかがでしたか?
準備からフォローアップまで、すべてがプレゼンテーションです。
ぜひこれらのコツを活用して、あなたの営業力をさらにアップさせてください。
※こちらの記事は『セールスハックス』より転載しております
>>元記事はこちら