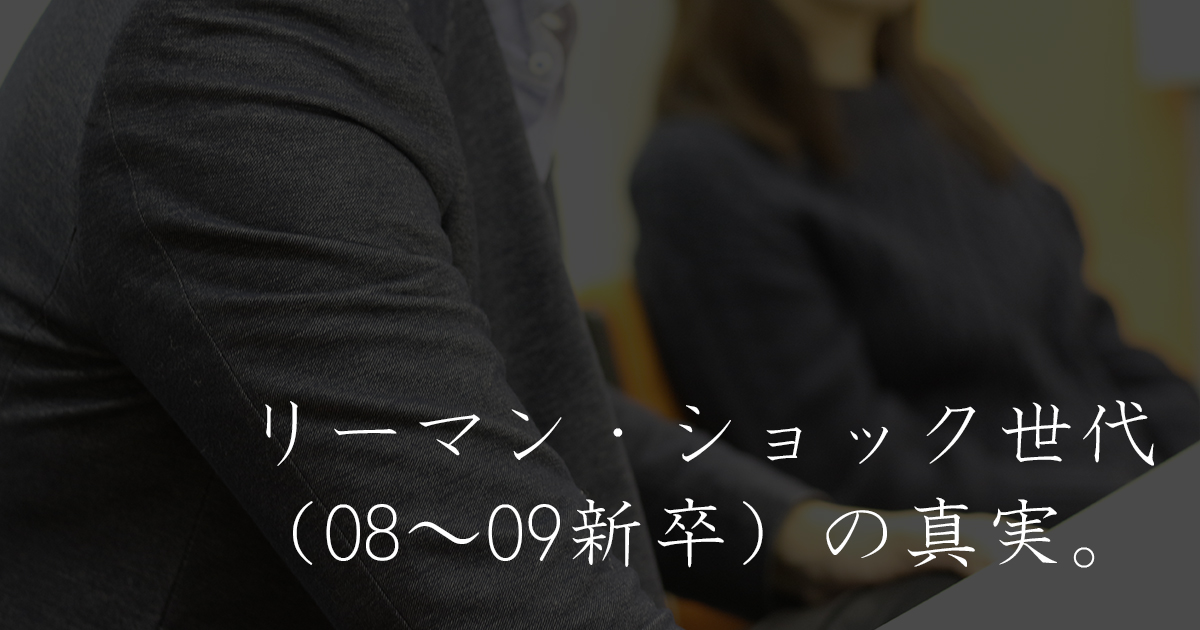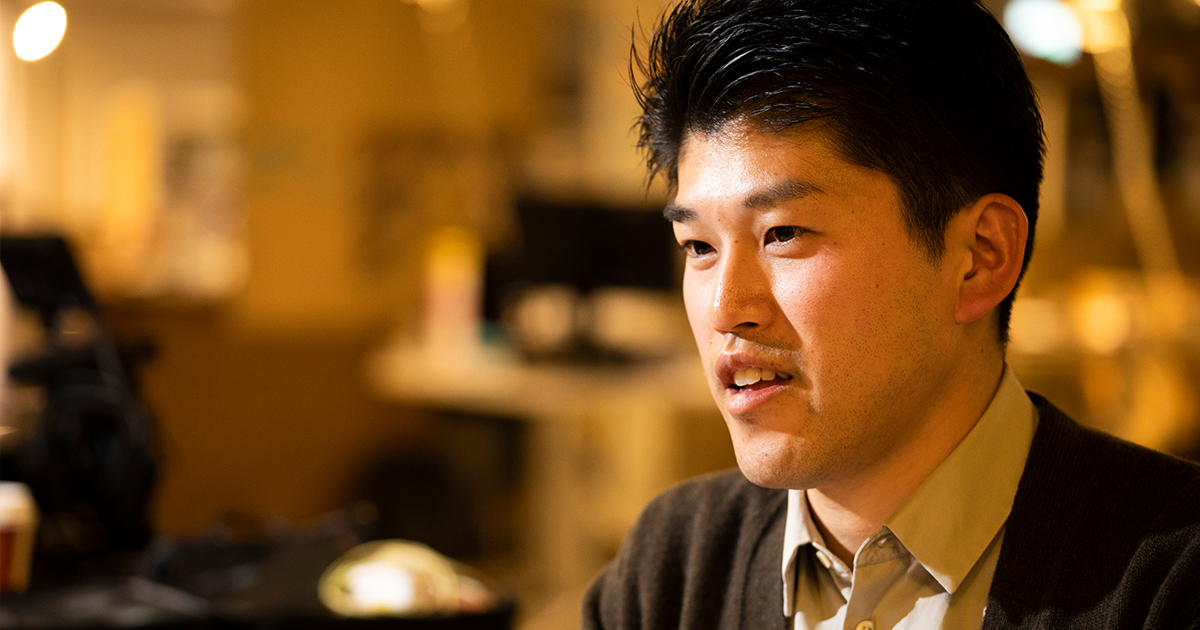ここ数年、日本でも「eスポーツ」に注目が集まっている。
「eスポーツ」とは、市販のビデオゲームを競技化したもの。すでに世界には多額の賞金を争うプロリーグやタイトル戦が存在する他、2022年に開催予定の「第19回アジア競技大会」では公式競技への採用が決まるなど、メダル競技としての認知も進み始めている。
テクノロジーを活用したスポーツが盛り上がりを見せる中、いわゆる一般的なeスポーツ種目とは異なるアプローチで注目を集める競技分野がある。2016年、株式会社meleapが発表したテクノスポーツ『HADO(ハドー)』だ。
HADOは、AR技術を活用し、掌で発生させたエナジーボールを対戦相手に向かって撃ったり、シールドを張って相手のエナジーボールから身を守るなど、ビデオゲームやアニメの世界ではお馴染みの光景を体験できるとあって、日本のみならず世界の若者たちの間で人気となっている。
HADOを展開しているのは、株式会社meleap(メリープ)CEOの福田浩士さん。HADOの原点は、「『ドラゴンボール』の主人公、孫悟空のようにかめはめ波を撃ちたい」という夢だ。大人になるにつれてほとんどの人が諦めてしまう”子どもの夢”を、福田さんはなぜ抱き続けられたのだろうか。
※本記事は姉妹媒体『エンジニアtype』からの転載です。元記事はこちら

株式会社meleap CEO
福田浩士さん(@okomesan)
東京大学大学院卒業後、株式会社リクルートに就職。2014年に独立し、株式会社meleapを設立。”かめはめ波”を撃ちたいという想いからAR技術を活用し、『HADO』(ハドー)を作り出す。現在、25カ国55箇所にHADOの店舗を展開。16年からはAR/VR初の大会『HADO WORLD CUP』も開催。「テクノスポーツで世界に夢と希望を与える」というビジョンを掲げ、サッカーを超えるスポーツ市場の創造を目指す
福田さんは、子どもの頃から空を飛んだり、超能力を使いこなしたりするような、超人的な身体能力に憧れを抱いていたと話す。「かめはめ波を撃つ」というのも習得したい技の一つだった。

「本気で修業すれば撃てるものだと信じていました。掌から“気”を出すべく本を読んで何年もかけて練習したり、気功の習得を目指したりしましたが、残念ながらかめはめ波を撃つことはできませんでした」
だが25歳の時、ネット上である映像を観て実現する方法が閃いた。
「メディアアーティストの真鍋大度さん率いるライゾマティクスが、2013年に発表した映像を見た時です。舞台上でパフォーマンスするPerfumeの3人の衣装に、さまざまな映像が投影されているのを見て、この映像技術とセンサー技術、ARを組み合わせれば、かめはめ波を再現できると確信しました」
その確信は揺るぎないものだった。その証拠に福田さんは映像を観た直後、当時の勤め先であるリクルートを退職した。しかし、大学院で建築や空間デザインを学び、リクルートで営業をしていた福田さんに技術的バックグランドはない。
「でも『必ずできる』という確信があったので、辞めるのに躊躇はありませんでしたね」
福田さんを突き動かしたのは「子ども時代からの夢を実現したい」という熱烈な思いだけだった。
「僕にとって一番大事なことは身体能力の拡張でした。難しいことをやり遂げてこその人生だと思ったので、できると思った時点で会社を辞めたんです。実際、あの映像を観て、リアルとバーチャルが混在する未来が見えましたし、必ず実現できるという確信があったので挑戦してみることにしました」
とはいえ、確信だけで夢は実現できない。開発力や資金を獲得し、継続的な収益源を確立する必要がある。福田さんはどうしたのだろうか。
「ハッカソンに行っては、参加者のエンジニアに声をかけてチームをつくり、一緒に開発を行いました。お金をかけなくてもできる試みは何でもやりました」
「人集めと資金集めには苦労した」と福田さんは当時を振り返る。アイデアを面白がってはくれても、実際に技術力が際立つ優秀なエンジニアや投資を実行してくれるベンチャーキャピタルを巻き込むのは至難の業だったからだ。

「実績がありませんから、『本当にできるの?』って尋ねられても、『やるしかありません』と答えるしかないわけです。それに、予算もほぼなかったため、初期のプロトタイプはかなりレベルが低く、当然満足できるものではありませんでした」
だが、HADO開発を始めた数ヶ月後、2014年10月にゲームディレクターだった現CCOの本木卓磨さん(@motokitakuma)が入社したことで風向きが変わり始めた。
「当初はAR上でモンスターにエネルギー弾を放って戦うというコンテンツを開発していました。そこに本木が入って、対人戦を前提とした競技ルールを整備し、HADOをスポーツ化する道を開いてくれたんです。スポーツ化を目指すことで、消費されないコンテンツになり、文化に根付く大きな市場に育てることができるというビジョンが見えました。今では、彼は『HADOの生みの親』といわれています」
さらに2015年にはポニーキャニオンから出資を得て経営基盤も安定。2016年に入るとアメリカでゲーム会社を経営した経験を持つ冨田由紀治(現COO)さんや、ゲームビジネスの店舗展開や中国事情にも詳しい林先健さん(現執行役員)の入社がさらなる追い風となった。
「彼らの入社で海外展開の筋道が見えましたし、2016年は、『Oculus Rift』や『HTC Vive』、『Microsoft HoloLens』、『PlayStation VR』が立て続けにリリースされるなど、VR/AR/MRが世間的な注目も集めました。これらの要素がHADOの成長の後押しになったのは間違いありません」
人材と資金を得たことで、スマホのカメラを利用した独自の画像トラッキング技術も開発に成功。グラフィック品質も順次グレードアップされ、2016年、HADOはついにリリースされた。
福田さんは、子ども時代の夢を大切に守り続け、その夢を世界中の若者たちに支持されるビジネスに昇華することができた。多くの人は大人になるにつれ、子ども時代の夢を「夢」として胸の内に葬ってしまう。実は福田さんも、起業前にリクルートで働いていた頃、一度は夢を見失いかけたことがある。
「学生の時からリクルート時代までずっと、『自分が心の底から人生を捧げたいと思えるものは何か』『自分は人生で何を実現したいのか』を考えていたんです。そうしたら、やっぱり僕の夢は『かめはめ波を撃ちたい』だった。それならその夢を実現するために人生を賭けたい。改めて原点に立ち帰れたのは大きかったですね」
とはいえ、「そんな子どもの頃のような夢、実現するのは無理だろう」と思ってしまいそうなものだが、福田さんには「根拠のない自信」があった。

「世界には大勢の偉人がいますが、『彼らに世界が変えられたなら自分にもできない理由はない』と考えていて、そこに疑う余地はないんです。『福田君って、起業した5年前から話している内容が変わらないよね』と言われますが、それは必ず夢を叶えることができると信じていたから。『かめはめ波なんて撃てるわけない』と言われようと、どれだけ難しい課題に直面しようと、諦める理由はありませんでした」
難易度の高さゆえにまだ実現できていないけれど、世界中の人たちが共感してくれる可能性があって、実現できたら大きなインパクトがもたらされる。それこそが福田さんにとって価値あるビジネスだと言う。
「当面の目標はサッカーの観戦人口と並ぶこと。30億人に到達できたらかなりいい勝負になると思っています。ただ、HADOがサッカーと並ぶような世界的なスポーツになるためには、もっと認知度を上げなければなりませんし、魅力的な観戦体験の設計や、ファンとプレイヤーのコミュニケーションプラットフォームの構築など、まだまだやらなければならないことがたくさんあります」
かめはめ波を撃つという夢は一見叶えたように見えるが、「理想のHADOを100%としたら、現状のHADOは5%程度」と福田さんは言う。
「ARは現実を拡張するものではなく、私たち自身を拡張してくれるテクロノジーです。究極の目標は、バーチャルかリアルなのか分からなくなるような体験をつくり、生活に溶け込ませること。例えば、学校への登校途中で敵と戦うなど、日常に溶け込むような状況をつくることは目標の一つ。まだまだ理想は遥か先にあると思っています」
ここで、どうしたらそんな世界を作れるのかという問いは無意味だ。それは、自動車やテレビ、コンピュータやスマートフォンも、実際に人々が手にするまではただの夢でしかなかったことを振り返れば明らかだろう。
「僕は誰にもできないことをやり遂げてこそ価値ある人生だと思っているので、難しい道を選ぶことに躊躇はありません。テクノスポーツはリアリティーある表現が命。技術力が大きく左右します。これからもエンジニアの皆さんと一緒に議論をしながら、あえて難しいテーマに挑戦し、ワクワクするような方向に世界を導いていきたいと思っています」
優れたテクノロジーは人類を遠くに連れてってくれる。これを先導するのが、福田さんのような先見の明を持つビジョナリーたちだ。だが彼らが夢想する優れたビジョンも、実現する手段が見つからなければただの夢で終わる他ない。

「自分のやりたいことができずに、歯痒さを感じている人も多いですよね。そんな時は、一度自分が本当にやりたいことを見つめ直す時間を確保してほしいです。なぜなら、エンジニアにはテクノロジーでビジョンを世の中に反映できる力があるから。それが未来を切り拓く原動力になるのは間違いありませんし、技術進化による時代の追い風もあります。子ども時代に思い描いた夢を世の中に表現することができるのは、エンジニアにしかできないことですし、日本のエンジニアが幼少期に描いた夢をテクロノジーによって実現することができれば、きっと未来はもっと面白くなるに違いありません」
取材・文/武田敏則(グレタケ) 撮影/赤松洋太 企画・編集/君和田 郁弥