「編集」は誰でも使えるビジネススキル
「編集」と聞くと、雑誌や書籍関連の話と思いがちだが、実は、イベント企画や商品開発、さらには町おこしまで、あらゆるビジネスに役に立つスキルである。問題解決に困っていたり、なにかブレイクスルーがないと悩んでいたりする人は、本書を読んでみると、何かヒントを得られるかもしれない。

タイトル: 魔法をかける編集
著者:藤本 智士
ページ数:240ページ
出版社:インプレス
定価:1,728円
出版日: 2017年07月21日
Book Review
「編集」と聞くと、雑誌や書籍関連の話だと思うかもしれないが、実はそれはある意味限定的な「編集」の解釈である。本書は、編集というものをもっと広義に捉え、企画や商品開発、さらには町おこしまで、あらゆるビジネスに役に立つスキルとして紹介している。イベントや商品など、あらゆることに「編集という魔法」をかけることで、様々な問題がクリアになり、状況が変化してゆく。本書では、そのプロセスや考え方が、親しみやすい文体で書かれている。
著者は、編集を、学校や出版社や編集プロダクションで学んで身につけたわけではない。素人として、自分で考えながら、本や雑誌を作ってきた。しかし、自ら編集長を務めた雑誌「Re:S」や、秋田県発行のフリーマガジン「のんびり」は、人々の目を地方に向けさせ、着実に世の中に影響を与えてきた。著者自身、状況を変えてゆく「編集の魔法」に魅せられ、追求してきた一人なのである。
「魔法」という言葉を使っているが、編集の力は、本来誰にでも備わっている力なのだと著者はいう。インターネットなどの発達によって、個人が声を発することが容易になった現代は、この力を発揮することがより容易な時代でもある。問題解決に困っていたり、なにかブレイクスルーがないと悩んでいたりする人は、本書を読んでみると、何かヒントを得られるかもしれない。
編集という魔法
広義の意味での編集

「編集」という言葉を聞いたり読んだりした時、一般的にイメージされる「編集」とは、おそらく雑誌や書籍などの編集だろう。著者が本書で扱うのは、もっと広義の「編集」、すなわち、「メディアを活用して状況を変化させるチカラ」である。「メディア(媒体)」にあたる部分は、雑誌や書籍である場合もあるが、もっと多様なものとして捉えることができる。たとえば、文章から離れて、「町」をメディアとして捉える。あるいは「商品」や「店」をメディアとして捉える。これらに編集という魔法をかけることによって、目の前にある様々な問題が解決する。
メディア=ローカルメディアと考えてみること
編集の魔法をかけるために不可欠なのが、「ローカルメディア」である。
「ローカルメディア」と聞くと、地方や田舎で作られている雑誌や新聞やウェブ、というようなイメージを抱くかもしれない。しかし「東京ローカル」という言葉があるように、ローカルを「局所」という意味に捉えることもできる。もしそう捉えるならば、究極のローカルメディアは自分自身だといえる。誰と付き合い、何を話し、どんな服を着て、どんな行動を取るか。それらすべてが自分自身からの発信なのであり、そうするとつまり、自分自身がメディアだと考えられる。
メディア=マスメディアと考えがちだが、メディア=ローカルメディアと考えることで、メディアというものをコントロール可能なものに引き寄せることができる。この認識を持つことが、編集の魔法を身につけるために必要なのだ。
編集は目的ではない
編集というのは、前述のとおり「メディアを活用して状況を変化させるチカラ」である。だから、たとえば状況を変えるためにミニコミを作るとして、それを作ること自体が目的になってしまってはいけない。作ったあとに世界がどのように変化するかが大切なのだ。
編集自体を目的としてしまわないようにするために、必要なのが「ビジョン」と「謙虚さ」だ。ビジョンとは数値目標ではなく、理想とする未来への意志やイメージのことである。数値目標にとらわれると、数字で表れないものに気づかなくなってしまう。数字の危険に陥らず、一人ひとりの暮らす世界そのものであるビジョンを真摯に思い描けば、自分の理想がすべての人にとっての理想でないことにも当然思い至るだろう。そのように考えていくことで、自分の考えたビジョンに対しても謙虚でいることができる。
編集は世界を変える
日本酒を編集する

ここで、広義の編集の例を挙げてみよう。
秋田県の日本酒「雪の茅舎(ぼうしゃ)」を造っているのは、齋彌(さいや)酒造店だ。そこで酒質の責任者である杜氏を務める高橋藤一(とういち)氏は、これまで酒造りに欠かせない工程の一つとされていた櫂入れ(かいいれ)に疑問を持った。櫂入れとは、発酵を均一にするために酒を掻きまわす作業である。独自の実験を繰り返した結果、櫂入れの工程が不要であることを実証し、微生物の対流に任せた自然な酒づくりを成功させた。
ここでいう自然な酒とは、米と水だけでつくられた純米酒を指しており、醸造アルコールを加えたいわゆる普通酒とは異なる。日本酒と呼ばれているもののほとんどは普通酒であったが、櫂入れをしない美味しいお酒が業界に浸透するにつれて、純米酒のシェアも伸びつつある。
日本酒というローカルメディアに、高橋氏は「人間がつくるのではない、自然に任せた酒づくり」という編集をほどこした。そして、「自然な酒づくりをする、添加物を多用した酒ではなく純米酒をスタンダードにする」というビジョンを実現させたのだ。
水筒を編集する
もうひとつ、著者自身がかかわった事例を挙げてみよう。
著者たちは、あるとき、使い捨てる文化への危機感から、みんなペットボトルでなく水筒を持ち歩けばいいのにと思い至り、『すいとう帖』という本を作った。そのことが縁となり、著者は魔法瓶の会社である象印マホービンとかかわることになった。本を作るという狭義の編集が、その地平を大きく広げた瞬間だった。
魔法瓶は衰退の一途をたどっていたが、著者は真逆の意見とビジョンを持っていた。「ペットボトルの普及は、飲料を持ち歩くというインフラをもたらした。ペットボトルを水筒にチェンジさせられれば、魔法瓶はこれまで以上に売れる」と。その実現のため、自分たちが持ちたいと思うようなシンプルで美しい水筒を作ることを提案した。 「水筒」という言葉は、「ボトル」に変化した。水筒は単純な樹脂製のものを指すという、象印マホービンの専門的な感覚によるものだったが、そこから生まれた「マイボトル」という言葉は、結果としてあたらしい暮らしのありかたをイメージさせるものになった。あたらしい物事を提案するには、あたらしい言葉が必要だ。
ステンレスの「マイボトル」は、順調に普及していった。ステンレスボトルの生産数は、『すいとう帖』を作った二〇〇四年には六百万本であったが、二〇一六年には千八百万本に増加。職場にマイボトルを持っていくことはごくスタンダードなことになった。これこそが、編集の魔法のチカラだ。
秋田県発行フリーマガジン「のんびり」の挑戦
秋田は「ニッポンの未来のトップランナー」
編集のチカラに魅せられた著者は、雑誌「Re:S(りす)」を創刊し、自ら編集長を務めた。「Re:S」は、「Re:Standard」、つまり、「あたらしい“ふつう”を提案する」というコンセプトをちぢめたタイトルだ。この雑誌では、既存の雑誌づくりのやり方はせず、日本中を旅取材しながら、ローカルな絶対価値を発信し続けるというスタイルを大切にした。
三年間、全十一号で「Re:S」を終えて、次に挑戦したのが、秋田県のフリーマガジンだった。雑誌企画「のんびり」は、秋田県庁が募集する、あたらしい紙メディアの制作企画のコンペで見事選ばれた。評価されたのは、「のんびり」の作り方が他の提案とまったく違っていたことだった。
秋田県は、少子高齢化・人口減少日本一の県である。この傾向が日本全体にあてはまる中で一位であるということはすなわち、秋田は「ニッポンの未来のトップランナー」であることを意味する。ずいぶん前から右肩下がりの世界で暮らし、「減って」いようと幸福を感じてきた田舎の人たちに、著者は未来を感じるという。
秋田だからこそできたこと
「のんびり」をはじめるにあたって描いたビジョンは、「どの地方よりも編集の魔法を使いこなす、ローカルスターターとしての秋田県の姿」だ。 そのビジョンを実現させるべく集めた仲間には、いわゆる編集者は一人もいなかった。「のんびり」をつくることを通して、広義な意味での編集者を育てるつもりだった。
「Re:S」のときからの著者の取材スタイルは、事前に下調べをしてアポイントを取るということはせず、「行き当たりばったり」ということである。酒蔵や温泉を訪ねるときにもその場で交渉し、いい人に出会えればその勢いで家にあがることもある。都会ではなかなかできないスタイルだが、おおらかな秋田だからこそできた。自分なりの編集というものを突き詰めたいと思っていた著者を受け止めてくれたのが、未来ある秋田という町だった。
編集術、公開します
尺に縛られない、うまくまとめない
「のんびり」を作る過程でメンバーに伝えていた編集術が、本書では八つにまとめられている。ここではそのうちのいくつかを紹介したい。 まず、雑誌の設計図である「台割」に縛られず、ページ数や文字数などの制約である「尺」をフレキシブルにすることだ。普通のやり方だと、台割も尺も細かく決めてから取材や執筆に臨む。だが、あまり尺に縛られると、臨場感に欠けてしまうことがある。だから、前述の「行き当たりばったり」を大切にし、自分自身でも予測不可能な展開の面白さを伝える。いわば、取材現場でライブで編集作業をするようなイメージである。
そして、そういった現場の温度を伝えるために、「まとめることの罠」に陥らないようにすべきだ。もちろん、まるごと世界を伝えられないから編集が必要なのだが、うまくまとめすぎてしまうと、現場の熱量が失われたり、本来伝えたいものが伝わらなかったりしてしまう。「うまくまとまった!」と思ったときは、いい部分の八割は消えている。百あるものを全体から薄く取り出して十にまとめるより、ありのままの十を抜き出した方が、読者は残りの九十を豊かに想像できる。例えば、年配の方の会話では、よく同じことが繰り返される。それは原稿になると真っ先に削られてしまうところであるが、何回も繰り返すのはそれが大切だからだ。繰り返しだからといってむやみに削除するのは誠実ではない。
見出しは見晴らしよく、テキトーを適当に
見晴らしのいい小見出しを作ることも大切だ。見出しもまた、「まとめることの罠」にかかってしまいやすい。見出しとは、山登りにたとえれば、途中のちょっとした見晴らし台のようなものだ。つい、見出しというと記事の内容をきれいに要約したくなるが、そうではなく、一読で意味がわからなくても印象的な言葉を拾うほうがよい。そのほうが見晴らし台としては魅力的で、記事を読ませるチカラがある。見出しは「テキトー」なくらいがちょうどいい。
そして、タイトルも同様だ。「テキトー」な言葉が結果として「適当」になる時、その見出しやタイトルは、真に優れたものとなる。逆に、つけてはいけない見出しやタイトルというものは明確にある。たとえば「のんびり」という雑誌は秋田県庁発行のPRマガジンだが、タイトルに、「秋田」という言葉を入れることだけは避けたという。なぜなら、もしタイトルに「秋田」という言葉が入っていたら、秋田県に興味がある人しか手に取らないからだ。「のんびり」とは響きのよさと秋田県に対する印象でつけたそうだが、本当の豊かさや幸福について考えるほどに、経済的にはビリでも別の価値観で見るとビリじゃない、つまりNONビリ=「のんびり」なのだ、という意味が立ち上がってきたという。テキトーなタイトルが適当になったわけだ。
現場から百パーセント持ち帰り、チームプレーを
現場から百パーセント持ってくることを意識することも大切だ。あとでネットで調べればいい、電話で聞けばいいといった甘えがあると、現場の緊張感が一気に薄れてしまう。誌面に必要なことは現場で取材相手にしっかり語ってもらえるように、場合によっては、知っているのに知らないふりをして聞き出すことも重要だ。
そして、一人で全部やらないことだ。自分と違う感覚を持った仲間と意見を交わしながら、一見無理に思えることを実現していくのが編集の醍醐味である。編集はチームプレーだという意識を持つことが大切だ。
一読の薦め
「東京では売れない雑誌を作りたい」と取り組んだ「Re:S」の制作について、ウェブやケーブルテレビなどのこれからのメディアについてなど、本書には魅力的なトピックがたくさんある。メディア関係の方にはもちろん興味深いことと思われるが、それにも増して、「編集」という言葉を遠く感じる方にぜひお読みいただき、「編集」をそれぞれの分野に活かしていただきたい。
※当記事は株式会社フライヤーから提供されています。
copyright © 2024 flier Inc. All rights reserved.
著者紹介
-
藤本 智士
編集者。有限会社りす代表。
1974年兵庫県生まれ。雑誌「Re:S」編集長を経て、秋田県発行フリーマガジン「のんびり」、webマガジン「なんも大学」の編集長に。自著に『風と土の秋田』『ほんとうのニッポンに出会う旅』(共に、リトルモア)。イラストレーターの福田利之氏との共著に『いまからノート』(青幻舎)、編著として『池田修三木版画集 センチメンタルの青い旗』(ナナロク社)などがある。編集・原稿執筆した『るろうにほん 熊本へ』(ワニブックス)、『ニッポンの嵐』(KADOKAWA)ほか、手がけた書籍多数。
ホームページ http://re-s.jp/
Twitter @Re_Satoshi_F -

《本の要約サイトflier フライヤー》は、話題の書籍や名著を1冊10分にまとめた要約が読めるサービスです。経営者や大学教授などの著名人・専門家などが「ビジネスパーソンがいま読むべき本」を一冊一冊厳選し、経営コンサルタントなどのプロフェッショナルのライターが要約を作成しているので内容の信頼性も安心。無料ユーザー登録をすれば、20冊分の要約を読むことができます。
この記事に似たテーマの要約
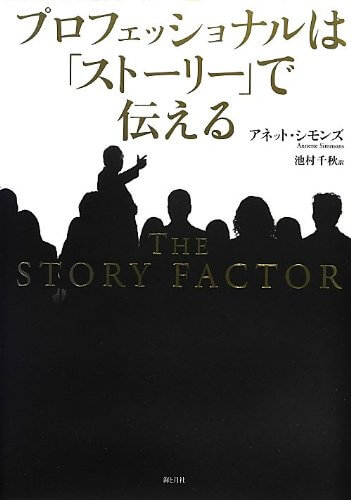
ストーリーは、人を動かす最良の手段–10分で読める要約「プロフェッシ…
著者:アネット・シモンズ 著/池村 千秋 訳
出版社:海と月社
プレゼンの場など、ビジネスシーンでのストーリーテリングの有効性が語られてから久しいですが、皆さんは正しくストーリーテリングを活用できていますか? 今回はその正しいやり方をレクチャーした指南書を要約しまし
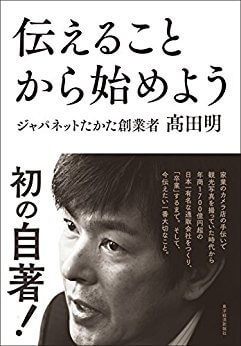
ジャパネットたかたの「伝える」ノウハウが詰まった初の自叙伝『伝えることから始めよ…
著者:髙田 明
出版社:東洋経済新報社
「ジャパネットたかた」の社長として長年活躍してきた髙田明氏。そんな彼が「伝える」技術を詰め込んだ1冊を、本記事では要約している。26年にも及ぶプレゼンター人生で彼が手に入れた技術とは? 「伝える」を「伝わ
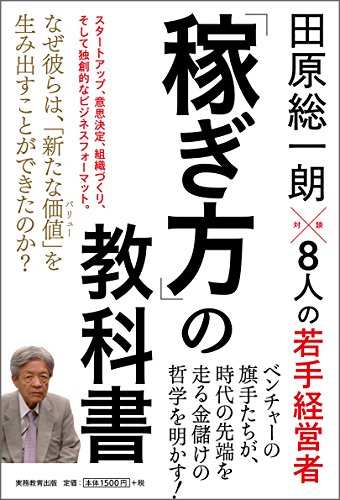
なぜ彼らは、「新たな価値」を生み出すことができたのか?田原総一朗が対談で切り込む
著者:田原 総一朗
出版社:実務教育出版
各分野で第一線をひた走る若き起業家に、ジャーナリストの巨匠、田原総一朗。そんな彼が独自の視点で切り込む対談集を10分で読める内容に要約しました。「新しい価値」を生み出してきた先駆者たちの生き方や、挑戦へ
.png)





