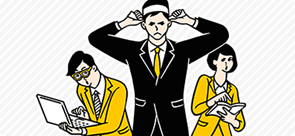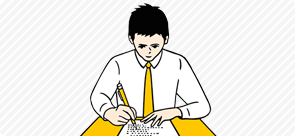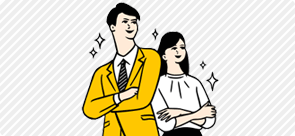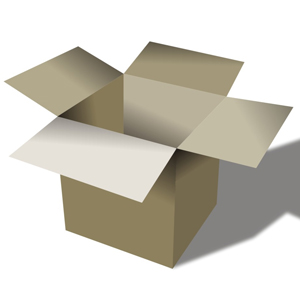
アメリカ映画でとても印象的なシーンのひとつに、「おまえはクビだ!」と宣告されたサラリーマンがダンボールに自分の荷物を詰めてオフィスを出て行くというのがあります。映画やドラマで一度や二度は目にしたのではないでしょうか。
人気俳優ジョージ・クルーニーが『マイレージ、マイライフ』という映画で演じたのが、まさにこの解雇宣告のプロ。契約企業の社員へのクビ言い渡しを代行するため、年間300日以上もアメリカ全土を飛びまわります。飛行機で出張するのですからマイレージは貯まる一方。それが人生の楽しみという切ない役柄でした。
実際に、証券会社や銀行が軒を並べるウォールストリートでは金曜日の夕方4時に上司に呼ばれ、解雇を言い渡され、残りの時間で荷物をまとめるという幕切れが定番といわれます。
ダメージを受けても果敢に立ち上がり、再起をはたす
こうしたシーンを法律的に支えているのは、米国特有の「解雇の自由」という雇う側の権利。従業員の退職の自由に対抗する解雇の権利が保証されており、法律では「いかなる理由においても従業員を解雇してもよい」と定められています。
つまり、労動者はいつ退職してもよい代わりに雇用主もいつでも労働者を解雇することができるわけですね。終身雇用が多い日本人からすると、ある日突然の解雇は少々乱暴な感じもするのですが、アメリカでは労働者がどんどん動くことで経済の柔軟性を維持しているという説もあります。
日本人だとすぐには立ち上がれないようなダメージを受けても、アメリカ人は数か月分の給料と医療保険の補助をもらって果敢に立ち上がり、再起をはたしていくわけですね。
横暴な上司には住みづらい国になる?
こうした人たちへの様々なサービスがあるのもビジネス先進国、アメリカらしいところです。よく知られているように、まず前職の会社がキャリアカウンセラーを紹介して再就職支援活動で手をとり足をとって重要な役割をはたします。
また、企業と契約している人材斡旋NPOが一括して他社へ就職させることもあります。しかし、最近ではこうした企業本位のやり方が社会的な反発を招いており、企業は株主だけではなく従業員や地域社会の利益も考慮に入れるべきことを定める法律が続々と誕生し、一方的な解雇権にも制約を加える動きになってきたということです。外資系企業のドラスティックなイメージのひとつに変化がもたらされるのは確実といえます。