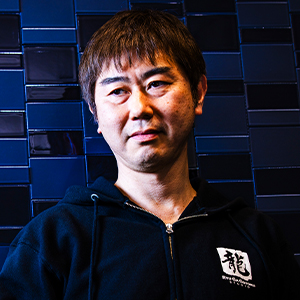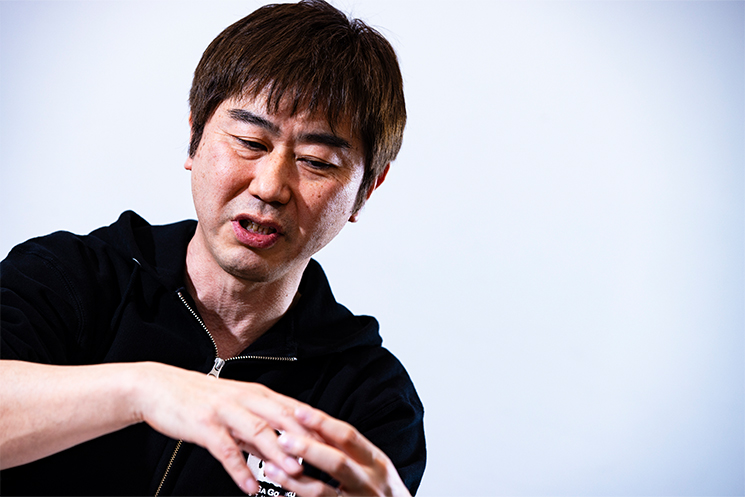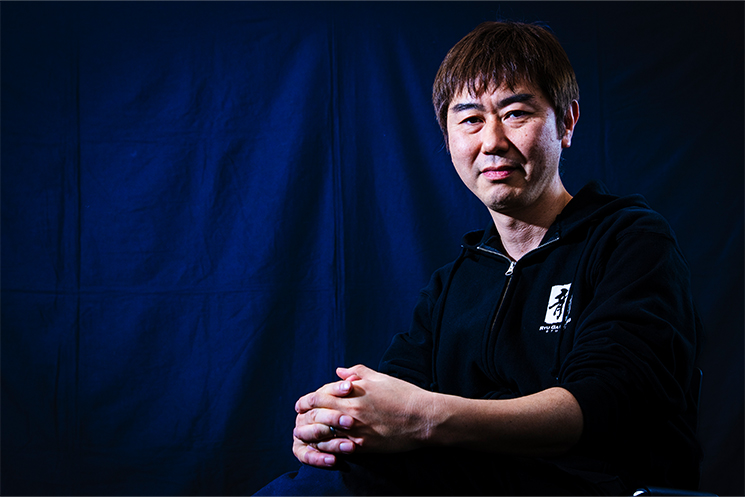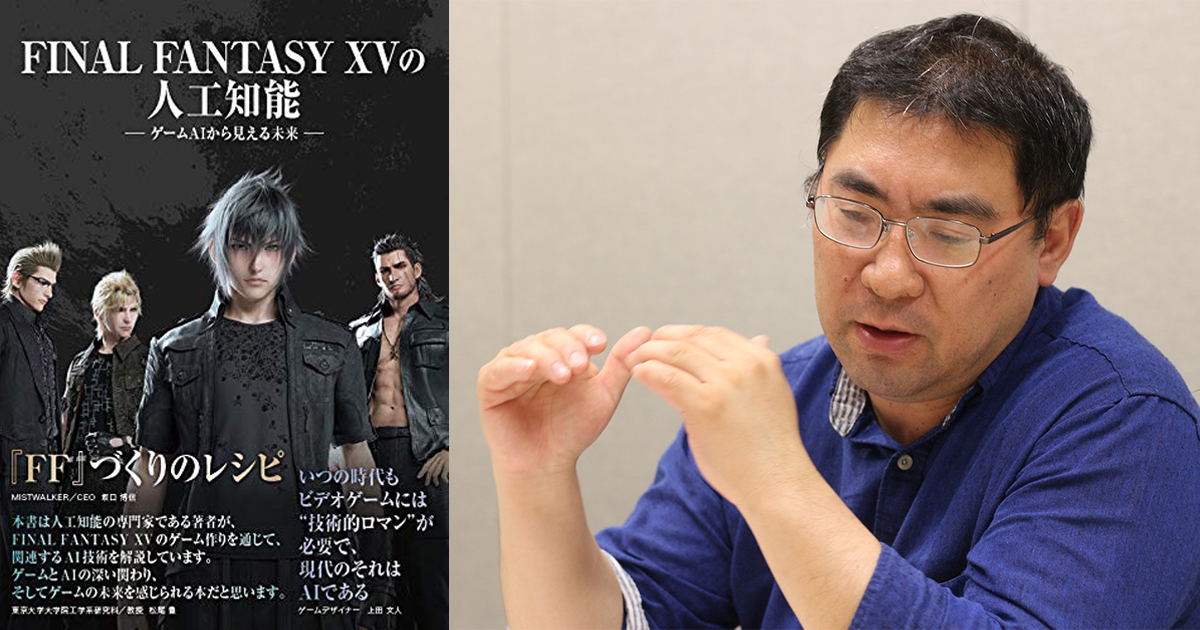巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描く『龍が如く』シリーズ。
2005年の誕生以来新作を出し続け、今や世界中にファンを持つ本シリーズから、24年1月、最新作となる『龍が如く8』が発売された。
日本とアメリカを舞台とする重厚なストーリーに加え、新バトルシステム『新ライブコマンドRPGバトル』などが国内外で高く評価された本作は、発売1週間で全世界累計販売本数が100万本を突破する過去最高記録を達成した。早くも「シリーズ最高傑作」との呼び声が高まっている。
一体どのような開発チームが、『龍が如く8』のような大ヒットタイトルを生み出せたのだろうか。
初代の作品から『龍が如く』シリーズのバトルシステム開発に携わり続け、現在「龍が如くスタジオ」の技術責任者を務める伊東豊さんは、「プログラマーはゲームを面白くするために影響を与えられる存在」と力強く語る。
今最も熱いゲームを生み出している「龍が如くスタジオ」。そのプログラムチームの軌跡と本作での挑戦について、伊東さんにお話を伺った。
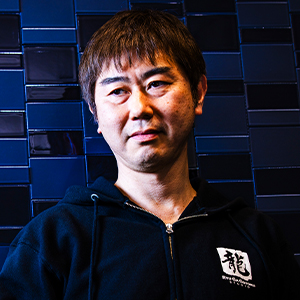
株式会社セガ
ゲームコンテンツ&サービス事業本部 第1事業部 第1開発6部 部長
「龍が如くスタジオ」技術責任者
伊東 豊さん(@YutakaIto_RGG)
1996年、セガ・エンタープライゼス(現・セガ)に入社。プログラマーとして、セガサターン版『ファイティングバイパーズ』『ファイターズメガミックス』、アーケード版『スパイクアウト』『バーチャストライカー』などの開発に携わる。龍が如くシリーズには第一作目から開発に携わり、2021年、『龍が如くスタジオ』の体制刷新によりスタジオ技術責任者へ就任。『LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶』ではディレクターも務めた
15年の経験は財産。40、50代のリーダーが率いる層の厚いチーム
―― 伊東さんはどのような経緯で、「龍が如くスタジオ」の技術責任者になられたのでしょうか?
これまで約30タイトルの開発に携わったのですが、プログラマーとしての実質的なキャリアの始まりは、『スパイクアウト』というアーケードゲームでした。
私が所属していたのは『バーチャファイター』を作っていた部署だったので、格闘ゲームの開発技術を学ぶには最高の環境だったのですが、『スパイクアウト』はそれまでの一対一の格闘ゲームを多人数に拡張するという新しいプロジェクトだったので、ひたすら勉強と挑戦の毎日でした。
試行錯誤を繰り返して作り上げた『スパイクアウト』は、結果的に多くの方に支持していただいたのですが、それが大きな自信にもなりましたし、このプロジェクトによって自分自身がゲームクリエイターとしても技術者としても大きく成長することができたと思っています。
それからしばらくして、私は『龍が如く』第一作目の開発終盤にチームに加わったのですが、当時はアーケードゲームの開発チームと家庭用ゲームの開発チームが統合されたばかりで、まだチーム全体としての一体感もなく、なんとなく居心地の悪さを感じながら淡々と仕事をこなしていました。
そんな中、バトルパートはアーケードチームのメンバーが多く、バトルシステムも『スパイクアウト』の技術を取り入れているということを知り、「ここなら自分の経験や技術を活かせる」と思い、バトルパートのプログラマーとして自分の居場所を見つけることができました。
それからバトルパートのプログラムリーダー、メインプログラマーを経てディレクターになり、「龍が如くスタジオ」の体制が刷新されたタイミングで技術責任者になったという経緯です。
―― 『龍が如く』シリーズは、二つのチームが統合されて生まれたのですね。
そうなんです。しかも初期の頃は、「アドベンチャーパートに強い家庭用チーム」「バトルパートに強いアーケードチーム」というようなイメージがチーム内にもあって、アドベンチャーパートとバトルパートのコミュニケーションも不足していたと思います。
初期の『龍が如く』シリーズは、街を歩いてるときに敵に出会うとロードが入ってモードが切り替わっていましたが、それは各パートごとに自分たちが作りやすい方法で作っていたからなんです。
今はバトルチームとアドベンチャーチームに加えて、ムービーシーンなどを担当するイベントチームの3チームが存在していますが、チーム間の壁は全くありません。
そうなったのは『龍が如く6 命の詩。』以降です。バトルとアドベンチャーの本当のシームレスを実現するために、今まで連動していなかった部分をどうやってマージするかを話し合いました。それからシリーズを追うごとにどんどん組織が混ざり合い、特にプログラマーはほぼワンチーム体制で開発をしています。
―― 伊東さんのXのポストで拝見したのですが、プログラムチームは年齢層も厚いそうですね。
新卒を積極採用しているので若手も多いですが、リーダー層は40、50代です。私も50を超えていますが、年齢を感じたことはほとんどありません。新しいゲームで積極的に遊んでいますし、最新の技術もどんどん取り入れています。
むしろ『龍が如く』を作り続けて得たスキルや経験は財産であり、スピード感のある開発に役立っています。若手の提案に対して「その仕様は昔のシリーズで一回検討したけど、こういう理由でうまくいかなかったんだよね」ということを説明してあげられるのは、ベテランならではのことかと。
一方で、若手の存在によってシリーズが進化できた部分も大いにあります。
例えば最近は動画でゲームを楽しむ人も増えているので、「前作までは動画サイトで見て、今作から初プレイ」という方を想定して、画面上に常に操作説明を表示したり、動画によるチュートリアルを表示するようにしています。今の若い人たちがどうやってゲームを楽しんでいるのか、ということについては若手の意見がとても参考になりました。
「ゲームはプレイして面白ければそれでいい」というのは昔の話で、今は様々なゲームの楽しみ方があると思います。ベテランがキャッチできない情報を提供してくれたり、現代の価値観で提案をしてくれる若手の存在は、ありがたいですね。
技術目線の提案で生まれた『新ライブコマンドRPGバトル』
―― 『龍が如く8』の開発において、プログラムチームのミッションは何だったのでしょうか?
一つは、『龍が如く7 光と闇の行方』で取り入れた「ライブコマンドRPGバトル」の完成度向上です。
「ライブコマンドRPGバトル」とは、『龍が如く』シリーズが培ってきた従来の喧嘩アクションと、いわゆるRPGのコマンド操作を融合したものです。この新しいバトルシステムをどのように設計すべきかは、実はプログラムチームの提案によって生まれました。
『龍が如く7』がRPGになることは決まっていたのですが、RPGといっても世の中にはさまざまな作品があります。プランナーも人それぞれ頭で描くものが異なっていたり、いくらミーティングをしても方向性が定まらなかったりした状況がしばらく続きました。
何かのきっかけになればと、私は「1時間ください」と言って資料を作り「技術ベースで考えるこれからのRPG」という提案をしました。
―― 「技術ベースで考えるこれからのRPG」とは?
『龍が如く』シリーズは、『ドラゴンエンジン』という内製のゲームエンジンで開発していますが、そこには、これまでシリーズが培ってきたアクションゲームの仕組みが全部入っているんです。人が吹っ飛んで壁に当たるとか、店の中に入って商品をめちゃくちゃにできるとか。
コマンドRPGになることでそうした機能が全部使われなくなってしまうことが、本当に悔しかったですし、もったいないなと思ったんですね。
それで「リアルタイムで殴ったり、物が壊れたりする仕組みを活かした、新しいコマンドRPGを作ってみてはどうですか?」という提案をしました。
例えばコマンドで「戦う」を選択しても、実際に攻撃がヒットしなければダメージにならない。吹っ飛んだ先に別の敵がいたら、その敵にもダメージが入る。そういう風に、アクションゲームのシステムでコマンドバトルを作ったら新しいものが生まれるんじゃないかと思ったんです。
龍が如くのコマンドバトルは、内部的にはアクションゲームと同じシステムで動いている。ユーザーがコマンドを選択すると、攻撃モーションを再生し、実際にヒットしたかどうかを判定して、ダメージが入る仕組みになっている(画像の赤い部分が攻撃判定のある部位)
―― 『龍が如く7』では、バトルシステムの刷新が新しいユーザーの獲得につながったそうですね。
はい、アクションバトルが苦手だった人にも『龍が如く』シリーズを遊んでもらえるようになったのは非常によかったです。ただ初めての取り組みだったので、完成度は決して高くはありませんでした。
『龍が如く7』では「実際にバトルの場に立っていたら、自分はどう行動するか」を想像してシステムを作り込んでいったのですが、リアルを重視しすぎた結果、どうしてもテンポが落ちてしまう部分がありました。そこで『龍が如く8』では前作の無駄を無くし、ゲームとしての面白さを高めることに挑戦しました。
―― 『龍が如く8』のバトルには、どんな新しい要素が加わっているのでしょうか?
例えば『龍が如く7』では、コマンドを決定するときにキャラクターの位置を動かせませんでしたが、『龍が如く8』では自ら位置取りをしてからコマンドを決定できるようにして、戦略性を高めました。
それから『龍が如く8』には、桐生が一定時間アクションモードになり、過去シリーズのように相手を攻撃できる「絆覚醒モード」があります。コマンドRPGが途中でアクションゲームに切り替わるのは、バトルのベースがアクションゲームで作られている『龍が如く』だからできることで、他のコマンドRPGではなかなか真似できないと思います。
こうした新機能を生み出すことはそれなりに大変でしたが、ゼロからシステムを考えた『龍が如く7』ほどの苦労はありませんでした。
『龍が如く7』では「本当にRPGにして大丈夫?」という不安を持っている人もいましたが、『龍が如く8』のときには解消されていましたし、同時に前作の欠点もみんなが理解していました。だからアイデアはメンバーからどんどん出てきましたし、改善の方向性がブレることもなかったです。
3つのゲームエンジンを使いこなす「トリリンガル教育」
―― 『龍が如く』シリーズは毎回映像が美しくなっていますが、『龍が如く8』もグラフィックにはかなりこだわったのでしょうか。
グラフィックの強化も、プログラムチームに与えられたミッションの一つでした。実は『龍が如く8』のグラフィック向上の背景には、『龍が如く 維新! 極』での経験が活かされています。
先述したように『龍が如く』シリーズは、ドラゴンエンジンという内製のゲームエンジンで開発しているのですが、この『龍が如く 維新! 極』では『Unreal Engine』という汎用のエンジンを使いました。つまり、全く新しい環境で『龍が如く 維新!』を作り直し、『龍が如く 維新! 極』という新しいゲームを作ったんです。
すると、今までの我々に足りていなかったものが見えてきました。その一つが、光の表現です。『龍が如く 維新! 極』ではUnreal Engineを使ったからこそ、昼の明るい環境下での光沢表現や、高度な被写界深度表現などをとても綺麗に表現することができました。
一方、『龍が如く8』はドラゴンエンジンで開発しましたが、「『龍が如く 維新! 極』で実現できた表現を『龍が如く8』にも取り入れたい」という相談を受けて、ドラゴンエンジンにライティングの新機能を加えたりもしました。
―― なぜドラゴンエンジンがありながら、Unreal Engineで『龍が如く 維新! 極』を開発したのですか?
普通はそんなコストがかかることはしないですよね(笑)
それでもあえてこの選択をしたのは、我々がゲーム業界の変化に対応しなければならないからです。もしかすると将来、非常に優れた汎用のゲームエンジンが出てきたら、世の中のゲーム会社がみんなそれを使うようになるかもしれません。
そのときに「龍が如くスタジオ」がドラゴンエンジンしか使えない状態だったら、もうこの世界で戦えなくなってしまうかもしれませんよね。
これからゲーム業界や開発環境がどの方向に進むかはわかりません。だから「龍が如くスタジオ」の新人研修では、ドラゴンエンジンに加えて『Unreal Engine』『Unity』の3つのエンジンでゲームを作り方を学んでもらっています。
他の2つのエンジンを知ることで、ドラゴンエンジンをより良いものにすることができますし、ゲーム業界の方向性が変わったときにはいつでもついていけるでしょう。そのためのトリリンガル教育です。
―― 今後のシリーズの存続も考えて、幅広い経験を積ませる新人教育をしているのですね。
はい。ただ『龍が如く』を作る上で、ドラゴンエンジンは絶対に無くしてはいけないものですし、内製エンジンの開発は今後も続けていきます。
ドラゴンエンジンは『龍が如く』にとって必要な機能に開発リソースを集中していますし、何より新機能の追加スピードが早いのは大きなメリットです。汎用エンジンを使用している場合、サポートにメールして3日程度で返事が来るところ、隣のプログラマーに依頼すれば5秒で済みますから。この違いは大きいと思います。
だからといって「自分たちのゲームエンジンが最高だ!」と思ってしまうのは良くありません。特に我々プログラマーは「あっちの方がすごいぞ、もっと頑張らなくては」という危機感を常に持っているべきだと考えています。
『龍が如く』とは何か。答えをくれるのはユーザーの声
―― 以前伊東さんがXで「細かいことを気にするよりは、プログラマーの誰もがストレスなく効率的に仕事ができることがベスト」とポストされていました。開発者にとって自由な環境があるのでしょうか?
そうですね。例えば一般企業や行政機関で使われるようなシステムは、不具合やトラブルを防ぐためにも細かいルールを守って開発することが大切なんだと思います。
ただ我々にとっての目標は「面白いゲームを作ること」なので、好きな環境や好きな書き方でプログラミングをすることによって効率が上がり、ゲームを面白くするための時間が増えるなら、それがいいんじゃないかというだけの話です。
実際、我々にはプログラムのコーディング規約のようなものはありません し、自主性に任せている部分は大きいです。
―― 自由に開発をしてもらいながらも、スケジュールを守った開発ができるのはなぜなのでしょうか?
これはプログラマーの例になりますが、1週間後に実装の締め切りがあるとして、もちろん全ての作業が終われば良いのですが、なかなかそうは行きません。そういう場合にどう対応するかは各パートに任せています。
例えば締め切りのあとに行われる打ち合わせの目的が、ボスキャラクターの「動き」を確認することであれば、たとえ「見た目」が未完成であっても、そこまで大きなボトルネックになることはありません。つまり、何のために締め切りが設定されているのかを理解した上で、各パートが優先度を決めて開発することを、多くのプログラマーができているのだと思います。
特に細かい指示をしているわけではないのですが、15年以上ゲームを作り続けてきたからこそ、スタジオ内に「阿吽の呼吸」のようなものがあるのを感じます。
―― 個人に大きな裁量が与えられているにもかかわらず、方向性がブレずにシリーズの世界観が守られていることに驚きます。
企画がFIXする前の段階で、プランナーやデザイナー、プログラマーのリーダー層を集めたブレストを行っていることも大きいかもしれません。
そこで各セクションのリーダーがそれぞれの立場で意見をぶつけ合い、徹底的に揉まれた企画が全体に共有されるので、メンバーに下ろしたときにも納得感があるんだと思います。最初から「みんなで自由にやってから後でまとめよう」は難しいでしょうね。
―― プランナーとデザイナー、プログラマーの意見は、簡単にまとまるものなのでしょうか?
いえいえ、今でこそ目線が合ってきましたが、バラバラになりかけたこともありました。三者それぞれに大切にするものが違いますから。
一番ぶつかったのは『龍が如く6』のときです。開発当初、バトルチームが『龍が如く0 誓いの場所』の開発で一時的に抜けていたのですが、戻ってみると、アクション性を大きく落とす方向性でバトルの研究が進められていました。
まるで映画が再現されているかのような映像中心のバトルシステムは、見ている分には楽しくても、触って楽しいものではありませんでした。これは『龍が如く』ではない、触って楽しいものにするべきだと、根気よくメンバーに意見を伝えて、バトルアクションをゼロから作り直しました。
職種の違うメンバーが同じ方向に進めるようになったのは、こうして何度も意見をぶつけているうちに「『龍が如く』とは何か」についての目線が合ってきたからだと思います。
作ったゲームは、決して満足するものにはならない
―― シリーズ最高傑作とも言われている『龍が如く8』ですが、プログラムチームはなぜユーザーの期待を超え続けられるのでしょうか。
ユーザーが何を期待しているのかを考え、それを超えたものを出す、ということを心がけているからだと思います。
例えば以前『龍が如く OF THE END』というゾンビ物のタイトルを作ったときに、敵をたくさん出したいという相談を受けました。それまでのシリーズでは敵が多くても15人程度だったので、今回は100人出したいと。
でもそのとき私は「敵が100人出てくるゲームは他にもありそうだから、思い切って1000人出しませんか」と大風呂敷を広げました。結果的に、同時に1000人は出せなかったのですが、次から次へと湧いてくる仕組みにして、街の中には1000人のゾンビがいる、ということにさせてもらいましたが(笑)
―― 「1000人出しませんか」と言ったとき、本当に1000人出せると思っていたのでしょうか?
いいえ。でも言ってしまいました(笑)。いつもユーザーの期待を超えるということを意識しているので、目標は遠くに置くようにしています。だからいつも、作ったゲームは満足するものにはならないんですが。
ユーザーの期待が100%だとしたら、我々は500%を目指す。最終的に500%には届かなかったとしても、200%に届いたとすれば、ユーザーの期待を大きく超えるものは作れたわけです。じゃあ残りの300%の部分は、次のタイトルで挑戦しよう、と。その繰り返しですね。
―― それを15年以上続けてこられたのが本当にすごいと思います。
個人的には、『龍が如く6』の開発が終わった頃、「技術的にはやるべきことはやった、これ以上のものは作れないかもしれない」という気持ちになったことはあります。
そんなとき、次のタイトルがRPGになることが決まると「新しい方向性でまだまだできることがありそうだ」という気持ちに変わりましたし、『JUDGE EYES』では主人公が変わったことで『龍が如く』とは全く違った新しいアクションを追加することもできました。
だから、もしまたどこかで行き詰まったら、そのときは違う方向性を見つければいいと思います。そうすればこれからも新しい『龍が如く』を作っていけるでしょうし、我々も成長し続けられるんじゃないかと思います。
―― シリーズの継続を望むファンとして、非常に嬉しい言葉をいただきました。最後に、プログラムチームでこれからも大切にしていきたいことを教えてください。
一般的なプログラマーは、仕様書通りの実装を求められることが多いと思いますが、「龍が如くスタジオ」のプログラマーは、決して言われた通りにものを作るだけの仕事ではありません。「龍が如くスタジオ」では、プランナーの仕事はコンセプトを考えることで、それを膨らませて実装するのがプログラマーの仕事です。どうやったら面白くなるかを自分で考え、ゲームに対して影響を与えていけるのが、「ゲームプログラマー」という存在ではないでしょうか。
ゲームプログラマーは、技術者であり、クリエイターでもあります。だからこそ「どうすればもっと面白くなるだろうか」という視点は、ゲームを作り続ける限り、持ち続けていかなければならないと思っています。
取材・文/一本麻衣 撮影/竹井俊晴 編集/今中康達(編集部)