
Sucker Punch Productions LLC. クリエーティブディレクター
Nate Fox(ネイト・フォックス)さん
2009年発売のアクションアドベンチャーゲーム『inFAMOUS(インファマス)』シリーズ(PS3/PS4 発売元:SIE)でゲームディレクターを務めた後、怪盗アクションゲーム『怪盗スライ・クーパー』シリーズ(PS2/PS3 発売元:SIE)のゲームデザイン・シナリオを担当。本作『Ghost of Tsushima』ではクリエーティブディレクターを担当

今年最も話題となったゲーム、PlayStation®4用ソフト『Ghost of Tsushima』。
鎌倉時代の蒙古襲来(モンゴル帝国による対日本侵攻)を題材にした、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)発のオープンワールド時代劇アクションアドベンチャーだ。
プレイヤーは、日本侵略の足掛かりとして対馬に上陸した蒙古兵の攻撃をかろうじて生き延びた対馬の武士「境井仁」として、故郷を敵の手から取り戻すべく旅をする。
ストーリー、アクション、グラフィック、どれをとっても世界最高峰。だが、最も注目すべきは「本物の日本」を感じさせる表現力にある。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
あまりにも違和感のない“日本っぽさ”故に、「『Ghost of Tsushima』は日本人が作ったゲームだ」と思い込んでいる人も少なくない。
しかし本作の開発を手掛けたのは、アメリカ・ワシントンに本社を置くサッカーパンチプロダクションズのメンバーだ。
では、なぜ彼らはここまで高度に「日本らしさ」を表現することができたのだろうか?
開発元であるサッカーパンチのクリエーティブディレクター、ネイト・フォックスさんと、発売元であるSIEのローカライズチームに開発の裏側を伺った。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
まず初めに、サッカーパンチプロダクションズ・ネイトさんの独占取材をお届けしよう。彼らが『Ghost of Tsushima』にどれほどの情熱を注いできたのかが分かるはずだ。

Sucker Punch Productions LLC. クリエーティブディレクター
Nate Fox(ネイト・フォックス)さん
2009年発売のアクションアドベンチャーゲーム『inFAMOUS(インファマス)』シリーズ(PS3/PS4 発売元:SIE)でゲームディレクターを務めた後、怪盗アクションゲーム『怪盗スライ・クーパー』シリーズ(PS2/PS3 発売元:SIE)のゲームデザイン・シナリオを担当。本作『Ghost of Tsushima』ではクリエーティブディレクターを担当
『Ghost of Tsushima』では、クリエーティブディレクターを務めました。
本作のクリエーティブディレクターは、ゲーム全体の大まかなストーリーづくりから、乗馬時の速度をどうするか、といった細部の設定まで、ゲーム内で起こるありとあらゆる事象のアイデアづくりに責任を持つ立場です。
元々は、『ゼルダの伝説』の勇者リンクのように、プレイヤーの役割がすぐに認識できるオープンワールドゲームを作ろう、という構想があったんです。プレイヤーがゲームのキャラクターたちに必要とされる、波乱万丈な世界を作りたいと考えていました。
私たちにとって、そのキャラクターは“侍”以外にあり得ませんでした。だって、剣豪になりたくない人なんて、この世にいないでしょう?(笑)
それでしばらく調査をして、侍をキャラクターにするならば、その舞台は元寇の時の対馬がいいだろう、と決めたのです。
島中の民が、戦闘のプロである侍(プレイヤー)に助けを求めてくる。そんな状況で、元寇という大きな出来事の中にさまざまなドラマを生み出せるのではと考えました。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
もちろん大きなプレッシャーを感じていましたし、当初は「当事者ではない私たちが、史実を基にした物語をつくっていいのだろうか?」という疑念があったのも確かです。
しかし私たちはもともと日本の時代劇の熱狂的なファンで、「この時代や、武士という存在を描きたい」という激しい情熱を持っていたのです。
ゲーム画面がモノクロになる「黒澤モード」からも分かる通り、私は黒澤明監督の『七人の侍』を愛しています。
『Ghost of Tsushima』は他にもさまざまな時代劇から影響を受けており、同じく黒澤明監督の『用心棒』や『乱』、三池崇史監督の『十三人の刺客』なども参考にしています。
はい。ただ、それだけでは日本を舞台にしたゲームを開発できるほどの知識が足りないことも自覚していました。
そこで、日本の映画作品を参考にする以外に、日本の文化・風習に詳しい専門家や、SIEのローカライズチームにも協力を仰ぎました。
専門家の皆さんには、居合術や甲冑、兜(かぶと)、モンゴルのアクセントなどの本当に細かい部分にまでアドバイスをいただきました。
例えば戦闘においては武術考証として、古流武術「天心流兵法(てんしんりゅうへいほう)」の専門家にアプローチし、モーションキャプチャーを撮らせていただいています。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
それからSIEのローカライズチームには、日本の時代考証、文化考証のスペシャリストをアサインしてもらい、逐一「日本らしさ」について違和感がないか、意見を求めました。
彼らの協力があってこそ実現できたことだと思います。
他にも、何度か日本に取材チームを派遣して、対馬や日本各地の美しさを写真に収めたり、自然の「音」を集めたりもしました。実際にその景色を目にしたことで、「この美しさをゲームの中で表現したい」という思いがより強くなりました。

©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
もちろんです。日本では素晴らしいゲームが無数に作られていますが、中でも本作に影響を与えたのは『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』(発売元:任天堂)です。
『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』の開発陣は、プレイヤーが好奇心や驚きを求める心に突き動かされ、ゲーム内で「自分だけの道」を見つけられることを信じているのだと思います。
他にも、『Bloodborne』(PS4 発売元:SIE)のフェアでありつつハードな戦闘システムや、『ワンダと巨像』(PS2/PS3/PS4 発売元:SIE)の必要最小限のUI、みずみずしい色調も素晴らしいですよね。
記事後半では、サッカーパンチプロダクションズ(以下:サッカーパンチ)とアドバイザーたちがどのようなやり取りをしながら「日本らしさ」の表現を追求したのかを紹介しよう。
お話を伺ったのは、SIEローカライズチームの石立さん、坂井さん、関根さんだ。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント シニアローカライズプロデューサー
石立大介さん
国内市場のマーケティングや宣伝チーム・セールスチームとの連携、一部ローカライズ、プロデューサーとして全体的な統括を担当。『Ghost of Tsushima』(PS4)の他に、『Detroit: Become Human』 (PS4)、『The Last of Us Part II』(PS4)、『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』(PS5/PS4)などの日本語版製作・一部ローカライズを担当

ソニー・インタラクティブエンタテインメント アソシエイトローカライズスペシャリスト
坂井大剛さん
フリーランスの映像翻訳者として活躍した後、ゴルフやレスリングなどスポーツ番組の日本語版制作を多数手掛ける。現在は日本語版シナリオ作成やスタジオでの音声収録、監修などを担当。時代・文化考証のスペシャリストと連携し、より精緻なゲーム作りをサポートする。これまでに 『Firewall Zero Hour』、『Bravo Team』および『Wipeout Omega Collection』(いずれもPS4)などのローカライズを担当

ソニー・インタラクティブエンタテインメント アソシエイトプロデューサー
関根麗子さん
制作進行やスケジュール管理を主に担当。サッカーパンチとの交渉窓口や現地から届いた素材管理なども担う。プロデュースとしては『Days Gone』(PS4)、『アッシュと魔法の筆』や『マーベルアイアンマン VR』(いずれもPS VR)。また『INFAMOUS〜悪名高き男〜』(PS3)の字幕ローカライズでSP作品に初めて関わっている
石立:私たちはこれまでにも『Detroit: Become Human』(PS4)や『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』(PS5/PS4)などのさまざまなゲームのローカライズを担当してきました。
「ローカライズ」というと翻訳作業を想像される方が多いと思いますが、私たちの仕事は「日本語に翻訳するだけ」ではないんですよ。実はほとんどの場合では、作品のセリフを元にしながら、日本人が聞いても違和感がないような日本語のセリフを一から書き起こしているんです。
そのためローカライズの度に、作品の舞台について膨大な調査・研究を重ねています。例えば『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』(PS4)のローカライズを手掛けた時は、海賊に関する資料を読み込みました。本作でも参考文献に加え、専門家にも何度も話を伺いましたね。
そうやって一つ一つの作品を深く理解した上で、リップシンクや間合いなども考慮しながら、最適な日本語版のシナリオを作っているのです。
石立:そうですね。ローカライズに入る前の企画・制作段階からサッカーパンチの問い合わせに対応したり、取材旅行のサポートをしたりしていました。
ただ、ネイトも語っている通り、そもそもサッカーパンチの上層部には日本の時代劇映画や漫画、劇画に対する偏愛とリスペクトがものすごくあったんです。僕らからも度々アドバイスをすることはありましたが、ほとんどの事については彼らが自力で専門家を探し出してきて、監修を受けていましたよ。
坂井:われわれは、制作段階のトレーラーを見たり、テストプレイをしたりして、サッカーパンチでは気付けないような細かい部分を指摘したくらいでした。例えばゲームの舞台が鎌倉時代なのに、当時では考えられないような大きな大仏が置いてあるのを見つけ、「これは時代にそぐわないのでなくした方がいい」とアドバイスをしたことがありました。結局その大仏はそのまま残すことになりましたが。
石立:あと、フィールド上の「灯籠」についてはサッカーパンチとかなり議論しましたね。
例えば、ある時サッカーパンチから「この時代に提灯(ちょうちん)って使っていいんだっけ?」と質問が来たんですよ。でも、赤い蛇腹(じゃばら)の提灯は江戸時代後半に出てきたものなので、鎌倉時代の設定で登場させると違和感があるんです。
そもそも鎌倉時代には、街道に灯りなんてありません。夜になるともう真っ暗で、野盗が出るような世界だったわけです。なので、その点を丁寧に説明した上で「やめた方がいい」と伝えると、「ゲーム上、どうしても街道に照明を置かなければならない」と言われて。
じゃあ何なら代用できるのかと考えて、「灯籠だったらいいんじゃないか」と。実際は限られたお寺などにしか置かれてなかったと思いますが、一応鎌倉時代に存在はしていましたから。
そう助言をしたところ、どうしても灯りが必要な個所には、結果的に灯籠が置かれることになりました。

フィールドに設置されている灯篭
©2020 Sony Interactive Entertainment LLC.
関根:ええ。ただ、灯籠の件もそうですが、基本的に私たちから何か積極的に意見をすることはありませんでしたね。それよりもサッカーパンチのやりたいことが明確にあり、それをベストなかたちで実現するために、私たちが時代考証の専門家に話を聞いて、良い落としどころを探るような感覚でした。
「このアイテムは鎌倉時代に実在はしていなかったけれど、きっとこういう理由でこういうふうになったんだ」といったような、バックストーリーを見つけるといいますか。
石立:エンターテインメントとして成立させるためには、必ずしも時代考証に完璧に沿うことばかりが重要ではないんですよね。手紙なども、本当に当時の言葉にしてしまったらプレイヤーが読めないじゃないですか。
とはいえ時代にそぐわないアイテムばかりが沢山置いてあったら違和感を与えてしまいますから、そのあたりはバランスを取りながらやっていたと思います。
石立:はい。それは「侍」についての描き方も同じで、本当に史実通りの侍を描いてしまっていたら、日本以外の地域のユーザーは「俺たちの知ってる侍じゃない!」と感じてしまいます。
だからサッカーパンチなりに、本当に存在していた「日本の侍」と、自分たち北米を中心とした全世界のユーザーが考える「侍ファンタジー」の間でのスイートスポットを探そうと、工夫していたと思います。

石立:彼らはもともと時代劇や侍映画の熱烈なファンで、そのジャンルの一つとして作品を提供したいという思いを持っていました。だから日本をチープに見せたり、アイテムをただギミックとして適当に置いたりというようなことは、最初からやろうと思っていなかったんです。
「寿司・ゲイシャ・テンプラ」みたいに、いかにも海外の方々が好きそうな「THE 日本」という表現にならないように、開発側も、私たちも気を付けていましたね。
サッカーパンチが常に言っていたのは、「日本のユーザーが侮辱されたと感じないゲームにしたい」ということでした。「そこだけは絶対に踏み越えてはならないラインだ」と。
坂井:日本語のセリフについては100%こちらに任されていましたね。ただ、それは今回が特別というわけではなく、ローカライズをするときは基本的にいつも任せてもらっています。
特に『Ghost of Tsushima』においてはサッカーパンチ側も、「日本の市場やユーザー、文化に関しては君たちの方がわれわれよりもよっぽど詳しいと思うから、全てお任せします」というスタンスだったと思います。

坂井:武家については、「武士」らしい話し方にするために、現代劇の翻訳よりも充分な「間」をとって話せるようなセリフ回しを意識しました。例えば英語で「OK, I’ll do that!」(早口)というセリフがあったときに、洋画の吹き替えのような感じで「よし、分かった、やってやる!」って翻訳を詰め込むと、ちょっと軽薄なキャラになってしまうじゃないですか(笑)
だから、「む、よかろう」などの言葉で間を取れるようにして、武士らしい重みを持たせるというか。元のセリフと意図は同じになるようにして、セリフは変えていましたね。
石立:ええ。あとは「日本らしさ」の表現で言えば、実はBGMの動物の声については、本当に日本の動物の声を録音して使っているんですよ。
サッカーパンチから「この声とこの声を録ってきてくれ」って要望がきたので、日本側のサウンドチームが関東近郊の森などに行って、鳥の声や鹿の声を録音したんです。
石立:はい。『Ghost of Tsushima』の対馬は「日本全体の縮図のようにしたい」「プレイヤーに四季の変化を楽しんでもらいたい」というコンセプトがあったので、対馬以外にもさまざまな所に行っていたようです。
最初は春ごろに、福岡で北九州にある元寇防塁や対馬の風景、本州の古民家などを撮影して、その後もう一度秋に来日し、落ち葉やすすきなどを撮影し、山形など東北の方へ行って雪が降っている風景を撮っていました。ゲーム上の対馬は、ほとんど春か秋か冬でしたね。
なぜ彼らがここまで細かく日本の原風景にこだわったかというと、フォトグラメトリ(Photogrammetry)という手法を使っているから。さまざまなアングルから撮影した写真を解析して、ゲーム上の物体にテクスチャーとして貼り、オブジェクトを立体的に表現しています。つまり写真のクオリティーが、ゲーム内のグラフィックの精度に直結しているんです。
だから素材は多ければ多いほどいい。落ち葉を並べていくつも撮影したり、木の幹の皮まで撮影していました。他にも、自然の風景を集めた写真集や日本の旅行パンフレットも見ていましたね。そこでも本当の日本の美しさと、世界の人たちが想像する「日本の美」についてバランスを見て表現しようとしていました。
石立:やはり、「情熱」は間違いなくあると思いますね。彼らは開発が決まってから毎週1回「日本映画を見る時間」を設けて時代劇を中心に勉強していたそうです。チーム全体が情熱的で、「人を楽しませたい」という気持ちが大きかったからこそ、苦労をいとわずここまでのことができたのだと思います。
坂井:あとは、「外国人から見た日本の美しさ」をストレートに表現していたところですね。例えば私たち日本人がアメリカ映画に出てくる広大な小麦畑なんかを見ると、冒険心をくすぐられるじゃないですか。でも、きっとアメリカ人からすると、それはただの田舎の風景なわけです。日本人では気付けない日本の美しさや魅力に気付いて、表現できたのは大きかったと思います。
関根:特にアート系の方は、日本にしかない四季の色や季節感にすごく感動したみたいですね。侍の鎧の細かいディティールなんかにも。そういった、外から見て初めて分かる日本の魅力に気付いて、それを素直に作ってみようという気持ちになれたのは、海外の開発会社だからこそできたことなのかなと思います。

石立:また、日本の文化や日本人ユーザーの気持ちをよく知っている僕たちと密にコミュニケーションを取るスタンスを持っていたことも大きかったと思います。
基本的に開発力の高いチームの中には、コミュニケーションの量も質も意図的に高めようとする人がいるんです。サッカーパンチはそれが顕著で。
「おかしなところがあったら、なんでもすぐに指摘してほしい」「俺たちは批判が大好きなんだ」と言ってきて、すさまじい積極性がありました。
中には開発スケジュールを遵守するのに必死で「今マスターをアップするので手いっぱいだから、ローカライズの話は後!」って、余力のないまま突き進んでしまう開発現場もあるんですよ。
だけど、開発力の高いチームはスケジュールにも余裕があるし、エンジニアの技術力も高い。プロジェクト内のコミュニケーションも反応がいいので、締め切りぎりぎりになって慌てることがありません。だからこそ日本のローカライズチームとも、必要に応じて丁寧にコミュニケーションするための時間を割ける。
ローカライズ先のことを知るためにとことん情熱を傾け、ユーザーを楽しませるための時間と労力を惜しまないこと。その積み重ねが日本人をはじめとした、全世界のユーザーの感動体験をつくったのだと思います。

ローカライズチームの皆さんはインタビュー当日、開発チームが記念に作成し、一部関係者へ配布した『Ghost of Tsushima』のTシャツを着て取材に臨んでくれていた。彼らもサッカーパンチと同じく、この作品を愛していることが伺える。
取材・文/石川香苗子 編集/河西ことみ(編集部)
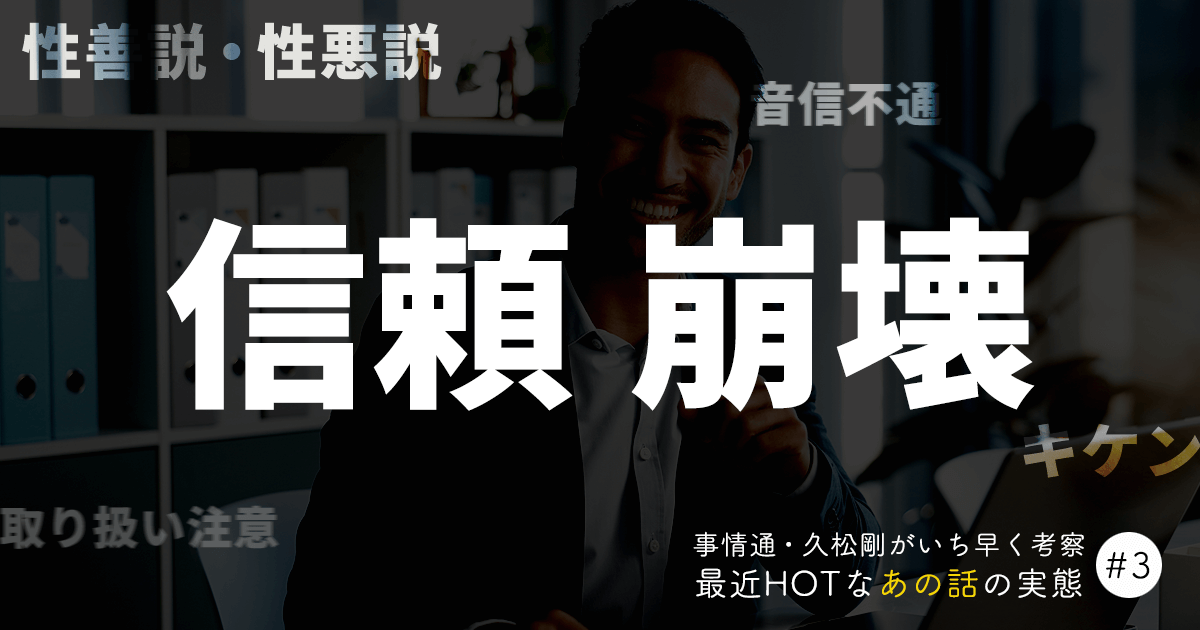
NEW!

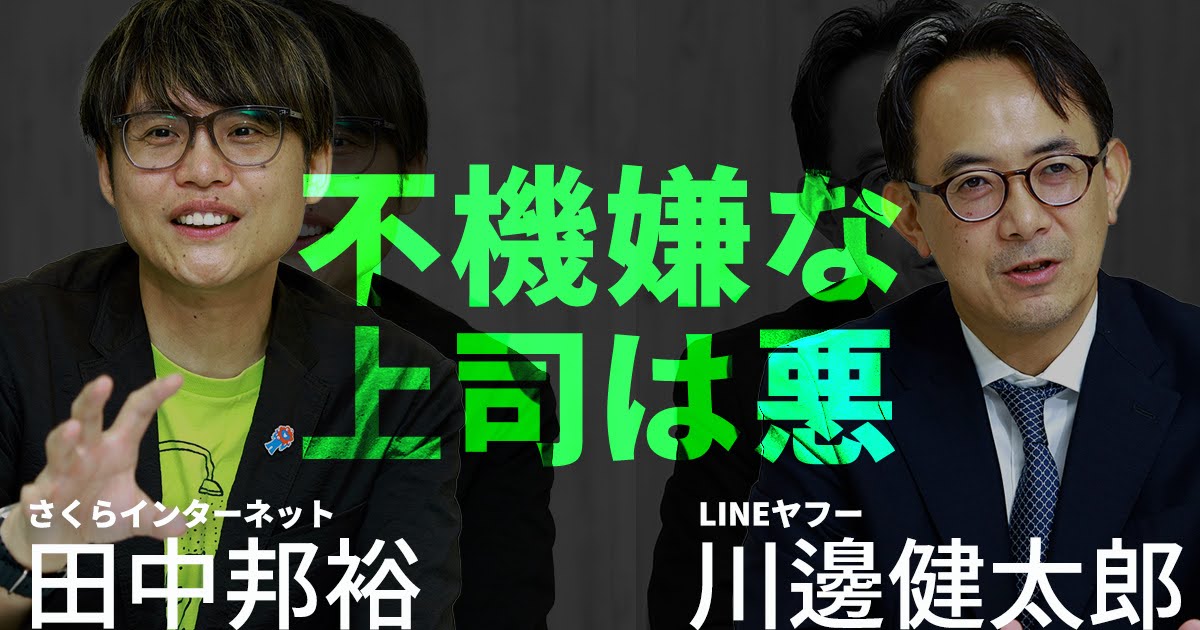


タグ