

元SEの30歳蔵元が今も「1割エンジニア」を続ける理由
栃木県小山市の西堀酒造は、明治5年創業の老舗酒造でありながら、アクリル製の特注の透明な酒樽、ご法度とされてきたLED照射など、革新的な酒造りで業界内外から注目を集めている。仕掛け人は六代目蔵元の西堀哲也さん、30歳。東大哲学科を卒業し、新卒で入社したのはワークスアプリケーションズ、2016年の冬に家業に入るまではエンジニアひと筋という異色のキャリアを歩む。
酒造業界に腰を据えた今も多忙を縫って一部、個人で受託開発を続けているという。エンジニアと蔵元の二足のわらじは、彼のキャリアに何をもたらしたのか。

西堀酒造 六代目蔵元 西堀哲也さん
1990年栃木県小山市出身。東京大学文学部哲学科を卒業後、株式会社ワークスアプリケーションズにてエンジニアとしてキャリアをスタート。2016年、明治時代から続く家業の酒造に参画
「分からないからこそ飛び込む」体に染み付いた現場主義
文系学生でありながらエンジニアになったのは「世界を知りたかったから」だった。就職活動を通じていろいろな業界を見ていく中で、もっとも目まぐるしく変化しているように映ったのがIT業界だった。技術書なんて一生読むことはないだろうと思えるほど、それまでの西堀さんはおよそテクノロジーとは無縁。だからこそ開発者となり、仕事としてやらざるを得ない環境に自分を放り込むことで、世界を広げられるのではないかと考えたのだ。中でも「尖っていて個性的な人が多そう」という理由でワークスアプリケーションズの扉を叩いた。
エンジニアという仕事にどんな種類があるのかも知らなかった。自分がその後担う役割がシステムエンジニアと呼ばれることも、入社後に知った。「教えない研修」として知られるワークスの半年間の入社後研修では相当に苦労したという。
「人に聞いてもいけないし、ググってもダメ。ただひたすらにコードを打ち込み、画面に現れる結果を見て、少しずつ理解できることを増やしていくといった内容で。半年かけてなんとか簡単なプログラムを提出し、晴れて配属となった先で、実務ではこんなに調べてもいいし、人に聞いてもいいんだ、そのことがこんなに幸せなことだったんだと知りました。今にして思えば、どんなバグを前にしても根性で解決し続ける忍耐力を養う研修だったのかもしれません」
配属先は原価管理システムの大規模開発チーム。モジュール化された管理会計の帳票出力部分などを担当し、ひたすらコードを書いた。言語はJavaとSQL。やればやるほどできることは増え、仕事は楽しかったが、3年も続けるうちにサーバサイドだけでなく、フロントエンドの技術も知りたいと思うようになった。2016年。世の中を見渡すと、SaaS市場が徐々に盛り上がりを見せていた。
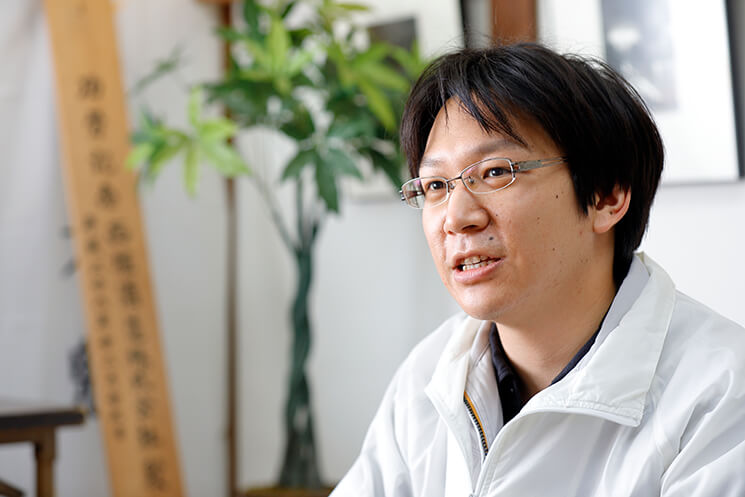
西堀さんは、独立し、個人事業主としてWebサイトの受託開発を始めることを決意する。レンタルサーバとCMSでできる簡単な仕事からスタートし、「ウイルスに感染したので駆除してほしい」といった細々した依頼も受けた。続けるうちにフロントのさまざまな技術を学び、加えてビジネススキルも自然と身に付いた。技術的には高度でなくても、組み合わせ次第で大きな価値を生み出せることもこの時期に学んだ。
しかしその年の冬、酒造りのピークの時期に実家の蔵人の一人が椎間板ヘルニアで酒造りを続けられなくなったという知らせが舞い込んだ。作業は3、4人で回しており、1人抜けるだけでもう回らなくなる。SOSを受けて、西堀さんは家業に戻ることを決めた。
「もともといずれは家業に入るつもりでいました。一度就職したのは、それゆえになおさら外の世界を知っておきたいと思ったから。どうせ戻るのであれば、現場の醸造の作業から入れるのはいいタイミングだな、と。製造にはノータッチというパターンもあり得たわけですが、イチ蔵人として全工程を見たい、現場を知りたいというのは、僕がこだわった部分でした。頭だけで理解しようとせず、手を動かすことを重んじるのは、最初に入ったワークスという会社の好きなところでもありました」
とはいえ、酒造りに関する知識はこの時点でゼロに等しい。「なぜこうするのか」「なぜ急ぐ必要があるのか」といったことはまったく分からないまま、指示される通りに忙しく手を動かし続けた。3月になり、ようやく最初のシーズンが終わったタイミングで、日本唯一の酒の研究機関である酒類総合研究所に研修に行き、そこで初めて理論的なことを学んで“答え合わせ”をした。まず飛び込んで手を動かし、徐々に世界への理解を深めていくやり方は、西堀さんの人生を貫く流儀のようだ。
非合理と向き合うための徹底した合理化

自ら設計した特注の透明タンクで発酵作業をする様子。世界初となる赤色LEDを照射した酒造りは世界から注目を集めた(写真は西堀酒造提供)
すべてを合理的に判断するエンジニアリングの世界とは対照的に、酒造りの世界は非合理の世界だった。当初は、目指す酒質から逆算するようにして要素分解していけば、ある種プログラミングのようにして理想の酒が作れるのではないかと考えていた西堀さん。だが、知れば知るほどそんなことは不可能だと分かった。
「各工程で起きていることが複雑すぎて何がどう影響しているのかが最新の研究でもよく分からない。蔵ごとに環境が違うから教科書通りにはいかないし、うちも含めた大半の酒蔵にとって1年に仕込めるのは100本に満たないから、ビッグデータ的なものも使えない。それどころか迷信や願掛けのようなものがまことしやかに信じられていて、職人の経験則任せなところが強い。でも、理論的には到底信じられないような経験則が、結果としてどんな理論よりもうまくいったりする。そんな不可解な世界でした」
だが、その非合理なところが面白いと西堀さんは思った。絶対にコピペできない、この蔵だけの酒を作れるということを意味するからだ。
酒造りの世界でも今では蔵元の世代交代が進み、オープンに情報を共有してみんなで業界の水準を上げていこうという機運が高まっているという(まるでオープンソースのようだ)。となると、技術や知識は大きな差別化要因にはならない。精米歩合を極限まで競うスペック競争の時代、モダンなラベルデザインでイメージ刷新を狙うデザインの時代を経て、次はストーリーの時代だとも言われる。だが、確たる答えはまだ出ていない。

個性を前面に出した西堀酒造の商品ラインナップ。後列左の『門外不出 純米大吟醸 CLEAR BREW』は、特注の透明タンク仕込みにより、酵母の自然な動きを阻害しない温度管理と櫂入れで柔らかな酒質を表現。前列右の『ILLUMINA(イルミナ)』は世界初となる赤色LED照射により発酵を促進し、ドライで酸味のきいた辛口に仕上げた
そんな環境下において西堀酒造が活路を見いだすのは、個性を前面に出した「自由闊達な酒造り」だ。一つのブランドに絞ってリソースを集中投下することが経営としては正しいと言われる中、西堀さんはその正反対に、あえてたくさんの実験的なブランドを立ち上げる多様な方向性を打ち出した。
西堀酒造は10年以上前から、商品化する予定もないのに古代米を使った酒を造り続けていた。六代目が戻る前からそういう「興味本位」の酒造りが許される自由な文化があったわけだが、西堀さんはその酒を一口飲んでみて「ここまで振り切った味になるのか」と衝撃を受けたのだという。
「これだけ幅広いバリエーションができるのが日本酒の世界なのであれば、造り手本意と言われようと、経営判断として正しくないと言われようと、面白そうなアイデアを思いついたらすぐに試してみるというような、そんな酒造りのできる蔵が良いのでは? と考えるようになりました」
日本で唯一となる、特注のアクリル製「透明タンク」にしろ、ご法度とされてきたLED照射を施した「光を使った酒造り」にしろ、西堀さんの常識を覆す挑戦は、非合理な世界であることを逆手に取った「個々のエネルギーの発揮」という文脈にある。
ところで、最初に酒造りがそんな非合理な世界だと知った時、実は「安心した」のだと西堀さんは振り返る。
話は哲学科時代からずっとつながっている。学部では西洋哲学の講義を受けたが、この世のすべてを記号的に記述しようとするなど、合理性に重きを置く西洋哲学特有の考え方は、理屈としては理解できるものの、現実との接続の部分に違和感が残り、机上の空論のように思えた。
西洋を代表する哲学者の一人であるウィトゲンシュタインも、当初はこの世のすべては論理的に記述できるものであるとして『論理哲学論考』を書き上げるが、その後のふとしたきっかけで記述しきれないものがあることに気付き、非合理の世界に足を踏み入れていく。あるいはゲーデルの不完全性定理が示すように、あれだけ完璧な学問に思える数学でさえ、根本から転覆されうる余地があるのだと知った。こうしたものに触れるにつれ、西堀さんは「世界はそもそも非合理なものであり、合理的なのはその一部分でしかないのでは」と思うようになった。非合理な酒造りの世界は、そのことを端的に示してくれていた。

西堀さん自作のもろみの遠隔温度管理システム。Raspberry Piで通信し、電磁弁の開閉により冷水の制御を行う。データはクラウドサーバ経由で逐次アップロード。スマホやPCで閲覧でき、必要に応じて設定温度を調整する
しかし、全体として世界は非合理だったとしても、一つ一つのプロセスを合理化することとは矛盾しない、と西堀さんは続ける。
「酒造りの世界にはアナログな部分がかなり残っており、いまだに温度管理が紙で、個人で行われていたりします。人力による米の計量作業や、発酵管理のための単純作業は深夜まで続き、疲弊してしまって、本当に必要な判断を妨げている部分もある。そうした非効率な部分を一つ一つシステムに置き換え、合理化を進めています。すべてを合理化することはできないですが、できるところは徹底して合理化する。そうすることで初めて、人間にしかできない部分、その人にしかできない仕事と向き合えるのではないかと思うんです」
エンジニアを辞めないのは主観と俯瞰を行き来したいから
「なにぶん零細企業なので、リッチなシステムをどんどん導入するといったことはできません。ですが、技術はものすごい勢いで進歩しており、数年前にはできなかったが今なら簡単にできるということがたくさんあります。単体で見れば技術的には大したことがなくても、うまく組み合わせると大幅に工数を削減できたりする。もろみの遠隔温度管理システムもそうやって、ありものの部品を組み合わせることで作りました。最近はPythonが流行りですが、こうしたものも、ちょっと調べればすぐに使える部品がたくさん転がっていますよね」
酒造りに軸足を置いた今も1割程度とはいえエンジニアリングの仕事を続けているのは、技術の進歩にキャッチアップし続けるためだ。そうした解決策が取れるかどうかは、単純に知っているか知らないかの違いだけ。最新の高度な技術を追い続けていればこそ、さまざまなソリューションの選択肢を持てる。
「一方で僕自身もかつてそうでしたが、エンジニアはしばしば技術的な高度さを追求して無用の長物を作ってしまう。本来は何か課題があったら、それを解決する手段としてエンジニアリングはあるはずなのに。その際には、技術的な高度さは必ずしも問題にはなりません」
エンジニア時代に細分化された「部分」の開発に終始していた時にはそのことに気付けなかったと、西堀さんは自戒を込めて振り返る。何かしら自分で事業をやると、解くべき課題ややりたいことがどんどん生まれる。そうすると、一方で追っていた技術を問題解決に存分に生かすことができる。これこそが二足のわらじを履くことの大きなメリットと言えるのかもしれない。
一つの業界、一つの企業、一つの技術だけを追っていると、どうしても視野が狭くなってしまう。酒造りの世界に“本籍”を移した今も、西堀さんはこうした意識の下に、業界外の人と積極的に交流するようにしている。そこから生まれたものの一つが、再生可能エネルギーを活用した酒造りの可能性を追求する『SAKE RE100』というプロジェクトだ。

日本酒造りのオフシーズンにはリキュールの製造にも取り組んでいる。スピリッツ製造の免許を取得済みで、試作したクラフトウオッカは上々の評価を受けた。海外市場を狙って半年以内にはリリースを予定。西堀酒造の挑戦は続く
「実は偶然という面も強いんですが、東京から栃木へと帰る新幹線で、同じ栃木に拠点を置くエネルギー業界の方とたまたま席が隣になって。いろいろとお話しさせていただく中でエネルギーという視点で見てみると、ビールやワインの業界には再生エネルギーを取り入れる流れがある一方、日本酒業界ではそんな話題さえ出ていなかった。であれば、僕らにもできることがあるかもしれないな、と」
活動の核にあるのはどこまでいっても日本酒の製造。だが、地場産の食品とのコラボレーションなど、そこから派生してできることの幅が広いのが日本酒のいいところだと西堀さんは考えている。内と外、主観と俯瞰を行き来することで、これからもビジネスとキャリアの可能性を広げていく。
取材・文/鈴木陸夫 撮影/竹井俊晴
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”
タグ
















