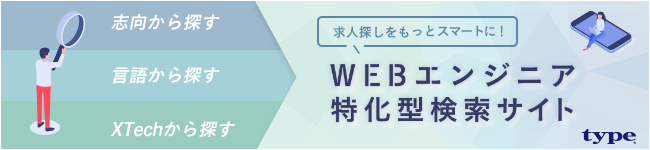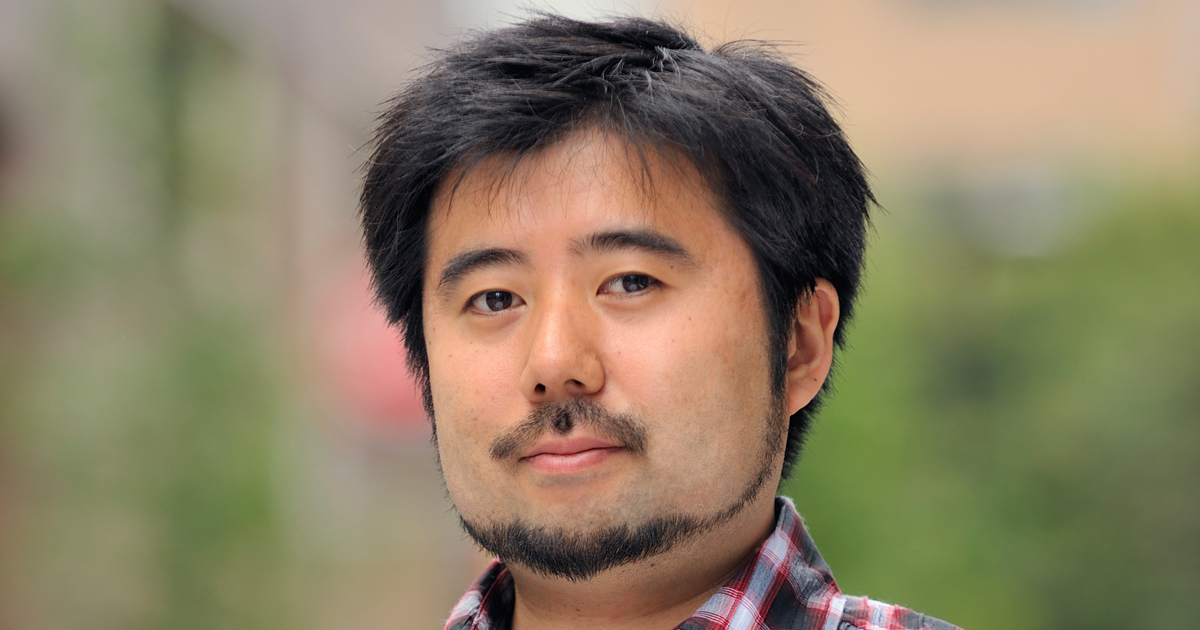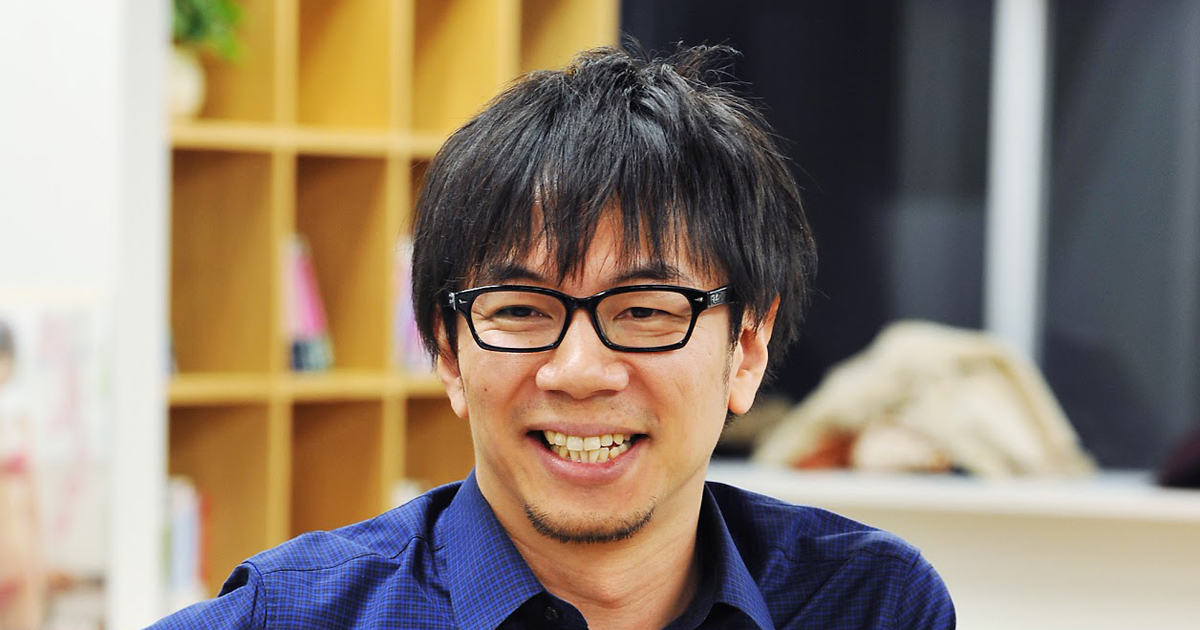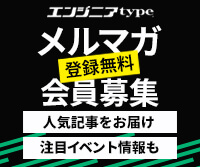日本でシェアリングエコノミーを普及させる3つのポイント~『Airbnb』や『Uber』が直面した課題に学ぶ
サービス・人材、プロダクトなど、有形無形のものを共有し、利用者が必要な時に利用してもらう「シェアリングエコノミー(共有型経済)」。
この新しいビジネス形態をとったサービスが、シリコンバレーを起点として、世界中に広まる兆しを見せている。
空き部屋を短期間貸し借りしたい人同士をマッチングする『Airbnb』、車の所有者が相乗りしたい人を募る『Lyft』などは、その代表格。スマホアプリを利用したオンデマンドタクシー配車サービス『Uber』も、広い意味でのシェアリングエコノミーに含まれる。

『Airbnb』や『Uber』は今年に入って日本展開を強化しており、国内のスタートアップ界隈でもシェアを前提としたサービスが徐々に目立ち始めた。
だが、人と人とがリアルな接点を持つこうしたサービスには、Web上で完結していた従来のサービスにはなかった、新たな課題もありそうだ。
サンフランシスコと東京を拠点とし、国内外のWebビジネスのトレンドに詳しいbtraxのCEO・Brandon K. Hill氏によれば、『Airbnb』の黎明期には利用者が借りた部屋を破壊してしまう事件が起き、サービス側が補償金制度を導入することになったという。
こういった事態が起こり得ることを踏まえて、これからシェアリングエコノミーのサービスを提供していこうとする人が注意すべきポイントは、次の3点に集約されるという。
ポイント1:互いに実名が大前提。透明性を確保せよ
1つ目のポイントは、透明性を確保することです。
人と人とがリアルに接するサービスの場合、匿名では成り立ちません。そのユーザーがどこの誰であるか、アイデンティティをクリアにしておく必要があります。
例えば『Airbnb』の場合は、プロフィールが実名であること、Facebookで共通の友人がいることなど利用の条件を設けることで、サービスの透明性を確保しています。
ポイント2:提供主だけでなくユーザーをも評価するシステムを導入せよ

『Uber』は、ドライバーとユーザーが相互に評価する仕組みを導入しており、ユーザーに関する評価は、ドライバー間で共有されています。
そのため、評判の悪いユーザーから配車のリクエストが来ても、ドライバーには反応しないという選択肢があるのです。すると、同じ場所にいたとしても、評判の良くないユーザーはいつまで経っても車が捕まらない、といった事態も起こり得るわけです。
このように、サービスを提供する側にも受ける側にも口コミで評判が広がる仕組みがあることが、リスクに対する抑止力になっています。
さらに、ドライバーは評価システムがあるために、いつでもスマホの充電ができるといった、ユーザーに喜んでもらうための方法を各自で考えるようになります。そのため、『Uber』は便利であること以上に、ドライバーの対応がいいということで評判になっているのです。
ポイント3:コミュニティーマネジャーを置け
ポイントの3つ目は、運営側の気遣い。具体的には、各地域を束ねるコミュニティーマネジャーを置くことです。
知らない人同士がネットを通じてつながっていくシェアリングエコノミーのサービスは、利用時にどうしても不安がつきまといます。実際、私が初めて『Airbnb』を利用した時も、部屋の貸し手の人から、プロフィールなどについて、かなり詳しく尋ねられました。
そうした不安を少しでも緩和するために、『Airbnb』は地域ごとのオフ会を開催しています。運営側がその地域を見てケアしているということをユーザーに体感させ、安心させるのです。
『Uber』もやはりコミュニティーマネジャーを置いていて、「社員の半数以上は本社にいない」と言われています。
しかし、普及には日本ならではのハードルも……
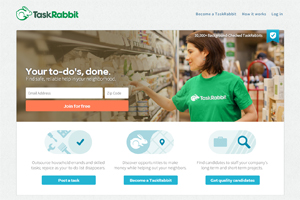
「とはいえ、シェアリングエコノミーは人の善意を前提としたものであり、100%安全ということはあり得ません。サンフランシスコはもともとヒッピー発祥の地でもあり、善意性が高く、シェアリングエコノミーが受け入れられやすい土壌だった、という背景があります」
そのため、シェアリングエコノミーが文化的背景の違う日本で普及するには、米国とは異なるハードルがあるというのがBrandon氏の考えだ。
「シェアリングエコノミーには、日本に古くからある近所付き合い的な側面があり、一見すると日本でも受け入れられやすそうな印象を受けます。しかし、日本人は知り合いとそうでない人とで接し方に大きな差があるので、知らない人と気軽にコミュニケーションを取ることが求められるサービスは、すんなりと受け入れられない可能性もあります」
引越しなどのちょっとした人手が欲しい時に、30分、1時間単位で労働力を売買できる『TaskRabbit』は、米国で急速に利用を伸ばしているシェアリングエコノミーのサービス。日本にもかつて同様のサービスがあったが、やはり受け入れられなかったという経緯がある。
両国の文化の違いは、トラブルが発生した時の世間の反応という形でも如実に表れると、Brandon氏は言う。
「アメリカでは、何か問題が起きても、基本的にはプラットフォームが責められることはありません。そういったものはインフラであって、問題の本質ではないという認識が共有されているからです。日本だと、ユーザー同士のトラブルであっても、『ネットが悪い』『サービス提供主が悪い』といった議論になりやすい気がします」
シェアは人間の本能 リスクに目を向けるよりチャレンジを

このあたりの課題について、すでに日本でシェアリングエコノミーのサービスを展開している企業は、どのように考えているのだろうか。
『スペースマーケット』は、映画館やお寺、野球場といった遊休スペースを貸し借りできる、BtoB向けシェアリングエコノミーのスタートアップ。2014年4月にサービスを立ち上げたばかりだが、順調に利用を伸ばしている。
法人同士が社名を明かして契約を交わすサービスであるため、この2カ月、オーナーとユーザーの間で大きなトラブルが発生したことはない。
だが、「中には交渉を中断して、オーナーと直接値引き交渉をする『中抜き』を図った企業もありました」(代表取締役の重松大輔氏)とのこと。ユーザーのモラルをどう担保するかは、BtoBにおいても無視できない課題だ。
ほかにも、お寺やギャラリーのオーナーは必ずしもITに明るいとは限らないため、問い合わせに対するレスポンスの悪さが原因で、契約が流れてしまうといった難しさもあるという。
「今後、サービスがさらに拡大すれば想定外のトラブルも出てくると思うので、いずれはオーナー、ユーザー双方に保険に入ってもらえるような体制にしていきたい」と話す重松氏は、同時に「日本人はネガティブな面に目を向けがちですが、リスクは仕組みで解決できる」と続ける。
「無駄遣いをしない、必要に応じて助け合うというシェアの考え方は人間の本能的なものだと思うので、日本に足りない部分は都度補いつつ、サービスを伸ばしていきたい」(重松氏)
ソーシャルゲームが課金方法についての整備を行い、LINEは出会い系として悪用されないようアカウント認証方法に制限を採り入れるなど、急成長するサービスはどれも「健全に使われる仕組みづくり」に力を入れてきた。
シェアリングエコノミーのサービスも、利用率の向上と合わせて、Brandon氏が挙げたポイントを加味しながら安心感の醸成に注力していく必要があるといえる。
取材・文/鈴木陸夫(編集部)
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング
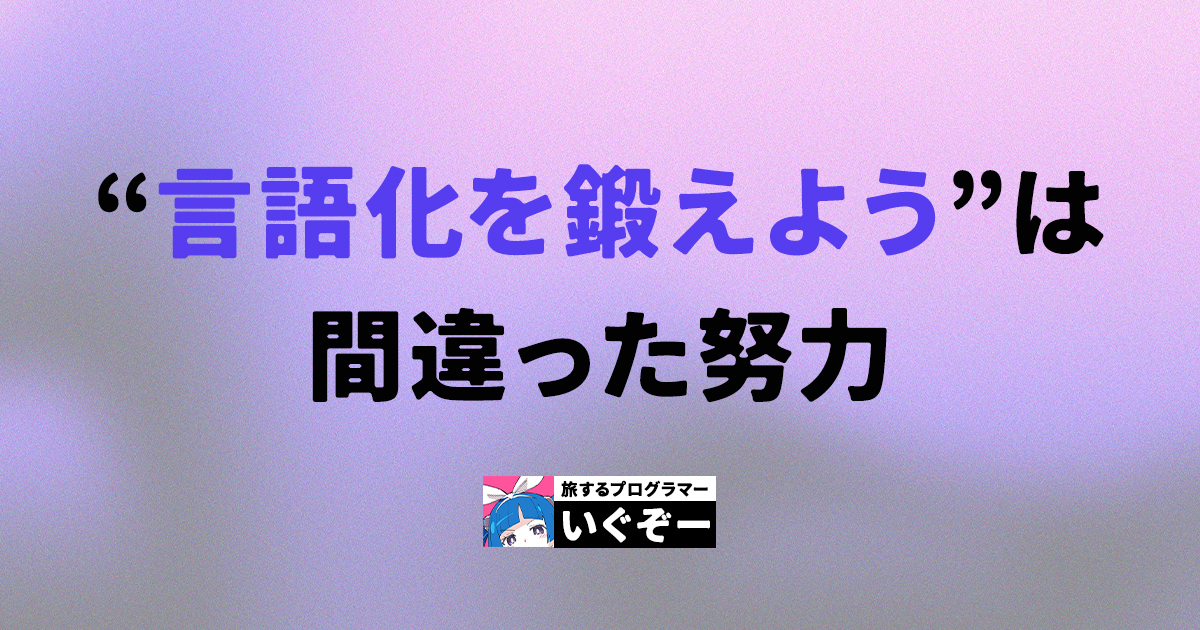
エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?
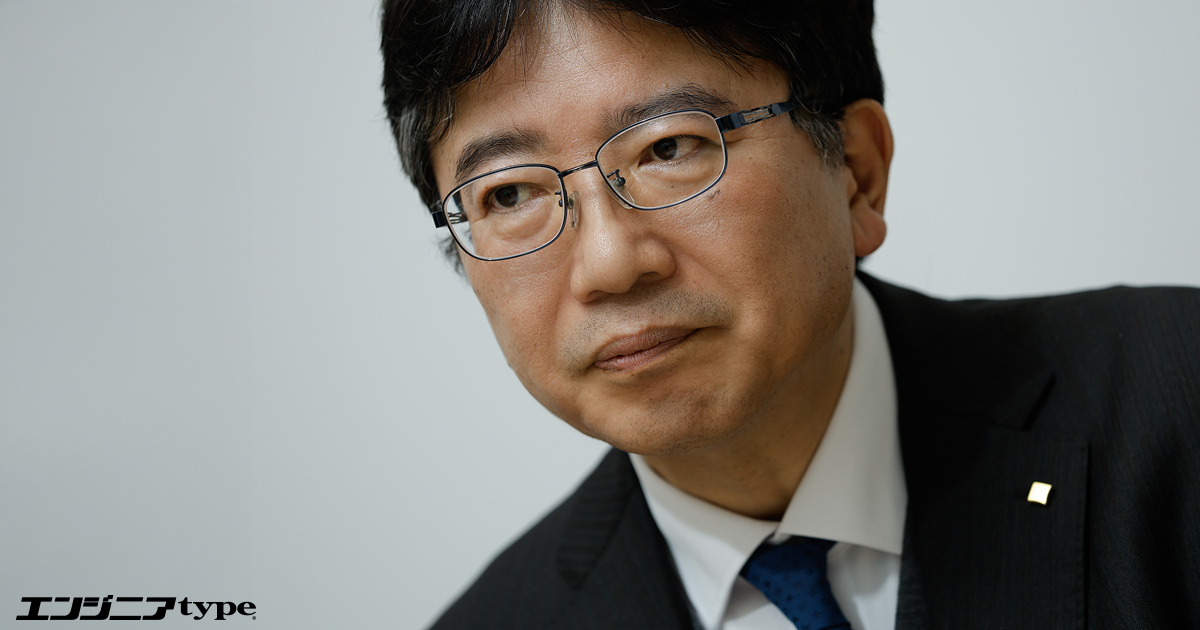
AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”
タグ