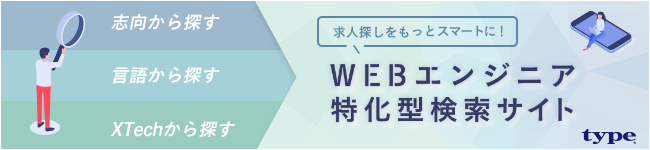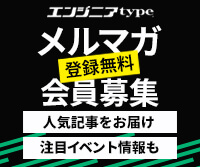【不足するAI人材、その実態とは?】LINEのリサーチラボで働くAIリサーチャーの知られざる働き方
今、世界で注目を集めるAI人材。経済産業省では、「AIやIoTなどを担う先端IT人材が2020年に48,000人不足する」という見通しを公開。特に国が危機感を示したのは、「最先端AIの研究・開発を進める人材の不足」だ。
そんな中、LINE株式会社では、AI関連技術の研究部門として「Research Labs」を2018年に設立。AI領域の基礎研究の発展に寄与することを目的としたこの組織には、現在5名の研究者が社員として所属しているという。
そのうちの一人が、AIリサーチャーの髙橋翼さん(34)だ。国内大手電気メーカーに在籍していた前職時代は、自身の研究で事業に貢献。転職後は「Research Labs」の立ち上げに参画し、現在はAI技術を扱う際のプライバシー保護についての研究に取り組んでいる。
日本ではまだ珍しい、企業に在籍しながら“研究に専念する”AIリサーチャーの働き方をご紹介しよう。

LINE株式会社
リサーチャー
髙橋 翼さん
1985年生まれ。木更津高専卒業後、現・筑波大学情報学群情報科学類に編入。卒業後に同大学院システム情報工学研究科博士前期課程を卒業。働きながら博士号を取得。2010年NECに入社し、研究所にて医療データや位置情報の匿名化に関する研究に従事。在社中にカーネギーメロン大学に滞在し、時系列データにおける異常検知技術の研究に携わる。18年12月にLINE株式会社入社。Research Labsに所属し、AI技術を扱う際のプライバシー保護について研究を続ける
“企業で働く研究者”だからこそ得られる醍醐味がある
学生時代にはソーシャルネットワークのデータマイニングの研究をしていました。当時はちょうどTwitterがブームになり始めた頃で、誰と誰がフォローし合っているのかなどを解析して、重要人物やフォローすべきアカウントをレコメンドする技術などを研究していたんです。その研究の中でデータ解析におけるプライバシーに興味を持ちました。
大学を出た後も、AIが価値を発揮できるような技術の研究を続けたいと思い、研究職の仕事を選びました。
社会で起こっているリアルな課題をテーマに研究できると考えたからです。企業が直面しているデータセキュリティーの課題を知ることもできるでしょうし、その解決方法を現場の営業やシステム担当者たちと真剣に議論できることも面白そうだと思いました。それに、自分の研究が事業化されるチャンスがあることも魅力的でした。
データベースを匿名化する研究です。統計学やデータ工学などの技術をベースとして、パーソナルデータを個人が特定できないように加工する仕組みについて考えてきました。
その研究に5年ほど取り組んだ後、自分の研究がコア技術の一つとして事業化されることに。当時は、営業担当と一緒にクライアント企業へ足を運んだり、実証実験のために大学病院へ出向いたりして、実際の医療データの匿名化に取り組むこともありました。研究テーマが事業化されたことは大きな達成感がありましたし、社会に貢献できてとてもうれしかったですね。
LINEの「Research Labs」で研究者としてキャリアアップを目指す
「基礎研究に力を入れたい」という気持ちが大きくなったことがきっかけです。AI技術の発展によって、AI特有のセキュリティ・プライバシーの問題があることが分かり、強い興味を持ちました。まだまだ基礎的な研究が必要な領域なので、応用への意識が強い前職とはベクトルがずれてしまっていると感じていたんです。一方で、リアルな課題の近くにいたいという想いもあって、企業で基礎研究ができないかと考えていました。

また、研究者としてキャリアアップをしていくのであれば、より多くの論文を書き、国際学会などでも発表、論文採択数を増やしていく必要がありました。そこで、自分の研究に専念し、論文執筆に集中できる環境で働けないかと真剣に検討を始めたのです。
その頃、LINEから基礎研究を主とした「Research Labs」を立ち上げるというお話を伺いました。いまの時代、企業が基礎研究のみにフォーカスした研究所を立ち上げるのはとても珍しいことだったので、すごく興味が湧きました。実際、基礎研究に没頭できる日本企業の研究所はほとんどないんです。
そして、研究所の立ち上げから関われるというのも魅力に感じて。自分にとってはすごくチャレンジングなことでしたし、日本の科学技術の発展にも寄与できると思うとすごくワクワクしましたね。いまここでLINEの「Research Labs」にジョインすることは、これからの自分のキャリアにとってベストな選択だと感じました。
実際に入社してみて、望んでいたとおり基礎研究に集中できています。将来的に研究結果を事業化する場合でも、サービスや開発のノウハウを持っているエンジニアを支援する形が取れればと思っています。
現在は国際学会における論文採択数で評価されることになっています。LINEの事業から完全に独立した研究部門なので、研究の仕方は大学の研究員に近いですね。
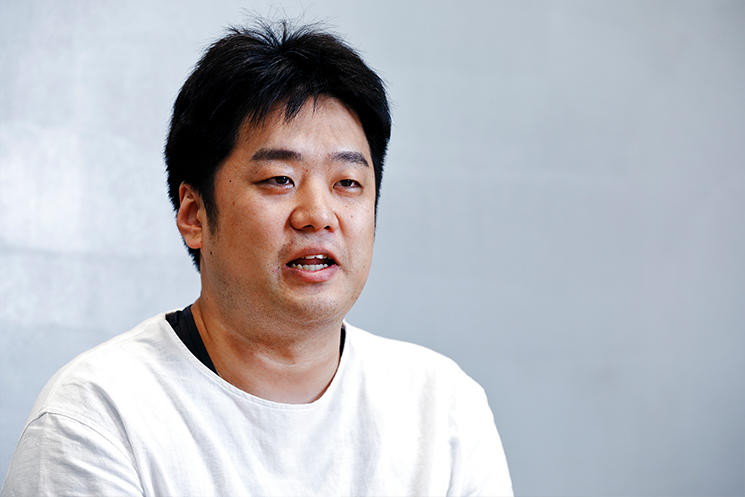
先ほど挙げた「AI特有のセキュリティ・プライバシー」の研究に取り組んでいます。AIの挙動から学習に使ったデータが推測されるリスクが知られています。統計学やデータ工学、暗号学に基づいてこのリスクを低減する研究、例えば、データ収集時にノイズを紛れ込ませて安全性を高める研究、そして、プライバシーを保護しながらAIをシェアする研究などが中心です。
そうです。集中しやすい職場環境で柔軟性の高い働き方ができています。いまは3~4カ月毎に国際会議に論文を投稿することができています。
いまはAIのニーズが世界各国で急激に高まっていることもあり、どの研究者も我先にと論文を発表しています。私もより多くの論文を書きたいとは思っていますが、実際のところ、論文が採択されるには高いハードルがあり、狭き門。諦めずに論文を出し続ける忍耐が必要ですね。
グローバルで活躍する研究者たちと対等に渡り合いたい
AIは、ほんの少し前まではSF映画の中の出来事でした。しかし、自動運転やロボット、人工知能と会話できるようになるなど、テクノロジーが具現化する様子を間近で見られるのはこの仕事の醍醐味です。LINEでは国内有数のエンジニアがプロダクトを開発しているので、そのプロセスを見られるのも面白さですね。
社内での役割が明確なので、バックオフィス業務などに忙殺されることもなく、研究者にとっては至れり尽くせりかもしれません。心身ともに余裕を持って取り組めるので、新しい研究のアイデアも浮かびやすいです。

「お風呂に入っているときや、寝る前にアルゴリズムが降りてくることも多いです(笑)」
もし自分の研究が世に出ることがあるなら、LINEというプラットフォームを存分に使って世界に発信できるという期待も大きいですね。
先日はサイバーエージェント主催の『CCSE(企業研究所カンファレンス)』というイベントに、LINEからは私も含めて3名の研究者が登壇しました。楽天やジャパンタクシーなど最先端の研究を手掛けている他社の研究者と交流できるのは、この仕事の面白さだと思います。
今後は、継続的に論文を書き、自分の研究者としてのキャリアアップを図っていくこともそうですが、LINEの知名度を上げるような研究成果も出していきたいです。自分の代名詞となるような論文を執筆し、いつか事業にも活用されるような研究ができたらいいなと。グローバルで活躍する研究者と対等に戦えるような論文を書き、それが採択されるように今後も精進していきます。
取材・文/石川 香苗子 撮影/竹井俊晴
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

「便利なものを作ったら負け」OSS界の巨人・mattnが語る、アウトプットの心理的ハードルとの付き合い方

Metaの精鋭エンジニアたちが「設計の最適解」を導くために頼る一冊。世界規模の開発を支えるシステム設計のバイブル

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側
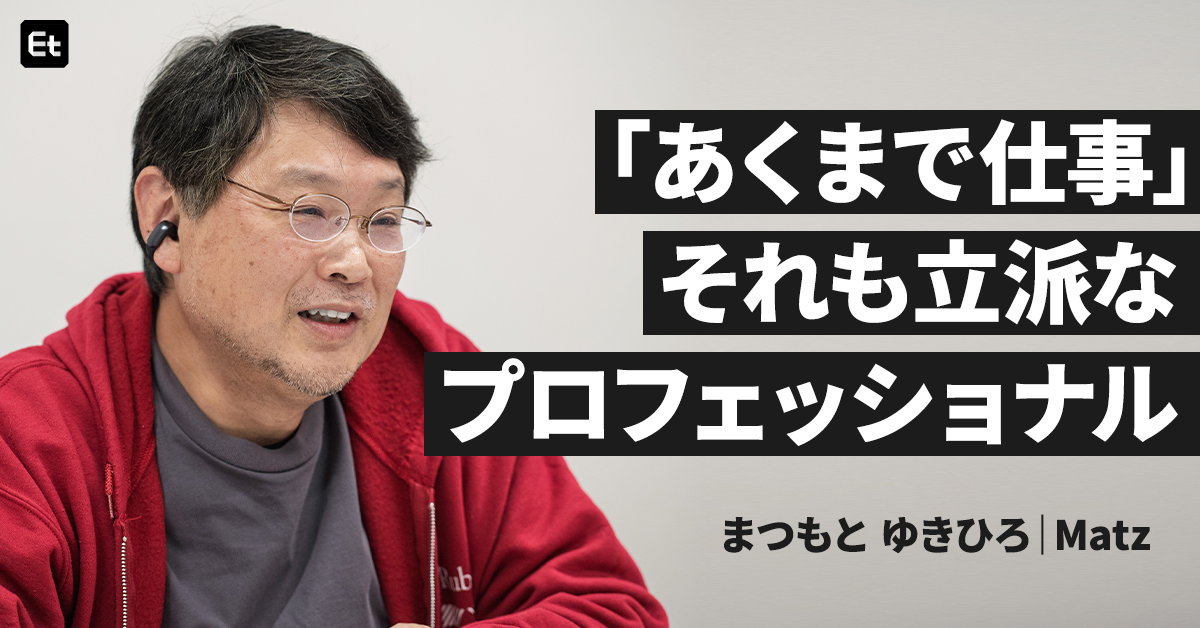
「休日もコードを書け」は正義か? Ruby父 まつもとゆきひろが肯定する“仕事と割り切る”エンジニアの在り方

「ホワイトハッカーとして育てろはナンセンス」徳丸浩が斬る、未成年不正アクセス事件への“誤解”
タグ