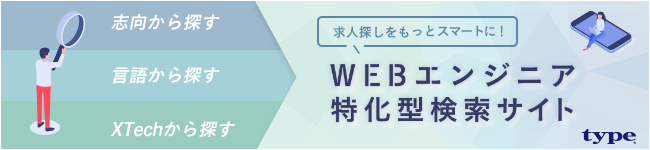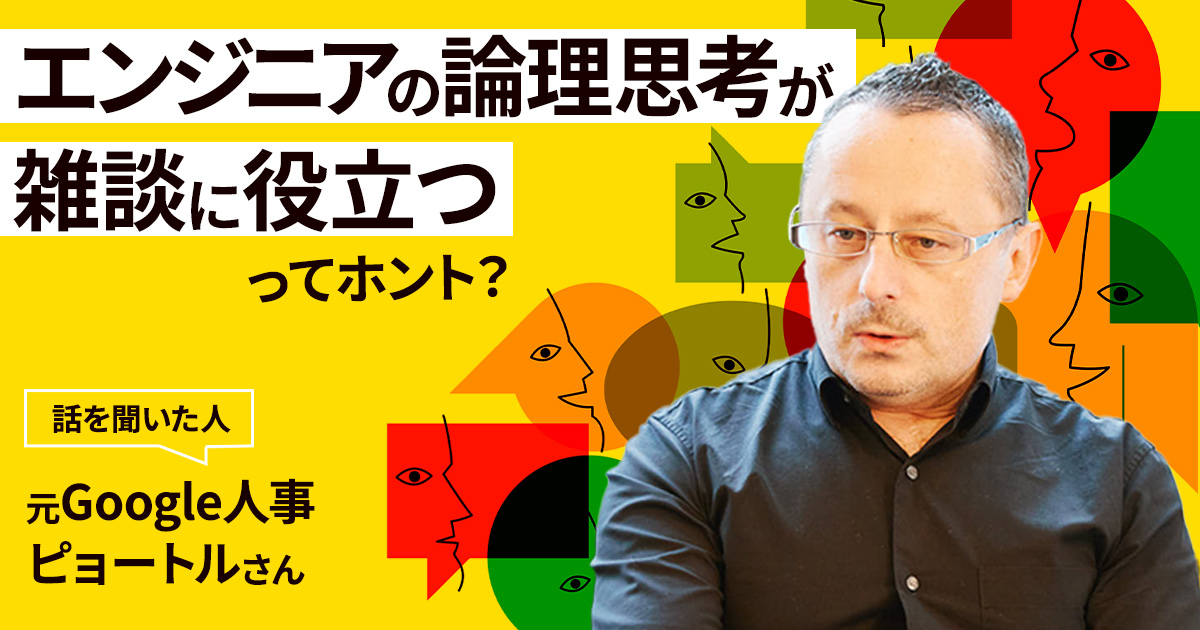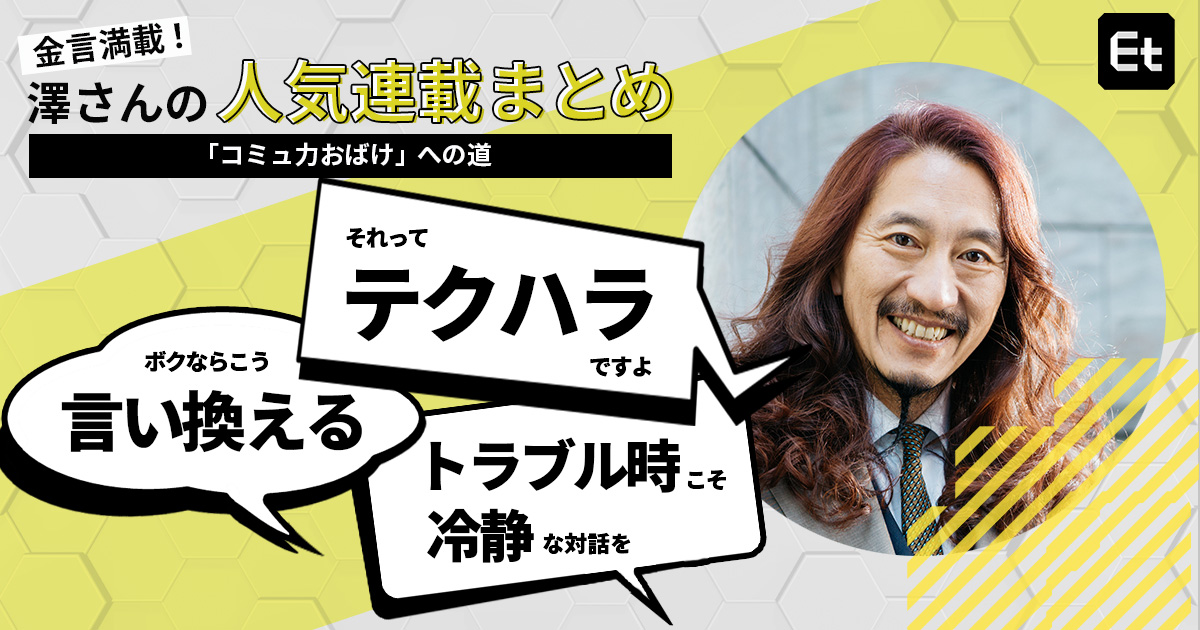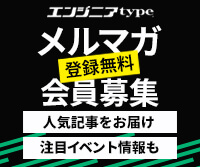「プロジェクトの途中でトラブルがよく起こる」「自分の説明が伝わっていない気がする」そんな“技術以外”の課題の背景にあるのは、ひょっとして「コミュニケーション」の問題かもしれない。プレゼンの神・澤円が自身の経験やノウハウをもとに、仕事がスムーズに進むコミュニケーションのヒントを伝授!

「本心が分からない」「多くを語らない」そんな相手との対話に役立つ五つのケーススタディー【澤円「コミュ力おばけ」への道】

株式会社圓窓 代表取締役
澤 円(@madoka510)
立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフトに転職、2020年8月に退職し、現在に至る。プレゼンテーションに関する講演多数。武蔵野大学専任教員。数多くのベンチャー企業の顧問を務める。 著書:『外資系エリートのシンプルな伝え方』(中経出版)/『伝説マネジャーの 世界No.1プレゼン術』(ダイヤモンド社)/『未来を創るプレゼン 最高の「表現力」と「伝え方」』(プレジデント社)/『「疑う」から始める。これからの時代を生き抜く思考・行動の源泉』(アスコム社)/『「やめる」という選択』(日経BP社) Voicyチャンネル:澤円の深夜の福音ラジオ オンラインサロン:自分コンテンツ化 プロジェクトルーム
皆さんこんにちは、澤です。
仕事をしていると、誰かとコミュニケーションをしなくちゃいけない場面は避けられません。これは、エンジニアであっても不可避といっていいでしょう。
ただ、会話が得意ではない人とのコミュニケーションは、なかなか大変だったりしますよね。
相手の考えていることをいまいち聞き出せなかったり、こちらが伝えていることが受け取られているかどうかが確認できなかったりすると、結構しんどいものです。
1on1で会話が全然弾まなかったり、会議で発言を促しても「特に何もありません」と塩対応だったり…….。やたらと強い言葉で攻撃してくるタイプの人とは、また違ったストレスを感じることもありますよね。
そんな状況とどう向き合うのかを考えてみます。
活発なコミュニケーションだけが正解ではない
まず、大前提として「相手が話し下手で会話がうまく成立しない」という事象に対して、「良くないことである」と考える必要はないと思っています。
世の中、「活発なコミュニケーションこそが正義」みたいな状態になっていますけど、ボクは特にそう思っていなかったりします。
エンジニアとして職場で活躍するスタイルは、いろいろなタイプがあっていいでしょう。みんなでワイワイ仲良く話すことだけが正義ではないのです。
正論をぶちかますならば、人にはそれぞれコミュニケーションに対する考え方や価値感が存在していて、全て尊重されていいと思っています。
ボクは、外見はまぁまぁ派手に見えるかもしれませんが、実は相当内向的で、あまり人と話をするのが得意だという意識はありません。むしろ超ぼっち好きで、できれば人と話さずに過ごせる方が気楽だとさえ思っています。
そんな人間なので、「会話をするのが苦手」「うまく話すことができないのがコンプレックス」という人の気持ちは理解できる方だと自覚しています。
「あんた、プレゼンでメシ食っとるやんか」という方もおられるでしょう。
でも実は、ボクは「人と会話をするのが好きだからプレゼンをしている」という訳ではありません。むしろ、「プレゼンをしている間は会話しなくてもいいのが楽」という側面もあります。
この辺りのメカニズムを知ることが、会話下手の人とコミュニケーションを取る上で参考になるかもしれませんね。

五つのケースから考える、無口な方との向き合い方
「会話が下手」だと他人から見られる人の内側がどうなっているかは、その本人にしか分からなかったり、あるいは本人にも分からなかったりするかもしれません。「他者との間のインターフェースの情報量が少ない」という事実だけが認識できているわけです。
でも、それは問題ではないと思うのです。
「会話がうまく進まないことによって引き起こされていることが何なのか」によって、問題なのかどうなのかを測る必要があります。
例えば、Aさんという方が「無口で会話がなかなか成立しない人」と周囲から思われているとしましょう。
では、問題はなんなのか。
いくつかケースを考えてみましょう。
【1】 Aさんの得意分野・不得意分野が分からない
本来これって、採用時や育成時期にマネジャーが把握しておかなくちゃいけない部分ですね。とはいえ、進化スピードの速いこのご時世において、1年前のスキルシートなんて役に立たないかもしれません。
これは、会話をしなくてもいいような入力フォームを用意して、締め切りを作って書いてもらうことで「会話をせずにデータ化する」というアプローチがいいでしょう。
ChatGPTに「ITエンジニアの得意分野を知るための質問項目を挙げてみてください」というめちゃくちゃ大雑把な質問をしたら、たくさんの質問項目を作ってくれました。生成AIの助けを借りて、フォームを作ると面白いかもしれません。
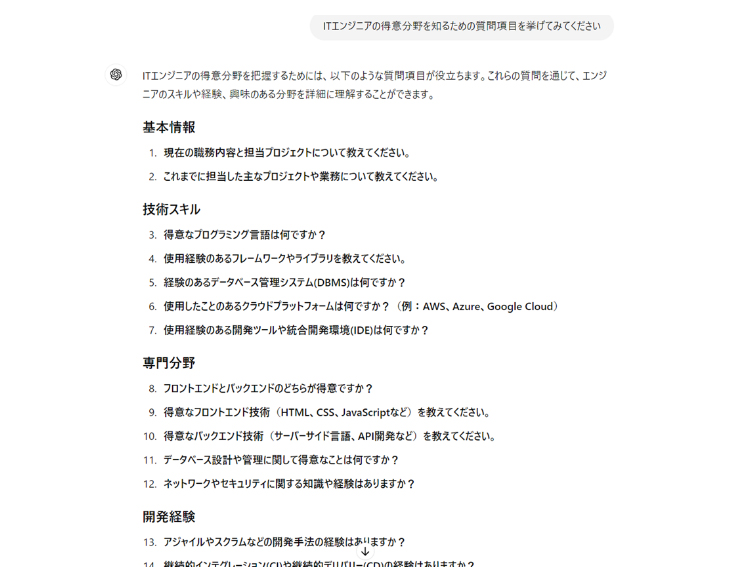
【2】 Aさんが担当している開発領域の進捗が分からない
これも、データ化するのが基本ですね。「見りゃすぐ分かる」状態を作るためにも、プロジェクト管理ツールの活用は不可欠でしょう。
「進捗管理のためにタスクを増やす」ことはできるだけ避けたいものですし、それを会話でカバーしようとするのは時間の無駄と考えるエンジニアも少なくないはずです。
「進捗管理は自動化が基本」という観点で見直す必要がありそうです。
【3】 Aさんの将来のキャリア展望が分からない
マネジャーはメンバーのキャリアについて考えるのも仕事。
でも、1on1であまり口を開いてくれなかったら、キャリアについて聞き出すことができないという状態になるかもしれません。
そういうときは、普段から観察を心掛けるしかないですね。
「普段職場で最も多く言葉を交わしている人はいるか? いればその人は誰か?」その辺りをなんとなく観察しておくのが、必要なアクションになります。そして、人間関係を把握した上で、会話している相手からそれとなく聞き出してみるのもいいかもしれません。
例えば、Bさんとはよく会話していることが分かったとしましょう。
ただ、Bさんに「ねぇねぇ、Aさんが全然口きいてくれないんだけど、Aさんについて教えてくれない?」みたいに正面突破を試みると、警戒されちゃう可能性もあります。
そこで効果的なのは「ポジティブ陰口」のアプローチ。
「Aさんのプログラミングは完成度も高いし緻密にやってくれるし、とても助かってるんだよね~~。将来はもっとこの分野で活躍しようとか思ってるのかなぁ……?」と世間話の体で聞くのもアリです。
これは、完全に個別戦略。じっくり観察してアプローチを決めましょう。
【4】Aさんが困っているかどうかが分からない
実はマネジメントしていく上で最も問題になるのはここですね。何かしらのトラブルに見舞われているとき、助けを求めようとしないというのは、後で取り返しがつかなくなるリスクがあります。
マネジャーやチームメンバーは、困った人をサポートするのも大事な仕事です。ただ、それを表面に出さないと、助けようがないのも事実。
そこで大事なのは「【2】Aさんが担当している開発領域の進捗が分からない」の内容です。
困っていることの有無は、進捗に現れることがあります。進捗が遅れがちなら、何かしらネガティブな要因がありそうです。進捗の遅れを追究するのではなく、そのデータをもとに「何か助けられることはないか?」と会話するのが大事です。
もちろん「いえ、特にないです」と答えるかもしれません。そうなったら、残念ですけどこれは本人の意思として尊重するしかありません。
しかし、進捗が遅れているということは、評価に反映させることが必要です。「助けますよ」というメッセージを出しつつ、評価はフェアに行うというバランスが求められます。
【5】 Aさんのプライベートが分からない
うーん……。これは、踏み込むかどうかはめちゃくちゃ悩むところですね……。
実は、ボク自身メンバーがずっとプライベートの問題を隠し続けてしまい、さらに大きな問題に発展してしまった経験があります。
ただ、その時にもっとプライベートまで含めて踏み込んでコミュニケーションした方が良かったのかどうかは、今でも答えを持っていないのが事実です。
そのメンバーは、「澤には心配をかけたくない」という強い意思を持っていたと、後で知りました。これは本人の覚悟だったんだろうな、と思うことにしています。
「プライベートを明かすかどうかは本人次第」と考えるのが一番良いのではないか、というのが今のボクの結論です。
さて、今回は口下手なメンバーとのコミュニケーションについて考えてみました。
最も重要なことは「相手を変えようとしない」「自分の行動だけを変える」。
これに尽きるということを、最後にお伝えしておきます。

2023年10月19日に澤の新著が出版されました!
自分自身をメタ認知するための考え方について書いた本です。
ぜひ手に取ってみてください。
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング
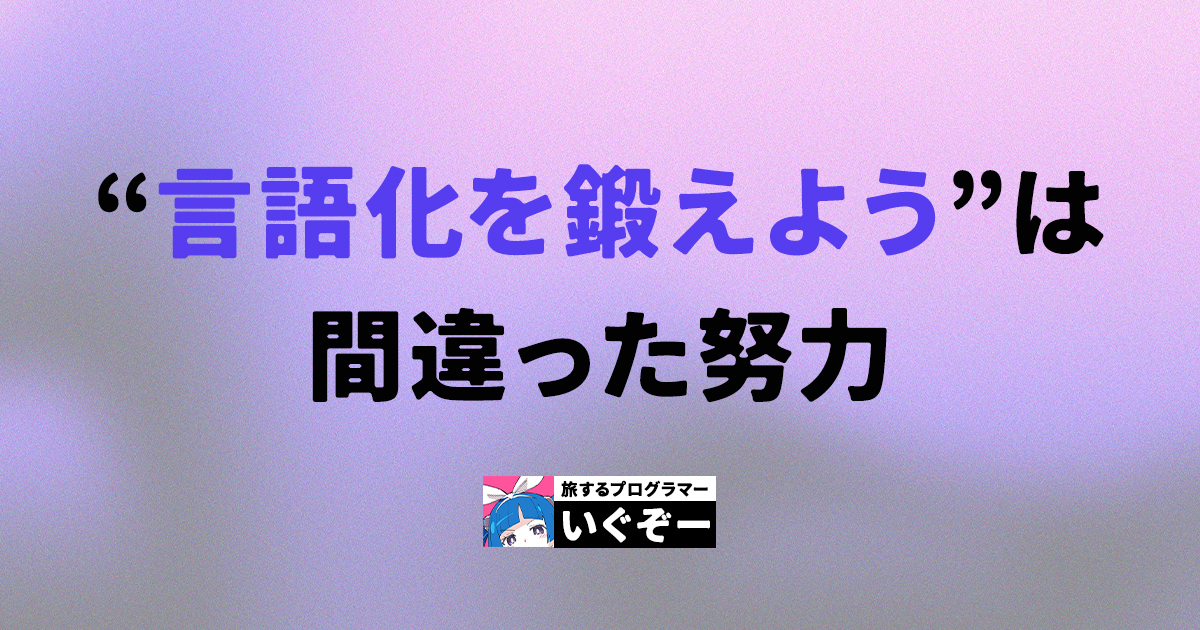
エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?
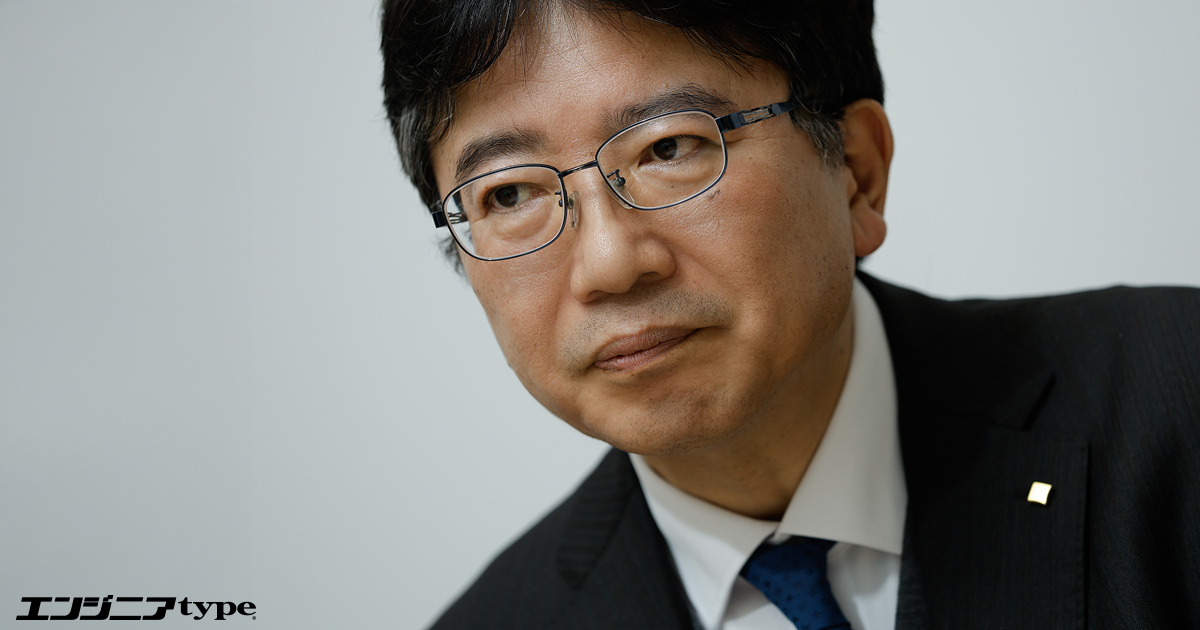
AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”
タグ