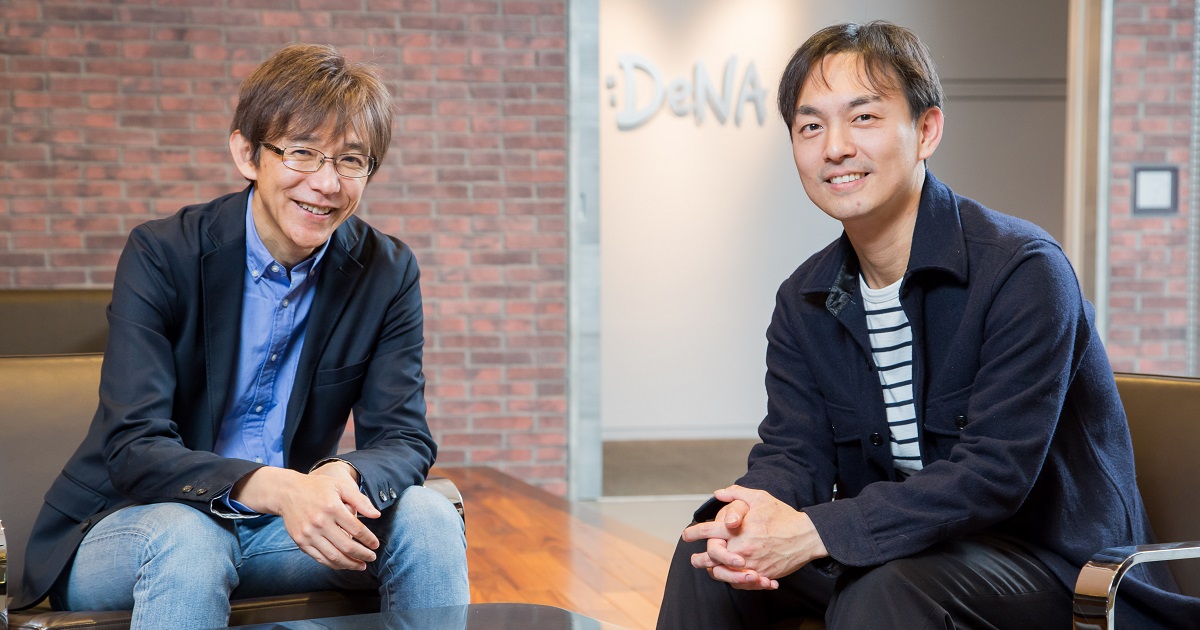話題沸騰のARアプリ企画『ドラえもんの動くぬりえ』を生んだ、1年前の教訓「ただ立つだけを超えたかった」
自分でぬりえをしたドラえもんが、そのままの色で3D化して動き回る。ARを駆使した江崎グリコの『動くぬりえ』が話題だ。
必要なのはポッキーやプリッツなど、人気商品に付属するぬりえの台紙と、無料のiOS/Androidアプリ『グリコぬりえ』。オリジナルの色に塗られたドラえもんが動くその様子は、スクリーンショットを撮影して簡単にSNSなどにシェアできる。
7月1日の発売から3週間で30万DLを突破。さらに、各ユーザーが彩色した独創的なドラえもんの写真が複数のネット記事で取り上げられるなど好調のようだ。
開発を担当したのは、マーケティングソリューション企業のファースト。実は1年前にも江崎グリコとコラボし、ARを用いたキャンペーンを行った実績がある。
「昨年も評価をいただきましたが、AR自体も進化したので、より楽しめる内容を目指しました。昨年の経験を生かして、今回の企画はさらに盛り上げたい、という意気込みがあった」
そう語るのは、ファーストの開発リーダー田原朋子さんだ。1年前の「経験」とは? そして、そこからどう進化させたのか? 『動くぬりえ』開発裏話から、技術と表現の適切な関係を探る。
ストーリー性とインタラクティブ性を追求

(写真左から)ファーストの開発リーダー田原朋子さん、江崎グリコのチョコレートマーケティング部永島延浩氏
『動くぬりえ』は、菓子・アイス・加工食品等のカテゴリーやブランドを横断して毎年夏に行うオールグリコキャンペーン企画の一環として生まれたもの。ぬりえだけでなくARにまで触手を伸ばした狙いについて、江崎グリコのチョコレートマーケティング部永島延浩氏はこう語る。
「グリコグループの各商品には子供から大人までさまざまなターゲットを設定していますが、実際に購入する人となると、食品という特性もあり、30~40代主婦層が中心です。そうした大人の方々が自ら買いたい!と思えるような企画にすることが狙いでした。その中で、今年タイアップした3DCG映画『STAND BY ME ドラえもん』の持つ近未来感との相性、複数のブランドにまたがる象徴的な企画としての存在感、そして大人も楽しめるエンターテインメントとして、ARがふさわしいのではと考えていました」(永島氏)
後は具体的なコンテンツに落としこむだけ。企画を考える際に、2013年の反省が活かされることになる。
「昨年は、ARマーカーにスマホをかざすと3Dモデリングされたキャラクターが立ち上がる、といったアプリを作りました。クリエイティブチェックの時にはコンテンツホルダーからも『いい出来だ』と言われていました。しかし、キャラクターの動きがワンパターンだとユーザーは見るだけしかできない。加えてシェアする写真も同じような見た目になるので、飽きられるのが早かったんです。結果、シェア数もDL数もその時は評価されましたが、まだまだ満足のいくものではありませんでした」(田原さん)
この時の経験と教訓は、『動くぬりえ』においてストーリー性、インタラクティブ性を重視するという形で盛り込まれた。

『動くぬりえ』は9品のパッケージ、5種類のストーリーで遊ぶことができる。
「まずは、表示されるキャラクターに深みを持たせるためにストーリー性を持たせること。前回はただ立っているだけでしたが、今回は短い5つのストーリーに沿ってキャラが動きます。そうすることでシェアする時の写真にレパートリーが出る。
それから、インタラクティブ性という意味でぬりえは最強のツール。親しみのある遊びをさらに拡張させる仕掛けで、ユーザーも参加するハードルが下がったのでは、と考えています」(田原さん)
立つだけでなく動く、見せるだけでなく参加させる。『動くぬりえ』という名の通り、ストーリー性とインタラクティブ性をシンプルに愚直に追求した結果が今回の成功へとつながった。
エンジニアが表現を理解すれば強い
ブラッシュアップした企画を実現するには、当然技術も伴わなければならない。特に今回はお菓子のおまけということで、コストを抑えることが至上命題でもあった。
「まず『色をぬった画像を3Dモデルで立たせ、ワンタッチで動かす』技術を持った会社を探しました。AR技術は実用化されてから時間が立ち、多くの開発会社が実績を上げてきている。技術をゼロから開発しなくても既に持っている技術を流用すればコストは抑えられるのです」(田原さん)
展示会へ積極的に足を運び、個性的なアプリを開発する会社へのヒアリングを重ねることで理想の開発会社を見つけた田原さん。そんな田原さんの経験には、開発会社が「技術の売り込み」を効果的に行うヒントが隠されていた。
「AR技術のみならず、ニッチな技術を持っている会社はどのようにその技術を売り込んでいいか分からない人も多いはず。大事なのはただ技術を紹介するだけでなく、その技術を使ってどのようなコンテンツができるかの可能性を持っているかです。そのマッチングをコーディネートし、企業の要望にあったコンテンツをプロデュースするのが弊社の強みです。独自性のある技術をもった会社にはどんどんアピールしていただき、新たな可能性を一緒に探したい、と考えています」(田原さん)

新技術の「開発」ではなく既存技術の「応用」でコストを抑られたと話す田原さん。
すでに実用可能な技術を持つ会社と手を組むことでコストを抑えることに成功した開発陣。しかし、越えなければならないハードルがもう1つあったという。それは、国民的キャラクターを扱うがゆえの宿命だった。
「みんなが知っているキャラクターだけに、ぬりえから立体になるモデリングに対してはこだわりました。結果的には、かわいいドラえもんのモデリングが再現でき、子供から大人まで楽しめるアプリになりました。技術開発に時間を掛けずにモデリングに時間を掛けたことも功を奏しました」(田原さん)
失敗を糧に企画面、技術面のブラッシュアップを行い、ARコンテンツの成功例となった『動くぬりえ』。今後のARコンテンツの展望について聞いた。
「画面をかざすと何かが出てくるだけで驚かれる段階は終わっています。技術的には『Live AR』といった屋外やリアルタイムでの3D表示や巨大モニターでAR機能を使う、などできることの幅は広がってきている。映し出されたもので何を伝えるのか、どうユーザーを参加させるのか、がカギになってきます」(田原さん)
ユーザーを満足させるARコンテンツの実現には技術だけでは足りない。そのことをエンジニアも肝に銘じる必要があるという。『動くぬりえ』の開発にかかわるエンジニアも、ブレスト段階でストーリー性の共有を綿密に行ったという。
「自らが開発する技術で何を表現するか。エンジニアにもアウトプットの最終形を常に意識してほしかったからです。その成果もあってか、エンジニア自ら表現にこだわり、微妙な動きの差などを細かくテストしてくれました。ARに限らず、表現に関わる開発を行う以上、何を伝えたいかをエンジニアが理解することは強みになるはずです」(田原さん)
今後、Google Glassなどのウエアラブルデバイスが普及すれば、ARを用いたコンテンツも増えるはずだ。そうなれば、表現を理解することがエンジニアとしての価値を高めるかもしれない。
取材・文/長瀬光弘(東京ピストル)
RELATED関連記事
RANKING人気記事ランキング
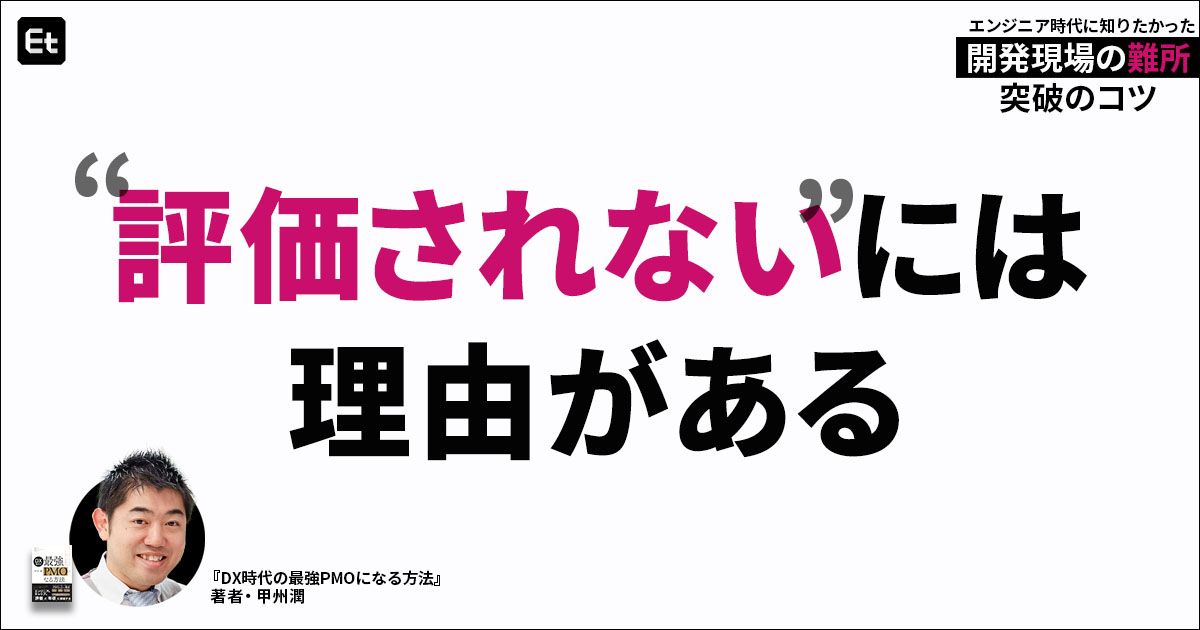
NEW!
“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

採用されない中高年の現実とは? 40代50代プログラマーが「年齢の壁」を突破する秘策

中島聡「未知の開発言語の勉強を、楽しめるかどうか」Windows 95の父が考える、エンジニア向きの資質とは
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
タグ