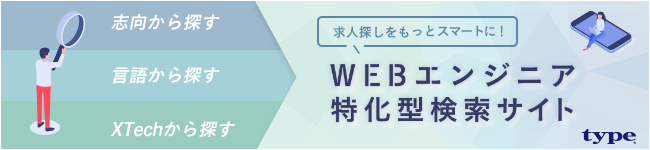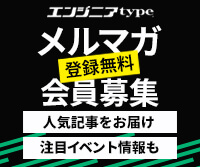本連載では、外資系テクノロジー企業勤務/圓窓代表・澤円氏が、エンジニアとして“楽しい未来”を築いていくための秘訣をTech分野のニュースとともにお届けしていきます

日本の交通インフラサービスはなぜイケてない?社会を進化させるためにエンジニアがすべきこと【連載:澤円】

圓窓代表
澤 円(@madoka510)
立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、外資系大手テクノロジー企業に転職、現在に至る。プレゼンテーションに関する講演多数。琉球大学客員教授。数多くのベンチャー企業の顧問を務める。
著書:『外資系エリートのシンプルな伝え方』(中経出版)/『伝説マネジャーの 世界№1プレゼン術』(ダイヤモンド社)/『あたりまえを疑え。―自己実現できる働き方のヒントー』(セブン&アイ出版)※11月末発売予定
Voicyアカウント:澤円の深夜の福音ラジオ メルマガ:澤円の「自分バージョンアップ術」 オンラインサロン:自分コンテンツ化 プロジェクトルーム
皆さんこんにちは、澤です。
Twitter(@madoka510)をフォローしている人は、ボクがよくタクシーに乗り、そしてそのサービスレベルにぶつくさ文句を言っているのをご存知だと思います(笑)
実は、これには明確な意図があって、「規制に守られ過ぎていてイノベーションを受け入れられなくなっていることに対する警鐘」の一つと位置付けているからです。
世界の各地では『Uber』や『Grab』、『Lyft』といったライドシェアサービスがどんどん浸透しています。一度でも使ったことがある方なら、その素晴らしさはまさに「イノベーション」と呼ぶに相応しいものだと分かりますよね。
行き先をいちいち説明する必要もなければ、お金の受け渡しも発生しない。目の前まで迎えに来てくれて、さっと目的地に連れて行ってくれる。
本来のタクシーに求めているサービスを、極めてシンプルに実現してくれます。これは、インターネットの力に他なりません。
スマホとクラウドのおかげで、「キャッシュレス決済」や「ダイナミックプライシング」、「地図サービスによるナビゲーション」などが実装されていて、さらにドライバー自身もスマホのカメラと画像認識AIの組み合わせによる「本人認証」によって安全性も担保されます。
まさにライドシェアサービスは、最新のテクノロジーによって人が恩恵を受けている典型例ですよね。
しかし、日本ではまだライドシェアのサービスは立ち上がっていません。そして、タクシードライバーはかなりの高齢化が進んでおり、かつ人手不足だそうです。
課題山積、まさにライドシェアが活躍する余地しかない! という状態にも関わらず、全くその恩恵には授かれていません。なぜでしょうか?
ライドシェアが普及しない理由「法律を変えることに対して及び腰な日本」
理由の一つに挙げられるのが「法規制」でしょう。
ライドシェアは、日本では「白タク」の扱いになってしまい、そのまま持ち込もうとすると違法サービス扱いになります。
つまり、私たち日本人がライドシェアを使いたければ、法律を変えるという必要があるんですよね。しかし日本の法律を変えるのは、相当大変です。
なにせ、先進国では唯一「現行の国の憲法を変えたことがない国」とも言われているくらい、法律を変えることに対して及び腰な国だからです(この辺は異論のある方も多いと思いますが、あくまでボクの主観ということで)。
ということで、ことはそう簡単には進みそうにありません。
そして、日本の交通インフラ系のアプリは、妙に「イケてない」感じがしてなりません。『Japan Taxi』が出てきた時にはかなり期待したのですが、まともにタクシーが来ることの方が珍しいというくらい、“謎の動き”をします。
聞くところでは、裏側では相当なマニュアルオペレーションがまだ残っているとか……。単に既存の超アナログな昭和のインフラの表面に、アプリを乗せているだけという説もあるんです。
また、エンジニアtype界隈では有名な及川卓也さん(@takoratta)も、JRのスマホアプリのクオリティーの低さには相当お怒りだったよう。
Twitterでも、問題提起ツイートを連発していたことがありましたし、別媒体のオンライン記事でも取り上げておられました。
テクロノジーで生活が便利になるって嬉しくないですか?
ちなみに、僕がヨーロッパに旅行したとき、『DB Navigator』というアプリに大変お世話になりました。これは、ドイチェ・バーンというドイツ国鉄を利用する時に使うアプリなのですが、とにかく便利!
日本にいながらにして列車の予約を日本語で取ることができ、運行状況も把握できる。そして、ドイツ国内だけではなくて、列車が乗り入れているヨーロッパのさまざまな国をまたいで使うことができるのです。
UIもとても優れていて、かみさんとのヨーロッパ旅行はとても快適なものになりました。
本来、テクノロジーは「ユーザーに快適性をもたらす」のが一つの大きな目的なはずですが、日本ではその価値がまだまだ浸透しているとは言えない状況のように感じます。
裏を返せば、「伸び代がとっても大きい」とも言えるのですが、何かのサービスを始めてみたら、どこからともなく役人が現れて「それはこの法律に違反しています」と指摘してきたりするリスクも。
同じことはもちろん日本以外でも起きてはいるでしょう。またこういうことを書くと「こいつは日本をdisってるのか!」と感情的になる人もいますね。
でも、日本での生活が便利になるのって嬉しくないですか? そして、それが余分な法律やら規制やらで縛られているのって、変えたいと思いませんか?
日本以上にあれこれ政府による規制が厳しそうな印象のある中国は、今やテクノロジー大国になっています。
北京近郊のコンビニエンスストアの決済は、70%近くが『Ali Pay』と『WeChat Pay』の二つで占められているそうですね。
また、結婚式のお祝儀などもQRコード決済にしてしまって、現金管理の問題を見事に解決しています。キャッシュレスという点においては、中国は超先進国。
日本では、だいぶ『Suica』や『ICOCA』など交通系ICカードによる決済も増えてはきましたが、端末が高価だったりして、浸透度合いはまだまだ一部に留まっている印象です。
日本ではまだまだ「現金」を使う場面が多く、ビジネスの在り方は昭和時代から変わっていません。手数料の問題や、店舗側に支払われるタイミングなど、解決すべき課題が多いことは確かです。
エンジニアはエグゼィティブたちの教師となれ
では、我々は諦めるしかないのでしょうか?
やはり、ここは「課題を感じたら声を挙げていく」というのも大事なアクションではないかと思います。別に国家転覆を狙っているわけではありません。
あくまで「もっと便利にする」「既存の課題を解決する」ために声を挙げていきましょう、ということです。日本人は、どうにもこうにも我慢強い民族ですよね。
しかし「本来テクノロジーで便利にできるのに、そうせずに我慢する」って、なんかおかしいと思いませんか?
世界には、既に便利になっているビジネスケースはいくらでもありますし、それに伴うリスクへの対応についても、たくさんの解決策が生み出されています。
それを取り入れればいいだけの話です。日本は、さまざまな組織構造の中で「トップがお年寄り」であることが多く、「最新のテクノロジーに疎い」ことも珍しくありません。
そういう人たちは、シリコンバレーや深センに視察旅行に行っても、お付きの人たちが何から何まで「日本にいるときと同様に」おもてなしをしてしまうので、現地のリアルなテクノロジーを体験せずに帰ってきてしまうことが多いようです。
でも、日本のシニアなエグゼクティブは「知らないだけ」かもしれません。
であれば、教えてあげようじゃありませんか。エンジニアtypeを読んでおられる方々は、テクノロジーに強い方が多いことでしょう。
前回の記事の中で「偉い人をトレーニングしましょう」と書きました。そう、我々は「エグゼクティブの人たちのアドバイザー」とならなければいけないのです。
組織のトップの人たちが「知らない」から「知っている」に状態が変わるだけで、経営判断は大きく変わります。
そういう方々のコネクションによって、場合によっては政治家や業界団体に大きな影響を与えてもらって、テクノロジーによって課題を解決しやすい土壌ができ上がるかもしれません。
そのためには、なんといってもエンジニアの皆さんは、数多くの「体験」をする必要があります。
新しいアプリは片っ端から試してほしいですし、海外に行ったら日本にはないさまざまな最新サービスを使いまくってください。
そして、その「体験」の語り部となって、エグゼクティブの人たちにアドバイスできるようになりましょう。
テクノロジーの力で、もっと便利で楽しい世の中にしていきましょう!

セブン&アイ出版さんから、私の三冊目となる本が発売されました。「あたりまえを疑え。自己実現できる働き方のヒント」というタイトルです。
本連載の重要なテーマの一つでもある「働き方」を徹底的に掘り下げてみました。
ぜひお手に取ってみてくださいね。
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ
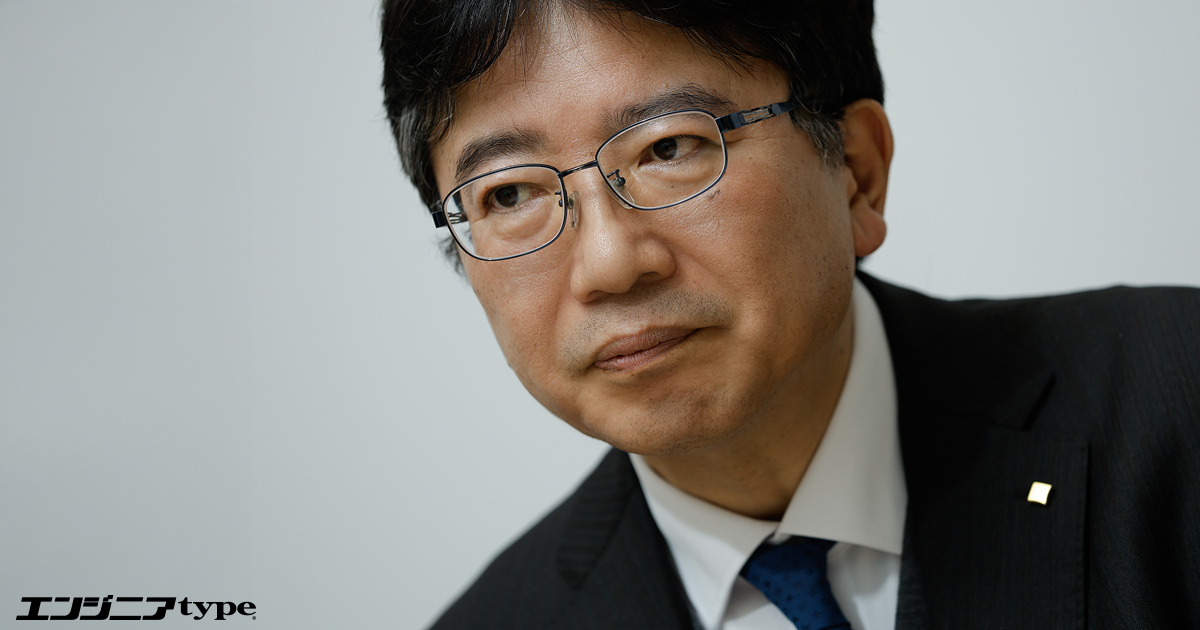
AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
タグ