あの企業の開発環境を徹底調査!Hack the Team
エンジニアが働く上で気になる【開発環境】に焦点を当てた、チーム紹介コーナー。言語やツール類を紹介するだけではなく、チーム運営や開発を進める上での不文律など、ハード・ソフト面双方の「環境づくり」について深掘りしていく。
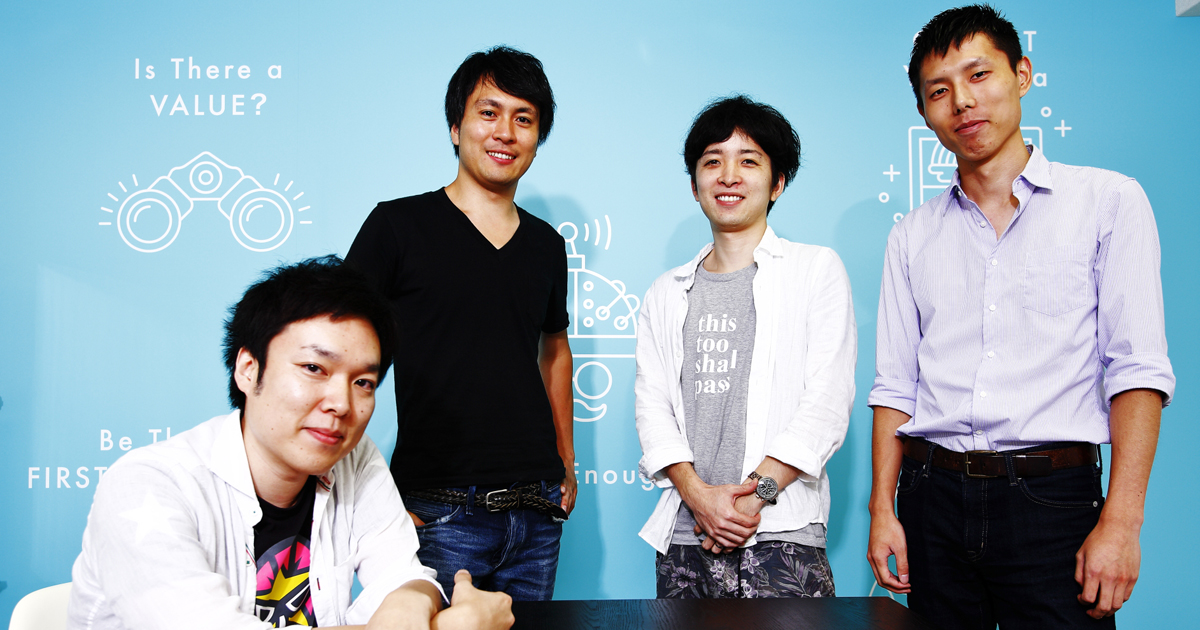
【PR】 転職
あの企業の開発環境を徹底調査!Hack the Team
エンジニアが働く上で気になる【開発環境】に焦点を当てた、チーム紹介コーナー。言語やツール類を紹介するだけではなく、チーム運営や開発を進める上での不文律など、ハード・ソフト面双方の「環境づくり」について深掘りしていく。
イタンジは、ITを使って不動産取引を滑らかにすることをミッションに掲げる、創業5年目のベンチャーだ。
管理会社向けの物件確認の自動応答システム『ぶっかくん(物確君)』や、不動産店舗に来店した客に自動でメールを配信するシステム『ノマドクラウド(旧名:追客くん)』など、昨年から今年初めに掛けてリリースしたBtoBのサービスが相次いでマネタイズに成功。旧態依然とした業界に新風を吹き込む存在として今、注目を集めている。

不動産賃貸/仲介会社向けのCRM・営業支援クラウドシステムとして成長中の『ノマドクラウド』
だが、順風満帆そのものに見えるイタンジが好調に転じたのは、最近のことだという。経営層が強いリーダーシップを発揮し、C向けサービスに軸足を置いていた1年ほど前までは、思うように利益が上がらず先行きの見えない状況にあった。
BtoB中心へと舵を切ったことが奏功した形だが、興味深いのは、この決定が経営陣のトップダウンで行われたものではないということだ。まず現場エンジニアの発案で前述の『ぶっかくん』や『ノマドクラウド』が生まれ、それが経営陣の予想を超えてヒットしたことが、会社の方針転換を促した。
イタンジはどのようにして、現場主導のサービス開発へとシフトすることができたのか。また、古くからの商習慣がいまだに色濃く残り、IT化の遅れた業界として挙げられることも多い不動産業界において、イタンジのエンジニアにはなぜ、管理会社や仲介業者のニーズを的確に捉えた提案が可能だったのか。
サービス開発プロセスの変遷について、イタンジの面々に現在のスタイルにたどり着くまでの歴史を聞いた。

(写真左から)イタンジCTO横澤佑輔氏、CEO伊藤嘉盛氏、エンジニアの福崎元樹氏と高橋建三氏
創業以来、賃貸物件の情報ポータルサイト『HEYAZINE(ヘヤジン)』など一貫してC向けサービスの提供を行ってきたイタンジの4年間を、創業者でCEOの伊藤嘉盛氏は「挑戦と失敗を繰り返しながら、少しずつ不動産業界を学んでいく日々だった」と振り返る。
もともと不動産仲介の営業マンだった伊藤氏は、物件情報の流通量が絶対的に少なかったり、いまだに紙やFAXでやり取りされていたりすることに、業界の課題を感じていたという。こうした課題をITで解決すべく、2012年にイタンジを創業して最初に立ち上げたのが、CtoCの不動産ポータルサイト『HEYAZINE』だった。
だが、サービスは思うようには伸びなかった。情報を投稿する管理会社はユーザー対応業務を行う部門を持ってないことも多く、せっかくユーザーからの問い合わせがあっても、迅速に対応できないという問題があった。
ならば仲介機能があればいいだろうと、次に立ち上げたのが『ヘヤジンプライム』というサービス(現在は『ノマド』に統合)だった。しかし、これも多くのC向けサービス同様、集客面で苦戦を強いられた。
SEO施策に力を入れ、さらには競合サービスであった『ノマド』を買収、システムを統合するなど攻めの手を打ち続けたが、思うように利益は出ず、資金繰りに苦しむ日々が続いた。
一連の試行錯誤を経て不動産業界についての知見はたまり、必要と思われる機能もひと通りそろったが、次の一手は見出せず、退職者もちらほらと出始めた。経営陣の間には、いつしか暗澹たる空気が漂うようになっていった。

経営が行き詰りつつあった2015年、CEOの伊藤氏(写真左)とCTO横澤氏(同右)が採った「ある打ち手」とは?
こうした空気に風穴を開けたのが、現場発の新規事業だった。
2015年4月ごろ、現在CTOを務める横澤佑輔氏の提案で、トップダウンで進めてきた既存事業を離れて新規事業の可能性を模索するチームが立ち上げられた。
ここから持ち上がったいくつかのアイデアの中に、『ぶっかくん』があった。ただ、提案があった当初、経営陣は『ぶっかくん』の成功に懐疑的だったという。
「管理会社のITリテラシーという、かつて『ヘヤジン』が直面したのと同じ課題をクリアできていないように思えたからです。それでも事業化まで進んだのは、とにかく新規事業を立ち上げなければ、という危機意識があったからでした」(横澤氏)
しかし、これが良い意味で経営陣の予想を覆した。右肩上がりでサービスが伸び、toCで苦しんでいたマネタイズにも成功。現在では、首都圏で発生する物件確認の問い合わせの5件に1件が、このサービスを通じて行われているという。
『ぶっかくん』の成功を受けて、昨年11月ごろから、会社として軸足をtoBプロダクトへと移すことを検討し始めた。それと歩調を合わせるようにして、現場からは第2の成功プロダクト『ノマドクラウド』のアイデアが持ち上がった。
これはもともと、イタンジのメーンプロダクトであるC向け仲介サービス『ノマド』の一機能として、担当エンジニアの福崎元樹氏が開発を検討していたものだった。
こうした現場発の動きに、会社としてのtoBシフトの方針がうまく重なったことで、『ノマドクラウド』は独立した一つのプロダクトとして世に出されることになった。

エンジニア主導の開発文化へシフトしていく中で起きた、開発チームの動き方の変化とは?
『ぶっかくん』や『ノマドクラウド』の成功は、経営層が完璧を目指して考え抜いたアイデアよりも、現場主導で「まずは作ってみる」ことが、遠回りのようでいてイノベーションへの近道であるということの好例だろう。
とはいえ、開発現場からユーザー企業のニーズを捉えた質の高いアイデアが上がってきたのは、全くの偶然というわけでもない。そう言える理由を、福崎氏は次のように説明する。
「まず、C向けサービスを展開していた4年間を通じて、会社としても現場エンジニアとしても、不動産業界についてある程度学習できていた。そして、僕らエンジニアはただ開発に専念するというのではなく、物件の内見や営業にも同行して、リアルな現場を経験してきました。そのため、ユーザー企業がどんな機能を必要としているかを肌感覚で知っていたことが大きかった」(福崎氏)
エンジニアが内見や営業にも出向くというのは、ルールとして決まっているわけではないという。イタンジが窮状を迎えた2014年ごろに、自然発生的に生まれた不文律だ。
例えば横澤氏は、入社直後に担当したサービスが、システム的には決して悪くないはずなのに全く売れないことが不思議だった。だが、「技術に問題がないとすれば、問題はユーザー体験にある。そう考えたら、ユーザーのことを知るために何でもやるという姿勢になるのは、自然なことでした」と自身の変化を振り返る。
福崎氏も、入社当時は「できれば開発に専念したい」と考えるタイプのエンジニアだったという。営業担当者と顧客の下へ出向き、ユーザーニーズを聞いて回る。入社前、そんな姿を想像することはなかったと明かす。
「でも、自分がイチから関わったプロダクトには愛情がわきますよね。そうすると、それがユーザーにどのように使われているのかまで気になり始め、いつからか自然と営業同行までするようになっていました」(福崎氏)
『ノマドクラウド』がマネタイズできるようになったのは、最初に某大手不動産会社が受注してくれたからだそうだが、そこにはCEOの伊藤氏と共に福崎氏もサービス説明と提案に行っていたという。
カルチャーはトップダウンで作るものではなく、その時置かれた状況で「勝とう」と思う気持ちが自然と生み出すもの――。そう気付かされたと伊藤氏は言う。

現在はRubyを用いた開発が中心となっているイタンジではあるが、求人では「極論、Rubyじゃなくても構わない」と謳っている。その理由は?
現在、AIチャットや機械学習を使った『ノマド』の顧客データ分析や、新サービスの『ノマドエージェント』などを担当するエンジニアの高橋建三氏は、まさにこうしたカルチャーにフィットした人材として、今年5月にイタンジに加わった。
「もともと自分で起業することも考えていたくらいなので、自分で考えて動けるイタンジの環境は理想的に感じました。一つの業界について深い知識を得たいという欲求もあったので、プロダクトまわりのことは何でもするというカルチャーも願ったり叶ったりでしたね」(高橋氏)
今のイタンジの強さは、こうしたカルチャーをメンバー全員がしっかりと共有していることにあると言えるだろう。
ただし、そうやって醸成されたカルチャーも、ビジネスのフェーズによって変わりゆくものだと伊藤氏と横澤氏は口をそろえる。だからこそ、現在行っている中途採用で求めるのは、必ずしも高橋氏のように今のカルチャーにフィットした人材だけとは限らない。

イタンジ株式会社の中途採用情報
不動産情報の一元化を実現するWebエンジニア募集!
「技術だけを追求したいという尖ったエンジニアが、今のイタンジのカルチャーにフィットしないのは分かっているんです。でもそれ以上に、組織が同じように考える人の集まりになって、硬直化する方が怖い。良い意味で僕らの考えを否定してくれるような血を入れることが、次のフェーズに向けて必要なことだと思っています」(横澤氏)
取材・文/鈴木陸夫 撮影/竹井俊晴





タグ