コードを書く時間は減らさない!
ビジネス書「10分」リーディングビジネスや世の中のことももっと勉強したい、でもコードを書く時間は減らしたくない!そんなエンジニアに、10分で読める要約版でオススメ書籍を紹介します
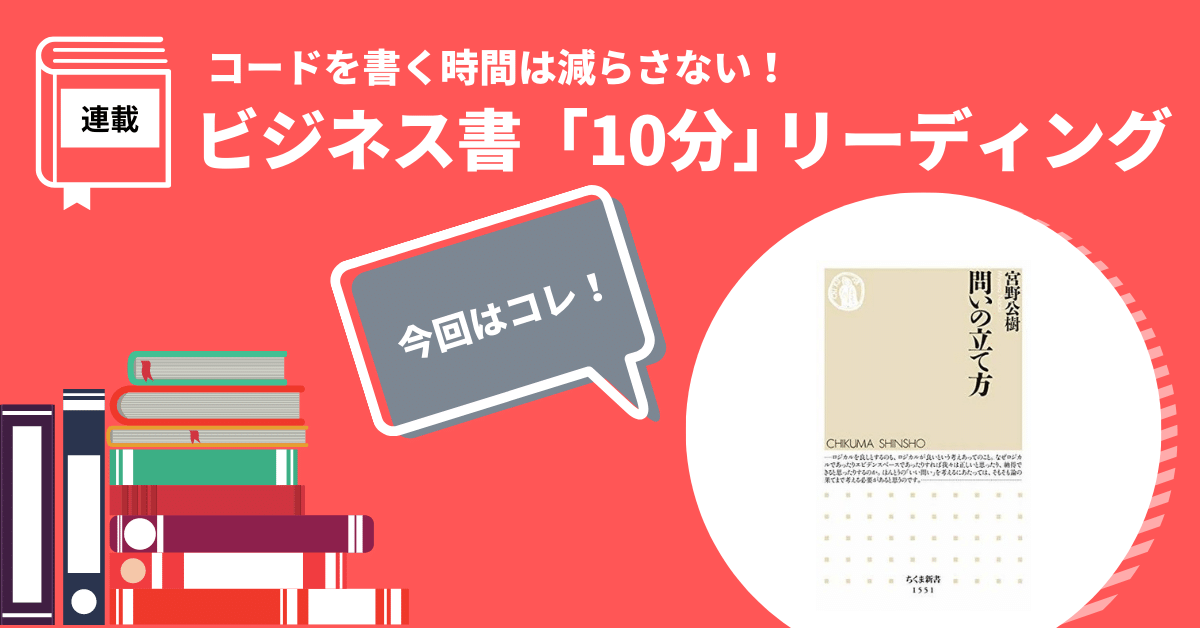
コードを書く時間は減らさない!
ビジネス書「10分」リーディングビジネスや世の中のことももっと勉強したい、でもコードを書く時間は減らしたくない!そんなエンジニアに、10分で読める要約版でオススメ書籍を紹介します
「エンジニアリングは問題解決である」とはよく言われるところだが、より本質的な仕事をするためにはそれ以前に適切な問題の発見ができる必要がある。小手先のテクニック論ではなく、そもそも「問い」とは何かから論じる本書は、あらゆる場面に通じる本質的な問いの立て方へと読者を導いてくれる。

『問いの立て方』
著者:宮野公樹/出版社:筑摩書房/定価:780円(税別)/出版日:2021年2月10日
Book Review
誰かに指示されたまま受動的に行動するのではなく、自主的に課題を設定して問題解決や探究を実践する――このような能力が、近年ではより強く求められるようになった。巷では、そのためのさまざまな方法論も提案されている。だが本書が提示するのは、個別の方法論や具体的な場面ですぐに役立つ答えではない。そもそも「問いとは何か」という、より深く本質的な思索である。
よりいい答えを得るためには、よりいい問いを立てる必要がある。だが本書で述べられているとおり、何が「いい問い」になるかは、場面や状況によって異なる。あらゆる場面や状況にも共通する、根本的で本質的な問いを立てるうえで、すぐに使える具体的な方法論はかえって役に立たない。「そもそもなぜこの問いが求められるのか」、「自分は何を求め、めざしているのか」など、深いレベルで考えていかなければならない。
本書は、生活や人間関係、仕事などで使えるアイデアを手軽に手に入れるためのものではない。自分の人生や物事の本質を突き詰め、よりいいものにしていくきっかけを得るためのものである。それは一見遠回りのように思えるかもしれない。だがあらゆる場面に共通する問いの立て方を掴むことは、たくさんの方法論を学ぶよりも、人生に大きな影響を与えるはずだ。本質に迫る「問い」を考えることは、あらゆる人にとって重要だと実感させられる一冊である。

「いい問いの立て方」を考えるために、まずは「いい問い」とは何かというテーマと向き合ってみよう。冷淡な言い方をすれば、何が「いい問い」なのかは場合による。不都合を解消したい場面では解決する方策を得る視点が、ワークショップでは参加者が必死になって考えたり議論が盛り上がったりするようなお題が、それぞれ「いい問い」となる。だが本書では場面を限定せず、あらゆる場面に共通する「問い」について考えてみたい。
さまざまな場面における問いを並列的に眺めてみると、それぞれの問いそのものよりも、問いの在り方、形式に意識が向けられる。そして答えが「ある」問いと答えが「ない」問いに気づかされる。人生には、とうてい正解などない「問い」があふれている。そもそも人生そのものが、正しい答えなど見つけられない「問い」だ。生きているということは、考えることそのものといえる。そう考えると、答えがあるかないかという分類は些細なことであり、我々が「問い」として存在している事実こそが重要である。
世の中には「……のときはこうしたほうがいい」というように、問いと同じ数だけの意見がある。しかし断定的な正しい答えを探し求めたり、自分の意見の正しさに過度に固執したりすることは、幼稚な態度である。問いがあるから考えや意見があるのであって、「そもそもなぜその問いがあるのか」と問う問いこそが、物事の大本に迫る「いい問い」につながる。それは場面や条件に依存せず、どのような問いにも共通して当てはまる本質的な問いだ。すなわち「いい問い」とは、「なぜその問いがあるのか」という根源的な存在についてまで考えられた、本質的な問いのことなのである。
あるテーマについて意見交換をすると、意見が対立してなかなか合意がとれず、平行線をたどることがある。しかし両者の意見が前提としている「そもそも」の観念の領域まで踏み込んで議論をすると、両者が共有している考え方が見いだされ、噛み合った話ができるようになる。安易に「人それぞれ」と言い出すと、建設的な議論が成り立たなくなってしまうが、共通している部分は間違いなく存在する。それを対象とするからこそ、「本質的」な「いい問い」となるのだ。
ある問いに対して、直接的に応答したり意見を考えたりするのではなく、「その問いがなぜ生じたか」という理由を、「問いを問う」という形式に従って考えることが大事である。そのためにも問いや意見、考えの前提にある「観念」を問うことが、本質的な問いに接近するうえでは必要だ。
さらに人間観や仕事観、社会観といった観念は、広義の「歴史」という、さらなる前提から生じている。私たちは生まれ落ちた国、地域の風土や慣習、育った環境や受けた教育なども含めて、ありとあらゆる要因を連鎖、重層化、相関させながら、自分の考えを形成している。私たちは問いを「持って」いるのではなく、問いの「内に在る」のである。私たちは歴史を「知って」いるというよりも、そもそも歴史の内に組み込まれた存在であり、むしろ歴史そのもの、言葉そのものだと自覚すべきだ。
自分の歴史の前提を考えると、歴史から引いた立ち位置に立つことが可能となる。たとえば日本で生まれて日本語で考える「私」の立ち位置を客観視したいのであれば、「インドに生まれてヒンディー語で考える人になっていたかもしれない」「縄文人として生まれていたかもしれない」と、世界の縦軸や横軸を意識し、並列的にとらえてみるといい。すると場所や時間が一瞬で溶け、自分が自分でないような心持ちになる。
自分と他者との境界が溶けたまさにこの瞬間、歴史のさらに前提となるもの、すなわち「存在」という「問いを問う問い」という形式の果てに至ることができる。その域まで考えることで、はじめて枝葉の考えから脱することができる。
結局は「歴史」も何かの結果にすぎず、その根源には「存在」が屹立している。それは問いを繰り返した果てに見いだされる、「なぜ在るのかはわからないが、とにかく在るから在る」という性質のものにほかならない。
自分を構成するあらゆる前提を問い続けていくと、そこに自分の独自性というものは一切見いだせなくなる。このとき私たちは自身の存在の曖昧とともに、「自分の存在とは世界そのものである」ということに気付かされるだろう。これが問いを問う形式で考え進めてきた論理の果て、すなわち「終点」である。
そして、この終点は「始点」でもある。自分を構成する要素をひとつひとつ問いによって解きほぐしていき、そこに何もなくなったとしても、私たちは依然として存在し、思考できる。そしてそこから、あらためて自分自身を構成することもできる。
そこで立ち上がってくるのが、「自分はどうしたいのか」という問いだ。世の中には、成功者による体験的な叙述やハウツー的方法論を著した本が数多くあり、そこから学ぶことも多いが、そればかりでわかった気になってはいけない。自身の内なる問いこそが自身を成長させる。「生きる」こととは、常に内省をして、自分は何者かを疑い続けることだ。したがって本書で示すのは、「考えよ」の一言だけである。

「いい問いにする」ことは、「問いを磨く」ということだ。磨くとは、何かと何かが接触して摩擦を生じさせることであり、「問い」も「矛盾」や「葛藤」によって磨かれると考えられる。
「問い」を磨く葛藤や矛盾として、「自分と世界の在り方における矛盾」がある。自分の見方でしか世界が見られないのであれば、世界は自分の内側にあり、自分と世界は同一になる。しかし世界には自分が認知しないもの、知らないものも存在している。また物質と精神のように、「可視なものと不可視なもの」という矛盾もある。人間はこうした個別と全体、可視と不可視という四象限の間に置かれ、その矛盾や葛藤の中で問いを確立させようとする。こうした営みこそが、まさに問いを磨くということである。
この矛盾の構造に、過去、現在、未来という時間軸を導入することで、さらに問いを磨くことができる。過去を意識すれば、「問い」の根拠、前提、歴史など、その問いに関心をもった理由や、問いの時代性を探ることができる。現在を意識すると、「その問いは、本当の問いか」、「その問いは、自分にとって本物か」という、直球の問いが浮かび上がってくる。未来を意識すると、自分が「どうなりたいのか」「どうありたいのか」という理想像を問うことになる。
いずれにしても、安易に他人の考えやハウツー、外的な評価に頼るのではなく、自分の精神に意識を向け、研ぎ澄まし、自分で自分を問いつづけることで、問いを磨いていかなければならない。
私たちは、もとから問いを抱えた存在だ。だからいい問いとは、どこかを探索したり発掘したりして発見するものではなく、おのずと「持ってしまうもの」といえる。
そもそも、いい問いの「立て方」という何かしらの方法論に沿って見つけられたものが、果たして「いい問い」であるのだろうか。「いい問い」とは、「持ってしまうもの」「持ってしまったもの」「持たざるを得なかったもの」というように、どうしてもそうなるものだ。
では「持ってしまう問い」は、どのようにして見つかるのだろうか。受動的、偶発的に気づくためには、「違和感」が重要になる。世間では、違和感を持つことの重要性について頻繁に言及されるが、違和感そのものについてはあまり述べられていない。違和感とは、「何か気持ち悪い」、「スッキリしない」と引っかかりを感じることだが、その引っかかる箇所や原因が明確に見当たらないのに、それでも自分の意識内に通常と異なる何かがあるときがある。それは「対象」と「自己」との差異に他ならない。
違和感の基準となるのは、私たちが持つ「考え」だ。考えの前提には、前述したように何かしらの観念があり、さらにその前提には歴史があって、突き詰めれば存在に行き当たる。違和感が生まれるのは自分の考えや思いがあるからであり、それは自分の在り様そのものである。すなわち違和感を持つとは、自分を持つことと同じなのだ。
いい考えやアイデアが「やって来る」「降りてくる」というとき、どこかから自分のもとにやって来るような印象を受ける。それらはどこからやって来て、どこから降りてくるのか。
結論を言えば、「自己(=個別)」の外にある「全体」は存在しない。ゆえに、いい考えがどこかから突然降りてくるということはありえない。そもそも書いてあること、話されていることを理解できるのも、自分のなかにその考えがもともと存在しているからである。
にもかかわらず偉人たちの多くは、「何かに突き動かされて行動した」と証言している。これは一体どういうことか。それは問いによって自己を突き詰めていった結果、自己と世界が同一のものとなったからである。この「個別と全体は同一」という境地に行き着くとき、「個別」を超えた力やアイデアのような何かを「全体」から得られるのだ。
自己の外側に対して問いを投げかけるのではなく、自己の中から答えが浮かび上がってくるように問いを立てること。そしてそのために、内省的かつ謙虚に問いを繰り返しながら日常を生きること。ソクラテスは「汝自身を知れ」と述べたが、結局のところ、私たちはその出発点に戻るのである。
宮野公樹 (みやの なおき)
1973年生まれ。京都大学学祭融合教育研究推進センター准教授。国際高等研究所客員研究員。学問論、大学論(かつては金属組織学、ナノテクノロジー)。立命館大学卒業後、McMaster大学、立命館大、九州大学を経て、2011年より現職。総長学事補佐、文部科学省学術調査官の業務経験も。著書に『学問からの手紙』(小学館)などがある。

話題の書籍や名著を1冊10分にまとめた要約が読めるサービスです。経営者や大学教授などの著名人・専門家などが「ビジネスパーソンがいま読むべき本」を一冊一冊厳選し、経営コンサルタントなどのプロフェッショナルのライターが要約を作成しているので内容の信頼性も安心。無料ユーザー登録をすれば、20冊分の要約を読むことができます。
※当記事は株式会社フライヤーから提供されています。
copyright © 2021 flier Inc. All rights reserved.





タグ