
ミノ駆動さん(@MinoDriven)
新卒でNEC の関連会社に入社。その後キヤノンでの10年のエンジニア経験を経て、Web系ITベンチャーの世界へ。クラウドワークス、READYFOR、スタメンを経て5月1日よりDMMにジョイン。著書にITエンジニア本大賞2023・技術書部門大賞『良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門』(技術評論社)がある

「つまりどういうこと?」「要するにできるの、できないの?」「それって何の話だっけ」
技術的にどうするべきか正解は見えているのに、頑張って説明しても返ってくるのはそんな言葉ばかり……。「うまく伝えられない」という悩みを抱えるエンジニアは、少なくないのでは?
2023年のITエンジニア本大賞・技術書部門で大賞を受賞した『良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門』(技術評論社)の著者であり、SNSでの情報発信やイベント登壇でも活躍する「言語化のプロ」であるミノ駆動さんも、昔は「君が何を言ってるのか分からん」と上司に言われていたそう。
ミノ駆動さんはどのように言語化能力を伸ばしたのか。聞くと、出てきたのは「合意駆動」というキーワード。その正体とは?

ミノ駆動さん(@MinoDriven)
新卒でNEC の関連会社に入社。その後キヤノンでの10年のエンジニア経験を経て、Web系ITベンチャーの世界へ。クラウドワークス、READYFOR、スタメンを経て5月1日よりDMMにジョイン。著書にITエンジニア本大賞2023・技術書部門大賞『良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門』(技術評論社)がある
ーーそもそも、エンジニアにとって言語化能力は重要なのでしょうか?
間違いなく重要だと思います。
どんな仕事も、何らかの問題解決によって対価を得るものですよね。問題解決のプロセスでは通常、同僚や顧客との「対話」が伴います。このとき言語化能力が不十分だと、関係者との目線や足並みが揃わず、仕事の正確性や効率が下がってしまう。つまり言語化能力とは、問題解決の正確性や効率を高めるために必要なスキルだと言えます。
特にエンジニアの場合、「その技術がどんな課題を解決するものなのか」「なぜその技術を使うべきなのか」をさまざまな人に説明できなくてはならない。ですが、エンジニアは技術についてプロであるがゆえに「専門用語を専門用語で説明する」ようなことをしてしまいがちです。残念ながら、それでは説明にはなりません。
相手に伝わらなければ、どんなに説明しても意味がないんです。コミュニケーションを単なる自己満足で終わらせないためには、相手の知識量を鑑みて、言葉を噛み砕いて説明する力が必要になります。
ーーXのポストで、ミノ駆動さん自身「7~8年前までは『君が何を言ってるのかわからん』といろんな人からツッコミが入っていた」と拝見しました。どのようなシーンで、自分の言語化能力に課題があると感じたのでしょうか。
言っておくけど本を執筆したワイでさえ7,8年前まで「君が何を言ってるのかわからん」といろんな人からツッコミが入るほど国語力が壊滅的だったからね。高校時代も赤点ギリだったし。
つまりちゃんと鍛えられる能力だ、ということです。みんなも鍛えよう。 https://t.co/j3uLaJQR9K— ミノ駆動 (@MinoDriven) April 2, 2024
現職のDMMではなく、昔在籍していた会社での話なのですが、当時の私はあるプロジェクトの開発リーダーとして、ソフトを開発する際に使う技術やプロジェクトの計画、品質担保の手段などについて、関係者に説明する責任を負っていました。
ところがプロジェクトの状況を報告するたびに、上司が首を傾げるんです。「何を言っているのかよく分からない」って。最終的には上司だけでなく、同僚からも「何を言っているのか分からないです」と言われてしまう始末でした。
何とかしなければと思い、プロジェクトの内容を詳細に文書化したり、スライドの表現方法を変えたりしてみたのですが、周囲の反応は変わりませんでした。あの時は相当悩みましたね。「こんなに一生懸命説明しているのにどうして分かってくれないんだろう。ひょっとしてみんなの知識不足では?」とすら思っていました(笑)
そんな状況が続いたある日、痺れを切らした上司が私の同僚に「代わりに説明してくれないか」と指示したんです。同僚が話すと、なんとその説明はすんなりと関係者に理解されたんですよ。これは私にとって非常にショックな出来事でした。
ーー当時のミノ駆動さんの説明と、同僚の方の説明は何が違ったのでしょうか?
まず、同僚の説明時間はとても短かったです。詳細に話しすぎず、要点を押さえて簡潔に話していました。
なぜこうした説明が自分にはできないのだろう……と考えた結果、私の話は技術、つまり「How」だけにフォーカスしていたことに気が付きました。
周りの人が知りたいのは「何のために何をするのか」という目的と手段のセットです。にもかかわらず私は「何をするのか」という手段の話だけを詳細に話してしまった。だから、相手はいくら聞いても「分からない」という顔をしていたんだと思います。
ーー当時は仕事の「目的」はあまり意識できていなかった、ということでしょうか?
そうかもしれないですね。振り返ってみると、当時の自分には仕事における目的意識が圧倒的に欠如していたと思います。
あくまでもビジネスとしてエンジニアの仕事をしているわけですから、技術の専門家であっても、まずはビジネスの目的に向き合わなければなりません。
言語化能力とは、単に国語力だけの問題に終始せず、「どれだけ目的と向き合えたか」なのだということを、経験とともに実感するようになりました。
ーーXのポストで、ご自身の言語化能力を「合意駆動」によって鍛えたと拝見しましたが、合意駆動とは何でしょうか?
「どうやって鍛えたのか気になる」とのコメントをいくつか頂いております。
自分の場合、利害関係者の合意を取り付けないと仕事が進まない状況において、相手の視座に立ち、どこで理解のつまづきがあるのか噛み砕き、合意を得るための要点を整理しまとめる、ひたすらこれの繰り返しでした。合意駆動。 https://t.co/yTQ3lPinY5
— ミノ駆動 (@MinoDriven) April 2, 2024
合意駆動とは、どういう「目標(条件)」をクリアすれば「目的」を達成したことになるのかについて、利害関係者と意見を一致させながら話し合いを進めることです。
例えば会議に参加しているメンバーは、立場も違えば持っている情報も違います。そうした状況のもと、協力しあってビジネスのゴールに到達するためには、相手の視座に立って合意点を模索する作業が欠かせません。これを何度も何度も繰り返した結果、言語化能力が磨かれていったのだと思います。
ーー言語化能力が伸びた結果、ご自身の仕事はどう変化しましたか。
周りの人の合意が得られてプロジェクトを進めやすくなっただけではなく、エンジニアとしての仕事の精度を高めることにダイレクトにつながりました。
私の生業はシステム設計なのですが、ビジネスの手段として最適なシステムを作るためには、常に顧客の目的を念頭に置く必要があります。この認識が足りていないと、単に自分の使いたい技術を使っただけの、顧客の要求を満たさないものが生まれてしまいます。
またサービスを作る上では、どこに開発コストをかけるべきかという選択も重要です。顧客が本当に求めるものを知り、自分たちが提供できる1番の差別化ポイントを見出し、そこにコストを投じる選択をする。そういう広義のシステム設計も、ビジネスの目的を意識し始めてからできるようになってきました。
ーー若手エンジニアが言語化能力を上げるためには、どうすれば良いでしょうか。
エンジニアの多くは技術に関心があるので、ビジネスの目的を忘れて「How」としての技術にばかり執着してしまうことがあると思います。
私自身もまさにそうでした。相手の反応なんて気にせずに、自分の言いたいことだけを早口で言って「あー気持ちよかった」と(笑)。ずいぶん独りよがりなコミュニケーションをしていたなと思います。
そうならないためには、あらゆるフェーズで目的を意識することが大切です。自分の仕事の目的は何なのか、その先にいる顧客の目的は何なのか、そもそもビジネスの目的は何なのかを意識することによって、うまく説明できるようになるでしょう。
また話す内容を考える際には、抽象化のプロセスを意識すると効果的です。目的に合致する言葉だけを拾い、それ以外を捨てて説明するようにすれば、シンプルに短く、相手が求めることを伝えられるようになります。
話す練習は頭の中で一人でやるのも良いですが、自分よりもビジネスを分かっている先輩や上司との壁打ちをすると良い訓練になるかもしれません。
ーー最後にミノ駆動さん自身の今後の展望について教えてください。
というわけで今日からDMMで働きます
— ミノ駆動 (@MinoDriven) May 1, 2024
5月からDMMにジョインしました。DMMプラットフォームの設計品質を全体的に改善し、プラットフォーム開発の生産性を高めることが私に課せられたミッションです。
大きな組織ならではの困難が想定されますが、さまざまな人とのコミュニケーションに悩み、乗り越えてきた自分だからこそ、挑戦しがいのある仕事になりそうです。
システム設計は目には見えずらい仕事なので、ソフトウエアの知識がない人にとってはなかなか認知するのが難しい世界ですが、開発全体に関わる仕事でもあるため、チームメンバーや関係者への働きかけは必要不可欠。こうした状況でより良い意思疎通を実現するための方法は、これからも個人的なテーマとして模索し続けていきたいと思います。
取材・文/一本麻衣
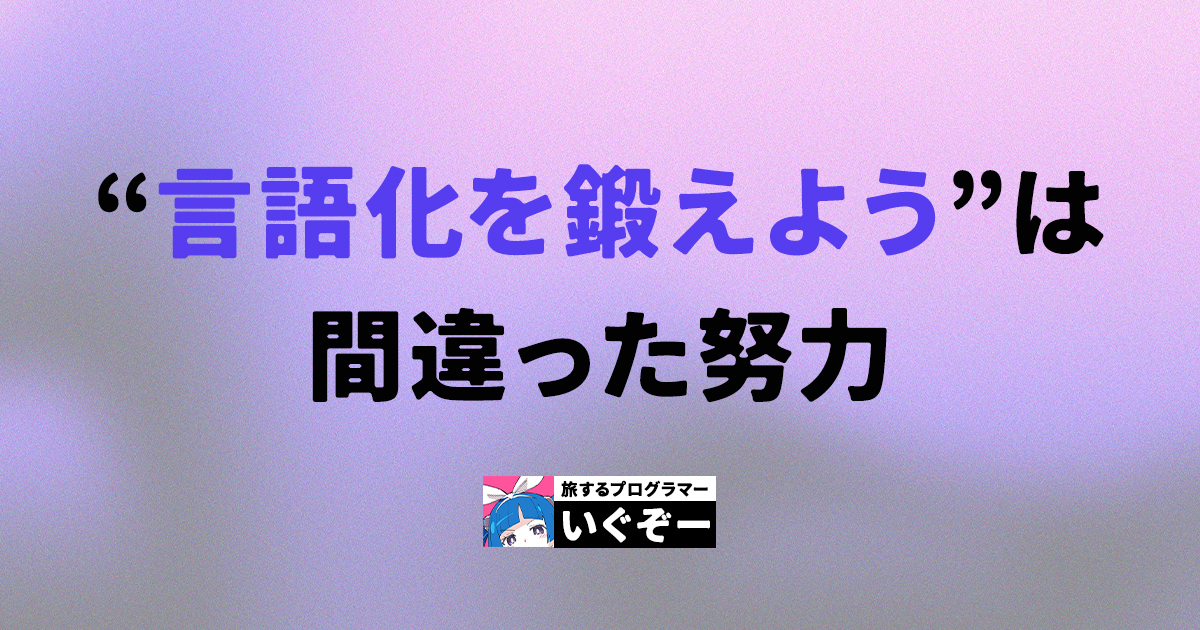
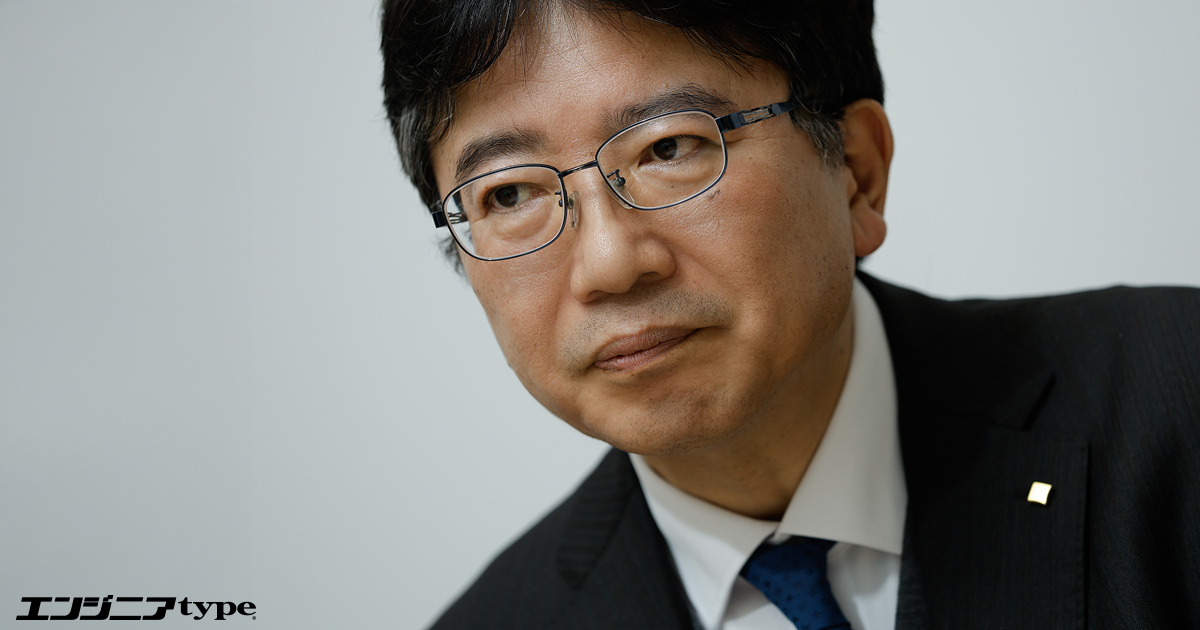



タグ