
株式会社LayerX
AI・LLM事業部 CPO 兼 プロダクト部 部長
小林 篤さん(@nekokak)
2011年DeNAに入社。Mobageおよび協業プラットフォームの大規模システム開発、オートモーティブ事業本部の開発責任者を歴任。19年より常務執行役員 兼 CTOとしてDeNAのエンジニアリングの統括を務める。25年1月より、LayerX AI・LLM事業部にジョイン。技術系カンファレンス多数登壇。技術系書籍・雑誌多数執筆
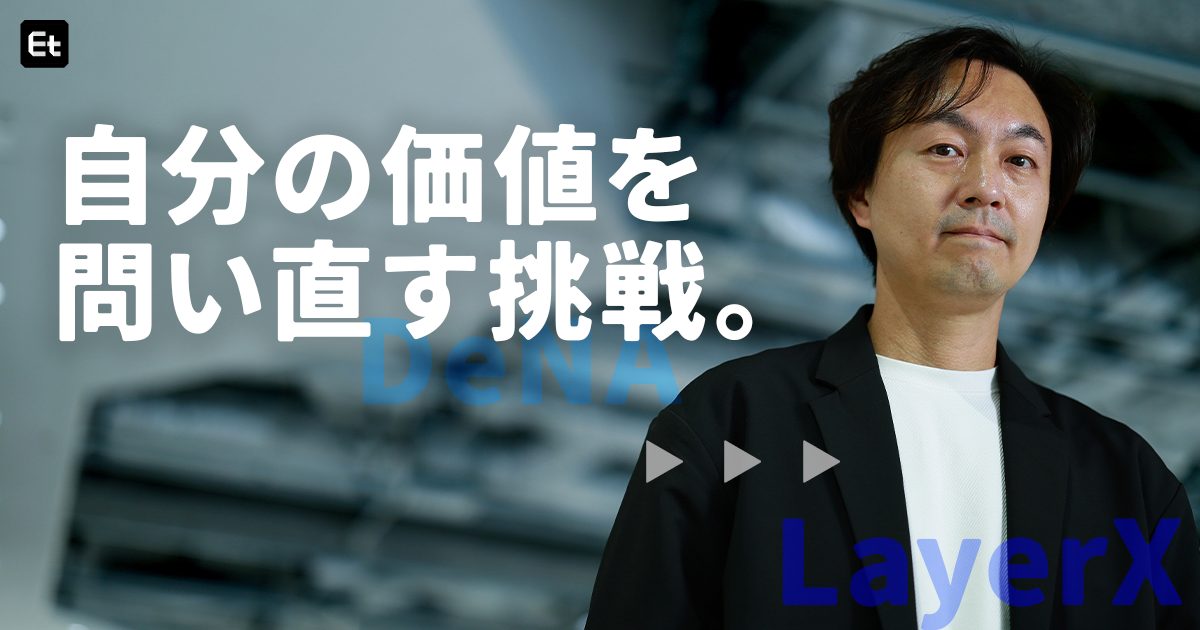
世の中には、肩書きや年収といった分かりやすい評価軸が存在する。だが、そうした外的な成功ではなく、自分の実力を内側から確かめたくなる瞬間がある。
DeNAでCTOを務めた小林 篤さん(@nekokak)が、新たな挑戦を選んだのも、まさにそんな“揺らぎ”からだった。
2025年1月、小林さんは約14年在籍したDeNAを離れ、LayerXのAI・LLM事業部へジョイン。その中核プロダクト『Ai Workforce』のCPOを務めている。
実績も信頼も積み上げた場所を離れ、あえてコンフォートゾーンの外へ出る決断の裏には、一体どのような思いがあったのだろうか。
小林さんへ話を聞くと、変化の時代を生きるエンジニアにとってのヒントが垣間見えた。

株式会社LayerX
AI・LLM事業部 CPO 兼 プロダクト部 部長
小林 篤さん(@nekokak)
2011年DeNAに入社。Mobageおよび協業プラットフォームの大規模システム開発、オートモーティブ事業本部の開発責任者を歴任。19年より常務執行役員 兼 CTOとしてDeNAのエンジニアリングの統括を務める。25年1月より、LayerX AI・LLM事業部にジョイン。技術系カンファレンス多数登壇。技術系書籍・雑誌多数執筆
目次
小林さんは前職のDeNAでは14年間、そのうち後半の約3.5年間をCTOとして過ごしてきた。長い年月を共にした会社を、なぜ今、離れるという決断に至ったのか。
「CTOとして、自分が実現したかったことは一通りやりきった実感がありました。ゼロから構想したプロジェクトを形にし、仲間を巻き込みながらやり遂げるという経験は、ある程度できたなと感じていたんです」
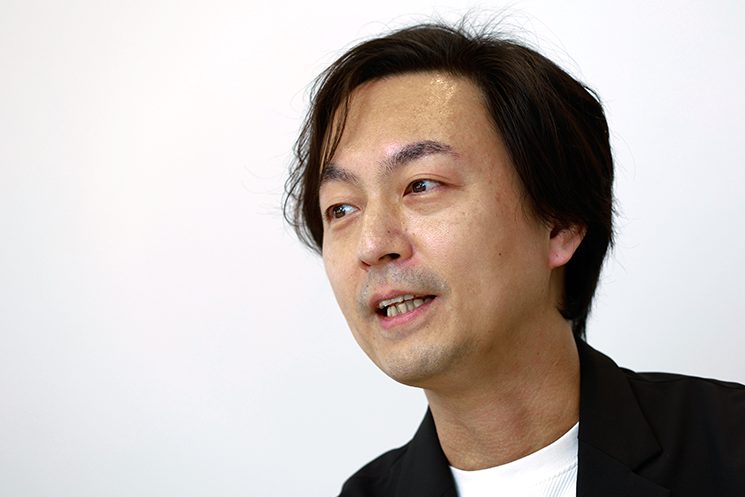
そんな日々の中で、小林さんはふとした瞬間に「自分はぬるま湯に浸かっているのではないか……?」と自問するようになっていた。
「周りのメンバーたちがとても優秀だったので、正直なところ『自分がいなくてもチームは回るんじゃないか』という思いが頭をよぎるようになったんです。実際、成功したプロジェクトを見ても、『これは本当に自分の力によるものなのか?』と考えるようになっていって……」
CTOという立場上、大きな方向性を描き、全体を統率する役割は担っていた。しかし、自分自身のスキルや経験がどれほど成果に寄与していたのかは、確かめようがなかった。
「このまま会社に居続けていたら、周りの人が優秀だったからできただけという印象が自分の中に残ってしまう。だったら、今このタイミングで一度外に出て、自分の力がどれだけ通用するかを確かめるべきだと思ったんです」
そうして小林さんが漠然と転職を考え始めたのは、2022年頃のこと。すぐに動けなかったのは、日々の業務をつい優先させてしまっていたからだ。ずるずると時間だけが過ぎていく中で、その流れを断ち切ろうと小林さんがとった行動は「とりあえず辞める」というものだった。

次の行き先が決まっていない中での退職に、不安や迷いはなかったのだろうか?
「もちろん、そういう気持ちが全くなかったわけではありません。ただ、自分の力に懐疑的になってしまった以上、前職にとどまるという選択肢はありませんでした。
モヤモヤした気持ちを解消するためには、自分を追い込むしかなかった。夏休みの宿題と一緒で、『あとでやろう』と思ってると、結局やらないままになる気がして(笑) だから社長の岡村さんに『来期の人員体制に私を含めないでください』と直接伝えました」
そんな小林さんが、次の舞台としてLayerXを選ぶ決め手となったのは、プロダクトにAIを活用するのではなく、「AIを使ったプロダクトを作る」ことだった。
「前職でもAI活用はしていましたが、既存プロダクトへAIを“後付け”するアプローチがメインでした。
例えば、コミュニケーションサービスに誹謗中傷を検知するAIを組み込み、サービスの健全性を担保するといったもの。もちろん重要な機能ですが、あくまで既存体験の延長線にすぎない。業務体験の構造自体を変えるものではありません」
小林さんが目指すのは、AIを中心に据えた体験設計そのものの変革だ。
「AIエージェントが見積書を自動で読み取って処理するといったように、人が手を動かしていた業務フロー自体を、その根本から変えていく。そうした新しい体験をプロダクトとして社会に実装していくところに、AIの本質的な価値があると感じています。
そう考えたとき、AI・LLMを核に新しい事業を立ち上げているLayerXなら、その本質に挑めると思ったんです」
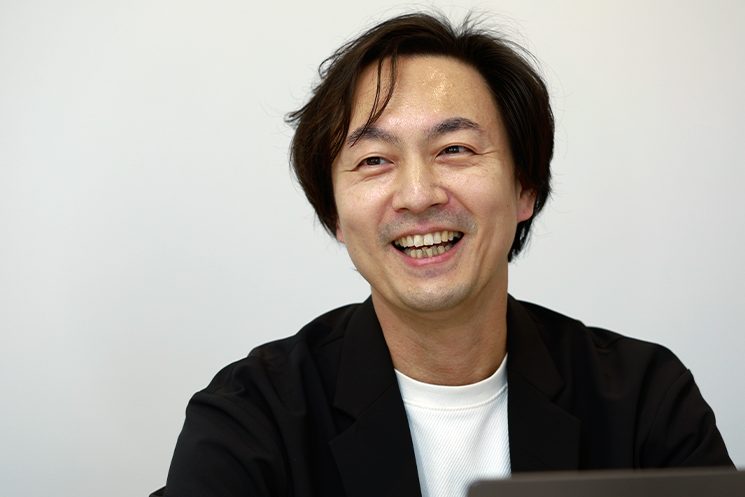
加えて、LayerXのプロダクト設計が「プラットフォーム志向」であることも、小林さんの性格とマッチした。
「LayerXのAI・LLM事業のプロダクト思想には、一つの仕組みの上にさまざまな業務やサービスが乗っかっていく“プラットフォーム的な発想”があるんです。僕自身もこれまで、ゲームやオートモーティブといった異なる領域で、そうしたプラットフォームの構築に携わってきました。
一つの機能を深掘りするより、複数のドメインを横断しながら使えるものを作る方が、飽きずに取り組めるし、チャレンジの幅も広がる。まさに自分に合ったスタイルでした」
DeNA時代は「ブルドーザー」と称されるなど、「荒地のような状況のプロジェクトを耕す仕事が好き」だと言う小林さん。そんな泥臭くも本質的な“創る”という営みにこそ、彼のエネルギーは向いているようだ。
「一定の顧客基盤を持つ『バクラク』(*)と違い、AI・LLM事業はまだ立ち上がったばかり。未整備な点も多いですが、だからこそ自分が直接手を動かす余地があるし、一つ一つ課題をクリアしていけば着実に前進していくフェーズとも言える。ダイレクトに成果につながる課題が目の前にたくさんある状況は、すごく面白いなと思いました」
(*)LayerXが提供する、請求書処理、経費精算、稟議申請、法人カードなどの支出管理をなめらかに一本化するサービス。シリーズ累計導入社数:15,000社
LayerXで小林さんが率いるのは、生成AIを業務に組み込むプロダクト『Ai Workforce』だ。文書処理を起点に、多様な業務に応用できる高い汎用性が魅力だが、その反面「何ができるのかが伝わりにくい」というジレンマを抱えている。
「今はまだ、良くも悪くも“なんでもできる”プロダクトなんです。ひと口に文書処理といっても、契約書や見積書、社内マニュアル、営業資料、原稿……と種類も用途も千差万別。すでにさまざまなユースケースに対応できる土台はありますが、それが直感的に伝わる状態にはなっていないのが現状です。
だからこそ、どんな場面でどう役立つのかを丁寧に言語化し、サービスの価値を社内外に共有していくことが、まず自分に求められている役割だと捉えています」

さらに、チームとしての基盤づくりも現在進行形の課題だ。『Ai Workforce』に関わるPdMは、小林さんを含めて3名。うち2名がエンジニア出身で、プロダクトマネジメントの型や定石に関しては、まだ学びの途上にあるという。
「今は優秀なエンジニアたちがスピード感を持って、いい意味で“ワーッと作る”スタイルなんです。でもそれだと、お客様がちゃんとスケールして使えるか、という観点ではまだ不十分。エンタープライズの取引先様が増えていることも踏まえ、システムの堅牢性も高めながら、企業としての信頼感を強める動きもしていく必要があります。
とはいえ、エンジニアのモチベーションや開発スピードが落ちてはいけません。この辺りのバランスの取り方については、前職時代にオートモーティブやメディカルといった“安全性が最優先されるプロダクト”に携わった経験が活かせそうです」
「AIをどう実装するか」ではなく、「AIによってどんな体験を再構築するか」。その思いを胸にLayerXの挑戦に加わった小林さんは、AIと人間の適切な関係性についても問い直している。
「LLMの登場によって、生産性は爆発的に向上しました。でも、ツールが出してきたものをそのまま使うだけでは不十分。背景にある構造や動作原理を理解し、自分の頭で判断できることが、エンジニアにとってこれまで以上に重要になってきていると思います」
ただ使うだけではなく、“どう使いこなすか”を自分で決める。小林さんが重視しているのは、ツールとの健全な距離感だ。Ruby on Railsが普及した当時、「裏側を知らないエンジニアが増えた」と語るように、AIもまた「表面的な利用に留まれば本質を見失いかねない」と懸念する。
「僕たちがつくるプロダクトもそう。どれだけ汎用的でも、使い方が伝わらなければ意味がない。だからこそ、“体験そのものを変える”ための提案ができるエンジニアと一緒に、プロダクトを育てていきたいと思っています」

そう語る小林さんの視線の先にあるのは、あくまで“プロダクト”だ。彼にとって、“肩書き”は単なる役割の一つにすぎない。DeNAでCTOを引き受けたのも、「この役職が不在のままでは会社にとってよくない」と判断したからだった。
「もしLayerXで『マネジメントだけやってくれ』という話だったら、多分来ていなかったと思います。プロダクトをどう作るか、顧客の声にどう向き合って動けるかどうかが、自分にとっては何より大事でした。
個人的に役職には全く興味がなくて、自分が何にワクワクできるかが全てなんですよね」
自身のキャリアについても、「明確な設計図は一度も描いたことがない」と笑う小林さん。その代わり、ひたすら目の前の仕事に全力を注いできた。その積み重ねが、自信となり、いつしか道になっていた。
「今やりたいと思えることに真っ直ぐ向き合って、目の前のことを120%でやりきる。それさえ繰り返していけば、きっとなんとかなる。ずっとそうやってきたし、これからも変わらないと思います」
AI・LLMがもたらす未曾有の変革期にあっても、小林さんのスタンスは驚くほどブレない。道なき時代を歩くために必要なのは、遠くのゴールではなく、「今、何をやりきれるか」なのかもしれない。

取材・文/一本麻衣 撮影/桑原美樹 編集/今中康達(編集部)
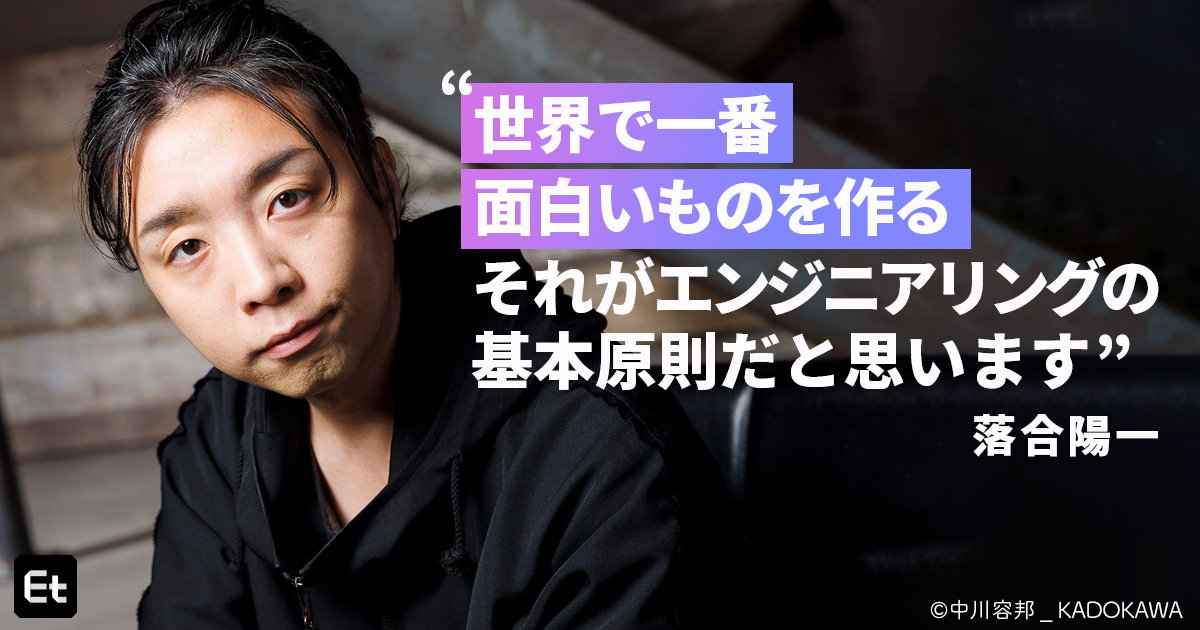

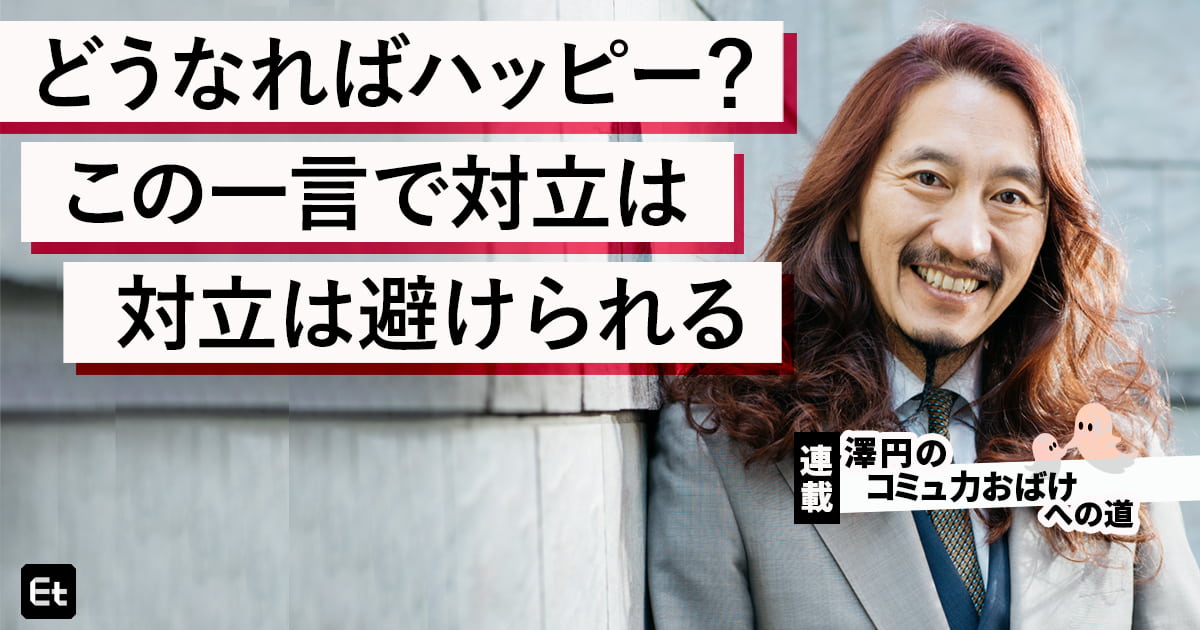
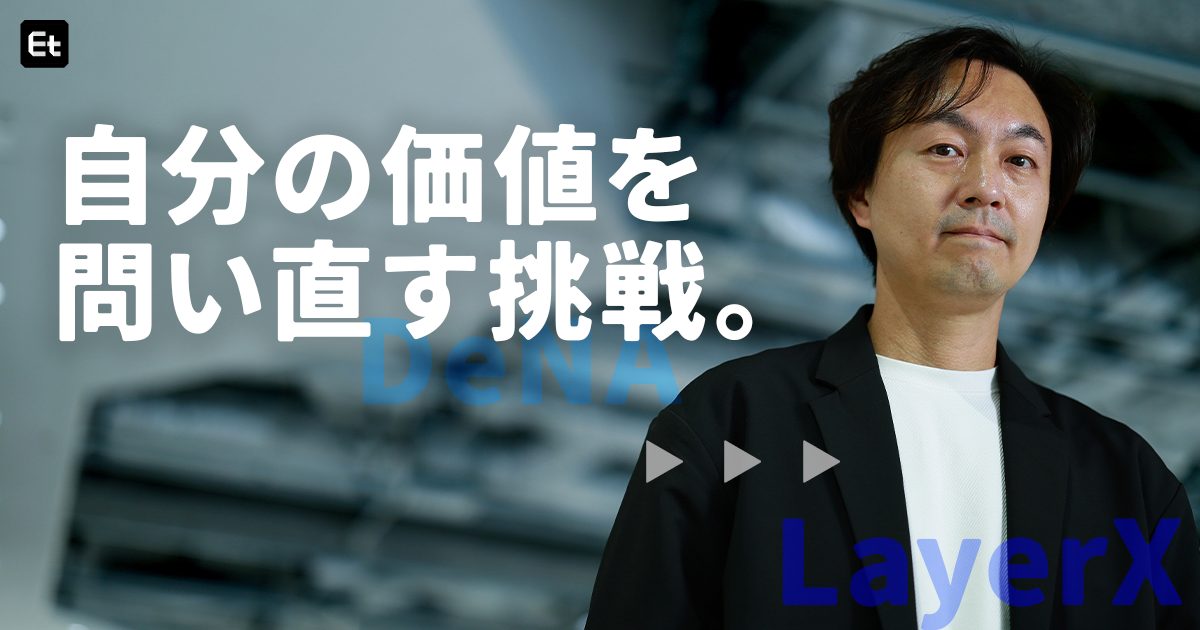

タグ