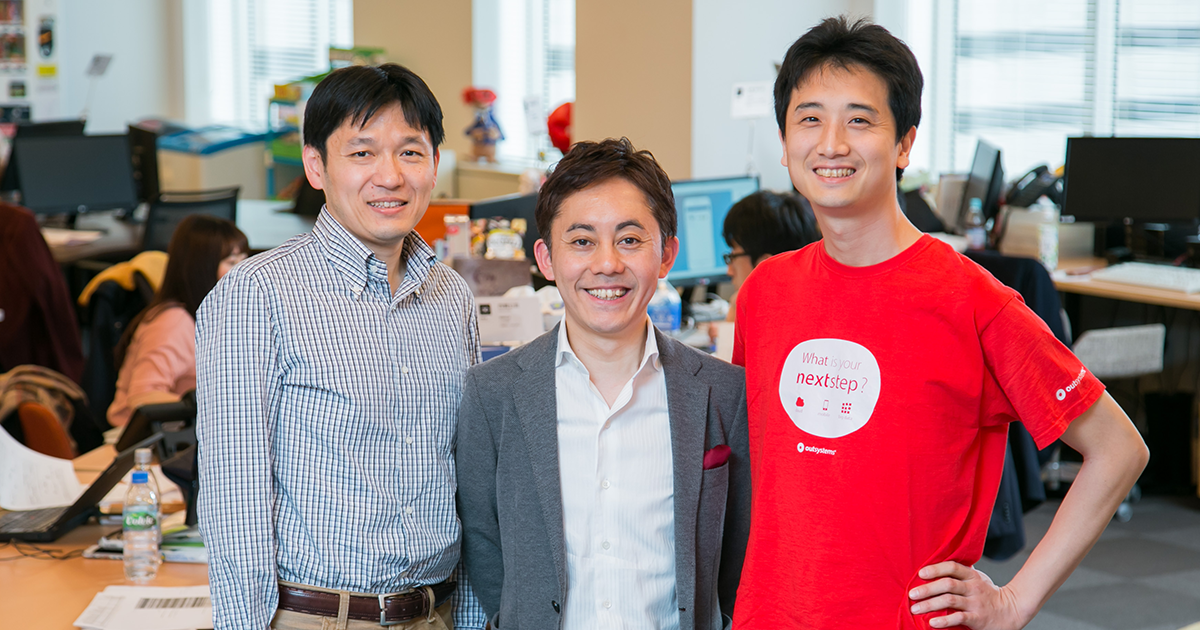社内公募で現場エンジニア5名を執行役員へ! “顧客評価=実力”を貫く「現場主義」社長のモノづくり哲学
【PR】 転職
「現場主義・実力主義で広い層にチャンスを提供する企業」というだけなら、決して珍しくはない。「若手をPMや中間管理職に抜擢する企業」というのも、IT業界では少なくない。
だが、「執行役員を社内公募で選ぶ企業」と聞けば、たいていの人は驚く。しかし、そんな企業が確かに実在する。システムの受託開発やERP導入ソリューションを軸にしながら、個人番号対応ソリューションや中国へのビジネス進出サポートといった事業も展開するベースだ。
協力会社のメンバーも含めれば合計600~700名もの人材が従事するこの会社が、執行役員の公募を実施。17人の立候補者の中から投票によって5人が選出され、2017年より新役員として就任しているという。果たして、ここまで徹底した実力主義・現場主義を具現化する意図はどこにあるのか? エンジニアのキャリア形成について、どのような思いを抱いているのか? 同社代表の中山克成氏に話を聞いた。

ベース株式会社 代表取締役社長 中山克成氏
「エンジニアの仕事」を誰よりも正しく評価できるのは顧客企業
例えば、起業したばかりの総勢数十名のベンチャーが、公募制のような形で経営幹部を選出したのだとしたら、さして驚くこともない。だがベースの創業は1997年。20年の歴史と数百名の社員を擁する企業で、執行役員を公募で決めるというのは、チャレンジングな試みだ。
この手法を選択し、実現に導いたのは、他でもない同社創業社長の中山克成氏。自身もエンジニア出身であることから、エンジニアの評価・育成には独自の哲学を持つ。社名の通り、その“ベース”となっている価値観は、「顧客の評価こそがエンジニアの実力であり、評価である」というものだ。
「上海出身の私は20代の頃、中国の大学で情報工学を学びました。卒業後は地元でSEとして働き始めましたが、早いうちから『ITで大きな仕事をするならば日本だ』と考えていたんです。30歳になったら日本へ行って働きながら勉強し、40歳までに起業をして、50歳の時に上場を達成、60歳で引退する……というように人生設計を描いていました。
そして、目標通りに30歳で日本へ来て、あるソフトハウスでSEとして働き始めた。勤務先は非常に良い会社でしたが、IT業界特有のピラミッド型の組織構造の不具合を感じるようになりました。実際に現場で成果を出しているエンジニアが必ずしも高く評価されない実態に直面することもあり、『自分が会社を作ったならば、徹底的に現場主義を貫こう』という思いを強くしていったんです」
IT業界全体で見れば、古き悪しき年功序列の慣習はやや緩和されつつあるというものの、それでも一定規模以上のSI企業の多くでは階層型の組織が存在する。経験値を積み上げたベテランがプロジェクトを率い、その上にはさらに現場を離れて長い年長者のマネジャー、もしくは現場経験のない管理職が組織を率いているケースも珍しくない。
エンジニアとして大きく成長できる機会をくれた勤務先に深く感謝をしつつも、当時のIT業界全体に根付く組織体質には違和感を持つようになった中山氏。人生設計通り、40歳で現在のベースを起業すると、フラットな組織作りを創業時から心掛けてきた。
「創業当初より随分社員が増えた今現在も、経営陣の下に本部長が1人いて、その下に15人の部長がいる、というシンプルかつフラットな組織を貫いています。部長はもちろん全員エンジニアです。ですから、“部長”といってもヒトや時間やお金の管理だけを担うマネジメント専業の管理職ではありません。彼らも現場リーダーとしてプロジェクトに参画しており、必要とあれば自分で手を動かすこともしています」
会社組織もプロジェクトの構成も極力シンプルな形に保ち、ピラミッド構造を排することで、現場の声や状況がダイレクトに経営陣に届く仕組みになっている。だが、直属上司が現場で一緒に働いている中、なぜあえて「顧客評価」を重視するのだろうか。

「私も含め、ベースはエンジニアの集団です。技術で勝負する会社だと思われがちですし、ある意味正解でもありますが、私はシステム開発事業を“サービス業”だと捉えています。お客さまに喜ばれて初めて報酬をいただけるビジネスなのです。どれだけ優れた技術を用いたかよりも、どれだけ発注者側に喜んでいただけたかによって価値が決まる。
開発したシステムに本当にご満足いただけたなら、お客さまは次に開発案件が持ち上がった時にも『またベースにお願いしよう』と思ってくださるはずです。そしてお客さまに満足していただける成果を返せるか否かは、すべて現場エンジニアたちの奮闘次第。そう考えると、『エンジニアを正しく評価できるのは社内の上司ではなくお客さまである』という結論に自然とたどり着くでしょう」
サービス業だから「お客さまに喜んでもらう」ことがゴール。技術の中身や質にこだわることは大切だが、あくまでもゴールに到達するための手段に過ぎない、という発想。先の組織に対する考え方と同様にシンプルであり、説得力がある。では、その顧客評価をどうやって適正に把握しているのか?
「これも至って明快です。担当したプロジェクトで一定の成果を出し、それをお客さまが認めてくだされば、プロジェクト自体が大規模化したり、新たなシステム案件をいただいたり、と次につながっていく。この“次につながる流れ”の有無が、そのまま顧客評価だと認識しています。
もちろん本当に次の案件が存在しないこともありますし、長期プロジェクトで明確な評価を聞くタイミングがないケースもありますから、必要に応じてお客さまの生の声を聞きに行くこともあります。
この指標をもちろん全社員も理解してくれていますから、良い意味で緊張感を持って成果にコミットする姿勢が現場に根付いているのです。そうして、成果を上げ続けることにこだわるエンジニアたちが、お客さまの期待に応えてきたことで、ベースという会社自体の信用やブランドを築いてきてくれました。当社が右肩上がりに成長することができた原動力は、間違いなく現場エンジニアたちなのです」
現場主義だからこそ、「逃げない姿勢」の持ち主がリーダーになるべき
「お客さま」と「現場」を重視するからこそ、あえてシンプルな組織と評価体制を整えてきた中山氏。エンジニアの成長を後押しするために、個々人に新たな挑戦や提案の機会を積極的に提供してもいる。とはいえ、執行役員を公募するという試みは大胆だ。その真意を問うと、中山氏は朗らかに笑ってこう答えた。
「最初に私の人生設計を申し上げましたけれど、設計通りにいかなくなったのは『50歳で上場』というところからです。ちょうどそのタイミングでリーマンショックが起きて、それどころではなくなったというのが実情ですが、どうせ計画が狂うのであれば、腰を据えてちゃんと準備をした上で目標に臨むべきだと考えを改めました。そして今、ようやく上場に向かっていく態勢が整いつつあります。
ところが私ももう61歳になりました。人生設計上は引退していたはずの年齢です(笑)。上場を目指すとともに、この会社の未来を託せる次世代の経営陣候補の育成を本気で取り組もうと考えたんですよ」
終始にこやかに語る中山氏だが、現場を重んじるからこそ、こう話す。「一定以上の年齢になれば必ず衰えは来る。人間は生き物ですから」と。中山氏自身、いつまでも社長の椅子に座っている気はない。安心して任せられる者が現れればすぐにでも明け渡す覚悟はできている。
では、どうすれば次世代の経営者候補は現れるのか。どんな人物にならば、経営という仕事を託せるのか。中山氏は熟考の末、必要条件について一つの答えに行き着いたという。それは「逃げない人」だと、短く一言で言い切る。
これまでも後進の育成にはもちろん取り組んできた。しかし、次の経営者を見いだすには至らなかった。その原因は、相手に「逃げる口実を与えてしまったから」だというのだ。
「社長が、この人ならば、と思った者を役員に任命する。これは珍しいことではありませんよね? 私ももちろんこれまではそうしていたんです。でも、このやり方だと逃げ道も与えてしまう。

『自分は適任ではないと思ったけれども、社長に頼まれたからやった』なんて気持ちを少しでも持っている人に、経営者として本気でビジネスを推進していけるわけがない。現場では、どんな局面に立たされても逃げるようなエンジニアは、ベースには一人もいません。そのトップに立つ者が、逃げ道を持っているなんてそもそもおかしい。
自ら手を挙げ、『私にやらせてください』と名乗り出たなら、覚悟を持って自分の責任で道を切り拓いていけるはずだ。むしろ、そうあるべきだと考えたんです」
オーナーシップを持ったリーダーの登場。中山氏が期待したのはその一点に尽きる。もちろん中山氏が公募制を初めて提案した時には、社内外から反対意見が挙がった。社内に与える影響や、クライアントからの見え方など、あまりにチャレンジングすぎる取り組みだけに不信感を持たれる危険もあると。
しかし、中山氏は「確かにチャレンジングかもしれないが、やってみよう」と周囲を説得し、賭けに打って出た。とはいえ、中山氏にも一抹の不安はあったという。
「どんな人が選出されるか、ということではなく、そもそも立候補者がちゃんと出てくれるかを実は心配していたんです(笑)。
当社は日本人と中国人が半々の割合で在籍しています。中国人にはチャンスさえあればどんどん自己主張する国民性がある一方で、日本人は逆に謙虚さを美徳としていて、あまり前に出てきたがらない。これまで、社内では日中の価値観や文化の違いが良い意味で共存していて、多様な視点を持って仕事を進められたり、お互いの強みを活かし合えたり、それがベースの強みにもなっていました。
そんな中で、もしも公募に立候補するのが中国人社員ばかりだったらバランスが崩れてしまう……という心配もありました。ところが蓋を開けてみたら5人の執行役員選出に対し、17人もの立候補者がいて、かつその半数以上が日本人社員だったんです」
立候補者はもちろん全員エンジニア。国籍に関係なく、多数の社員がベースの経営陣に就任するべく名乗り出てくれたこと、そして日中双方から立候補者が現れたことを中山氏は素直に喜んだ。
その後、17人の立候補者は、ベースの経営変革をテーマにしたプレゼンを行い、それをもとに60人の幹部社員が投票を行って、その上位5名を執行役員として選出した。投票結果を見た時、中山氏はさらに嬉しくなったという。
「投票だけでシステマチックに決めてしまうのも良くないと思い、最後は現経営陣による会議で最終決定することにしていました。ところが、私が事前に予想していた通りの投票結果が出たんです。オープンな公募と投票という手法でも、しっかりと選ばれるべき人が選ばれるものなのだという確信を得て、本当に嬉しくなりました」
劇的な展開もあった。もともと4人いた執行役員も同様にプレゼンを行い、投票の対象となっていたが、結果として再任されたのは1人。だが、中山氏はそれでいいのだと語る。
「執行役員の任期は1年です。今回選ばれた人たちが次も再任するかは分かりませんし、逆に今回落選した者たちにまたチャンスがめぐってくる可能性も大いにあります。逃げない気持ちを持っていれば、誰もが経営メンバーに挑戦できる。そして一度選ばれたら安泰なわけではなく、その後、結果を出さなければ当然退任となる。そうした程良い緊張感がこの会社をさらに強く大きく成長させていくと、私は信じています」
今回選出された執行役員は、今現在も現場に出て第一線で成果を上げながら、経営ボードとしての知見を磨いている。役員就任時、彼らに求める成果を明確に提示したという中山氏。任期が終了した時点で、結果は互いにクリアに分かる仕組みだ。役員人事もまた実力主義ということ。この切磋琢磨の連続が、個人と組織を強くしていくのだ。
「エンジニアはピラミッド組織の部品ではありません。現場で確かな成果を上げて、お客さまに支持された者がチームを率いるべきですし、その重責を果たして成長した者には、経営に携わるチャンスが当然与えられるべきなんです。
ベースは現場重視のフラットな組織ですから、役員になろうと社長になろうと、必要に応じて現場に出て行けば良い。現場には権限委譲の文化が浸透していますから、相手がどんな役職の人間であっても、オープンに議論をする土壌があります。そうして、あらゆる事柄から逃げない人間がそろった時、私はにっこり笑って引退しますよ(笑)」
取材・文/森川直樹 撮影/小林 正(スポック)
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

南場智子「ますます“速さ”が命題に」DeNA AI Day2026全文書き起こし

AI時代、技術の壁は消え「心理の壁」が残る。まつもとゆきひろが40年コードを書き続けて見つけた“欲望”の価値

NOT A HOTELが仕掛ける「経営陣専属エンジニア」体制はこれからのスタンダードになるか?

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
タグ