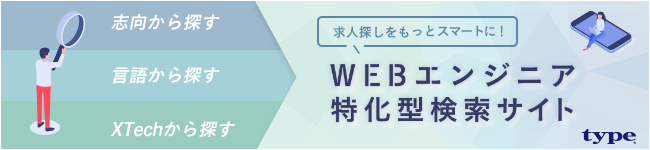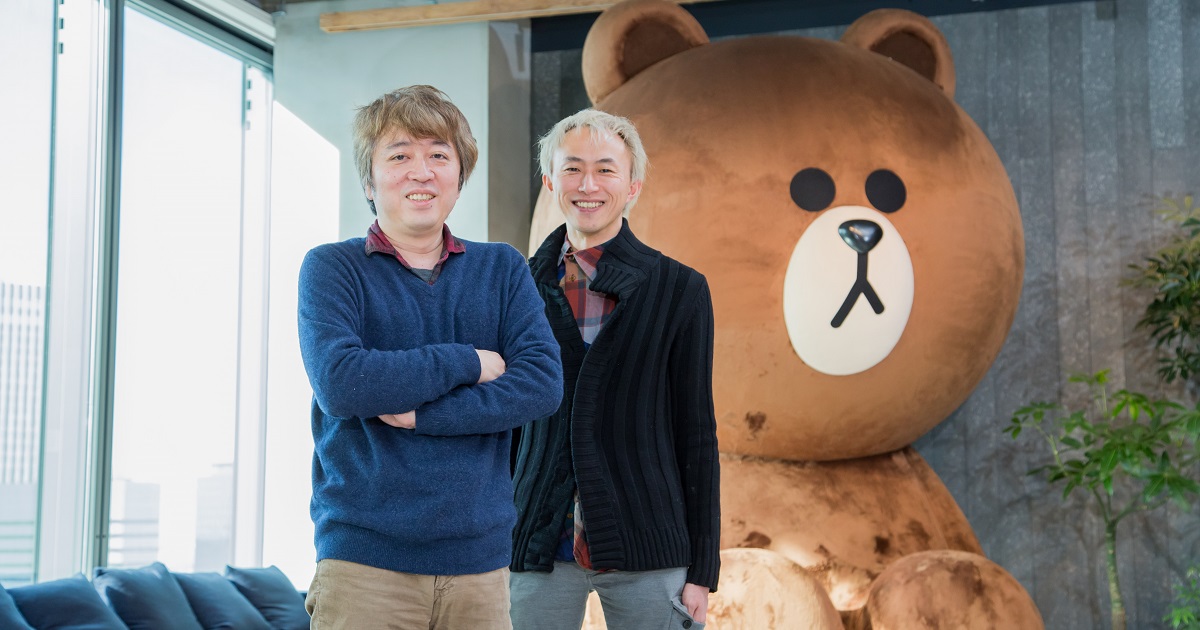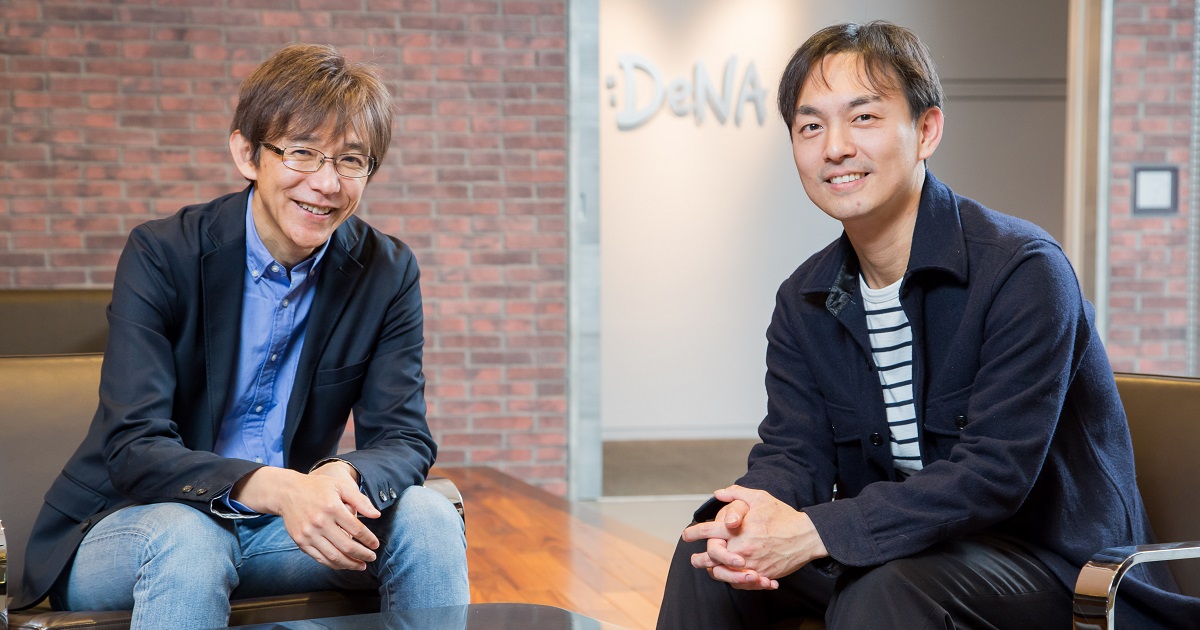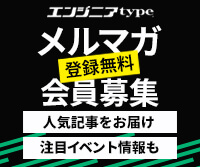無駄に元気な『チームラボMake部』の発起人による、アジアンMakerの注目人物紹介。チームラボ/ニコニコ学会β/ニコニコ技術部/DMM.Makeなどで活動をしています。日本と世界のMakerムーブメントをつなげることに関心があります

Apple創業者ともガチで語れる“ギーク大臣”が明かす、「技術で国家の未来を作る3つの指針」とは【連載:高須正和】

俺たちのMinistar
シンガポールの政治家はおおむねテクノロジーに関心があるようですが、Vivian Balakrishnan大臣(ヴィヴィアン・バラクリシュナン、以下ヴィヴィアンと表記)は極めつけです。

オプティマスのコスプレと一緒に写真を撮るヴィヴィアン大臣
僕はシンガポールMini MakerFaireの実行委員をしていて、ほかにもいくつかシンガポールのMakerイベントにかかわっているのですが、とても高い確率で、休日にヴィヴィアン大臣が、息子さんを連れていらっしゃいます。
最初にお会いしたのはMakeblockというDIYのイベントだったのですが、トランスフォーマーのオプティマスのコスプレと一緒に写真を撮っている人が大臣と聞き、ずいぶん気さくな人だなあと思っていました。
気さくな人だという印象はその後も変わらないのですが、かなり熱心に各ブースを見て回り、特にハッカースペースシンガポールのブースで売っていた、電子回路にはんだ付けなしでセンサー類を取り付けられるGrove Kitに興味を示していました。
ハッカースペースの人と「これにArduinoは入ってる?」、「RaspberryPiで使うことはできるの?」など、かなり細かい話をした後、ポケットマネーで買っていかれました。
その後、この記事を『コバルト爆弾αΩ』のomikronさんに教えてもらったことで興味が沸き、いろいろ調べてみて、そのギークぶりにすっかりファンになりました。

Grove Kitに興味津々のご様子
それから3週間後、シンガポールの『Mini Maker Faire』が開かれたのですが、そちらでも開場してから真っ先に来て、ブースを歩き回るヴィヴィアン大臣の姿が見られました。
注意してみていると、長い時間足を止めてるブースはどれもかなり面白いのです。
今は環境大臣をやっているので、リサイクルとかDIY太陽光発電のブースで話をしてる時間が長いのですが、他でも面白そうなブースでは例外なく足を止めていました。
ブースでの会話も、コンセプトだけではなく技術のかなり細かいところを聞いていたり、作品公開からの反応を聞いていたり、政治家にありがちな「仕事としての訪問」とはまったく違うものです。それは僕らと変わらない『MakerFaire』のお客さんでした。
シンガポールのMakerはたいてい彼と話したことがあります。シンガポールのMakerにとって、彼は「俺たちの大臣」なのです。

「ハッカースペースシンガポールでは珍しい、日本人のメンバーなんだよね。ありがとう」と、記念写真にも応じてくれました。僕が着ている赤いポロシャツはシンガポールMakerFaireの実行委員/出展者がもらえるもので、ヴィヴィアン大臣はMakerFaireのホストでもあります
Apple II plusからのコンピュータ使い
ヴィヴィアン大臣は今53歳。10年前、43歳の時からさまざまなポストを経験している、とても若い大臣です。
1961年、タミル系インド人(シンガポールの人口の1割ぐらいはタミル人で、タミル語は公用語の1つになっています)の父と中国人の母の間に生まれました。
高校生の時、医者だった父がApple II plusを60万円ほどで購入したことからコンピュータ歴がスタートします。日本だと、野尻先生(尻P)とか歴本先生とかとおおむね同じ世代のギークだとおもいます。
「コンピュータについては、1980年代に、ゲームをハックするところから学び始めた。『オデッセイ』という、“ローグ”みたいなキャラクタベースのRPGゲームを、ジョイスティックで動かせるようにした。当時はインターネットがなかったから、図書館でコンピュータを勉強し始めたね」
ヴィヴィアン大臣はその後、奨学金を得てシンガポール国立大の医療科に進学。さらに1990年代からイギリスに留学して医療について学び、ロンドンで眼科医として働き始めます。このときもコンピュータ熱はもちろん続いていて、当時の人気アプリ『Wordstar』をハックして、電子カルテシステムを自作していたと言います。
「さすがに仕事をしながらだと、出荷できるようなクオリティのものを作るのは難しいけど、電子カルテシステムは数少ない、ちゃんと使えたモノの1つだ」

DIY太陽光発電のブースに足を止めるヴィヴィアン大臣。左の少年は息子さん
その後シンガポールに帰国しても眼科医としてのキャリアを重ね、2000年ごろから陸軍病院に勤務、その後政治にも携わるようになりました。
ヴィヴィアン大臣は今も仕事が終わると電子回路やプログラムをいじって、何か工作をしています。3人の子供がいて、一番小さい子供は7歳なのですが、彼のためにLittleBitsで一緒に遊んだり、レゴ・マインドストームのためのプログラムを書いたりしています。
家族が家のドアをWeb経由で開けられるように、Webと連動したマイコンとリレー回路を使って、「携帯からパスコードを入れると家のドアが開くシステム」を作ったりもしている、ソフト、ハード、ネットワークまで一通り今も触っている現役のギークです。
クリエイティブすること
ヴィヴィアン大臣はコンピュータやプログラムそのものだけでなく、それが何に使われるかについても深い関心を払っています。
「子どもに正しいツールを与えると、僕たちの予想を超えて彼らのアイデアは広がっていく」
「価格破壊はもう起こっていて、『お金が原因で何かできない』ということはもうなくなっていく。父がローンを組んでくれたApple IIは$6000もしたけど、RaspberryPiは$38で、小学生以下の子供でさえ、プログラムを学ぶための情報が無料で手に入る」
MakerFaireのホストを引き受けたのも、「メイド・イン・シンガポール」のテクノロジーを生み出したいからだと言います。
次世代のシンガポール人に求めるABCとして、ヴィヴィアン大臣はこの3つを挙げています。いかにもMakerらしい言葉です。
A=Art
感覚に訴えかける、グッと来るモノは何かについてきちんと考えるべきだ。
B=Building
オリジナルのものを自分で「創る」というマインドをもたなければならない。
C=Communication
感覚に訴えかける良いモノを作った時、その「良さ」をきちんと伝えないとならない。「速い」、「安い」だけではダメだ。シンガポールを商人だけの国にしてはいけない。
また、ヴィヴィアン大臣は自分のブログで、スティーブ・ウォズニアックとApple IIのBasicやシンガポールの教育、クリエイティブについて語り合ったことを書いています。ウォズと普通に話せるハッカーが閣僚をやっているというのはすごいことだと思います。
アメリカでもオバマ大統領がホワイトハウスでMakerFaireを行ったり、Googleのエリック・シュミットCEOとの対談で、「100万の32ビット整数を効果的にソートするにはどうすればよいと思われますか?」と冗談をふられて、「バブルソートを使うのは間違いだと思う」と即答して会場の喝采を浴びるなど、テクノロジーに関心の深いところを見せています。
(もっとも、アメリカ人のMakerに「アメリカの政治家はすごいね!」と言ったら、「あれはオバマが特別で、ブッシュ親子はぜんぜんテクノロジー詳しくないと思うよ」と返されましたが)

僕が書いた「ギークが大臣をやってる国 シンガポール」のレポートを見て、「日本人が書いてくれたのは初めてかも。もっとたくさんの日本人ギークがシンガポールに来るといいね」と喜ぶヴィヴィアン大臣
MakerFaireでのヴィヴィアン大臣との立ち話で、「ホワイトハウスのMakerFaireはすごいですね、僕らもやりたいですね」と話したとき、「いいねえ、日本のほうが早いんじゃないかなー」とお答えになられたのですが、僕はたぶんシンガポールのほうが早そうな気がしています。日本のMakerが大臣と気軽にこんな話ができるのは、まだ先だと思うので。
日本でも与謝野馨氏(もと通産大臣)は自作PCのマニアだったようですが、最近の政治家でテクノロジー好きそうな人が見当たらないのがさびしいところです。
ハッカーにとって「俺たちの大臣」のいる国シンガポールには、多くのハッカーがいます。いろいろなアジアのハッカーをこれからも紹介していきますのでお楽しみに。
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング
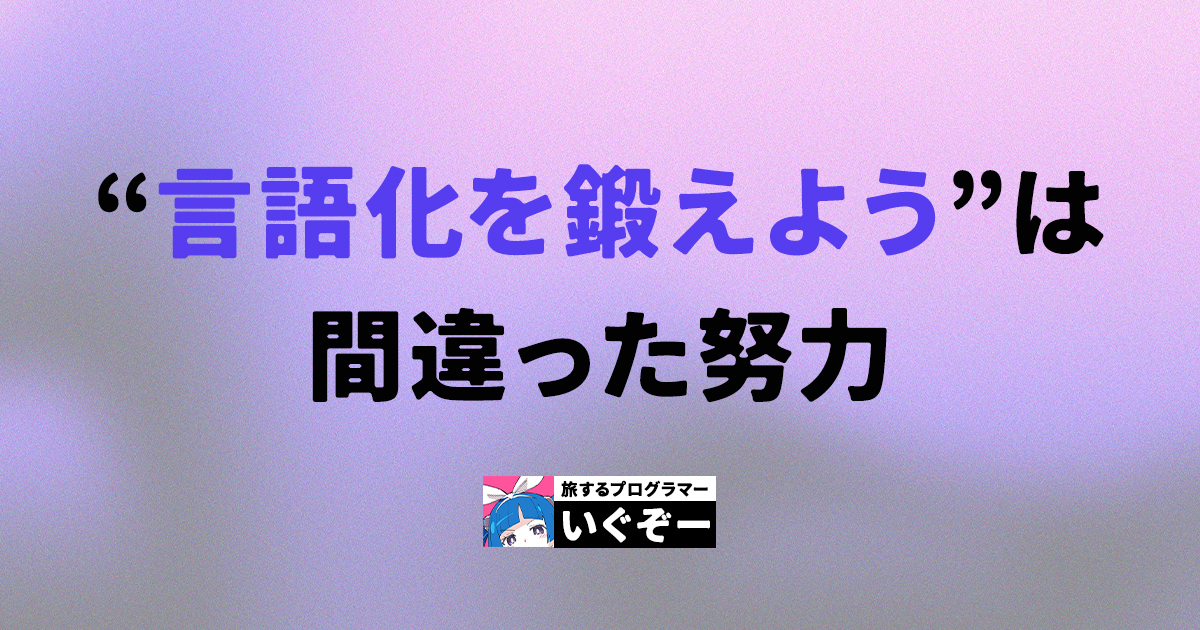
エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?
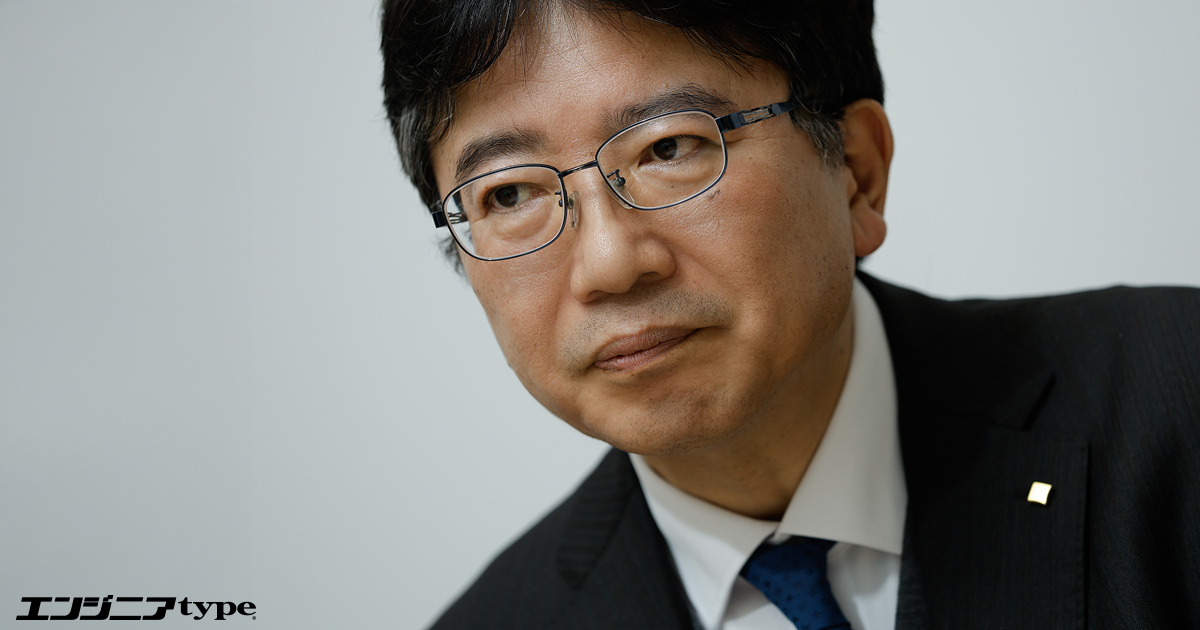
AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”
タグ