
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 第2IP事業ディビジョン 第3プロダクション ゼネラルマネージャー 河野一聡さん
1994年株式会社ナムコ入社。フライトシューティングゲーム『エースコンバット』シリーズのブランドディレクター。シリーズには、97年の『エースコンバット2』から関わっている。ヨコオタロウ氏とは大学の先輩後輩の関係で、ナムコの同期

新型コロナウイルスの影響で人々の在宅時間が増え、「可処分時間」の使い方に大きな変化が訪れた。
これまでは“おうち遊び”の代表格だったゲームの他に、YouTubeや電子漫画といった娯楽コンテンツの需要も急増。そうした中で、「選ばれるコンテンツ」を作り続けるためにはどんなことが必要なのだろう?
そのヒントを探るべく、4月13日(火)~17日(土)にかけて行われた『ENGINEER キャリアデザインウィーク』(ECDW)の中で、「熱狂を生んだゲーム開発者に学ぶ、最高の顧客体験の生み出し方」のセッションを実施した。
登壇してくれたのは、昨年シリーズ25周年を迎えた『エースコンバット』のブランドディレクターを務める河野一聡さんと、世界中に多くのファンを抱える『ニーア』シリーズのディレクター、ヨコオタロウさん、プロデューサーの齊藤陽介さんだ。

(写真左)『エースコンバット』シリーズ
バンダイナムコエンターテインメントから発売されているフライトシューティングゲームのシリーズ。2019年に12年ぶりのナンバリングタイトル、『エースコンバット7スカイズアンノウン』が発売された。シリーズの世界累計出荷数は1600万本を超えている(2021年時点)画像はTwitterより/ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN & © BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
(写真右)『ニーア』シリーズ
スクウェア・エニックスから発売されているアクションRPGのシリーズ。2017年に発売された『ニーア オートマタ』が世界累計出荷・ダウンロード販売本数で550万本を突破。21年4月には、10年に発売されたシリーズ1作目『ニーア レプリカント』のバージョンアップ版となる『ニーア レプリカント ver.1.22474487139...』を発売した
ゲーム業界の第一線を走り続けてきた3人の思考から、これからのゲーム開発者に必要なことを学ぼう。

株式会社バンダイナムコエンターテインメント 第2IP事業ディビジョン 第3プロダクション ゼネラルマネージャー 河野一聡さん
1994年株式会社ナムコ入社。フライトシューティングゲーム『エースコンバット』シリーズのブランドディレクター。シリーズには、97年の『エースコンバット2』から関わっている。ヨコオタロウ氏とは大学の先輩後輩の関係で、ナムコの同期

株式会社ブッコロ 代表取締役 兼 ゲームディレクター ヨコオタロウさん
1994年株式会社ナムコ入社。株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、株式会社キャビアを経て、株式会社ブッコロを立ち上げる。『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズや『ニーア』シリーズなどのディレクションを担当。ゲーム以外にも、漫画や舞台の原作などでも幅広く活躍中
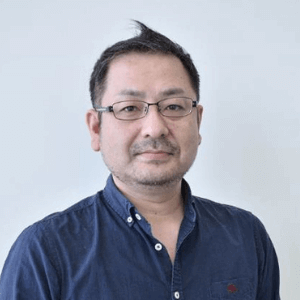
株式会社スクウェア・エニックス 取締役 兼 執行役員 齊藤陽介さん
1993年株式会社エニックス(現:株式会社スクウェア・エニックス)入社。 『ドラゴンクエストX オンライン』や、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』、 『ニーア』シリーズ等のプロデューサーを務める。 またアイドルグループ『GEMS COMPANY(ジェムズ カンパニー)』のプロデューサーも担当している
河野:前提として僕らは3人とも同世代で、同じようにゲームの歴史を体験してきたと思うんですよね。僕が初めて遊んだハードはスーパーカセットビジョン(1984年発売)でした。その後カシオのPV-1000(83年発売)を買って、その後にファミコンでしたね。それで、子どもの頃にゲームをプレイして感じていたのは、「こんなに自分が介入できる遊びがあるんだ」ということだと思います。
“インタラクティブ”な点がゲームと他のメディアの大きな違いですが、今はさらに「一人遊びのゲーム」と「コミュニケーションのツールのためのゲーム」は違うものなのでは、と考えるようになりました。
一人遊びのためのゲームは、「ゲームをすることで別の誰かになれる」もの。『ドラクエ』だったら勇者になれる。僕の作っている『エースコンバット』なら、エースパイロットになれる。僕はこれを「Be Needs」と位置づけています。
もう一方のコミュニケーションツールとしてのゲームは、協力プレイもそうですし、僕が今関わっている『鉄拳』などの対戦ゲームもそう。共闘や対戦をすることで人とつながることができるもの。こちらは「Do Needs」の位置づけです。
そして、これから先は「Be Needs」と「Do Needs」の二つを満たすゲームによって、どんどんと仮想世界に居場所がつくられていく。つまり、メタバース的な方向に向かっていくんじゃないか、というのが僕の考えです。『ファイナルファンタジーオンライン』などが分かりやすい例ですね。
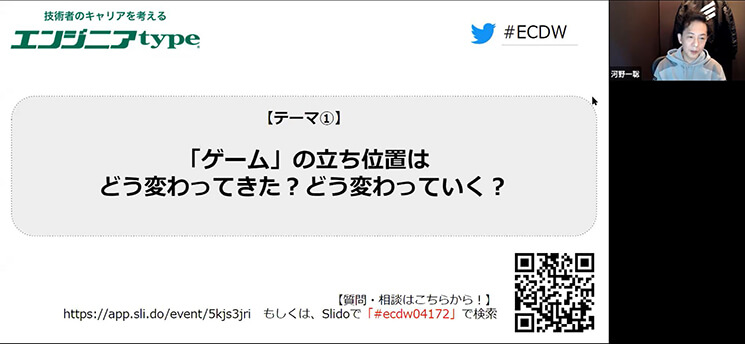
齊藤:昔のゲームはクリスマスや誕生日など、アニバーサリーなタイミングで欲しいソフトを買いに行くといった立ち位置だったけれど、今はもっと日常に密接なところにゲームというものがある感じはしますよね。
特にコロナ禍を通して感じたのが、世の中がいっぺんに変わってしまうようなことが起きた中で、ゲームよりももっと大切なものが山ほどあるんじゃないか、ということ。「ゲームなんてもういらないのでは?」と思っていたんです。
そんな話をしたらゲーム好きの皆さんから「こういうご時世だからこそゲームがあって助けられた」という声もたくさんいただいて、ありがたかったですが。
ただ、やっぱりエンターテインメントとしてのライバルは技術の進歩とともにたくさん生まれてきているので、僕らは面白いものを作り続けなければいけないな、と改めて思いましたね。
ヨコオ:河野さんも仰ってましたが、僕らはちょうど同年代でゲームの進化とともに歩んできたというのがあって。振り返ってみると、昔のゲームって、何というか、うさん臭かったんですよね。縁日の的屋みたいな、怪しい社会とつながっているような文化だった。
それが最近はちゃんとした大学を出ている方もゲーム業界に就職するようになって、産業としてすごく成熟してきたと思っています。
そんな流れの中で、僕はスクエニさんとゲームを作ってきたわけですが、昔のゲームはとにかく「プレイ時間を稼げ」って言われていたんですよ。それでひたすらプレイ時間を延ばす工夫をしてきたんですけど、最近は、そういうことはだんだん言われなくなってきたなって。
昔は、一人の時間を長く拘束するゲームに価値があった。でも今はもう時代が違ってきていますね。スマートフォンのゲームもそうですけど、これまでのゲームの要素が細かく小さくなっていて、生活に分散して溶け込みつつあるなと思っています。
河野くんの言うメタバースはそれらが統合された世界のイメージだと思いますが、僕はどちらかというと細かくいろんなところにゲームが埋め込まれていって、今みたいな形のゲームはいずれ消えていくのではないかと考えています。
ヨコオ:まず、皆さんは僕ら3人が並んでいるのを見て、同じような人間に見えているかもしれませんが、全然違うんですよ。
『サイコミ』の連載(真説ゲームクリエイター伝 ヨコオタロウ編)を見ていただくと分かると思いますが、僕はいろんなゲーム会社に勤めていろんなプロジェクトを毎回崩壊させて友だちをなくして今はフリーランスで孤独に戦っているっていう人間で、齊藤さんはその孤独な人間を、鞭を打って動かす人間。河野さんは唯一、会社の仲間たちとチームをつくっている人間なんです。
だから僕は、なぜ河野さんは仲間づくりに成功して僕は失敗したのか、というのを河野さんに教えてほしいです。
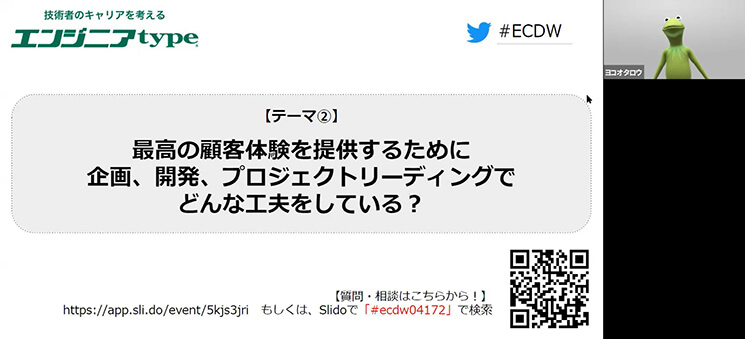
顔出し不可のヨコオさんはカエルの姿で登場してくれた
河野:やり方が汚いですね(笑)。そんな、綺麗な話はないですよ。ただ、本当に信頼できる仲間とずっとやれているので、そこは恵まれているなと思います。
特別気を付けていることはないのですが、最近はオンラインになってコミュニケーションがとりづらくなったというのが事実で、いろんなゲームを開発する中で雑談量を増やすようにしていますね。毎回の会議の冒頭で、僕が今見ているドラマや映画など、「面白い」と感じたことをみんなに伝える、という時間を取るようにしています。
目的は二つあって、一つは自分が面白いと感じたものをちゃんと言語化できるかを確かめること。「こういう構造で、こうなっているから受け手が面白いと感じるのである」という話をロジカルに整理できているかをメンバーに試し打ちしているんです。
二つ目は、その反応と結果を見ています。メンバーに話が響いた場合は、その「面白さ」のロジックがゲームに応用できるかもしれない。響かなかった場合は、僕の伝え方が悪かったのか、それともそもそも面白くないから響かないのかを探るんですよ。そうやって、みんなで「これは面白い」と感じるものの共通認識を作るといいますか。一体感づくりの一つです。
齊藤:うちも基本は在宅ですね。今は役員会なんかもzoomでやっています。でも、ヨコオさんはzoom嫌いなんですよね。
ヨコオ:zoom嫌いですね。毎回断ってます。
河野:じゃあどうしてるんですか?
ヨコオ:僕はslackでテキスト会議してます。週1回チームで決まった時間に集まって、質問とか雑談をしていいよ、みたいなことをやっていますね。その中で一問一答のやり取りがあったり、画像チェックお願いしますみたいな依頼がきたりするので、それを順番に見ていくという。
河野:なんかタロウさんに合ってますね。
ヨコオ:河野さんと違ってあまり人間が好きではないので(笑)
ヨコオ:僕は正直、上のポジションの人間なんて、現場にいない方が良いと思っているんですよね。
若手が自分たちだけで頑張って作れるという環境が一番大事で、若い人が船を操縦している間、船長である僕は後ろの方で寝てるだけでいい。でも前に進まなくなってしまったり、方向を迷いだしたりしたときにちょっと甲板に出てきて軌道修正するみたいな。そういう感じが理想だと思ってやっています。
齊藤:でも理想と現実は違いますよね。
ヨコオ:そうなんですよ。大体迷っているんですよね。だから常に甲板にはいなきゃいけない。なかなかうまくいかないです。
河野:状況としてはうちも一緒ですね。「もう完全に任せた! 僕は責任は取るけど見ない振り!」ってやっていたんですけど、あらぬ方向にさまよいだして2、3回世界観を作り直していた時もありました。
ヨコオ:でもやっぱり任せるときは、ダメでももうそれを製品で出してもいいくらいの覚悟で任せないといけないですね。
ヨコオ:僕は、できればニーアの世界観は毎回変わってほしいと思っていますね。『ニーア』というのはスクエニさんから出していただいているタイトルの一つでしかなくて、タイトルとは何かというと、「お金をもらう理由」だと思っているんです。だからそれを使って若い人がオリジナルのものを作るというのは全然アリだと思っています。
齊藤:でもまだ任せられないんですよね?
河野:違うものが出てきたら怒るんですよね?
ヨコオ:そうなんです。そこがダメなんですよね。でもお伝えしたいのが、本当に優れたトップランカーのようなディレクターって、そういうときに他の人を圧倒してスタッフを潰すことがあるんですけど、恐ろしいことにその自覚がないんですよね。
本当にトップの人は「僕はみんなとうまくやっている」って言いながら何人もの人を踏みつけている。
河野:かわいがっているつもりで頭をなでていたら首がもげちゃった、みたいなね。
ヨコオ:そう。僕はその領域には到達していないなと思います。悪いなと思いながらやっているので。
齊藤:たしかにゲーム業界でそれなりに成功しているディレクターさんは、方向は違うけど変わった人が多いですよね。言ってしまえば社会不適合者というか。普通のサラリーマンとしてはやっていけないような人が、本当に面白いものを作るんですよ。
河野:空気読みな人にはディレクターは難しいと思いますね。
ヨコオ:これまで「みんなで仲良くプロジェクトを回そう」とか「みんなの意見を聞いてやろう」という人を見てきましたけど、その人たちが軒並み失敗しているのを見ていると、とりあえず「みんなで仲良く」という戦略はディレクターには向いていないのだと客観的に感じました。
齊藤:ゲーム作りはみんなで一緒にというわけにはいかないから、最後は自分が引っ張っていくぞという気概がないと厳しいですよね。
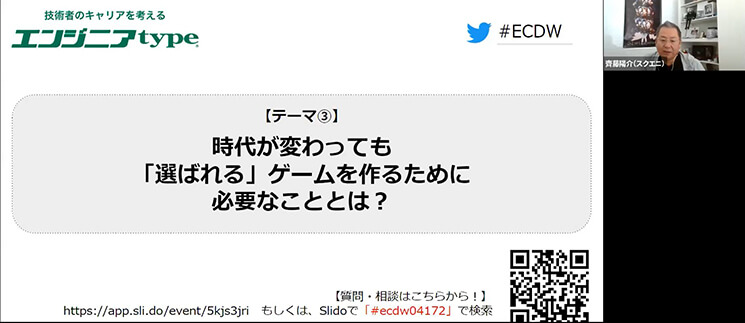
齊藤:これまでを振り返ると、ゲームの本質や「選ばれるゲーム」って昔から変わっていないと思っていて。どんなゲームでも、やっぱりちゃんと作らなきゃダメなんですよね。妥協したものや途中で右往左往したものってあまり売れていない感じがするんです。
『ニーアオートマタ』もヨコオさんと最初に作り始めたときに、プリプロダクション(本格的に製作に取り掛かる前の工程)のフェーズで作ったものがそのまま製品になったんですよ。

『ニーア オートマタ』
2017年2月に発売されたタイトルで、10年に発売されたニーアシリーズ1作目『ニーア ゲシュタルト/レプリカント』の後継作品。アクションRPGではあるものの「オートモード」を搭載し、アクションが苦手な人でも手軽に楽しめるようにしていたり、トロフィーをゲーム内通貨で購入できたりといった独自のシステムが話題を呼んだ。「第21回D.I.C.E. Awards」でRole-Playing Game of the Year、「ゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワード 2018」でAudience Award、「日本ゲーム大賞 2017」で年間作品部門 優秀賞などを受賞している
齊藤:そういった、最後までブレずに作り続けられたものが結果的にお客さんに喜んでもらえるゲームになるんじゃないかという気はしています。あとは、やっぱりスケジュールを伸ばすとゲームやアイデアの鮮度が落ちてしまうので、長く続ければいいものでもないと思いますね。
河野:妥協せずという点は僕も本当に一緒ですね。
「選ばれるゲーム」というテーマは非常に難しいと感じます。正直ゲームって、いまなら無料でいくらでもできるんですよ。選ばなければ。そうすると、選ばれるためには「価値をどう付けるか」だと思っていて。
一定のお客さんは、ゲームを買う前に時間のコストを計算していると思うんですよね。例えばスマホゲームだったら5分で楽しめるものもある。でもわれわれが提供するゲームの中には、全てを楽しむまでに100時間かかることもある。じゃあそれを超える価値をどうやって作るか、というのが選ばれるためには必要で。
そのために僕がずっと言っているのは、顧客満足を超える強烈な満足をつくらなきゃダメだということです。組織では「“顧客感動”をつくりなさい」という話をずっとしています。
顧客感動の定義は、「満足を超えた強烈な満足」です。強烈な満足を生み出すためには120%以上のパフォーマンスを発揮したゲームを作らないといけない。
120%のパフォーマンスができていると、お客さんはファンになってくれるんですよ。そして、ファンになってくれたお客さんは僕らの「次」に期待をしてくれる。だからこの順番を間違えてはいけないし、妥協してはいけない。そういうことを変わらずやっているつもりです。

河野さんは以前、エンジニアtypeの取材でも「顧客感動」について語ってくれている。
>>制作5年目でゼロから作り直し、2年の発売延期…『エースコンバット7』河野一聡が貫くスピード重視時代の“正しいこだわり”
ヨコオ:齊藤さんと河野さんっていう、大手企業に勤めて利益を上げなければいけない人に対して、僕はフリーランスなのでお金さえもらえれば基本何でも作るっていうポジションにいるんですよね。なので僕の考え方としては、お仕事をいただいてお金をもらえてさえいれば、作ったゲームが売れなくても別に構わないと思っていて。
だから感動なんか別になくてもいいんじゃないかなって思うし、『ニーアオートマタ』の時も「面白いゲームはもう作らなくていい。そこはあまり頑張らなくていいよ」という話を現場に言っていました。世の中に面白いアクションゲームってもうたくさんあるじゃないですか。だからそれをもう一つ作る意味はあまりないよねって。
僕には昔から抱いているイメージがあるんです。学校のグラウンドみたいな広い土の平原に穴がいっぱい空いているっていう。穴っていうのは「ゲーム業界でまだ誰もやっていないこと」を表しているんですけど。その穴を見つけては埋めるっていうのをやり続けなければいけないという一種の強迫観念に駆られているんですよ。
例えばスノーボードって「うまく滑る、かっこよく滑る」っていうのが王道の面白さじゃないですか。でも場合によっては「雪山で女性とイチャイチャする」とか「家族で行って、楽しい思い出になった」とか、さまざまな価値があると思うんですよ。
そういう、従来の価値がなかった場所の穴を探して埋めるっていうことをやっていきたいと、いつも思っています。
ヨコオ:まあ基本的にはスクエニさんが許してくれる範囲で、お金をもらえるルールの中で埋められる穴を探しているんですけどね。ルールがなければ「Aボタンを押したら人が一人死ぬ」みたいなゲームもいつか作らなきゃいけないなと思っています。まだ誰も作っていないので。単純に法律と予算が許してくれないだけで(笑)
齊藤:でも、スクエニの会長の福嶋康博さんも似たようなことを言っていましたね。年間100本のゲームが出たとして、そのうち95本はシリーズものや、これまでにあったようなゲームだとしたら、残りの5本くらいは全く新しいゲームが出ると。
それで、仮に年間3本のヒット作が出るとき、2本は前者の95本の中から出て、1本は後者の5本の中から出るとする。だったら、新しい5本のうちの1本のヒットを目指せって。「どうせやるんだったら新しいものを」っていう。
そういう意味では、選ばれやすいものを作るには「新しいもの」を突き詰める、というのは一つあるかもしれないですね。
ヨコオ:僕は二つあって、一つは『ICO』というゲーム。
いわゆる「華やかで面白い」ことがゲームの価値である、という時代が続いていた中、いろんな要素をそぎ落としたシンプルなアートスタイルをゲームデザイナーの上田文人さんという方が作られて、すごく衝撃を受けたんですよね。
ゲーム業界で初めて「引き算」を使った人だと僕は思っていて、そういう意味でICOはすごく表現の幅を広げた作品だと思っています。
もう一つは『斑鳩(いかるが)』というシューティングゲーム。音楽と映像がすごくリンクしていて、まるで舞台演出を見ているみたいな美しさで。こういうことをゲームでやれるんだ、という可能性の広がりをすごく感じました。
『ICO』
2001年12月、ソニー・コンピュータエンタテインメントよりPS2用ソフトとして発売されたアクションアドベンチャーゲーム。11年にPS3でHDリマスター版が発売されている。ゲームデザインを手掛けた上田文人さんの作品には、他に『ワンダと巨像』や『人喰いの大鷲トリコ』などがある
『斑鳩』
(株)トレジャーが01年に発売した縦スクロールのシューティングゲーム。当初はアーケードゲームとして稼働していたが、後にドリームキャスト、ニンテンドーゲームキューブ、Xbox 360などで販売。18年にはNintendo Switch、PS4で配信開始した
齊藤:僕は古いPCゲームなんですが『ザ・ブラックオニキス』というダンジョンもののRPGですね。友だちの家に毎日のように押しかけてやらせてもらっていました。
あとは初めてのボーナスで購入したMacでやった『ディアブロ』です。これもダンジョンを潜るRPG。当時は実家に暮らしていたのですが、まだネット使い放題じゃなかったので、月に10万円近い電話代を使ってしまい、「いやらしい電話番組を聞いているんじゃないか」という疑惑を家庭内に生んでしまいました。
あの頃は本当にゲームをやりまくっていて、会社から戻ってきて朝までやって、また会社に行って……っていう生活をしていました。そのうち家に帰らずに会社に泊まり込んでゲームをやっていましたね。
『ザ・ブラックオニキス』
1984年に発売されたPC用RPG。当時はまだ「RPG」というジャンルが成熟していない頃で、最初期の作品。後にファミコンやゲームボーイカラーでも発売されている
『ディアブロ』
アメリカのゲームソフトウェア開発会社Blizzard Entertainment社から1996年に発売されたゲームで、MORPG(Multiplayer Online Role-Playing Game=複数プレイヤー参加型オンラインRPG)の先駆けとなった作品
河野:僕が一番影響を受けたのは日本ファルコムの『イース』だと思います。イースで初めて高校を休んだんですよ。物語とビジュアルと音楽が融合した感動もそうですし、冒頭に話した「Be Needs」の現初体験がイースだったと思います。
『イース』
1987年に第1作が発売されたアクションRPG。『イース』シリーズは日本ファルコムの看板作品で、2019年にシリーズ9作目の『イースIX -Monstrum NOX-』が発売されている
>>イースポータルサイト
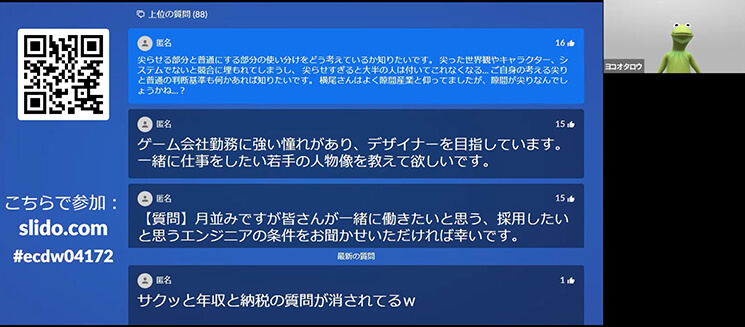
ヨコオ:ゲーム作りに限らずエンタメ全般に言えることですが、まず大前提として「分かる」必要があるんですよ。本にしても読みづらいのはだめだし、ゲームにしても遊んでいて今何をやっているのか分からないのはだめ。そういう、「迷う」要素を廃止するんです。
その後はモチベーションの維持をさせなければいけないので、面白くするとか快適にするとかが必要です。つまり「分かる」の次にくるのは「楽しい」といった要素。
その二つの土台があって初めて「その上に何を盛ろうか」と考えることになるんですけど、正直なことを言えばこの土台作りで大体のゲームは製作時間が終わってしまうと思います。
なので皆さんが既存のゲームで「尖っている」と感じるところには二つの可能性があって、一つは何かをちゃんと作ろうと思ったけどたまたま尖っちゃったもの。もう一つは無意識に何かが混ざってしまった変な尖り。意図的に「尖っているゲームを作りたいから何かをやる」っていうのはほとんどない気がします。みんな真面目に作ってると思いますよ。普通の人は。
齊藤:やっぱりゲームを作るのには時間が掛かるんですよね。あと、最後は情熱で押し切るしかないこともある。だからそういう意味では、情熱と元気があって、ゲームが好きだっていうことが強みになるんじゃないかと思いますね。そこにスキルとかが付いてくれば素晴らしいですけど。ゲームが好きであることが一番重要かと思います。
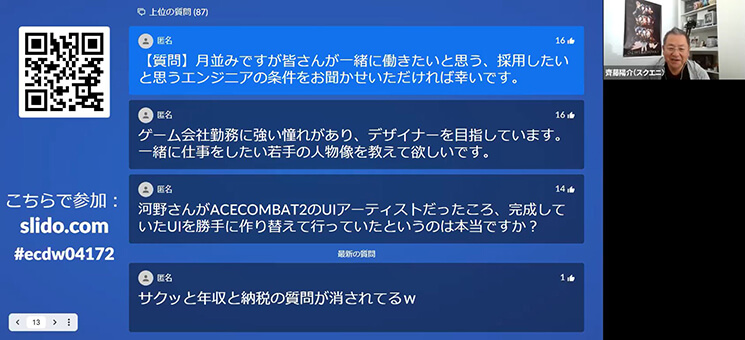
河野:僕も最近は面接をやっているんですけど、みんな優秀で幅広くて好きなものもしっかり語ってくれるんですよね。でも僕としては本当に一つの好きなことに変態的にハマっている、深さのある人の方がいいなと感じます。
なので面接のときもかなり深ぼりをしていくんですが、綺麗な言葉で表層的な返しをする方が多くて、変質的なこだわりを持っている人を発見するのが難しいんですよ。でも僕はそういう人と一緒に働きたいと思っています。
ヨコオ:僕はエンジニアに限らず、やさしい人がいいですね。自分がすぐ怒るタイプなので、僕みたいな人が増えるとしんどいから。人としてまともでやさしい人と働きたいと思います。
河野:じゃあ、僕がタロウさんの下で働きたいって言ったら採用してくれるんですか?
ヨコオ:河野さんは無理でしょ、すぐキレるじゃないですか。
河野:ははは(笑)
ヨコオ:スキルは学習でカバーできることが多いですけど、人間性はあまり直せないので、最初にまともな人がいいなって思います。人は自分にないものを欲しがるんですよ。
齊藤:あとこれも答えてあげたいですね。「ゲーム業界に入りたかったけど、面接で全滅してしまった。どうすればゲーム業界に入れますか?」という質問。
少なくともスクエニではそうですし、バンナムさんも同じだと思うんですが、ゲーム作りには「QA」、いわゆるデバッグ作業というものがあるんです。そこにアルバイトで潜り込んで頭角を現せば、ゲームクリエイター側にジョブチェンジとかも全然あり得るので、諦めず潜り込んでください。
河野:デバッグの人ってゲームをよく知っていますし、やっぱり顧客の気持ちにもなれるので、そこからクリエイターになるのはいいですよ。正攻法で入らなくても、エースコンバットも今開発者募集中なので、ぜひ僕にご連絡ください(笑)
ヨコオ:新卒でゲーム会社受けてダメだったっていう人はたくさんいると思うんですけど、新卒の入り口ってどの会社も意外と狭いんですよね。新卒じゃなければルートは実はいっぱいあって、プランナーとかいつでも募集しているゲーム会社さんはあります。希望している会社に入れなかったとしても、とりあえずどこかのゲーム会社に入れば、いずれなりたい自分になれるんじゃないかって思います。
一回違うところに入ってしまうと、そこからゲーム業界にシフトするのはなかなか難しいので。「業界のどこかにいる」っていうことを目指すのが、一番可能性の広い戦略なんじゃないかな。
動画でアーカイブを見ることができます。参加者からのQ&Aなど、セッションの全貌はぜひ動画をご覧ください。
文/河西ことみ(編集部)





タグ