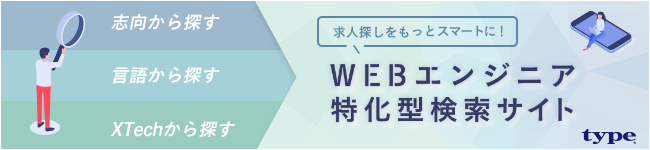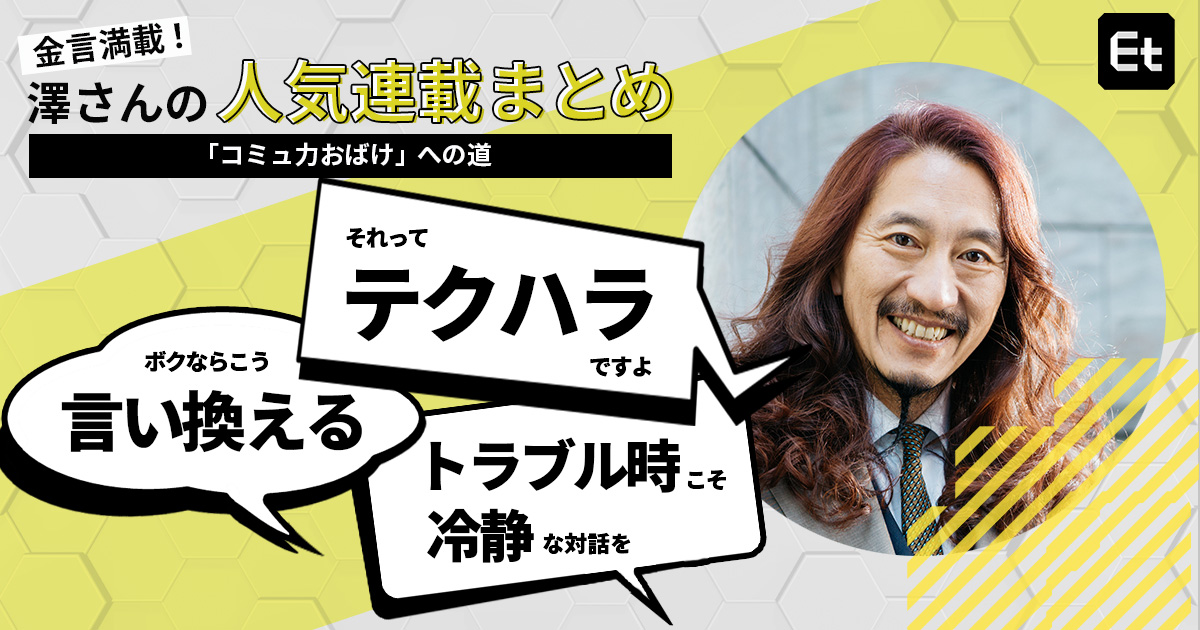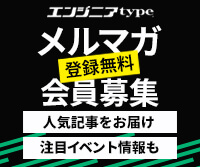「わざわざ現地に行く意味ある?」疑問だった僕が見つけた、技術書典のオフライン会場に行くべき三つの理由
ITや科学に関する技術書をテーマにした同人誌即売会こと『技術書典』。「技術者たちのコミケ」とも呼ばれ、2016年6月秋葉原での初開催から順調に規模を伸ばしている。24年5月に開催された『技術書典16』のオフラインイベントには、約3000人もの一般参加者が来場した。
なぜ紙媒体の技術同人誌のイベントに、これほどの参加者が集うのだろうか。『技術書典』はオンラインでも開催しており、出典作品の多くはオンラインで購入することができる。目当ての技術書を買うだけなら、わざわざ会場に足を運ぶ必要はない……。
「これは実際に行ってみて確かめるしかない」と思い立ったエンジニアtype編集スタッフは、『技術書典16』のオフラインイベントに潜入してみた!
目次
現地会場ならではの「三つの魅力」
『技術書典16』のオフライン会場に潜入するため向かったのは、東京・池袋のサンシャインシティ。エンジニアtype編集スタッフが現地に着いた頃には、既に多くの一般参加者で会場が賑わっていた。

入り口付近の写真。かなりの人混みで、熱気に溢れていた

さまざまなデザインのキャラクターが、会場を彩る。まさに技術者たちのコミケだ
想定していたよりもずっと大きな会場に驚きつつ、ブースめぐりをスタート!
【1】「思わぬ知識」との出会いが好奇心を刺激する
PythonやGOをはじめとした開発言語、TerraformやKubernetesといったクラウド関連技術など、本が扱っているテーマごとに各ブースの出店位置が分類されており、ジグザグに歩きながら各ブースのコンテンツを楽しむシステムだ。
いくつかのブースを歩いて見て回る中で、ふとこんな疑問が。
「ん?ITとあんまり関係ないテーマも多いな……」
というのも、初めて技術書典を訪れる私はもっと「ITにゴリゴリ特化した、ギークなエンジニアたちのためのイベント」という印象を持っていた。
ただ、実際は違った。
技術書典で扱われているテーマは、非常にバラエティに富んでいる。例えば、「手作りガジェットの製造方法」、「天文や気象などの科学技術」、「映像編集やCG制作」など、IT領域にとどまらないユニークな「技術」が数多く紹介されていた。
特に記者が心を奪われたのが、mysttさん著『楔形文字とユニコードの出会いにまつわるエトセトラ』と、ペンギンエクスプレスさん著『交通とUI Vol.1』だ。(記者は世界史専攻でゴリゴリの文系出身なのだが、まさか技術書典なる場で「楔形文字」を見ることになるとは……。想定外の遭遇に思わずテンションが高まってしまった)
ちなみにXでは『読み手に伝わる文章-テクニカルライティング』がバズっていた。ライティングや編集が生業の記者としても大いに惹かれるテーマだ。
すでに「来てよかった」と思い始める記者。非エンジニアの心も掴む技術書典、恐るべし!
会場から帰ってきたら「テクニカルライティング」がトレンド入りしてて5度見くらいしてしまった。#技術書典 16で出した新刊「#読み手につたわる文章 – テクニカルライティング」は技術書典オンラインマーケットで送料無料で購入できて、すぐ読める電子版も付いてきます!https://t.co/WlKbtKTnoG
— mochiko (@mochikoAsTech) May 26, 2024
買ってみました。よいですね > mochikoAsTech | 読み手につたわる文章 – テクニカルライティング #技術書典 https://t.co/pi7crQnAS7
— からあげ (@karaage0703) June 3, 2024
【2】著者との会話で得られる「追加情報」
本の著者と直接対話できることも大きなメリットだ。
ブースには著者たちが立ち、訪れる参加者と熱心に会話を交わしていた。こうしたリアルな「著者の声」は、Web上のオンラインショッピングでは得られない情報だ。
『[試して理解]Linuxのしくみ』(技術評論社)の著者、satこと武内 覚さんにテーマを選んだ理由を聞くと「開発を頑張っているエンジニアにエールを送りたかった」と話す。
個人的に、成功している人の話よりも、失敗談の方が得るものが多いと思うんですよ。なので、執筆した『失敗プログラマー第3版』では、私がこれまで経験した過去の失敗談や、そこから得た教訓をつづっています。
頑張っても大していいことなかった話や、超人や完全上位互換な人に出会ってしまったときの話、外部イベントの楽しみ方なんて話も書いてます。
まあ、自分の失敗を晒すのはそれなりに勇気がいりましたけどね(笑)

写真左がsatさん、右が風穴 江さん(@windhole)
現役エンジニアの失敗や成功から得たノウハウは、時として公式のドキュメントよりも実践的で役に立つこともある。実際、次のような声もあった。
実際の開発現場で起こる問題って、公式ドキュメント通りに処置しようとしても、上手く解決できないケースがよくあるんです。そこで威力を発揮するのが技術同人書の『生きたノウハウ』です。『公式にはAって書いてあるけど、実はBのやり方で処理した方がうまくいく』など、自分より先に躓いた人がどんな方法で解決したのかが分かるのも、技術同人書の魅力です
【3】千差万別な「アウトプットの仕方」も学びに
会場内にはさまざまな技術書が並んでいるが、同じテーマでも、著者ごとに異なる視点やアプローチがあることが分かる。
例えば、ネットワーク技術を漫画で解説している本の隣には、同じテーマを図解で解説する本が並ぶ。同じ技術でも、その伝え方や本の仕上げ具合は千差万別なのだ。
さまざまな創意工夫を目の当たりにすることで、自分のアウトプットの質を高めるために必要な視点やアイデアが得られるだろう。
主宰の日高さんに突撃インタビュー
一通りブースを回り終えた後は、技術書典を主宰している日高正博さん(@mhidaka)にインタビューを実施した。
そもそも技術書典を開催しようと思ったきっかけは?
世の中にはたくさんの『技術』がありますが、それぞれに魅力や面白さがあります。誰もが扱うような技術もあれば、ニッチなジャンルの技術もありますよね。そういった技術に気付くきっかけの場を作りたいと思ったことが、技術書典を開催しようと思った理由の一つです。
確かに、今日のイベントを通して、知らなかった技術領域をたくさん知ることができて楽しかったです!
ありがとうございます!後は、アウトプットの大切さをもっと広めたいという思いもあります。
エンジニアは日々いろいろな技術のインプットに勤しんでいると思いますが、それらを実務で活用することはあれど、体系化してアウトプットする習慣がある方は一部だと感じています。
勉強した内容を、体系化して整理することは、“自分の知識”として活用するためにとても効果的なことだと思うんです。ただこうしたアウトプットって、誰かに課せられたとたん、一気に気乗りしなくなりますよね(笑)
なので、技術書典の開催をマイルストーンに、気軽に楽しくアウトプットに取り組んでもらえたらなという気持ちもあるんです。
なるほど。私も、出版は難しくても、まずはブログなどで情報発信からチャレンジしてみようかなと思いました。ちなみに、日高さんの思う「技術書典のオフラインイベントに足を運ぶメリット」って何ですか?
出展している皆さんの熱量や雰囲気を、リアルに味わえることが一番の魅力だと思っています。一冊一冊に込められた情熱を肌で感じられますし、出展者たちの楽しそうな様子に自分自身もやる気をもらったり、元気づけられたりします。
オフラインを体験したことがない人にはぜひ足を運んでいただきたいですね。その場でしか味わえない刺激を楽しんでください!
あの有名エンジニアにばったり遭遇
そしてこの日のイベントでは、ポッドキャスト『聴くエンジニアtype』のMCこと、ばんくしさんに遭遇!
ばんくしさんは、自身がVPoEを務めるエムスリーのブースで、エムスリーの最新テックノウハウが綴られた解説本を販売していた。その名も、「エムスリーテックブック」。現在は1~6までシリーズが出版されており、MLOps事情、機械学習、DBトランザクション探求、Playフレームワークのマイグレーションなどが解説されたシリーズ4は特に売れ行きが好調で、すでに完売となっていた。
これらの冊子は、あのエムスリーテックブログにも記事を投稿するメンバーが有志で集い、社内のノウハウを外部にも展開しようという心意気の下に発行されている。
「エムスリーでは自分の得た知識や情報を言語化し共有するアウトプットの文化が根付いているんです」とばんくしさんは話す。

ちなみにばんくしさん個人では10冊近くも書籍を衝動買いしてしまったとのこと!中でもお勧めだった2冊を紹介してもらった。
【1】『ゼロから作る!HTTPルーター』(進捗ゼミナール)
私自身、前回技術書典では自作PackageManagerという本を書いていたので、“自作〇〇”には弱くて思わず購入しちゃったんですが、読んでみても最高でしたね。HTTPルーターを作ることに夢中になってのめり込めるような、良い本でした
【2】『traP TechBook』(東京工業大学デジタル創作同好会traP)
これも良かった。フラッとVimやRustというワードが目に止まって手に取ったら、Rustで作るGitや最新のVim pluginの話があって、『学生団体なんですか?』と聞いたら『600人くらいの情報サークルです』とかえってきて、その言葉のインパクトが良すぎて買いました
『技術書典17』も開催予定!
『技術書典16』のオフラインイベントを通じて、会場の熱気や盛り上がりはもちろん、技術同人書の魅力をより深く感じることができた。イベントに行かないと興味を持つことのなかったであろう技術との出会いも多くあり、自分自身の視野が広がったように感じている。
例年、年2回開催される技術書典だが、代表の日高さん曰く、第17回目となる『技術書典17』は今年の11月上旬に開催予定とのこと。
今回のオフラインイベントには参加できなかった方も、ぜひ次回は現地に足を運んでみてはいかがだろうか。オフラインイベントならではの魅力を肌で体感してみてほしい。
文・撮影/今中康達(編集部) 画像提供/技術書典運営事務局
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング
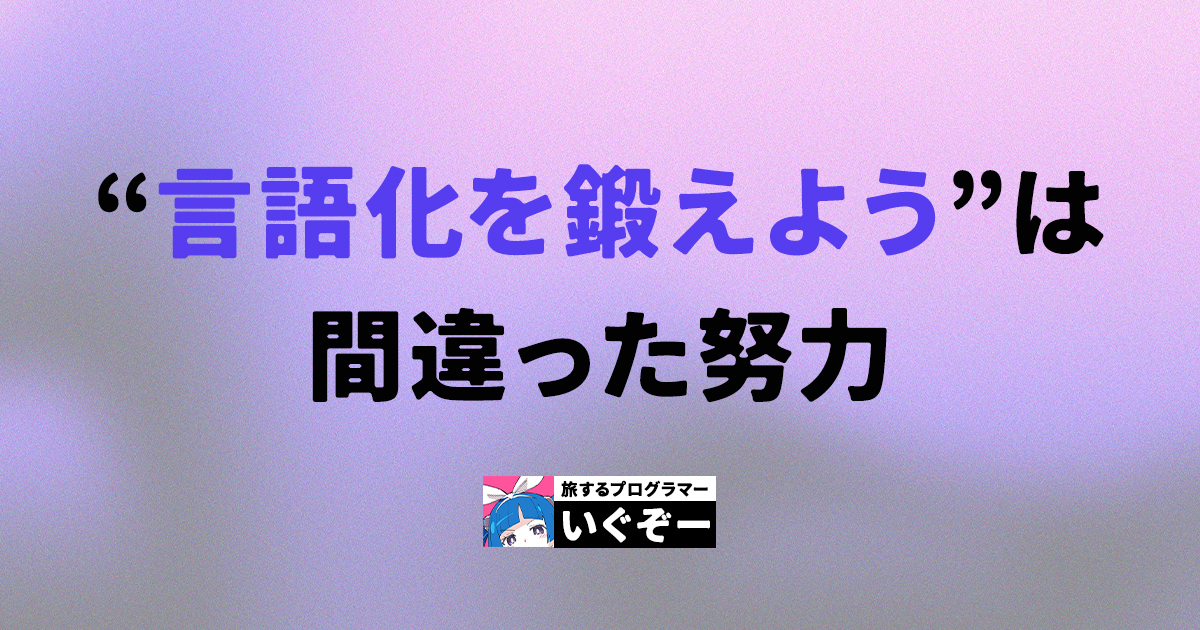
エンジニアを苦しめる「言語化力」の正体。鍛えようと努力しても、迷走してしまう理由とは?
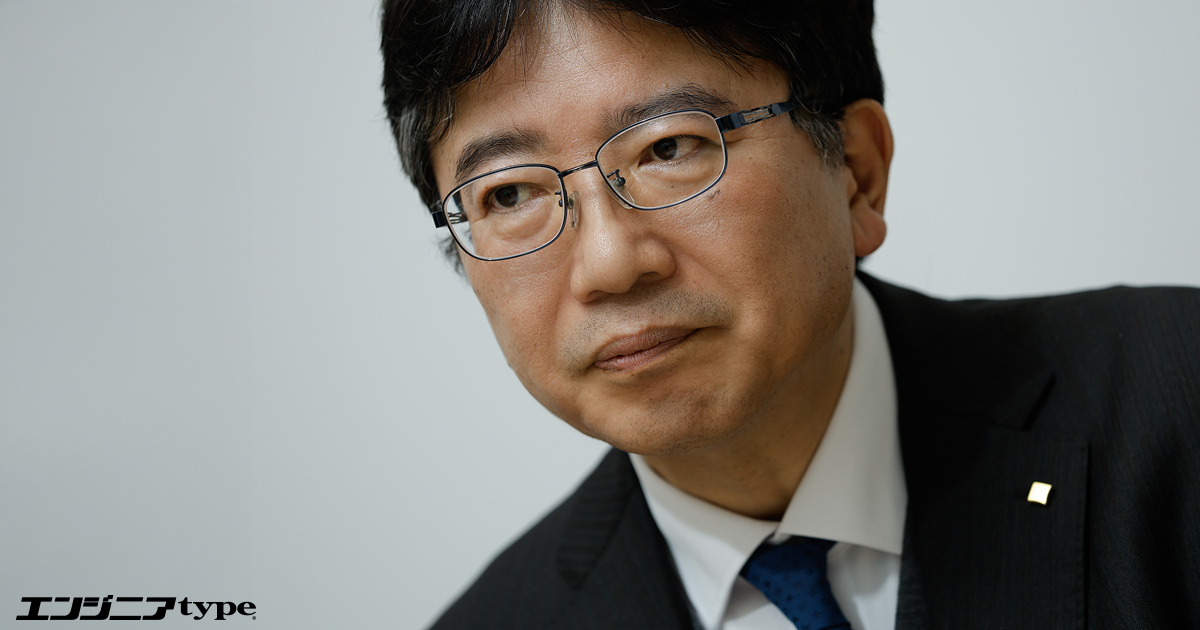
AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

サイボウズはSaaS is Dead時代をどう乗り越えるのか。経営陣が明かす「むしろ際立つ価値」とは

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”
タグ