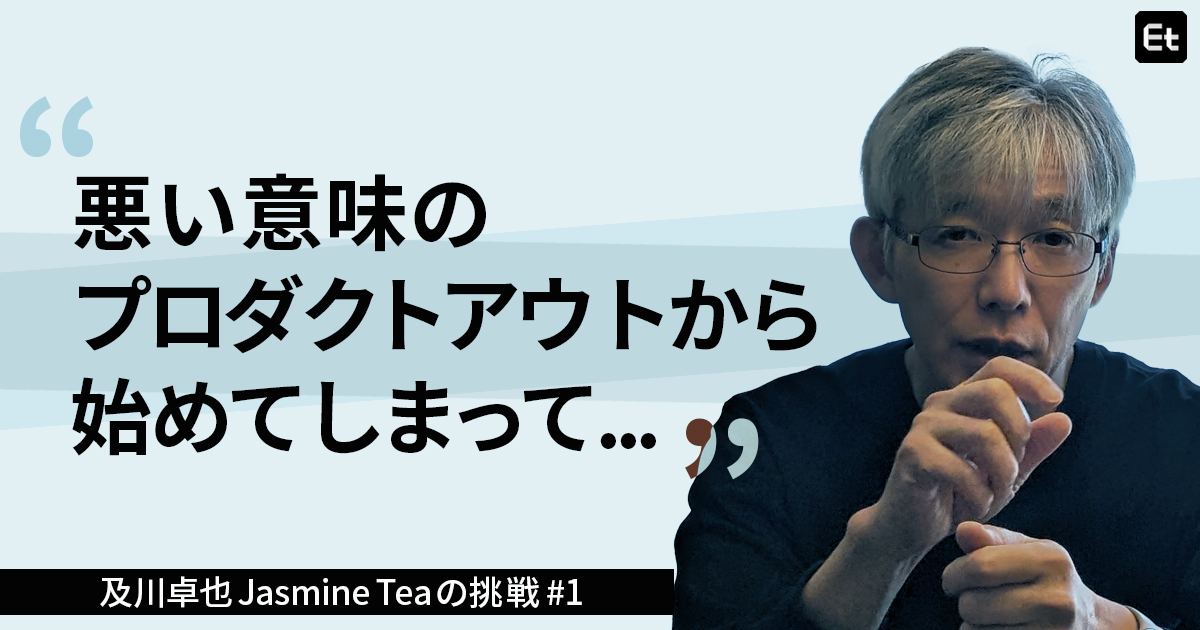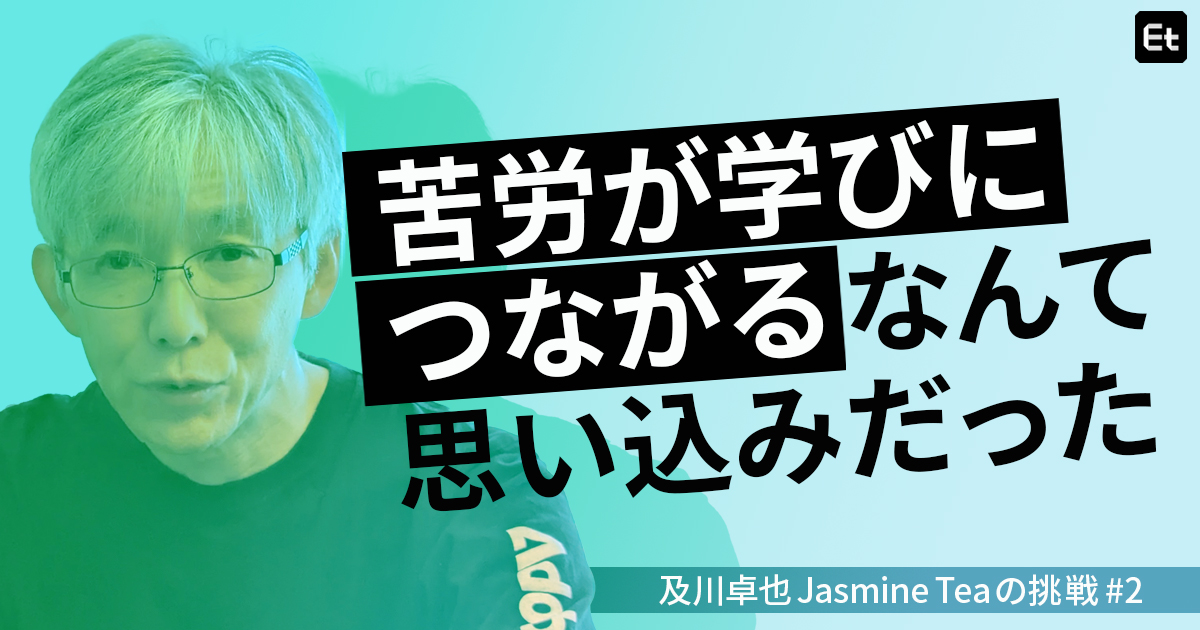※本記事は、2024年11月7日実施「ソフトウェアファースト x TRANSFORMED 出版記念イベント ~本気でDXを推進したい全ての管理職・企画職のために〜」の内容から、一部ピックアップして紹介しています。
【イベント情報】
主催:パーソルイノベーション株式会社
共催(会場スポンサー):パーソルキャリア株式会社
共催(フードスポンサー):株式会社ノンピ

”なんちゃってDX”脱出の鍵は、シリコンバレー企業の成功を支える「プロダクトモデル」にあり【及川卓也×横道 稔】
DXを推進するエンジニアの多くが直面するのは、「思うような成果が見えない」「方向性に確信が持てない」といった課題ではないだろうか。その原因の一つには、表面的な取り組みに終始し、根本的な組織のあり方やビジネスモデルを見直せていない現状があるかもしれない。
こうした状況を打破する鍵として注目したいのが、「プロダクトモデル」だ。プロダクトモデルとは“プロダクトマネジメントのバイブル書”と称される『INSPIRED』の著者、マーティ・ケーガンが提唱している言葉で、ケーガン曰く「シリコンバレーが世界をリードする理由は、このプロダクトモデルに秘密がある」という。
シリコンバレー企業の成功を支える「プロダクトモデル」とは何か。そして、DXに悩む日本のレガシー企業が取っていくべきアクションとは。
この問いに対するヒントを、ケーガンの新著『TRANSFORMED』を翻訳した横道 稔さんと、『ソフトウェアファースト』の著者・及川卓也さんの対談からお届けしよう。

Tably株式会社
代表取締役 Technology Enabler
及川卓也さん(@takoratta)
外資系IT企業3社にて、ソフトウェアエンジニア、プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャーとして勤務する。その後、スタートアップを経て、独立。2019年1月、テクノロジーにより企業や社会の変革を支援するTably株式会社を設立。著書『ソフトウェア・ファースト~あらゆるビジネスを一変させる最強戦略~』(日経BP)、『プロダクトマネジメントのすべて』(翔泳社)

Product People株式会社
代表取締役
横道 稔さん(@ykmc09)
LINEやサイバーエージェントなどの国内プロダクト企業にて、プロダクトマネジメント、エンジニアリング、アジャイルなどの領域でプレイヤー〜シニアマネジャー、フェローなどを歴任。 日本でのプロダクトマネジメントの普及のために、コミュニティ運営にも尽力。現在は自身で創業した会社にて、プロダクトコーチとして企業を支援している。プロダクト作りに関連する書籍の翻訳にも携わる
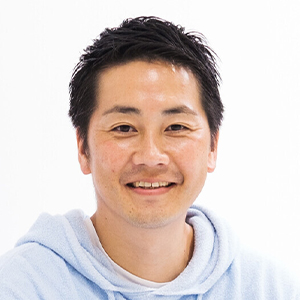
【モデレーター】パーソルイノベーション株式会社 片岡秀夫さん
2008年にパーソルキャリア(当時インテリジェンス)新卒入社。経営企画部、転職支援事業の事業企画部を経て、14年から出島組織としてのInnovation Lab.を設立し、新規事業開発およびオープンイノベーションを推進。国内外のHR Tech約10社への投資を実行し、約70名のプロダクト組織をゼロから立ち上げ、パーソルグループのDXにも深く貢献。 17年から『TECH PLAY』の事業責任者として、パーソルイノベーション株式会社内のバーチャルカンパニーをリード。現在は、主に大企業のDX実現のためにDXコンサルティング・組織づくり・人材育成を支援
「アジャイル導入=DX」ではない
ーー(片岡)マーティ・ケーガン氏の新著『TRANSFORMED』では、「プロダクトモデルこそDXの本質である」と主張されています。この「プロダクトモデル」とは、一体どのような概念なのでしょうか。
横道:企業がどのような原則に基づいて運営されているかを示すモデルのことで、簡単に言うと、ビジネスや存在価値の中心にプロダクトを据えて運営する考え方のことです。「プロダクト主導」や「プロダクトドリブン」などの言葉と近しいイメージですね。
ただケーガンは、これらの言葉を用いることで「プロダクトが何よりも優先される」と捉えられるリスクを懸念して、より汎用的な「プロダクトモデル」という表現を使っているようです。
及川:なるほど。それはいわゆるプロダクト主導型組織を意味する「プロダクトレッドオーガニゼーション」と同じようなものと考えていいのでしょうか?
横道:そうですね、基本的には同じと捉えていいと思います。
及川:プロダクトを中心に据える考え方には、私も大いに同意します。『ソフトウェアファースト』でも、「プロダクトマネジメントを全ての企業が導入すべき」だと、かなり振り切った主張をしているくらいなので(笑)
横道:『TRANSFORMED』の翻訳者という立場を抜きにしても、私もこの考え方には賛成です。
それこそDXと親和性の高いアジャイルですが、もともとはソフトウエア開発に特化したものとして生まれたもの。ただ現在ではその適用範囲が広がり、企業の人事や教育、さらには組織全体にも浸透していますよね。
プロダクトマネジメントも、アジャイルと同様だと思うんです。ソフトウェアプロダクトや物理的な製品に限らず、無形のサービスや組織運営をプロダクトだとみなすことで、十分適用できますから。プロダクトを通じて価値を生むという考え方は、DXを超えて広がる普遍的な概念だと考えています」

ーー(片岡)プロダクトがあらゆるものに適用できるとなると、そもそもプロダクトの定義とは何かが気になります。
横道:『TRANSFORMED』では、プロダクトとは有形無形を問わず、ビジネスの媒介となる製品やサービスを指していると読み取れます。ソフトウエアが中心にはなりますが、それに付随するサービスや関連領域も含めて総称されていますね。
及川:プロダクトマネジメントの観点から言うと、プロダクトとは市場で取引され、個人や団体のニーズを満たすものだと捉えていいでしょう。市場で取引されるとはつまるところ、一対多の関係が生じるわけなので、プロダクトはできる限り汎用品であるべきです。かつ、それに対価が生まれて収益を上げられるもの、言い換えると「何らかの形で事業貢献するもの」だと言えます。
ただこの認識だけでは、「うちはプロダクトを作っていない」と感じる企業もあるでしょう。そのためもう一つ抽象度を上げて、「誰かにとって役立つもの」という認識も必要です。要は、アウトプットではなくアウトカムを求めよということです。
横道:それこそソフトウエアは機能を作り込んだことで満足してしまいがちですが、実際には人の役に立たないとダメですもんね。
及川:はい。社員の生産性を向上させたらどれだけの経費が削減できて、企業の利益はどれだけ増えるのかといった風に、思考を正しく広げていけば「プロダクト」はほぼ全てのものに定義的に当てはまります。
ーー(片岡)ではこのプロダクトモデルを浸透させるためには、具体的にどのようなステップを踏めばいいのでしょうか?
横道:プロダクトモデルを実現するためには、ケーガンが提唱する三つの側面を変革することが重要です。
| ステップ | 概要 | ポイント |
|---|---|---|
| 【1】作り方を変える | プロダクトを頻繁にリリースし、効果を計測しながら改良を重ねるアジャイル的な開発手法を取り入れる | ●開発サイクルを短くし、頻繁にプロダクトを更新する ●効果を定量的に評価する仕組みを整える |
| 【2】問題解決の方法を変える | トップダウンの指示型ではなく、リーダーが戦略や課題を提示し、具体的な解決策は現場のプロダクトチームに委ねる | ●「課題は与えるが、解決は任せる」スタンスを取る ●現場をエンパワーし、権限を委譲する |
| 【3】解くべき問題の決定方法を変える | プロダクトビジョンや戦略を明確にし、組織全体で解決すべき課題を定義する。これにより、現場が注力すべき方向性が明確になる | ●プロダクトビジョンと戦略をインサイトを元に具体化する ●戦略的背景を共有し、組織全体のベクトルを揃える |
横道:ただこれらの三つのポイントを、一度に全て変えるのは現実的ではありません。実際にケーガンも「まずはできるところから進めよう」と説いています。例えば大企業の場合は、この三つをそれぞれの組織や部署ごとに適用してみるのが良いでしょう。
小さな単位で実践することで、成功体験やノウハウが組織内に蓄積されます。それを少しずつ他の部署に展開していく。その積み重ねによって、最終的には全体が変わっていくはずです。
そして、この三つの変革を実現する方向に企業が向かっていくこと自体がDXの本質だと、ケーガンは述べています。DXとは単なるツール導入ではなく、組織のあり方そのものを見直し、変えていくこと。そこに真剣に取り組むことが求められます。
及川:一つお伺いしたいのですが、「作り方を変える」まではやるけれど、そこで終わってしまう企業ってよくあるような気がします。実際はどうなんでしょうか。
横道:その課題は英語圏の企業でも見られるようで、「アジャイルを導入すればトランスフォーメーションが完了する」と勘違いしている人が少なくないという話が実際に挙げられています。
いくら作り方を変えて、アジャイル的な開発手法を取り入れたとしても、その上段にある「解くべき課題」を見直さない限りDXは進展しません。ケーガンもこの点について警鐘を鳴らしており、プロダクトモデルを正しく実現するには、単にプロセスを変えるだけでなく、課題の設定自体を見直す必要があると強調しています。
内製化ではなく、「手の内化」を目指す
ーー(片岡)横道さんに質問です。プロダクトモデルの観点から『ソフトウェアファースト』を読んでみて、何か気になる点はありますか?
横道:基本的な理念やベースは、両書とも似ている部分が多いと感じます。ただ『ソフトウェアファースト』の中で特に印象的なのが、「手の内化」という考え方です。これってDXでよく言われる「内製化」とはどう違うのでしょうか? わざわざ別の言葉を使っている理由があるのかなと。
及川:私は内製化という言葉では、本当に必要な組織の変革を表しきれないと思っています。
これはケーガンの著書『EMPOWERED』の中でも機能開発チームという言葉で説明されているのですが、「企画を考える人」と「作る人」に分けることで内製化組織を作ろうと考える企業は少なくありません。ただこの形態では、たとえ自社内で作業が行われていても、本質的には外注の構図と何ら変わりません。社内にチームがいる分、外部委託よりはコミュニケーションが取りやすいかもしれませんが、根本的な問題解決にはつながらないのです。
大切なのは、企業が自らの価値創造に責任を持ち、プロダクトを通じて競争力を維持・向上させるための柔軟なアプローチを取ることです。このアプローチを表現するには、「内製化」ではなく「手の内化」と呼ぶべきだと考えています。

横道:と、いいますと?
及川:例えば、機械学習の最新論文を読んで、それを用いたモデルを作れない限り企業の競争優位力を保てないケースがあったとしましょう。当然、全ての企業が大量のデータサイエンティストを採用できるわけではありませんよね。このような場合、外部の専門家に委託するのも一つの方法です。
ここで重要なのは、委託を単なる外注で終わらせないこと。モデルの学習や再学習に伴うリスクを十分に理解し、外部パートナーともビジョンを共有した上で進める必要があります。このように、自社の「手の内」をきちんと把握し、価値を生む核となる部分はコントロール下に置く。これが「手の内化」の本質です。
内製化ではないけれど、自分たちの手の内を見せながら進めている。こうしたアプローチこそ、現代の複雑なプロダクト開発やDX推進において必要な視点だと考えています。
横道:確かに内製化が進んでいても、社内で分断が生じている状態では本末転倒ですね。あくまでも、エンパワーする対象はプロダクトチームそのもの。プロダクトマネジャーだけでなく、チーム全体に力を持たせ、動けるようにする必要があります。この点は、両方の本に共通していると思います。
一つ違いがあるとすれば、ケーガンは内製化をかなり強調している点ですね。『TRANSFORMED』のまえがきにて、「自分たちのチームは外部ベンダーを管理するような形で働いているのですが、この本は役に立ちますか?」という問いに対し、彼は「NO」と即答しています。
もちろん現実には難しいケースもあるのでいくつか柔軟なアプローチも示されてはいますが、内製化に強いこだわりを持っているようです。
及川:私もケーガンのような原理主義者になりたい気持ちはありますよ(笑) でも現実的に考えれば考えるほど、完全な内製化は無理だと言わざるを得ないんですよ。
以前とある日本企業とやり取りした際、担当者から「GoogleやMicrosoftは全て内製化しているのですか?」と尋ねられたことがありました。そのとき私は、「何言ってるんですか。もちろんそうですよ!」と答えたんですね。
でも後になって冷静に考えてみると、GoogleもMicrosoftも、大量のオープンソースを活用して日々開発しているわけです。自分たちの技術だけで、ゼロから作っているわけではない。それに現在では一般的になっているパブリッククラウドも正確には内製化と言えるのかも怪しいですしね。完全に内製化をするなら全てをオンプレミスで運用するしかないですが、現実にはほとんど不可能です。
だからこそ、自分たちのコアコンピタンスは何かをしっかり定義することが欠かせません。自社が差別化を図れる部分に集中し、そこは自分たちで価値を生み出すべきでしょう。IaaSなどは既存のものを利用すれば十分です。自分たちの付加価値を創出する部分こそ、本当に内製化すべき部分だと思います。それ以外は、SaaSを活用するので十分であることも多いです。
横道:なるほど。ケーガンも「コアコンピタンスを内製化しないのはどうなんだ?」と述べていました。文化的な背景や制約の違いもあるのでしょうが、『ソフトウエアファースト』の方は、より現実的な部分に踏み込んでいる印象を受けますね。
DXを声高に連呼するのは、恥ずべき状態
ーー(片岡)及川さんの著書『ソフトウェアファースト』では「なんちゃってDXはもうやめよう」と強く提唱されていますよね。改めてこの言葉が意味するものを教えてください。
及川:「DXとは何ですか?」という質問に、明確な答えを持っていない状態が「なんちゃってDX」です。実際、こうしたケースは非常によく見られます。
そもそもDXは、プロセスであり通過点に過ぎません。DXができている企業では、DXなんて言葉を使う必要がありませんから。むしろ、DXと連呼しているのは恥じるべき状態なんです。そこへの危機感が、日本企業はまだまだ足りていない印象です。
「トランスフォーム」と言えば聞こえは良いかもしれませんが、日本語に訳すと「デジタル変革」です。事業、社内システム、サービスなど、全てを「プロダクト」として捉え、人と組織を根本から変えなくてはならない。変革には痛みを伴いますが、それに本気で向き合う覚悟が必要なのです。

ーー(片岡)その変革を実行するために、どのようなプロセスから着手すべきなのでしょうか。
横道:企業によっては、既存のプロセスが十分にデジタル化されていないケースもありますが、それでも新しい事業を立ち上げて、スタートアップのように新しいビジネスを生み出すことは可能です。必ずしもDXの三段階ステップを順番通りに進める必要はなく、一気に最終段階を目指す選択もできます。そうしたアプローチを取る企業も増えてきていますし、外部からリーダーを迎え入れることで変革を加速するケースも多いですね。
ただこうした試みが成功しにくい理由の一つとして、日本の企業文化に『お手並み拝見』的な風潮があることが挙げられます。新たに迎えたリーダーに対して、冷ややかな視線を向けるだけでなく、彼らが成功することを真剣に支援する体制が必要ですね。経営層はもちろんのこと、現場のメンバーも覚悟を持ってフォロワーシップを発揮してほしいです。
及川:それこそ外部から専門人材を迎え入れることは、一つの成功パターンだと思います。
実際に、CDO(Chief Digital Officer)のポジションを設けて、元IT業界の有識者をスカウトして成功している企業もあります。医療分野で新たにビジネスを始めようとするとき、医療の専門家を採用することは当然の選択ですよね。それと同様に、DXに本気で取り組みたいのなら、デジタルのプロを入れるべきだと思います。
編集・構成/今中康達(編集部)
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

AIを「便利な道具」と思う限り、日本に勝機はない。AI研究者・鹿子木宏明が語る“ズレたAIファースト”の正体

「アジャイルの理屈を押し付けない」大手金融機関が10年かけて実践した“アジャイル文化”作りの裏側

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
タグ