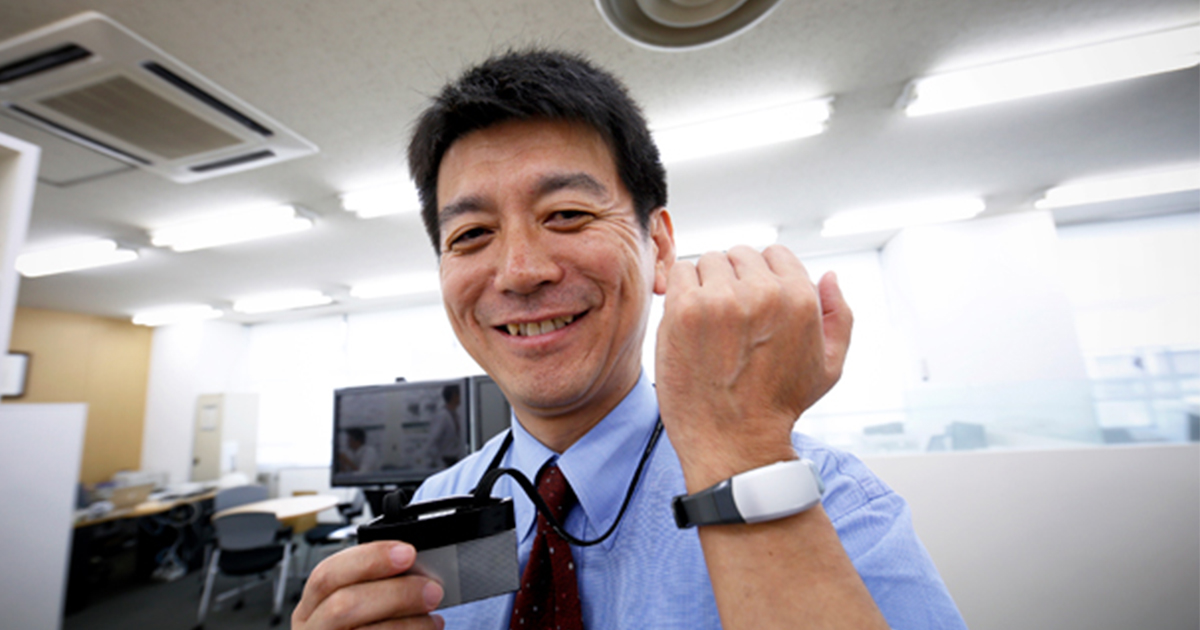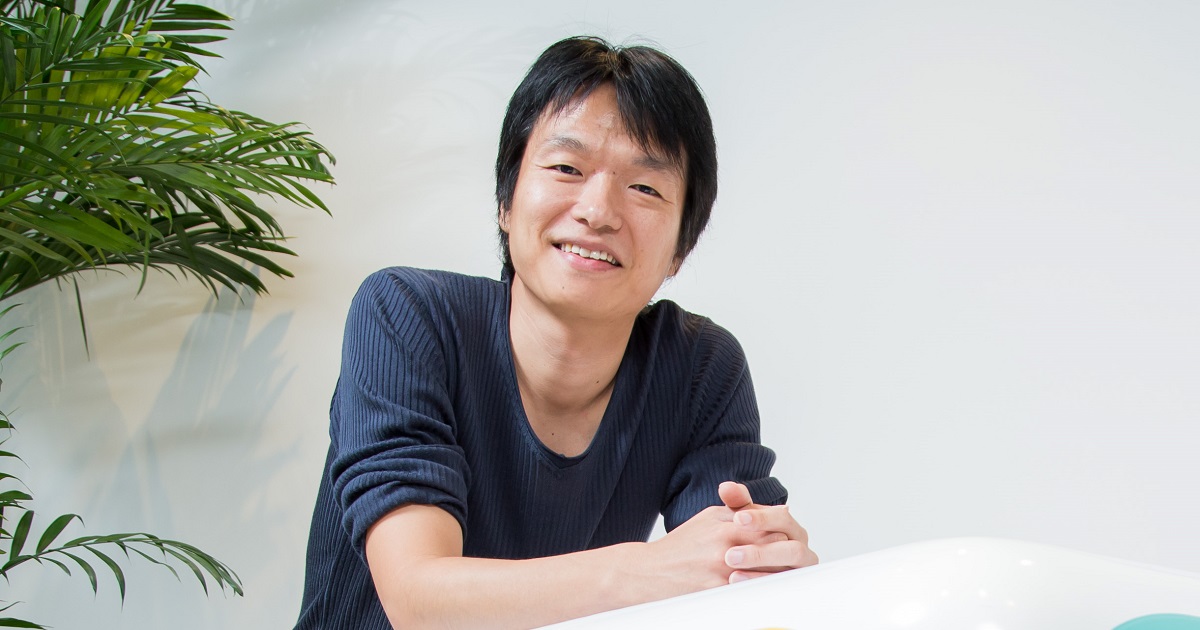「いろいろな説明の仕方はありますが、そうなっちゃったということ。なぜそうなったかというと、社内外、さまざまな分野の人たちと議論したからでしょうね」
日立製作所(以下、日立)で研究開発グループ技師長を務める矢野和男氏に、「なぜAIやビッグデータというテーマを選んだのか」を聞くと、そんな答えが返ってきた。矢野氏はいまや、この分野のトップランナーの1人。2014年に上梓した『データの見えざる手』(草思社)では、「幸福」や「運」といった人間の感覚や営みと、データとの意外な関係を明らかにして世に衝撃を与えた。
矢野氏が長年取り組んだ半導体研究を離れ、データというテーマに本格的に関わり始めたのは2000年代前半のこと。経営の方針を受けて、決定的な選択を迫られたからだ。この頃、日本の半導体メーカーは逆風のただ中にあった。2003年に日立の半導体事業は切り出され、三菱電機の同事業と統合されてルネサス テクノロジ(NECエレクトロニクスとの経営統合後、ルネサス エレクトロニクス)が生まれた。
時代の流れとともに、大きなキャリアシフトを余儀なくされた矢野氏。決して平坦ではなかったその歩みを追ってみたい。(以下、敬称略)

株式会社日立製作所 理事 研究開発グループ 技師長
矢野和男氏
1984年、早稲田大学物理修士卒。日立製作所入社。93年、単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功。2004年から先行してウエアラブル技術とビッグデータ収集・活用で世界をけん引。論文被引用数は2500件。特許出願350件。のべ100万日を超えるデータを使った企業業績向上の研究と心理学や人工知能、ナノテクまでの専門性の広さと深さで知られる。博士(工学)。IEEE Fellow。電子情報通信学会、応用物理学会、日本物理学会、人工知能学会会員。日立返仁会監事。東京工業大学大学院情報理工学院特定教授。文科省情報科学技術委員。著書に『データの見えざる手』(草思社)がある
20年培ったスキルをいったんリセット
矢野和男は20年にわたり、半導体の研究開発に携わってきた。1993年には、単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功。慣れ親しんだ分野には、気軽に情報交換できる知己が世界中にいる。築いてきた資産や知見も、これからは使えなくなるだろう。新しい分野をゼロから切り拓かなければならない。
「20年間培ったスキルとかポジションといったものを、いったんリセットしなければなりません。残念なことでしたが、見方を変えればチャンスでもあります。正直に言うと、当時は本気でそう思えたわけではありません。でも、チャンスだと思おうとはしました」
気持ちのスイッチを切り替えるのは難しい。「半導体を20年もやっていると、頭がハードウエアになっていますからね」と矢野。考え方の枠組みや発想は、無意識のうちに“半導体思考”になっている。新しい分野を切り拓くためには、こうした枠組みをいったん取り払う必要があった。
そのために役立ったのが、多様な専門分野を持つ人たちとの対話、議論である。冒頭の言葉のように、こうした経験がAIやビッグデータへの道につながった。
日立が取り組むべき新しい事業は何か。どこにイノベーションの可能性があるのか。矢野を中心に集まった社内のコアメンバーは約20人。ある程度の方向性が見えるまで、チーム内での議論は穏やかなものではなかった。むしろ、侃々諤々と形容できるようなものだったようだ。
「メンバーのバックグラウンドは多種多様。半導体出身もいれば、無線やデータ解析の専門家もいます。AIやビッグデータの議論をすると、それぞれが自分の知っていることをベースに、それ以外については想像で話をするわけです。使っている言語も違えば、見ている方向も違う。最初は会話すら成り立たないほどでしたし、険悪な雰囲気になったこともあります」
一方、チームを取り巻く社内環境もまだら模様だった。研究開発を続けさせた上層部は、全体としてサポーティブだったといえるだろう。ただ、社内から厳しい視線を投げ掛けられることもあった。
「常に何らかの研究成果を出してはいたので、自分たちとしては着実に前進している感覚を持っていました。ただ、『それで、どんなビジネスにつながるの?』と聞かれると、納得させられるような返答は難しい。そういう状態が、10年くらいは続きました」と矢野は振り返る。
「AIをやろう」と言いだして周囲と軋轢
風向きが変わったのは2013年、14年頃だったと矢野は言う。矢野らのチームの成果が周囲の認識を変えさせた面もある。同時期に、海外で注目される動きもあった。例えば、2012年に行われた画像認識のコンテストでは、ディープラーニングの手法を用いたトロント大学チームが圧倒的な強さで優勝。グローバルな規模で、AIの大きなうねりが起きようとしていた。
ただし、当時もAIという言葉はあまり使われなかった。過去のAIブームの苦い記憶から、ネガティブな響きがあったからだ。1980年代から90年代初頭にかけて推進された「第5世代コンピュータ」プロジェクトには、500億円を超える国の予算が投じられ、関係各社からも少なからぬ研究者・技術者が参加した。
このプロジェクトでAIは重要な柱だったが、結局のところ、ビジネスにつながるような成果を生みだせなかった。以来、AIという言葉に染み付いたマイナスイメージは根強く残っていたが、矢野は「AIをやろう」と周囲に働き掛けた。2011年から12年にかけてのことである。
「当時は、AIというだけで周囲と軋轢を生むこともありました。しかし、そろそろ人工知能、AIと呼べるようなものが現実化しつつある。私としてはそんな確信のようなものがありました。おそらく、しばらくの間は研究者としての信用を落としたのではないかとも思います」
その後の展開は、言うまでもない。研究仲間からは、「あの時、矢野さんが言っていたことは正しかったね」と声を掛けかけられるようになった。今では、新聞のような大手メディアでも連日のようにAIが話題に上る。AIがまとっていたイメージは大きく変わった。
結果として、矢野は時代を先取りしたことになる。ただ、本人は「タイミングの問題も大きい」と言う。半導体やセンサー、ソフトウエア技術など、さまざまな要素がそろっていなければ、プラス何年かの苦節を強いられていたかもしれない。その間に、研究開発に幕引きをする意思決定が下された可能性もある。
とはいえ、準備をしていなければチャンスをつかむこともできなかった。「精一杯努力して、かつタイミングが来なければ、大きな成果に結び付けることはできなかったでしょう」と矢野は言う。程度の違いはあっても、未知の分野とはそういうものだ。フロンティアは挑戦者に残酷な仕打ちをすることもある。
幅広い事業の価値をレバレッジする何か
10年にわたる雌伏の期間には、海外有名大学などからの誘いもあったが、矢野は日立に残ることを選んだ。同社の持つリソースやポテンシャルに、大きな魅力を感じているからだ。日立の売上はおよそ10兆円で、情報・通信システムや社会・産業システムなど、10ほどの事業ドメインに分かれている。
全ての事業ドメインに寄与する何かをつくりだせば、そのインパクトは大きい。10兆円の事業に対して、仮に1%のレバレッジを実現すれば1000億円、10%なら1兆円分の価値創造につながる。
「せっかく10兆円のビジネスがあるんだから、これを11兆、12兆円に伸ばすことを考える方が世の中のためになるのではないか。私はそう思っています。もしゼロからスタートアップをつくるとしたら、同じようなレベルの仕事はできないでしょう。スタートアップによる10億円の事業創出は貴重なことですし、10を11、12に伸ばすよりも難しいことかもしれません。ただ、自分にとっては、今のやり方が性に合っているように感じます」
では、全ての事業に貢献できるような何かを、本当につくることができるのだろうか――。半導体の次のテーマを考える時に、矢野が最も悩んだことである。
「特定の事業ドメインに貢献しようとすると、その分野の専門家になる必要があります。しかし、各ドメインにはすでに実績のある技術者が多数活躍している。そこに割り込んだとしても、おそらく提供できる価値には限界があるでしょう。かといって、『全ての事業ドメインに役立ちます』と漫然と言っているだけでは、誰にも信用されません。本当にそういうことが可能なのか、私にもよく分からない時期が続きました。幅広いドメインに適用できるものがあるとしたら何だろうか――。一縷の望みがデータだったのです」
2000年代の半ば、ビッグデータやIoTなどの言葉を使う人はほとんどいなかった。ただ、センサーの小型化・低価格化の方向性は見えていた。現実世界のデータを大量に集めて、コンピュータで処理し、現実世界に自動でフィードバックできれば、面白いことができるのではないか。そんな妄想に近いポンチ絵をつくってみたりした。10年余りを経た今、その妄想は現実のものとなりつつある。矢野は今も、プレゼンなどの機会には当時の絵をほぼそのまま使っている。
1000行のアルゴリズムでマルチドメインに対応
矢野は大学院で理論物理を学んだ後、日立に入社した。このことが、データを扱う上でプラスになったと考えている。
「電気工学や情報工学などを専攻したエンジニアなら、電気やコンピュータといった特定ドメインにこだわる傾向があるかもしれません。しかし、物理は特定のドメインとだけ結び付いているわけではない。抽象度が高く、データを扱う機会も多い。だから、ドメインに対するこだわりも、さほどありません。物理という学問は、AIやビッグデータと親和性が高いのではないかと思います」
抽象的な思考に慣れていることが、特定ドメインに依存しないAIづくりに役立った。矢野らのチームが開発し、2015年秋にリリースされた『Hitachi AI Technology/H』(以下、『H』)は幅広い業種業態に適用することができる。
『H』は金融、交通、流通、物流、プラント、製造、ヘルスケアなど、さまざまな分野で導入され、すでに50以上の事例がある。店舗における顧客単価15%向上、物流倉庫の生産性8%向上、コールセンターの受注率20数%向上など、大きな成果も上げている。
事業ドメイン固有のビジネスロジックを担う企業システム、最適化に向けた提案を行うAIという役割分担により、『H』は非常に小さなサイズでマルチドメインからの要求に対応することができる。
「従来のようなシステム開発とは、全く別の世界。『H』を含めて、世の中にあるほとんどのAIは1000行程度に収まる大きさです。今までの1000行と、AIにおける1000行とでは全然意味が違う。なぜコンパクトにできるかというと、複雑性をデータ側に持たせているからです」
逆に、アプリケーションに複雑性を持たせようとすると、際限なくシステムは巨大化する。世界中で競争が激化するコネクテッドカーを例にとると、すでに一部の高級車は1億行のプログラムを搭載しているといわれる。こうした巨大システムの開発には膨大な数のエンジニアが必要だ。1000行のプログラムなら、1人の天才がつくることもできるかもしれない。矢野の答えはYesであり、Noでもある。
「確かに、1人の天才がアルゴリズムを書くことはできます。しかし、素晴らしい才能を持つ開発者がいたとしても、現物のデータにまみれなければ、そのアルゴリズムに到達することはできないでしょう。さまざまなドメインの現場とそのデータに学び、得られた経験を抽象化する能力が求められます」
このような意味で、日立の持つリソースや販売チャネル、顧客基盤は極めて重要だ。『H』というイノベーションには、日本を代表するコングロマリットの強みが鮮やかに刻印されている。
ルールに縛られた世の中を変えたい
今、矢野は次世代のAI創出に向けて、研究開発を加速させている。一例を紹介すると、2017年12月に発表した自己競争型のAI技術がある。
「AIを動かすために、どの程度のデータが必要か。今後のAIを考える上で、重要なポイントだと思います。過去のデータが必須なら、新しい分野ではAIを活用できないことになります」
AIとビッグデータはセットで語られることが多い。しかし、必ずしも常にセットとは限らないようだ。矢野らのチームはAI群同士がコンピュータ上で自己競争を行う環境をつくり、人が用意した実績データなしに、サプライチェーンの課題解決に寄与できることをシミュレーションで確認した。サプライチェーンの発注に関して、人の判断に比べて、在庫や欠品による損失を4分の1に抑えることができたという。
「ビジネス課題を与えたAIが、データなしでも機能することが分かりました。しかし、データが不可欠な分野、データに依存しない分野の境目はまだ不明確です。両者の線引きを明らかにして、AIがデータなしにできることを増やしていきたいと思っています」
こうした取り組みの先に、矢野が見ているのは社会の多様性や柔軟性を支えるAIの姿だ。例えば、同じ小売チェーンの店であれば、A店とB店の品ぞろえはほとんど同じというのが普通だろう。商圏の顧客層に応じて品ぞろえを大きく変えると、オペレーション効率の低下を招くことが懸念されるからだ。進化したAIを導入すれば、顧客層の属性や嗜好に合った多様な店舗を効率良く運営できるようになるかもしれない。
「フレデリック・テイラー以来、ベストプラクティスを標準化して横展開するというスタイルが世の中に浸透しました。それが、社会の豊かさにつながったことは確かでしょう。しかし、結果として標準化とルールに縛られる世の中になった。もちろん、ルールが必要な対象はあります。しかし、ルール以外に頼るものがなく、やむを得ずルールを維持している分野も多いはずです。そんな世の中を変える可能性がAIにはあります」
矢野が追求するのはAIそのものではなく、その何段階か先にある、人々が幸せに暮らす社会である。そのためにAIが貢献できると信じるから、AIを研究している。「ほかに方法がないからと諦めているけど、ルールに頼らない方法がAIとデータで実現できる可能性があります。ルールに縛られた杓子定規の考え方を壊し、人間の多様性を讃えたい。それが、私がやりたいことです」と矢野は言う。
半導体の研究に没頭していたころ、世界の最前線に身を置くことの喜びを実感した。一方で、矢野は物足りなさも感じていたという。「半導体は部品なので、なかなか全体が見えにくい」からだ。「全体」とは商品の全体像であり、半導体を用いた商品群が形づくる社会像である。
10年以上にわたるAIとの関わりを通じて、矢野は社会を俯瞰する視座、人間とテクノロジーを深く考察する喜びを得た。半導体時代に感じた不全感を埋めるには、十分すぎるほどのものだろう。
取材・文/津田浩司 撮影/竹井俊晴