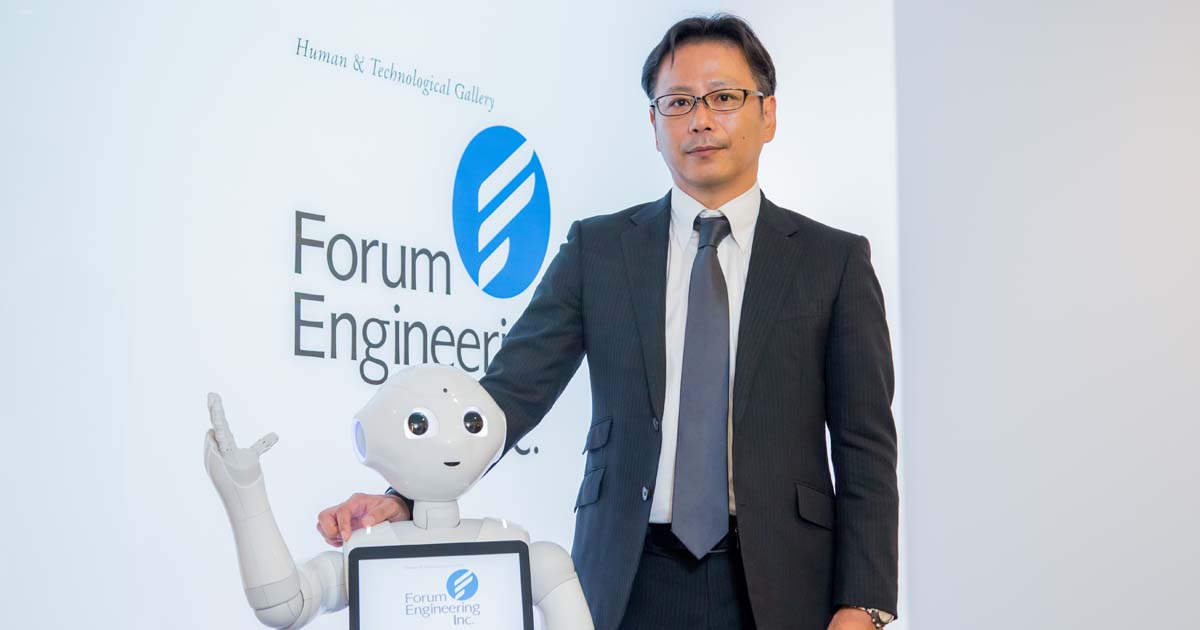優れた技術者たちは何を目指すのか?各社の「匠」の視点を覗こう

「ソニー最後の異端」と呼ばれた映像技術の匠が語る、イノベーションの罠【連載:匠たちの視点-近藤哲二郎】

アイキューブド研究所株式会社 代表取締役社長
近藤 哲二郎氏
1949年、愛媛県生まれ。1973年に慶應義塾大学工学部・電気工学科を卒業後、日本無線に入社。1980年にソニーへ転じ、映像技術の研究に従事。以来、400件に迫る特許を出願・登録し、1995年に出井伸之氏からその才を見出される。そこでかねてから構想していた映像の高画質化技術「DRC」を実用化。同技術を搭載した『WEGA』、『BRAVIA』シリーズは大ヒットを記録する。2009年にソニーを退き、アイキューブド研究所を設立。現在も映像技術の革新に挑み続ける
「今日の日本メーカーは事あるごとにイノベーション(技術革新)を口にします。でも、本当に必要なのはイノベーションなのでしょうか。わたしにはそうは思えません。今最も必要なのは、イノベーションよりインベンション(発見・発明)だと思うのです」
かつて「ソニー最後の異端」と呼ばれた男は、苦境が伝えられる日本メーカーが抱える課題をこう斬って見せた。
言葉の主は近藤哲二郎。
ハイビジョン放送の黎明期、標準映像(SD映像)を高精細なハイビジョン映像(HD映像)にクリエーションする高画質化技術DRC(Digital Reality Creation)を生み出した元ソニーの研究者であり、現在アイキューブド研究所の代表を務める現役の研究者だ。
「そもそもイノベーションというのは、知恵や情報が普遍化していくプロセスを指すものであり、たとえその革新を阻む課題があったとしても、時間とともに解消されていく性質のものです。これに対して、インベンションが自然発生することはありません。なぜなら開発に携わる者に自己否定を迫るものだから。ここから今一度、真に新しいものを生み出すことができるかどうか。これこそ、日本メーカーが問われている課題なのだと思います」
デジタルでしか成し得ないことを実現するため、ソニーへ
近藤が日本無線の研究所からソニーに転じたのは1980年。おりしもさまざまなエレクトロニクス製品が、アナログからデジタルに移行し始めた時期にあたる。
彼がソニーを新天地に決めたのは、「まだ誰も挑戦してないことにチャレンジする」ため。だが入社してみると、先進的と考えられていたソニーにおいてさえ、過去にとらわれた研究者が少なからずいたことに驚かされた。
「例えば、新人研究者が何か質問しに行っても、なかなか本質的なことを教えてもらえない。おかしいと思って理由を聞くと、『何十年も掛かって手に入れたノウハウを簡単に教えるわけがないじゃないか』と。確かに過去の成功は自信につながるものでしょうし、自分にしか持ち得ない情報はそれ自体エントロピー(価値)が高いので、守りたくなる気持ちが湧くのは理解できます。
でも、当時はアナログからデジタルへの大転換期。過去からの延長で発想したアイデアやノウハウを大事に抱え込んだところで、新しいモノなんて生み出せるはずはありません。おかしいなって思いましたよ」

80年代、世界の先端メーカーとして知られたソニーだが、社内は端境期を迎えていた
近藤の目には、研究者の多くが「アナログで培った資産をいかにデジタルに展開すべきか」に腐心しているように見えた。しかし、彼にはそうした考えに与するつもりはなかった。
「アナログをデジタルに置き換えるだけなら誰でもできます。わたしがやりたかったのは、アナログでは成し得なかったことを、デジタルで実現すること。アナログ時代の考え方を踏襲してデジタル化を進めようとは考えませんでした。ましてや自分だけのノウハウとして取っておこうなんて、思いもしませんでしたね」
実際、DRCを考案した時も、研究所内で自らのアイデアを口にする機会は多かったと言う。
「自分にしか知り得ないノウハウやアイデアを他者と共有することで、次の段階に早く進めると考えたからです。もしその情報に本物の価値があるなら、守ろうが守るまいが自然と広まるでしょうし、他人がそれを真似しても、自分は次の段階に進めばいいわけですから。情報のエントロピーが下がることを気にするより、自己否定を重ねながら、少しでも早く前に進む方がよっぽどいいと思いました」
技術力に自信があるからこそ、守らず、手放し、次に進む。それが彼の言う「自己否定」の意味するものだ。
ただ、自己否定には相応の痛みが伴う。
「理解してもらうのには相当苦労しましたし、社内のみならずアカデミズムの世界からも、『“鉛”をいくらいじったところで“金”にはならない。近藤のやろうとしていることは“錬金術”だ』と非難されました。もちろん彼らの言う通り、SD映像をいくらいじってもHD映像にはならない。ですからわたしは、SD映像の見栄え良く加工するような小賢しい手法は初手から捨てて、研究に臨んでいました」
“錬金術”ではなく“手品”に見出した高画質化の本質
当時に行われていた映像の高画質化とは、限られた画素を電子的に補った上で輪郭やコントラストを強調するという手法が一般的。高画質化というより、映像に“お化粧”を施すようなものが多かった。
これを「アナログ時代の考えを引きずった手法」だと考えていた近藤は、デジタル時代にふさわしいやり方を新たに編み出すことで、映像の高画質化に革命をもたらそうとしていた。
「データをサンプリングして捕まえられるのが、デジタルならではの特性の1つです。そこで、『捕まえられるなら置き換えられだろう』と気が付いたのが、DRCを発想する原点になりました」

DRCの基本的な働きはこうだ。
テレビに入ってくるSD映像のデータを、内蔵したHD映像の波形を収めたデータベースと照らし合わせ、適合したHD映像とSD映像とを置き換えて表示する。
つまり、入力されたSD映像は使わず、その信号をもとに新しく創造したHD映像を視聴者に届けるわけだ。この発想の大胆さこそ、彼を“異端”たらしめている要因と言えよう。
「わたしがやって見せたのは、“錬金術”じゃなくてむしろ“手品”。懐に忍ばせた“金”を“鉛”と差し替え、お客さんにお見せしたことになります」
近藤がこうした発想をわが物にできたのは、ソニーが他社に先駆けHD機器の技術で先行していたことも大きかった。ソニーには、他社が持ち得ない膨大なHD映像のデータベースがあったのだ。
「ですから、DRCはソニーでなければ作れなかった技術といっても過言ではありません。とはいえ、いずれはほかの研究者も同じような手法を考えついたでしょうから、やはりアイデアを自分の中に抱え込む意味なんてまったくなかったと思います。早く一般常識にしてしまった方が、技術の進化に貢献するのです」
ソニーを離れ、目も脳も疲れない新たな映像技術を確立
2008年、ソニーの組織再編に伴い、同社の映像技術研究を担っていた近藤率いる「エー・キューブド研究所」は廃止されてしまう。が、ソニー時代、近藤の才能をいち早く見抜いた出井伸之氏(元ソニー代表取締役社長)らの支援を受け、翌2009年、独立系の映像技術研究所「アイキューブド研究所」として蘇る。
代表はもちろん近藤その人であり、彼を慕う多くの部下たちも彼と行動を共にした。
「今はソニー以外の会社とも仕事をしますが、仕事の進め方はソニー時代とほとんど変えていません。変わったのは周囲の環境くらい。ただ粛々と研究に取り組むだけです」
研究への取り組み姿勢に変化はなくても、今、近藤が取り組んでいる内容はDRCとは比べ物にならないほど大きな進化を遂げている。
それが、人間が「現実の風景」を見た時に発生する「脳内での認知」と同じ体験をうながす4K映像のクリエーション技術ICC(Integrated Cognitive Creation)と、別技術で大型スクリーンに最適化させたISVC(Intelligent Spectacle Vision Creation)技術である。

左側のディスプレイに映るハイビジョン映像に比べ、右側のICCを駆使した映像は人が脳内で認知するものに近付いている
ICCを搭載したテレビとして、シャープの次世代液晶テレビブランド『ICC PURIOS』が今年から受注生産を開始したと報道で知った人も多いはずだ。
「これから4K、8Kとますます映像の解像度は向上していくことになりますが、われわれが目指すのは、1人の人間では処理し切れないほど情報があふれる時代の中で、いかに多くの人に喜びや感動を与えていけるかだと考えています。例えば、食料に事欠く時代であれば腹を満たすことにお金を費やすことが目標になり得ますが、現在のような飽食の時代において、貧しかったころのやり方で押し通そうとしたところで無理がある。
それと同じように、映像の世界も、われわれの“おなか”は帯域すなわち解像度とコンテンツの量において、すでに満たされつつあるというのが現在の状況です。でも本当の勝負はここから始まります。映像においても 、量ではなく質の時代が来る。食で言えば“味覚”に相当する部分をどう料理するか、それが今問われているのです」

アイキューブド研究所が開発した、「光クリエーション技術」と呼ばれるICCのチップ
人間の目の解像度は約650万画素に相当すると言われている。一方、ハイビジョンの4倍の解像度を持つ4Kは800万画素。もはやテレビの解像度は人間が持つ視覚の限界を凌駕しているのだ。帯域がリッチになるだけでは満足し得ない時代がやって来るのは自明のことだろう。
「そこでわれわれは、人間の限界を超える帯域を、現実の自然を眺めた時に感じる雄大さやダイナミックさといった、これまでのテレビでは再現し得なかった付加価値の提供に費やしていこうと考え、ICCやISVCを開発しました。これらの技術で実現するのは、自然を眺めるのと同じように、目も脳も疲れない映像を作り出すことなのです」
取材後、ICCとISVCのデモンストレーションを見せてもらったが、この時の驚きを文字に表わすことはかなり難しい。少なくとも現行のハイビジョン映像や4K映像とは比較にならないほどの立体感や質感、臨場感が感じられるものだったのは確かだ。
その理由を、近藤は「遠くの山並みに焦点を合わせる時は目の中の水晶体が薄くなり、手前の人物に焦点を合わせる時には水晶体が自然と厚く調整されているから」と説明してくれた。雄大な風景を前に何時間過ごしたところで、目や頭が疲れないのと同じ理屈だ。
「脳が映像を自然な風景として認識しているからこそ、目もそのように機能するわけです。実際に比較してみると、現在一般に流通している映像の不自然さが分かると思います」
「人に否定されたり反論されたりしたことには何か意味がある」
最後に、研究所におけるリーダーの役割を「遠くの未来を見通す力を示すこと」と定義付ける近藤に、パラダイムが大きく変化する時代に際して、経験の浅い若者がどのように身を処すべきか聞いてみた。
「これから自分のやろうとしていることが『インベンション』に該当するかどうか、簡単に判断する方法を教えましょう。もし、やりたいと思ったことを人に話した時、否定されたり反論されたりしたら、その試みには何か意味があると思っていい。
逆に、もし賛同されたり褒められたりしたら、そこには新しさはないと思うべきです。なぜなら、人は自分の知っていることを反復された時にしか喜びを感じない生き物だから。新しい考えは常識と相容れません。若い人たちには勇気を持って、この常識を乗り越えていってほしいですね」
取材・文/武田敏則(グレタケ) 撮影/竹井俊晴
RELATED関連記事
RANKING人気記事ランキング

NEW!
ひろゆき×ドワンゴ川上量生が「エンジニアは頭が悪くないと大成しない」と語るワケ

NEW!
登大遊、落合陽一を生んだ、未踏の父・竹内郁雄に聞く「優れたエンジニア」に必要なこと

NEW!
怒鳴り散らして周囲がドン引き、組織崩壊……今だから語れる「若手時代のやらかし」で学んだこと【澤 円、松本勇気、ばんくし他4名】

新NISA普及の壁とは?「日本経済を影で支える」技術屋の働き

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
タグ