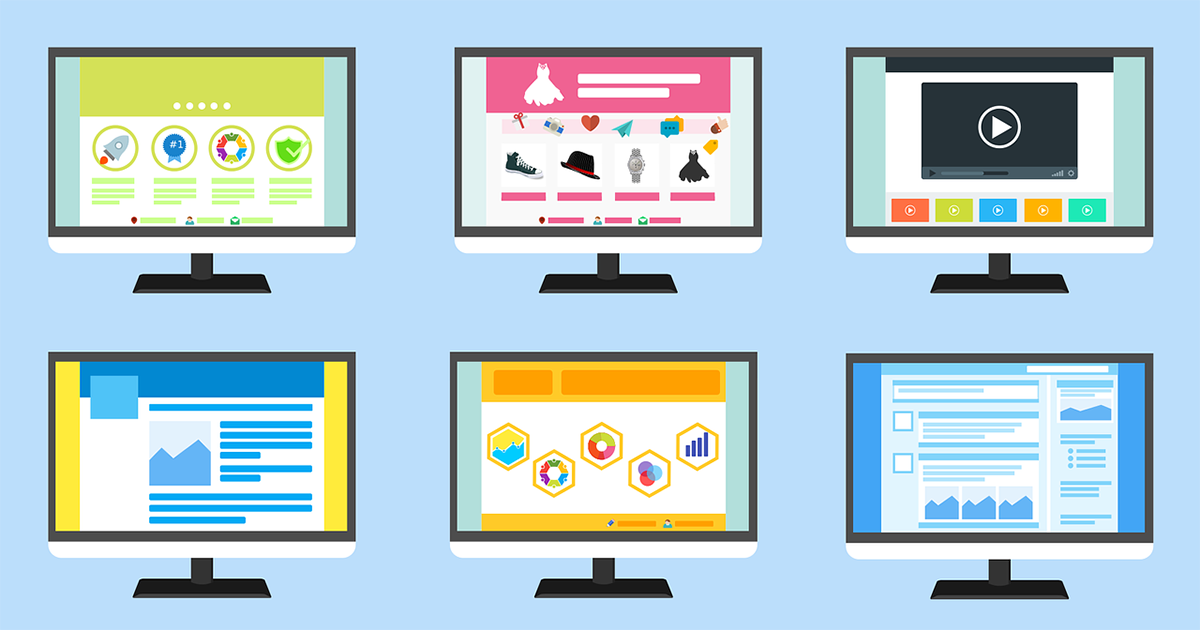増井俊之、未来のUI開発に向けた思考と試行~希代の発明家は、なぜ今研究室を“リビングルーム化”するのか?
みんなジョブズに騙されている――。
UI研究の第一人者、慶應義塾大学環境情報学部の増井俊之教授が昨年9月、エンジニア向けトークイベント『TechLION』の壇上で放ったこの刺激的なフレーズはその後、ネット上で多くの反響を呼び、(時には言葉だけが独り歩きする形で)活発な議論を巻き起こした。
>>「みんなジョブズに騙されている」増井俊之教授が進歩の止まったコンピュータのUIを問い直す【TechLIONレポ】
AppleでiPhoneの日本語入力システムを開発したことでも知られる増井氏であるから、その意図が単なるスティーブ・ジョブズ批判であるはずがない。30年以上前に開発されたGUIを、いまだ「当たり前」のものとして無条件に受け入れることに対する、研究者や開発者に向けた問題提起であったことは容易に想像できる。
ゼロックス社のパロ・アルト研究所でGUI開発を中心で担った研究者、アラン・ケイの「未来を予測する最も良い方法は、それを発明することだ」という言葉を引き、「未来の当たり前、未来の常識を発明したい」と増井氏は語る。
新著『スマホに満足してますか? ユーザインターフェースの心理学』の中でも「現在のコンピュータのユーザインタフェースはまだまだ理想には程遠い」と指摘している増井氏は、どんな未来を見据え、新たな「当たり前」を発明するために今、どんなことに取り組んでいるのか。
その答えを知るべく湘南藤沢キャンパスにある研究室を訪れると、そこかしこに「思考」と「試行」の跡が散らばっていた。
リビングのような研究室で、生活者目線のUIを探る
専門書がぎっしりと並べられた本棚は、いかにも研究者のそれらしい。
しかし増井氏の研究室にはそれとともに、大きなソファーやテーブル、いくつかの照明や箱型の物入れなど、およそ研究室には似つかわしくない家具が数多く配置されている。ゆくゆくはこれに、テレビなどが加わる予定もあるという。
自宅並みに快適な空間で研究を進めたいから、というわけではもちろんない。リビングルームを思わせるこのレイアウトこそ、未来の「当たり前」を発明するためのアイデアの源泉なのだ。
「ちょっと前まではどこのオフィスにも巨大なコンピュータが並んでいたものでしたが、どんどんと小型化が進み、現在ではスマートフォンがかつてのスーパーコンピュータ以上の役割を果たすようになりました。この流れが究極的に進めば、コンピュータの形をしたものは全てなくなり、日常の中に完全に溶け込む。これが、ユビキタス・コンピューティングの世界です。
私が目指しているのは、将来そうなった時に当たり前のものとして受け入れられるようなUIの発明。コンピュータの機能をすべて家具に埋め込むのがいいのではないか、というのが現時点での私の考えです」
リビングルームを模した研究室の中を自宅で生活するように自由に歩き回ることで、生活者にとって本当に便利な形とは何かを日々、模索しているというわけだ。その際に大切にしているのは、家具の元々の形状や機能は極力変えないことという。
「台所で料理をしながら音楽を聴いたり、自由にレシピを参照したりしたいからといって、それを実現するために台所の形状が変わり、料理しづらくなってしまうのでは本末転倒。それはあくまで開発者側の都合です。
電気をつけるのに壁のスイッチを押さなければならなかったり、テレビを見るのにリモコンで操作しなければならなかったりするのも、利用者にとってそれがベストだからではなく、すべて技術的な制約から来ています。
今はそういったものをすべてネットで制御できる時代。技術的な制約からは解放されたわけです。それなのにいつまでもリモコンを使わせているのはおかしな話で、本来はもっと便利なものを提案できるはずです」
こうした考え方から生まれた一つの成果が、たった2つのキーだけで操作するコンテンツナビゲーションシステム『Gear』だ。
従来であれば、ニュースを読むのにはキーボードをたたいて検索しなければならなかったし、音楽を聴くのにも専用のアプリを起動しなければならなかったが、このシステムであれば、上下2つのキーを使うだけで全てが事足りる。
圧力センサを備えたペダルの形状にすることで、料理で両手がふさがったままでもレシピをめくることができるし、ソファーの肘掛けに埋め込めば、背もたれに寄りかかったまま自由にテレビを操作することもできる。その時、台所やソファーの機能性が失われることはない。
最適な組み合わせを追い求めた電子工作の日々

思い付いたらすぐ試す電子工作の日々
「ハードとしてのコンピュータが消えたとしても、センサやソフトはどこかに残るわけです。その時に大事になるのは、どういう種類のセンサやソフトを、どう組み合わせるか。その可能性を探るために、今はもっぱら電子工作に明け暮れています」
例えば研究室のドアは、NFC機能のあるスマートフォンをかざすと画面に回転式のカギが現れ、それを回すことで解錠できる。ドアの内側にはセンサとサーボモータを組み合わせた装置があり、そこからWebへとつながっている。
部屋の隅に無造作に置かれた箱は明るさセンサで、研究室に訪問者があるとWeb経由でメンバーに通知するというもの。天井付近に敷かれたプラレールは、カメラを載せた鉄道模型を走らせることで、遠隔地から会議に参加できるシステムになっている。
思い付いたアイデアはすぐに形にする――。雑然と置かれた半田ごてや各種マイコンボードは、そういった姿勢の表れだ。
「EdisonやArduinoなどのマイコンがいまや簡単に手に入りますし、一方では3Dプリンタやレーザーカッターの普及によるメイカームーブメントも盛り上がりを見せています。『IKEA Hackers』というサイトに象徴されるように、一般の人が簡単にいろいろなものをHackできる時代です。
メーカー企業が、古い常識や自社の都合にいつまでも縛られて本当に便利なものを作れずにいるようであれば、こうしたユーザーの動きがうねりを生み、それに突き動かされる形でメーカーが重い腰を動かす、といったことも十分に起こり得るでしょうね」
こうした工作の数々は、今盛り上がりを見せているIoTを連想させるものだが、増井氏は「IoTには現状、共通規格がないために、各企業が独自にネットワークを構築せねばならず、非常に効率が悪いという課題を抱えている」とも指摘する。
増井研究室のこれらのシステムはすべて、独自に開発した一つのソフトで制御されており、IoTが抱えるこうした課題に対する回答にもなっている。
必要なのは、「実装する力」と「当たり前を疑う力」
さて、来るべきユビキタス・コンピューティングの時代に向けて、エンジニアに求められる能力とは何だろうか。増井氏が考えるポイントは2つある。
一つは、前述した電子工作で自ら実践しているように、思い付きをすぐに実装する力だ。
「私が今考えているように家具になるのか、単なる板になるのか、“正解”はまだ分かりませんが、今後の『当たり前』がハードであることは間違いない。ですから、エンジニアもそれを試作できないことにはどうしようもなくなるでしょうね。
システムと動き、デザインのすべてをトータルで作る力がエンジニアにも求められるようになる。それができないというのは、JavaScriptが書けませんと言っているようなものです。takramが提唱するデザインエンジニアリングなどは、そうした必要性をいち早く感じて実践している好例と言えるでしょう」
そしてもう一つは、増井氏が「みんなジョブズに~」というメッセージを通じて伝えたかったこと。自分が現在の「当たり前」にとらわれているということに、常に自覚的でいられる力だ。
「人はリモコンを使ってリモートにテレビをコントロールしたいわけではなく、放送されている映画を見たいだけ。『当たり前』のように使っているリモコンを離れて、そのことを正確に認識することができるか。人はそもそも何がしたいのかに立ち返って考える必要があるでしょう」
そこで増井氏が提案するのが、「長屋コンピューティング」という発想法。長屋とはすなわち、何もない生活の象徴だ。
「何もない長屋のようなところにいることを想像し、最低限何があれば自分は満足できるか、それを形にするためには最低限何が必要なのかに向き合ってみる。『当たり前』に囲まれた生活から一歩離れることで見えてくるものがあるのではないでしょうか」
「死ぬほど便利なもの」を求めた孤独な戦い

今ある常識を疑い、本当に便利なものを発明する道は非常に孤独だ
ただし、そうした「思考」と「試行」の末に、仮に未来の「当たり前」になりうるものを発明したとしても、それが世間に受け入れられ、本当に「当たり前」になるまでにはさらに高いハードルが待っている。
増井氏の発明であり、今では多くの人に当然のように使われている携帯電話の予測入力システム『POBox』も、開発当初は「利用者本人の意思に反した誘導につながる」などと多くの批判や懐疑的な意見にさらされたという。
「人間は慣れ親しんだものを使い勝手がいいと判断しがちなため、全く新しいものを正等に評価することが難しい。また、苦労して機能を限界まで削ったとしても、そのことを理解できずに、結果としてほとんど使わないような機能が開発者の手によってどんどん付け加えられてしまい、シンプルさが損なわれるといったこともよくあります」
今ある常識を疑い、本当に便利なものを発明する道のりというものは、非常に孤独な戦いであると言えるのかもしれない。
増井氏はかつて、決してITリテラシーが高いとはいえない自分の母親でもスマートフォンを使えるよう、顔アイコンをタップするだけで任意の相手に電話が掛かるシンプルなシステムを作ったことがあった。
「しかし、母親はそれでも使いこなせなかった。電話の切り方が理解できなかったからです。実際に使ってもらうためには、放っておくと勝手に電話が切れるなど、さらにもうひと息、簡単にしなければならなかったのです」
ここから得られた教訓は、未来の「当たり前」を世間に受け入れてもらうには、「それなりに便利」というレベルでは足りないということだ。
「研究者や開発者は、死ぬほど圧倒的に便利なものを作り出すしかないのです」
取材・文/鈴木陸夫(編集部) 撮影/竹井俊晴
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

南場智子「ますます“速さ”が命題に」DeNA AI Day2026全文書き起こし

AI時代、技術の壁は消え「心理の壁」が残る。まつもとゆきひろが40年コードを書き続けて見つけた“欲望”の価値

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

「休める仕組み」が強い開発チームを作る。主力エンジニアの3カ月育休を支える“失敗を許容する”空気感

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
タグ