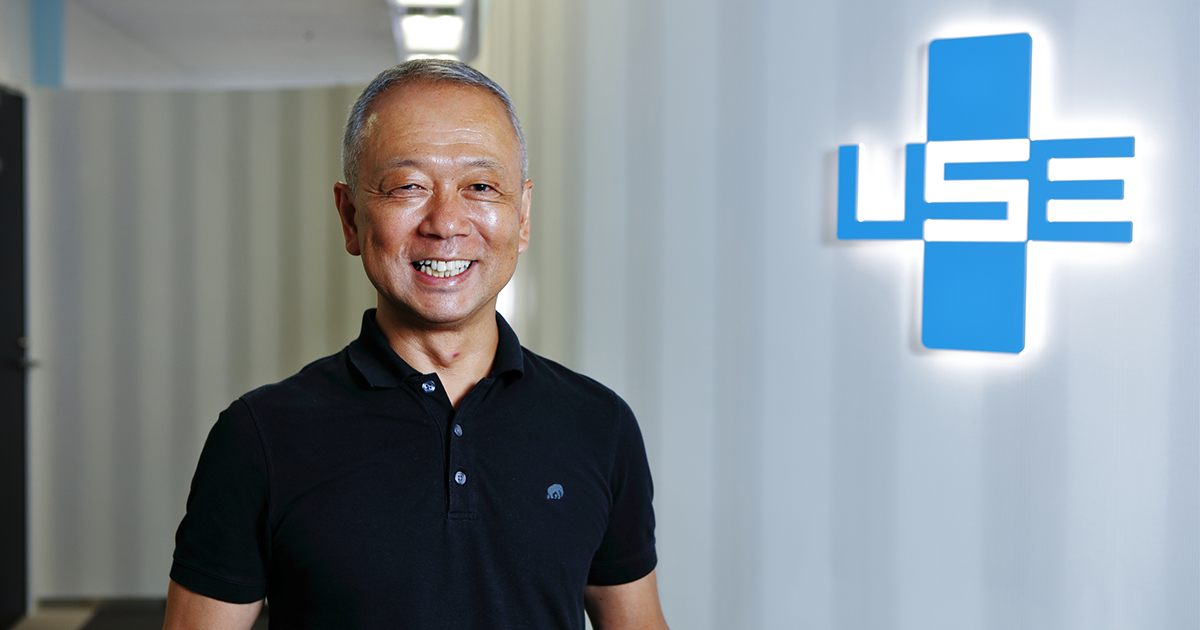優れた技術者たちは何を目指すのか?各社の「匠」の視点を覗こう

UI研究の第一人者・増井俊之が目指す「コロンブス指数」の高い発明とは?【連載:匠たちの視点-増井俊之】

慶應義塾大学 環境情報学部 教授
増井俊之氏
1959年生まれ。ユーザーインターフェースの研究者。東京大学大学院を修了後、富士通半導体事業部に入社。以後、シャープ、米カーネギーメロン大学、ソニーコンピュータサイエンス研究所、産業技術総合研究所、Appleなどで働く。2009年より現職。携帯電話に搭載される日本語予測変換システム『POBox』や、iPhoneの日本語入力システムの開発者として知られる
「理想的なインターフェイスってどんなものだと思います?」
そんな問いかけにどう答えるか困っていると、慶應義塾大学環境情報学部の増井俊之教授は、少し間を置いて、自身が考えるユーザーインターフェースの本質について教えてくれた。
「泥酔していても使えること。それが大事だと思うんです」
「泥酔していても~」とは、使い方に頭を悩ませたり、身体的な能力の差や言葉、文化の違いによらず、誰にでも簡単に使えるということ。これが、増井教授の考える、優れたユニバーサルデザインを体現したインターフェースである。
多くの携帯電話や情報端末に取り入れられた日本語予測入力システムや、iPhoneの日本語入力システムなど、長年にわたって情報機器と人間の間を取り持つインターフェースの研究に労力を費やしてきた増井教授ならではの考察と言えるだろう。
「たくさんプログラムを書いて物事を解決するのは好きじゃない」
そして、増井教授の守備範囲は、わずか数インチの液晶画面に収まりきるものではない。
例えば、と言って増井教授がポケットから取り出したのは、一台のAndroid端末。その端末をあるカードの上に置くと、起動音とともにボリューム状のコントローラーが画面に表示され、端末の微妙な回転に合わせて画面上のコントローラーが回転。ゲージも自在に増減する。
増井教授のもう一つの研究テーマである「実世界指向GUI」の即席デモンストレーションだ。

課題を単に解決するのではなく、解決の美しさやシンプルさを追求することを理想に掲げる増井氏
「不思議に見えるかもしれませんが、特に複雑なことをしているわけじゃないんです。種明かしをしちゃうと、SuicaやTaspoのようなICカードの情報を、Andoroid側のNFCリーダーで読み取って操作しているだけ。使っているのもJavaScriptとブラウザだけですから簡単です」
増井教授は以前、これと同じ仕組みとCDパッケージを使ってプレゼンテーションを行ったことがあった。テーブルのある位置にCDのパッケージを置くと、自動的に音楽が再生され、さらにそのパッケージを回転させると音量が加減できる。この様子を見た観客たちは、まるで魔法でも見るような面持ちだったという。
「そもそも大量のデータを力業で解析していたり、たくさんプログラムを書いて物事を解決するのって、あんまり好きじゃないんです。そういうのってオシャレじゃないでしょう?(笑)。僕が好きなのは、大きな問題を複雑に解くのではなく、面倒なことや不便なことをちょっとした手間で解決すること。そっちの方が性に合っているんです」
自らが理想とするシステムは、「コロンブス指数が高いシステム」と呼んでいる。「コロンブス指数」とは、得られる感動や解決方法を、システムの複雑さで割ったもの。つまりこの値が高いほど、「コロンブスの卵」的な喜びに満ちた創造になるわけだ。
「どんなに酔っていても使えるのは『泥酔指数』が高いシステム。ユーザーの使い勝手を考える上ではこっちの指数もすごく大事なんですよ」
増井教授はユーモアを交えながらそう力説する。
標準化以前の「カンブリア大爆発」を経験した青年時代
「小学校の終わりから高校にかけては、アナログシンセサイザーなんかを自作するような電子工作少年でした。高校になってしばらくしたころ、『トランジスタ技術』を読んでいたら、『マイコン』というものの存在を知り自分でも作ってみようと思ったわけです」
自身の幼少期をこう話す。当時はキットなどなく、自分でICチップや必要な部品を一つ一つ手に入れて、イチから作らなければならなかった。
「もちろん、プログラムするにしても今みたいにキーボードやモニターはありません。トグルスイッチを使ってメモリに直接マシン語を書き込む、そんなことをやっていましたね」
電子工作少年だった増井少年が、マイコンとの出合いをきっかけにソフトウエアの世界に引き寄せられるまでには、それほど時間は掛からなかった。
大学、大学院で電子工学を学ぶ過程で、ますますソフトウエアの魅力に引き込まれていった増井氏は、卒業後、富士通に入社する。しかし、配属先に望んでいた仕事はなかった。入社から2年後、増井氏は念願のソフトウエアの世界に飛び込べく、シャープへの転職を決意。この時代から、現在に通じる予測インターフェースや検索システムなどの研究に取り組むようになった。
「シャープに移って最初の仕事は、UNIXに載せるウィンドウシステムの開発でした。当時はまだ今のように開発環境もメソッドも整備されておらず、標準も確立されていない時代です。何事もゼロから作らなければなりませんでした」
CPUもメモリも制約だらけで不自由と言えば不自由だったが、確立されたルールがない分、「コンピュータの世界に無限の可能性が感じられた」と当時を振り返る。
「生物の歴史で言えば、ちょうど『カンブリア大爆発』みたいな状況でしょうか。大変でしたけどすごく楽しかったのを覚えています」
ただ、ほとんど無限の可能性があるかに見えたコンピュータの世界だったが、その多くは子孫を残すことなく、歴史の闇に消えていってしまった。
「ウィンドウのデザインは、Macintoshの前身にあたるLisaあたりからほとんど変わっていません。もはやウィンドウシステムはもうこれ以上大きな進化はしないと言うことなんでしょうね。昔は『こんなウィンドウシステムを考えた』なんて情報がよく耳に入ってきたものですが、今はそんなことを言う人は誰もいなくなりました。もっと進化できたはずなのに、もはや前提の一つになってしまった。とても残念なことだと思います」
技術に携わる者にとって、頭を悩ませる領域が小さくなることは、必ずしも良いことばかりではない。前提という名の既成概念が幅を利かせると、新しい発想はしづらくなる。増井教授はそれを憂えているようだった。

CPUの構造を知らなくても開発できる便利さと不幸
高スペックなコンピュータを誰もが所有し、高速インターネット回線で世界中に接続していることが常態化している今、知りたいこと、欲しいものは即座に手に入れられる時代になった。
開発環境はかつてないほど充実し、ネットをあたれば必要なコードを入手することさえも容易だ。効率化は目に見えて進んでおり、良いこと尽くめのようにも見えるが、長年この世界に携わってきた増井教授の目にはメリット以外のものも映っている。
「基礎的な素養を身に付けないまま開発できてしまうことが、かえって心配です。確かにCPUの構造を知らなくてもアプリは作れますが、発想の豊かさとか開発力の面で、すぐに壁にぶつかってしまうんじゃないかと憂慮しているんです」
素養の乏しさゆえ、ボロが出るのはもしかしたら何年も先になるかもしれない。それがかえって恐ろしいとも感じている。

開発の基礎を知らない技術者が増加している今こそ、原点に立ち返って学ぶことの大切さを語る
「よく、人からどうしたら発想力が高まるのか? と聞かれるんですが、何時間も考えた末に出てきた答えや、数時間のブレストで導き出した答えって実はあんまり信用していないんです」
たくさんの文献を読み、数多くの人と接した上で考えたことが、何カ月か後にポコッと出てくるアイデアの方が筋が良い――。こうした状況を作るには、インプットを充実させておかないと上手くいかないという。
「質もそうですが、たくさんの幅広い知識に触れることが必要ですし、理解するには基礎的な素養も問われるんです」
長期間、モノづくりにかかわり続けていきたいと思えば、アイデアの枯渇は命取りになる。上部レイヤーの華やかな部分だけでなく、その背景にある周辺技術について学んでおくのは、息の長い開発者になるための必要条件といえるだろう。
目先の面白さだけを追いかけていても、生き残るのは難しいはずだ。
「慣れ親しんでいるから」というだけでまかり通る世界を駆逐したい
富士通から転職したシャープで、ソフトウエアを実装することの難しさと面白さを知り、それ以降のライフワークともなる予測インターフェースや検索システムの研究に出会った増井教授は、シャープ在職期間中にカーネギーメロン大学の客員研究員など、海外生活も経験。帰国後もソニーコンピュータサイエンス研究所や産業技術総合研究所、そして再びアメリカにわたりAppleで活躍するなど、現職に就任するまでの間、めまぐるしく職場を変えてきた。
人生の転機と呼べる出来事はたくさんあったというが、そのきっかけはたいてい、相手側からのアプローチによってもたらされたという。
「シャープにいた時は奈良の天理にある研究所にいたのですが、ちょっと自分には刺激が少な過ぎて、それで理由を見つけてはちょくちょく東京に行っていたんです(笑)。あんまり深い考えなしに動いてきたように思う部分もあるのですが、今改めて考えてみると、そうやって多くの人に出会ったことで、いろいろな方から誘いを受けることができたのかもしれません」
こうした経験から増井教授は、今の若い開発者は内にこもらず、勉強会でもイベントでも、どんどん足を運ぶべきだと考える。見識や人脈を広げる第一歩になると思うからだ。

慣れ親しんでいる物事にも、イノベーションの可能性は大いにある。そう信じて研究を行う
でも、参加するだけに満足するのでは意味がない。自ら進んで「発表すること」にも積極的であってほしいと言う。「発表すること」は、「観る」、「聞く」以上の成長をもたらしてくれるからだ。
「僕らの仕事は、世の中の人が見過ごしている不便さを解消すること。早い段階で良いものを出していかないと、昔から慣れ親しんでいるというだけの理由で、世間に不便なものをはびこらせてしまうことにもなりかねません。わたしのかかわったiPhoneの日本語入力システムだって、決してベストな入力方法とは言えませんし、今後も良くないインターフェースが現れたらちゃんと対抗策を提案しないといけないと思っています」
「技術の進歩には終わりはないんです」。そう締めくくった増井教授の胸には、環境や人から与えられる刺激を自らの創造力に転化させ続けなければならないという矜持がある。問題は、そうした場に身を置き続ける強い意思があるかどうか。
選択肢が増え、開発への障壁が低くなった今、開発者の覚悟が試される時代に突入してきた。
取材・文/武田敏則(グレタケ) 撮影/竹井俊晴
RELATED関連記事
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
RANKING人気記事ランキング

南場智子「ますます“速さ”が命題に」DeNA AI Day2026全文書き起こし

AI時代、技術の壁は消え「心理の壁」が残る。まつもとゆきひろが40年コードを書き続けて見つけた“欲望”の価値

年収2500万でも貧困層? 米マイクロソフトに18年勤務した日本人エンジニアが「日本は健全」と語るワケ

「休める仕組み」が強い開発チームを作る。主力エンジニアの3カ月育休を支える“失敗を許容する”空気感

AWS認定資格12種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も
タグ