今後の成長に期待が膨らむネオジェネレーションなスタートアップをエンジニアtype編集部がピックアップ。各社が手掛ける事業の「発想」「技術」「チーム」にフォーカスし、サービスグロースのヒントを学ぶ!

“テスラ越え”を目指すTuringの「1台目」開発裏!「自分たちならできる」実感はなぜ大事?
「We Overtake Tesla(テスラを追い越す)」を合言葉に、完全自動運転EVの量産メーカーを目指す――。
壮大なビジョンを掲げたTuring(チューリング)は、史上初めて名人に勝利した将棋AIソフト『Ponanza』を開発したCEOの山本一成さんと、米国カーネギーメロン大学で自動運転を研究したCTO青木俊介さんが2021年に創業したスタートアップだ。
22年7月にはシードラウンドで10億円を調達するなど、その将来性に大きな期待が集まっている。
自動運転システムの開発に取り組むスタートアップは国内にもあるが、ハードウエアとしての自動運転車をいちから自社で製造し、量産化まで目指しているのはTuringだけ。30年には完全自動運転EVを1万台生産・販売することを目標に据え、前人未到の挑戦をしている。
その達成に向けての一歩として「今年1月に初のエンドユーザー向け製品となる『THE 1st TURING CAR』を販売しました」と語るのはCTOの青木さんだ。

2023年1月に初のエンドユーザー向け製品となる『THE 1st TURING CAR』を発売。自社開発のAI自動運転システムを搭載した製品を1台限定で販売し、大きな反響を呼んだ(参照元)
ただ、この1台目の車両は、同社が目指す完全自動運転車ではなく、他メーカーの既存車にTuring製の自動運転システムを搭載した、いわば改造車だ。
完成車メーカーを目指す同社にとって、この1台目の販売にはどんな意味があったのか。CTOの青木さんとUXエンジニアリング チーフエンジニアの渡邉 礁太郎さんの二人に話を聞くと、前例のないチャレンジをするために必要なものが見えてきた。
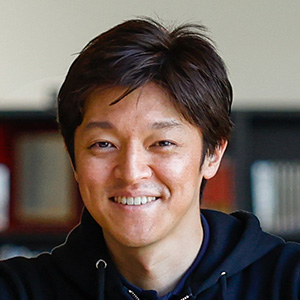
Turing株式会社 共同代表/CTO 青木俊介さん(@aoshun7)
米国カーネギーメロン大学計算機工学科でPh.D(博士号)取得。米国では自動運転システムの開発・研究に従事し、サイバー信号機の開発やGM社ウルトラクルーズの開発に携わる。2021年より国立情報学研究所の助教に着任。同年、山本一成氏とTuringを共同設立

UXエンジニアリング チーフエンジニア 渡邉 礁太郎さん
新卒でサイバーエージェントに入社し、エンジニアとしてゲームやWebサービス、ECの開発に従事。その後リクルートに転職し、Webフロントエンドの開発に携わる。2022年8月、Turing入社。『THE 1st TURING CAR』の開発ではプロジェクトオーナーを務めた
売らないと、売れない。だからまず1台だけ造って売った
−−Turingはなぜ、自動運転システムにとどまらず、ハードウエア(完成車)まで造る会社にしようと思ったのですか?

青木:どうせ事業を起こすなら、世の中の価値観や、長年解消されない社会課題を払拭するようなことを成し遂げたかったんです。
中でも自動車産業はグローバルで300兆円規模にもなる市場でありながら、国内では長い間、新しいカーメーカーが生まれていません。一方海外に目を向けると多くのスタートアップが挑戦しています。
特に、EV専業メーカーであるテスラはその代表格。だから私たちも創業時からテスラを追い越すという明確なミッションを掲げています。
−−今年1月に初のエンドユーザー向け製品となる『THE 1st TURING CAR』を発売しました。なぜこのタイミングで、しかも「1台限定」で販売したのですか?
青木:エンジニアにとって「自分が書いたプログラムで車が動く」というのはワクワクする体験で、ものづくりの楽しさが手に取るように実感できる時間だと思います。
ただ、気を付けなければいけないのが、目の前の研究開発に夢中になりすぎて、単なる研究部隊になってしまうことです。
今取り組んでいることが楽しいゆえに、放っておくと自分の研究を論文で発表して満足してしまう、といったことになりかねません。
Turingが目指すのはあくまで自動車メーカーであり、テスラを超えるにはプロダクトを完成させてユーザーに売らなければいけない。
ところがエンジニアが集まると、どうしても技術の追求に目が向いてしまい、「誰のためにこのプロダクトを開発しているのか」「つくったものをどうやってお金にするのか」などを見失いがちです。
私は創業当初から、そんな事態に陥ることだけは避けなくてはいけないと危機感を抱いていました。だから「車を造って売る」というプロセスを一度回してみるべきだと考えたんです。
まずは1台でいいから売ってみれば、エンジニアも「自分たちは研究するためではなく、プロダクトを売るためにこの会社にいるのだ」と実感できる。それが『THE 1st TURING CAR』のプロジェクトをスタートさせた理由です。
−−まだ実体のないプロダクトだからこそ、実感が必要だったのですね。

青木:そうですね。まずは1台売ったことで「Turingは自動車を造って売る会社なのだ」と社内外に示す実績をつくれたのは、よかったですね。
最終到達点と比較すると小さな出来事かもしれませんが、この小さな有言実行こそ、エンジニアを含めた全メンバーの自信になったと思いますし、「テスラを超える完全自動運転EVの量産メーカーになる」というゴールを改めて全員で強く意識できたのは大きな収穫でした。
自分たちのアイデアや技術を製品に落とし込む過程をメンバー全員で楽しむことができたと同時に、お互いの強みや性格をより深く知ることができましたし。
「この人にはこんな一面もあるんだ」といった発見も多かったので、Turingが次のステップへ進むときは、他のメンバーの思考や行動をより解像度高く理解しながらチームワークを発揮できると思います。
大手完成車メーカーにできない次世代の車づくり。キーマンは、ソフトウエアエンジニア
−−渡邉さんは『THE 1st TURING CAR』のプロジェクトオーナーを務めたとお聞きしました。今回の開発の概要を教えてください。

渡邉:製品の発売は今年1月でしたが、青木の話にもあった通り「22年末までにまずは1台の車両を開発・販売する」というマイルストーンを置き、同年8月頃から本格的にプロジェクトが始動しました。
どうしたら「まず1台」を達成できるか逆算して考えたとき、いきなり完成車を目指すのではなく、まずは自動運転システムを既存の車体に搭載するところから始めようとゴールを決めました。
結果、『THE 1st TURING CAR』はレクサスRX450hをベースに、自社開発した自動運転システムを搭載する形で落ち着くことに。
3年後の25年に「レベル2の自動運転機能を備えた独自のEV車を100台販売」という目標を見据えていることもあり、自動運転レベルはレベル2相当に設定しました。
いわば改造車なので、ハードウエアで追加したのはカメラとコンピューター、ディスプレーくらい。なので、今回のプロジェクトに関しては、IVI(車載インフォテイメント)開発と呼ばれるソフトウエア領域の開発が中心でした。
−− 完成車メーカーと聞くとハードの印象が強いですが、AI技術がコアとなる自動運転車だと様相が違ってくるのですね。完全自動運転車の開発において、IVIはどんな重要性を持つのでしょうか。
渡邉:現時点におけるIVIの重要な機能は「自動運転の可視化」です。おっしゃるとおり、完全自動運転車のコア技術はAIですが、一般の人からすればAIがどうやって周辺の状況を認識し、次の行動を判断しているのかよく分からない。
分からないものに運転を任せるのは不安だと感じる人も多いでしょう。そこで重要になるのがIVIです。
例えば、『THE 1st TURING CAR』では、車内に設置したディスプレーにカメラの映像をリアルタイムで映し、AIが道路の白線や前を走る車、進行方向などをどのように認識しているかを表示しました。
世の中にレベル5が普及して自動運転が当たり前になるまでは、運転者に安心を与えるIVIの可視化機能が必要になると考えています。
−− 1台目の開発において、困難だった点やチャレンジングだったことはありますか。
青木:どこまで攻めるかの線引きは難しかったですね。自動運転機能はどのレベルを目指すのか、ベース車両にどこまで改造を加えるのか。
これも大学の研究室ならなんでもやりたいようにやってみればいいのですが、私たちは製品として売ることが目的なので、実用性や安全性、さらには法律や規制なども考慮しなければいけない。
でもルールを守ることだけに気を取られていると、例えば「本当はこんなUIUXが理想だけど規制に収まらなくなるからやめておこう」と保守的な発想になり、新しい挑戦ができなくなってしまいます。
だから自動車の法規に関する本を読み込んだり、官公庁や法律事務所に相談したりして、何がどこまでできるのかを徹底的に調べました。
渡邉:例えば実証実験の段階では、カメラを窓ガラスの中間部につけていたんですが、製品として販売する場合は「カメラはフロントガラスの上側20%以内に設置しなければいけない」と法律で定められていることが分かって調整しました。
とはいえ、こうした課題は一つ一つつぶしていけばいいだけなので、メンバーがそれぞれの技術力を発揮してクリアしていきました。
−− 一般的にIVIは「情報」と「娯楽」を提供するシステムと定義されています。可視化は情報の提供にあたりますが、今後は娯楽の提供も充実させていく予定ですか。
渡邉:走行中に音楽を聴いたり、ゲームを楽しんだりする機能はいずれ搭載することになるでしょうね。機能としてはスマホの延長みたいなものなので、Webやアプリ開発を手掛けてきたエンジニアなら、その経験をIVI開発で生かせると思います。
その際に私がこだわりたいのは、デジタルネーティブ世代が違和感なく使えるUXを提供すること。
例えばカーナビは古くからある車載製品ですが、基本的な操作性は昔からあまり変わっていない。だから最近はカーナビより便利なスマホのナビ機能を使う人が増えています。
もし自動運転車にスマホやタブレットのような機能が組み込まれたら、ユーザーは同等の操作感を期待するはず。
「車だからこんな感じでいいよね」ではなく、デジタル社会で暮らす現代の人たちが満足できるUXを追求したいと考えています。

青木:渡邉が手掛けている技術がまさにそうですが、ソフトウエアで操る領域を増やせば、車はより楽しくて使いやすいものになります。なので、自動車業界にはもっとソフトウエア人材が入ってきていい。
もし車が利便性だけを提供するプロダクトだったら、電車やバスなど代わりの交通手段がある地域の人には必要ないはずです。
それでも車に乗りたいと思ってもらうには、「車って楽しいな」と思える体験を提供する必要があります。
カメラや時計も利便性だけを考えればスマホで代替できますが、それでもあえて一眼レフや高級時計を買う人たちがいるのは、使うのが楽しいからですよね。
これからは自動車も「使って楽しいプロダクト」を目指すべきだし、そのためにはソフトウエアの技術や知見が必要なんです。
「いいヤツの集団」を意識的に構築
−−自動運転システムの開発だけでなく、自動車そのものを自社でいちから造るという前例のない挑戦をするにあたり、チームづくりにおいてこだわっている点はありますか?
青木:チームづくりの前提となる採用にはかなり力を入れています。30年を見据えた中長期的なチームづくりを考えると、最初に集まる10人や30人が会社のカルチャーを決める土台になりますから。
なので、エンジニア含め全候補者をCEOの山本と私で必ず面談しています。二人のうち一人が少しでも迷ったら採用を見送るくらい妥協のない採用をしています。

特に大事にしているのが“いいヤツ”を採用すること。いくらエンジニアとして優秀でも、周囲にマウントを取ったり、攻撃的な物言いで仲間を傷つけるような人が入ったら、チームがギスギスしてしまいます。
それでは一人一人がのびのびと力を発揮できないし、メンバーがお互いに教え合い、学び合いながら、高め合っていくこともできません。
中長期的に組織として成長していくには、“いいヤツ”が集まった雰囲気の良いチームで気持ちよく働いてもらうのが一番。現在は30名弱の正社員が在籍していますが、私から見ても優しくて気遣いのできるメンバーばかりです。
−−完成車メーカーを目指すにはハードウエアとソフトウエアの開発を同時に進めていく必要がありますが、開発組織はどのような体制で動いているのですか。
青木:自動運転において「脳」の役割を果たすAI開発を担う「brainチーム」と、「身体」にあたる車両の開発を手がける「vehicleチーム」に分かれています。
Turingの場合、難しいのは開発体制で参考にできる事例がほとんどないことです。近年成功したスタートアップのほとんどはソフトウエア企業で、自動運転車をいちから造るために立ち上げたスタートアップは存在しない。

経済産業省が主導するスタートアップ育成支援プログラム「J-Startup」の支援企業に選出されたTuring。そこでも「日本でほぼ唯一の完成車メーカーを目指すスタートアップとなるだろう」と推薦コメントが寄せられている。
青木:ハード開発とソフト開発がシナジーをいかに生み出すかについては、現在も手探りで進めているのが正直なところです。
ただ、自分たちなりに工夫も重ねていて、二つのチームのメンバーを定期的に混ぜたりしています。
例えばbrainチームに入っていたインターン生をvehicleチームに動かすと、「こっちのチームはこんな取り組みをしているのか」と気付きを得る。そうすると「向こうのチームではこんな進め方をしていますよ」と自然と情報交換の機会が生まれます。
こうして人を行き来させることで、双方のチームがお互いのやり方を学び合い、良い部分は自チームに取り入れながら発展していけるのではないか。まだまだ試行錯誤ですが、今後も良いアイデアがあればトライしていきたいと思っています。
−−渡邉さんは『THE 1st TURING CAR』のプロジェクトオーナーとして、チーム運営で意識したことはありましたか。
渡邉:第1号車のプロジェクトは2チームのスクラムで進めました。2週間でスプリントを回したのですが、私が意識したのはプロセスごとのマイルストーンを言語化すること。
各スプリントが終了した時点で、どのような状態になっていたいのか。それさえ明確になっていれば、エンジニアも次に自分が何をすべきかわかるので、行動に迷いがなくなります。
加えて今回は「車を売る」という最終ゴールに着地させることが何より重要だったので、決められた期日までにやり遂げるためのノウハウをメンバーにインストールするように努めました。
例えば、プロダクトを世にリリースするにあたってどんなプロセスをたどり、途中何が必要になるのか、どこに気を付けなければいけないのかなど。
その点においては私がTuringに入社以前に、サイバーエージェントやリクルートで約30個のプロダクトを出してきた経験と知見が生きましたね。
−−完全自動運転車メーカーといえど、プロダクトをリリースする点では他のソフトウエア開発会社と変わらないわけですね。
渡邉:そうです。プロダクトがゲームやアプリであろうと、自動車であろうと、決められた期日までに求められる品質のプロダクトを届けるという点では全く同じですから、前職までの経験が非常に役立ちました。

−−完全自動運転EV量産というビジョン達成に向けて、最後に改めて意気込みをお聞かせください。
渡邉:技術はある日突然進化するのではなく、日々の積み重ねで進歩していくものです。正しい技術を正しく積み重ねていくから、ブレイクスルーも生まれる。
だから10年後も私たちは今と変わらず技術を積み重ねているんじゃないかと想像しています。大きな目標を掲げているからこそ、足元の階段を一歩ずつ着実に昇っていきたいですね。
青木:Turingはエンジニアリングの会社なので、ものづくりに真正面から取り組んでいきたい。そして日本のエンジニアが憧れる会社になりたいと思っています。

私が大学生だった10年ほど前、日本の学生たちはGAFAに憧れていました。当時は日本人が米国のGoogleに入社したことがニュースになるくらいだったので、私も「Googleは世界のトップ人材が集まるすごい会社なんだ」と信じていたんです。
ところが実際に米国に渡ってみて、意外な事実を知りました。私は当時カーネギーメロン大学で自動運転の研究をしていたのですが、周りの優秀な学生や研究者でGoogleやAmazonにジョインする人はほとんどいなかった。
トップ人材と呼ばれる人たちは、仲間とスタートアップを起業したり、新興企業にCxOとして参画したりと、新しいことにチャレンジする道を選んでいたんです。
それを知って「日本は負けてるな」と思ったんですよね。海外の人たちは次々と新しい挑戦をしているのに、日本人はGoogleに入れてもらって喜んでいるなんて、すごく悔しいじゃないですか。
だから自分は日本発のスタートアップを立ち上げて、社会的に大きなインパクトを出せることに挑戦し、日本の学生や技術者が憧れるような会社をつくろう。その思いがずっと自分の根底にあります。
今は完全自動運転車の開発に取り組んでいますが、それを達成した後にまた新たに取り組むべき社会課題が出てきたら、違うテーマにトライする可能性も十分あります。
常に大きな夢を掲げて全力で追いかける。Turingはそんな組織であり続けたいと思っています。

取材・文/塚田有香 撮影/桑原美樹 編集/玉城智子(編集部)
RELATED関連記事
RANKING人気記事ランキング
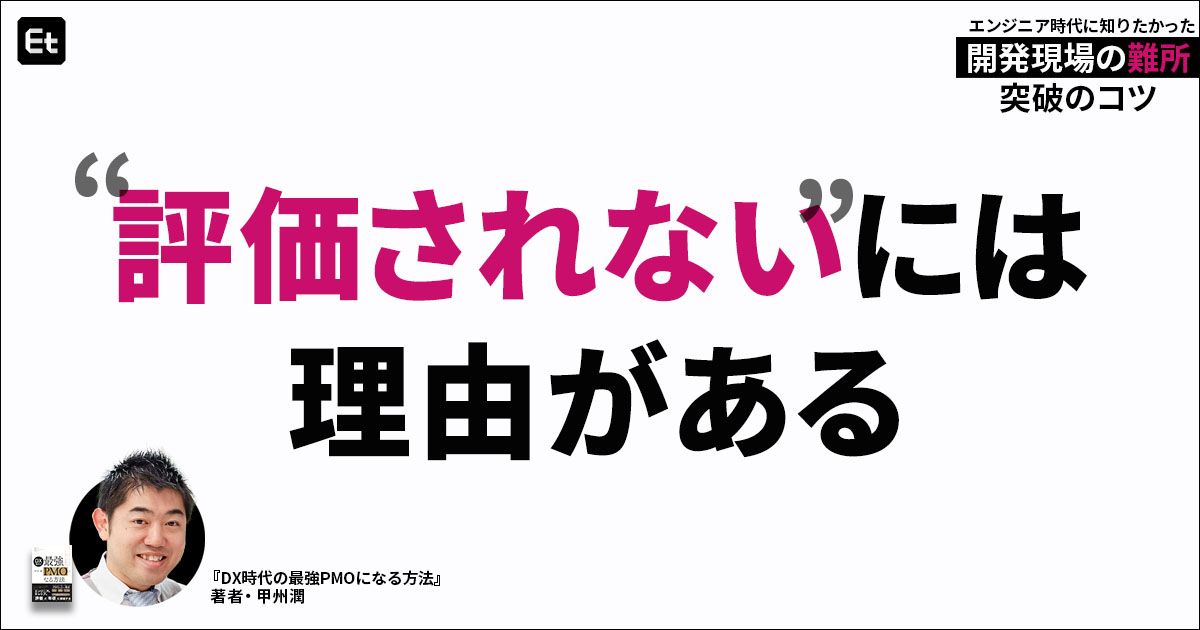
NEW!
“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

NEW!
コードを書かない管理職にはなりたくない、生涯プログラマー希望者のバイブル【ソニックガーデン・伊藤淳一】

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

NEW!
ノーベル物理学賞、本当は日本人研究者のもの? 甘利俊一の功績を忘れてはいけない【今井翔太コラム】
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
タグ


















