
株式会社 システム・リノベイト
社長室所属 kintone事業責任者
原山国治さん
東京のシステム開発企業にてNotes/Domino事業に従事した後、2020年4月システム・リノベイトへ入社。現在は事業責任者として、同社のkintoneビジネスをけん引している

【PR】 スキル
「エンジニアはシステムを“作る”ことが仕事」という概念が、変わりつつある。
ひと昔前までは、若手エンジニアはコードを書く経験をできるだけ積み、プログラミングの技術を磨くことから始めるべきだといわれていた。
しかし今後、エンジニアに対する「プログラミング」の需要は減少していくだろうと警鐘を鳴らすのは、企業のDX導入支援やWebシステム開発を手掛ける株式会社システム・リノベイトの事業責任者・原山国治さんだ。
生成AIの出現やオフショア開発の浸透で受託開発のニーズが減少し、エンジニアの役割が変化している近年。システム・リノベイトでは、若手エンジニアの育成方針を時代に合わせてブラッシュアップしているという。
今、若手エンジニアはどのような経験を積むべきなのか。顧客から求められるエンジニアになるために必要なスキルとは何か。システム・リノベイトの事例から紐解いていこう。

株式会社 システム・リノベイト
社長室所属 kintone事業責任者
原山国治さん
東京のシステム開発企業にてNotes/Domino事業に従事した後、2020年4月システム・リノベイトへ入社。現在は事業責任者として、同社のkintoneビジネスをけん引している
ーー近年、クライアントから寄せられる開発ニーズはどう変化していますか?
大規模なシステムを除き、直接コードを書いてプログラミングする案件は少なくなってきている印象です。
私は社会人になってからずっとIT畑におりますが、以前はお客さまからの要望に沿ったプログラムを作って納めるのが、エンジニアの主な仕事でした。
しかし、4GLのようにコードを書かなくてもプログラミングできる言語が出現したことや、オフショアでプログラミングを外注するのが当たり前になったことで、エンジニアという職種の概念が変化してきたように感じます。

ーーシステム開発でエンジニアが担う役割が変わってきているということですか?
そうです。以前は受け取った設計書通りにコードを書き、お客さまが求めるシステムを作るだけでも、十分エンジニアとしての役割を果たせていました。
ただ今は、お客さま自身が「業務に必要なシステムは自分たちで作っていこう」という考えに変わってきています。
弊社が導入支援を行っているサイボウズ社の『kintone(キントーン)』は、まさしくそのような要望を叶えるツールです。kintoneは、ノーコード・ローコードで開発できるクラウド型の業務改善プラットフォーム。高度なプログラミングスキルがなくても、利便性の高い業務システムを実装することができます。
私たちエンジニアはコードを書く機会が減った分、お客さまの要望を専門的な視点でヒアリングし、本当に必要なシステムを設計していく、コンサルタントのような役割が求められることが多くなりました。
他にも「より高度なシステムを実装する手伝いをしてほしい」「ツールを使いこなせるようにトレーニングしてほしい」というご要望をよく受けます。お客さまがkintoneを効果的に活用できるよう伴走する案件が増えていますね。
ーーエンジニアの役割が変化したということは、求められるスキルにも変化がありそうですね。
はい。基本的なプログラミングのスキルやIT知識は重要ですが、これからの世代のエンジニアたちには二つのスキルがより一層求められるようになるでしょう。
一つ目が、お客さまのニーズを汲み取る「傾聴力」。そしてもう一つが「想像力」。これらは、ニーズの背景にあるお客さまの業務課題にまで思考を巡らせ、システム設計に落とし込むために必要なスキルです。
実際の開発工程以上に、お客さま自身のシステム開発を支援する役割が強くなってきた以上、ただ言われた通りにプログラムを書くだけでは不十分。ITのプロフェッショナルとしてお客さまの想像を超えた価値を発揮することが必要なのです。

ーー「傾聴力」や「想像力」を養っていくために、若手エンジニアはどのような経験を重ねていくべきでしょうか。
コードを書くだけでなく、お客さまと対峙しコミュニケーションを取る経験を積むべきでしょう。
多種多様な業界の人たちと話をする機会を増やすことで、各業界の特徴や顧客ニーズを知ることができます。
ーー顧客折衝は上流工程を手掛けるシニア層が担うケースが一般的ですよね。若手エンジニアが関われるチャンスは少ないのでは?
私たちが手掛けているのはノーコード・ローコードツールの導入支援なので、プログラミングの工程が通常の開発案件よりも圧倒的に短いんです。なので、エンジニアの業務は顧客折衝がメインです。
そういった点では、ノーコード・ローコード開発そのものや、ノーコード・ローコード開発ツールの導入支援に携わることは、若手エンジニアが「傾聴力」「想像力」を養っていくための有効な手段の一つといえるでしょう。
仮に、若手のうちからスクラッチ開発の上流工程にチャレンジできたとしても、顧客折衝の経験をより多く積むためには、やはりノーコード・ローコード開発をお勧めします。
ーーそれはなぜでしょう?
スクラッチ開発と比べて、ノーコード・ローコード開発はお客さまとのやり取りの回数が圧倒的に多いからです。
スクラッチ開発では、論理的に書かれたシステムの設計書があれば、大体のことがプログラムで実現できます。対してノーコード・ローコード開発では、プラットフォーム上でできることが限られているため、好き勝手に作ることはできません。つまり、お客さまの要望をプログラミングだけで解決できないケースがあり得るのです。
制限を受けた部分は、人を配置して業務で補うなど、プログラミング以外の手段を検討する必要があります。要望を100%満たせない中でも解決策を模索してお客さまに満足してもらう経験を現場で積めるため、自ずと「傾聴力」「想像力」が身に付いていくでしょう。

ーーシステム・リノベイトの若手エンジニアは、どのようなステップを踏んでスキルアップしていますか?
弊社ではエンジニアの主体性を育むことを重視し、若手のうちからプロジェクトを主導する経験を積めるようにしています。
まずは、シニアエンジニアと一緒にお客さまの元へ行き、どうやって要望を聞き出すのか、どのように進めるのかを学ぶ。次に、先輩の同伴の下で自らお客さまと密にコミュニケーションを取る経験を積んでいくのです。
私自身、若手エンジニアのサポートに入ることもあります。例えばあるお客さまへのkintone導入支援では、一人の若手エンジニアにメイン担当を任せ、私はフォローに回りました。
その時、お客さまから出されたのは実現が難しいオーダーでした。ITの専門知識を持たないお客さまへの説明は、決して容易ではありません。そこで彼は工夫を重ね、紙に絵を描いて説明したんです。こういう理由で直接データをつなげられないため、別のデータベースを経由させる必要があると。
彼はまだ顧客折衝の経験がほとんどありませんでしたが、無事やりきったことで自信をつけ、今も活躍しています。
ーーまさに顧客に寄り添いながら、最善のシステムを模索する経験を積んでいるわけですね。
はい。お客さまに対する伴走支援は、弊社が特に強みにしている部分です。
私たちが目指しているのは、業務改善につながるIT活用を、お客さまが自身の力で実現できるように後押しすること。そのため単なるkintoneの導入支援にとどまらず、導入後の運用支援にも力を入れているんです。kintoneの利用トレーニングや、kintone以外のアプリケーションと連携する際のアドバイスなどを通して、顧客ニーズをより高い満足度で満たせるように心掛けています。
また時として、お客さまの要望に応えるためには、kintoneの機能だけでは不十分なケースもあります。弊社はそのような場合に、サイボウズ社のパートナー会社が提供しているプラグインツールを用いることで、kintone単体では実現できない機能の実装も可能にしています。
こうした一連のサービスを、弊社では『伴走サービス2.0』と銘打ち提供しています。お客さまと深い関係を築ける環境が整っているので、若手エンジニアはスピーディーにステップアップできるでしょう。
ーーkintone事業が若手の成長に大きく寄与しているのですね。システム・リノベイトでは、今後もkintone事業に注力していくのでしょうか?
弊社としては、今後も若手エンジニアの「傾聴力」と「想像力」を育てることに効果的なノーコード・ローコード開発ツールに関わるこの事業をさらに拡大していきたいと思っています。また、kintone事業で学び培ってきた、お客さまの想像を超えた新しい価値を生み出す力を武器に、今後は弊社独自のポータルサービスも手掛けていく計画です。
ここ数年、システム・リノベイトの業績は右肩上がりで伸びていますが、それもkintone事業の成長があってのこと。kintoneを運営するサイボウズ社が毎年実施する顧客満足度調査でも高い評価を獲得し、450社以上あるパートナー企業のうち、数少ない二つ星評価もいただいています。
中には、アンケートで弊社の若手エンジニアの名前をあげ、高く評価してくださったお客さまもいました。頑張りに対する評価が可視化されるkintone事業は、若手エンジニアにとって、「もっと成長したい」という強力なモチベーションアップにつながるでしょう。

>>株式会社 システム・リノベイトの採用情報はこちら
文/宮﨑まきこ 撮影/桑原美樹 取材・編集/今中康達(編集部)




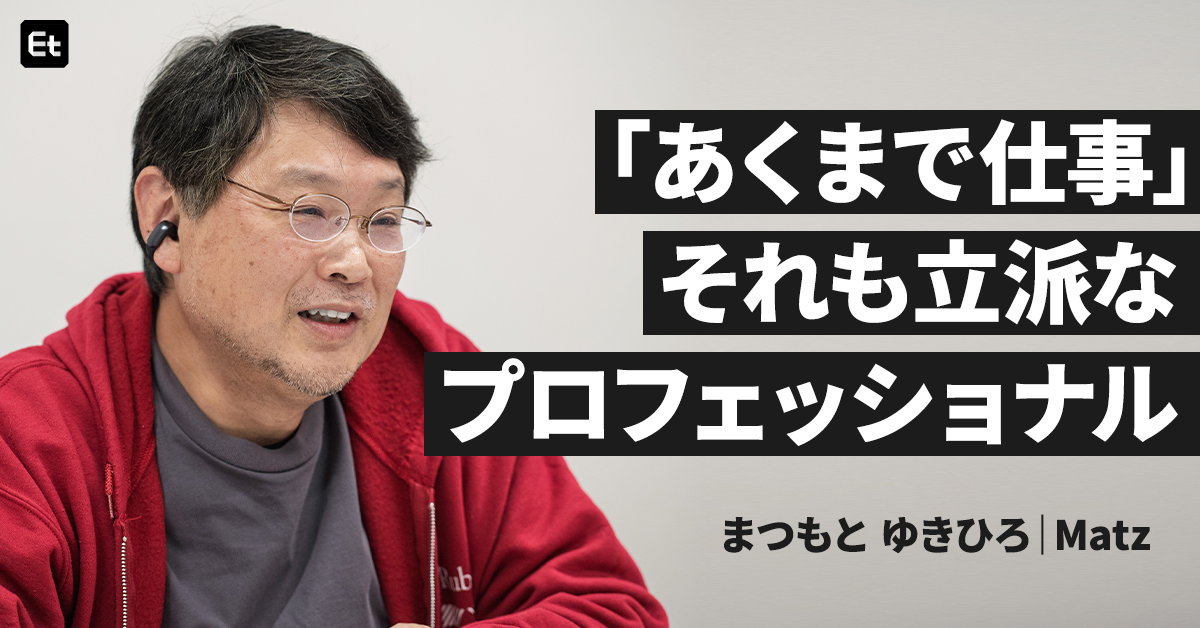
タグ