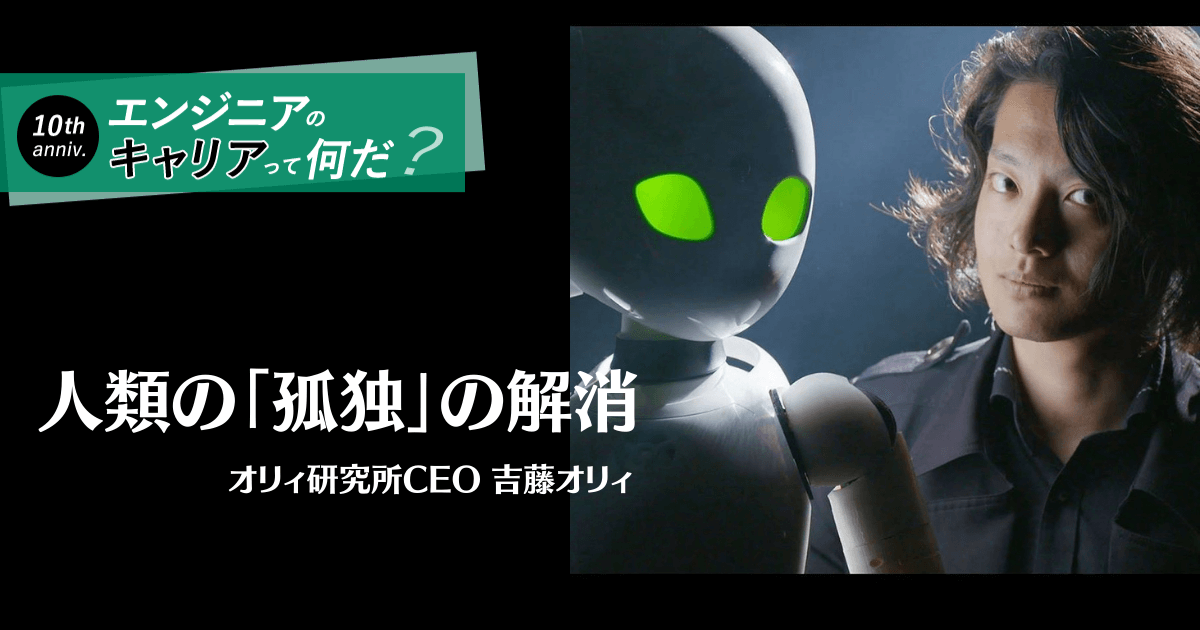ロボットクリエーター高橋智隆に問う、日本のロボット普及への道筋「開発前提を覆さねばイノベーションは生まれない」
少子高齢化による労働者不足やコロナ禍を機に加速した非接触サービスへのシフトなど、さまざまな社会課題を解決する手段として、ロボットへの期待が高まっている。一方で、世の中のニーズに応えるロボットがなかなか普及しない現実もある。では日本のロボット産業は、どうすれば明るい未来へと歩めるのだろうか。
そこで今回は、世界から注目を集める『ロビ』『エボルタ』などを生んだロボットクリエーターであり、この分野における第一人者である高橋智隆さんに、日本のロボット産業の現在地と未来、そしてロボット開発に携わるエンジニアに求められる資質やマインドについて伺った。

ロボットクリエーター
高橋智隆さん
1975年生まれ。京都大学工学部在学中よりロボット開発を始め、2003年の卒業と同時にロボ・ガレージを創業。代表作にロボットスマホ『ロボホン』、デアゴスティーニ『週刊ロビ』など
「購入者の間で失望が広がった」2000年代のロボットブーム
「ロボットブームは、数年前に一度終わりましたよ」
日本のロボット産業の現状について尋ねると、高橋さんからはこんな答えが返ってきた。
2000年代後半から2010年代に掛けて、マイクロソフトやGoogleなどの大物プレーヤーが鳴り物入りでロボット事業に参入。さらには数多くのスタートアップが続々と誕生し、この分野は一気に盛り上がった。
「ロボットブームを牽引した原動力が、クラウドファンディングです。それまでハードウエア開発に新規参入するには、生産設備や原料の仕入れに多大な先行投資を必要としました。参入障壁があまりに高過ぎて、ハードアウエア関連のスタートアップが誕生しにくい状況だったのです。
それがクラウドファンディングの登場によって、ものを作る前に購入希望者を募り、注文を確保して資金を集めることが可能になった。ロボット開発を前提とした起業も成立するようになりました。これ自体は画期的な出来事だったと言えます」

だが、製品がまだない段階で資金調達できるクラウドファンディングのメリットが、ここでは裏目に出た。できるだけ多くの予約注文を集めようと、各スタートアップは魅力的なプロモーション映像を作ることに力を注ぎ始め、自分たちが作れる以上の機能やデザインを備えたロボットが実現するかのように人々を錯覚させてしまったのだ。
「結局、購入者の手元に届くプロダクトは期待を裏切るものとなり、失望が広がった。ついには最初から製品を作る気がないのにプロモーションだけでお金を集める詐欺まがいのプロジェクトまで出てきて、クラウドファンディングへの信用不安も拡大し、ハードアウエアスタートアップは軒並み潰れる結果となりました」
普及のポイントは「ロボットをロボットとして作ろうとしないこと」
こうしてハードウエアスタートアップ各社のロボットブームは、あっという間に終焉を迎えた。だがロボットに対する社会のニーズは失われるどころか、むしろコロナ禍を機にますます高まりを見せている。今は、真剣にロボットに向き合う会社だけが生き残っている時代とも言い換えられるだろう。
人との接触を減らしたり、リモートワークを拡大したりするには、さまざまな現場で人間の代わりに作業やオペレーションを担うロボットがどうしても必要だ。人と会う機会が減って孤独を感じる人が増え、対話や触れ合いが可能なコミュニケーションロボットに期待する声も大きい。
一過性で終わったブームの反省を踏まえてこれから考えるべきことは、「どうすればロボット産業の持続的な発展を実現できるか」だ。この課題を解決するカギは、「ロボットをロボットとして作ろうとしないこと」にあると高橋さんは話す。
「私がコミュニケーションロボットの『ロボホン』を作って分かったのは、ロボット用に最適化した部品でプロダクトを製造するのは無理だということ。なぜならスマートフォン用の部品と比べたら、値段も性能も太刀打ちできないからです。
ハードウエアの制作は“数が全て”の世界です。100台や1000台しか売れる可能性がないプロダクトのために専用のバッテリーやカメラを作っても、100万台売ることを前提に作られるスマホ用のバッテリーやカメラの性能には遠く及ばない。しかもコストはロボット用の100分の1や1000分の1です。
だから『ロボホン』のようなコミュニケーションロボットを普及させるには、スマホのサプライチェーンに乗っかるしかありません。スマホの部品を使い、スマホのソフトウエアを搭載し、スマホの販路を利用して、スマホの販売代理店で売る。現時点ではこれが最善策だと考えています」

モバイル通信サービス対応で、電話もできるモバイル型ロボット『RoBoHoN(ロボホン)』
ロボットという未知のプロダクトに対する一般消費者の心理的ハードルを下げるためにも、人々が慣れ親しんだ既存製品をベースにする戦略が有効だという。
高橋さんも「現在の『ロボホン』はロボット7割・スマホ3割の製品だが、むしろもっとスマホに近づけたい」と話す。
「スマホは誰もが使っているので、ロボットの機能を少し足したくらいの製品なら、新しいものに抵抗がある人も手に取りやすいはず。そこからスタートして、段々とロボットならではの機能を増やしていけば、その過程でユーザーが新しい遊び方や活用法を生み出しながら、ロボットとの間に愛着や信頼関係を見出していけるのではないかと考えています。
こうして丁寧にステップを踏まなければ、保守的な消費者の価値観を変えるのは難しいし、新しいテクノロジーは普及しない。先ほども言ったように、ロボットをロボットして作り、ロボットとして売ろうとするのは、作り手として強引で図々しい行為に思えます」
つまり、ロボットを普及させるには、「マーケティング的な発想が必要不可欠なのだ」と高橋さんは言う。
ロボット掃除機『ルンバ』爆発的ヒットの裏にあったマーケティング戦略
マーケティング的な発想でロボットの普及に成功した最たる事例といえば、ロボット掃除機『ルンバ』だ。この製品は、まさに「丁寧なステップ」を踏んで市場を拡大した好例と言える。
「ルンバは2002年に米国で発売されましたが、同時期に日本の家電メーカーも掃除機ロボットを開発していました。その中でなぜルンバだけが成功したか。それを最初のモデルを“おもちゃ”として売り出したからです。機能を最小限にして値段も格安に設定し、おもちゃ屋に並べ、クリスマス商戦で大ヒットしました。
大半の人はちょっとした話題のネタとしてお遊び感覚で購入したので、性能には期待していなかった。ところが使ってみると、掃除機としてもちゃんと役に立つ。こうして人々に『ロボット掃除機って便利かも』と思わせてから、10万円以上する本格的な製品を売り出した。非常に賢い戦略です」

ロボットではないが、テスラも電気自動車を普及させるために、同様のマーケティング戦略を取ったことで知られる。同社が初めて生産した電気自動車は、イギリスの自動車メーカーが作った車体や部品を流用し、パソコン用のリチウムイオン電池をバッテリーとして搭載することで、スポーツカーとしては格安の1200万円ほどで売り出すことに成功した。
これが新しいもの好きで知的好奇心が旺盛なアメリカのセレブたちに刺さり、順調な売上を達成。この製品で稼いだ資金を元手に、今度は4ドアセダンの電気自動車を開発し、着々と市場を拡大していったのだ。
「人間のやり方」を前提に開発されたロボは役立たない
ロボットを広く普及させるために、もう一つ重要なことがある。それは開発の前提条件を変えることだ。
高橋さんによれば、これまでは「人間のやり方をロボットに代替させる」という発想で開発が行われてきた。小売の現場で使う接客ロボットなら、人間と同じようにレジを打ち、お客からお金を預かって、レシートとお釣りを渡せるように作ろうと考える。だがこれでは作業効率的にもコスト的にも、ロボットを導入する意味はほとんどない。本当に社会の役に立つロボットを作るには、発想を大きく転換し、機械に適したやり方を前提とした開発が求められる。
「従来の前提を覆してイノベーティブなプロダクトを生み出した事例に、Amazonの物流センターに導入されているロボット『Kiva』があります。倉庫内を走り回って商品のピックアップや運搬をするのですが、このロボットの凄さは、商品を分類しなくても目当てのものが置かれた棚を自動的に見つけ出せること。
人間が作業する場合、例えば歯磨き粉なら『日用品の棚に設けられた洗面用具コーナーの中の歯磨き粉のスペース』といった具合に、あらかじめ指定された場所に商品を分類しておかなければいけませんが、Kivaは入荷データを元にどの棚にどの商品が置かれていても必要なものをすぐ見つけられる。
つまり人間のやり方とはまったく異なる前提で開発された製品なのです。それにより、分類の手間が省ける上、商品の点数や種類がどれだけ増えても柔軟に対応できる革新的な倉庫システムが誕生しました」
日本のロボット開発者に足りないものは「マクロ視点」
また、ロボット開発に取り組む日本のエンジニアは、個別の技術を磨いたり改善したりするのは得意な反面、大胆で自由な発想は苦手な傾向がある、と高橋さんは指摘する。

日本からイノベーティブなロボット製品を送り出すには、物事の仕組みやプラットフォームを理解し、より広い視野に立って開発の前提をドラスティックに変えることが必要だ。
「どんな世界でも、仕組みを理解した人は強いものです。例えば現代アーティストの村上隆さんは、アート市場の仕組みを知った上で、今の時代に日本人の自分が何を制作すればマーケットから高く評価されるかを戦略的に考えている。だから作品にあれほど高額な値段が付くのです。
私がロボット開発にスマホのサプライチェーンを活用するという発想に至ったのも、このプロダクトが世界の市場を席巻している仕組みを知ったからこそ。エンジニアはどうしても目の前の技術を追いかけがちで、視点がミクロに偏りやすいのですが、マクロな視点で世の中の仕組みを理解すれば、もっとそれぞれの技術力が日の目を見るはずです」
技術力だけでなく、物事を広く俯瞰して見る視点や従来の常識にとらわれない自由な発想力を備えていること。それがロボット業界の未来を担うエンジニア像と言えるだろう。
取材・文/塚田有香 撮影/竹田俊晴
RELATED関連記事
RANKING人気記事ランキング
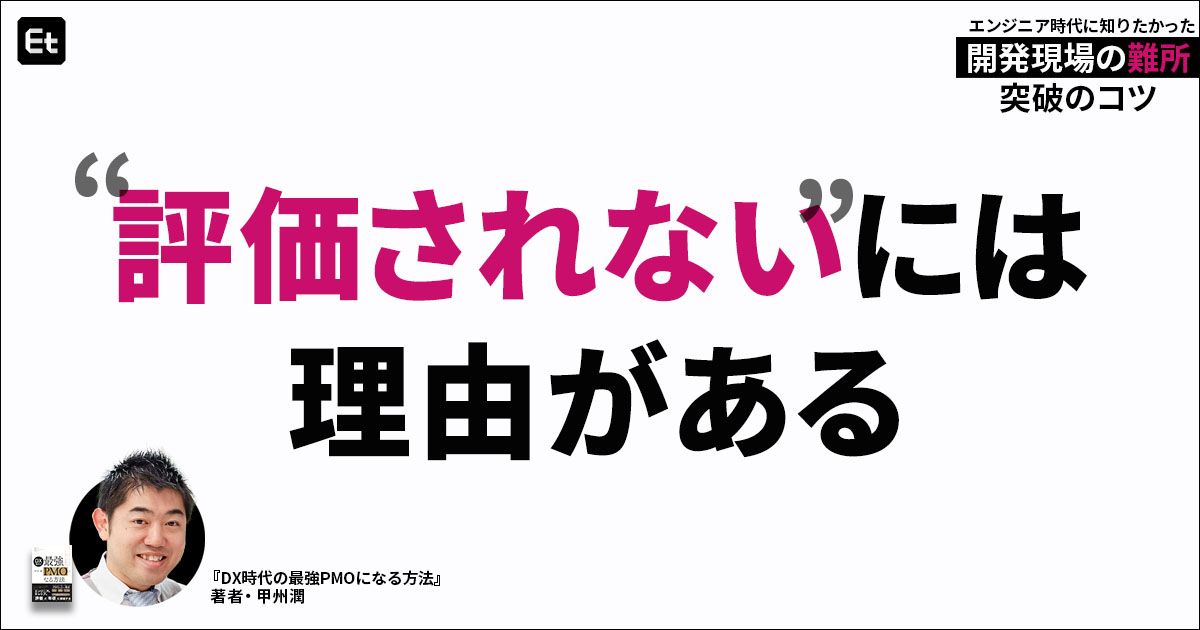
NEW!
“最強PMO”が指摘する、会社で評価されない人が陥りがちな認識のズレ【連載Vol.9】

落合陽一「2026年にはほとんどの知的作業がAIに置き換わる」人間に残される仕事は“とげ作り”

NEW!
コードを書かない管理職にはなりたくない、生涯プログラマー希望者のバイブル【ソニックガーデン・伊藤淳一】

AWS認定資格10種類を一覧で解説! 難易度や費用、おすすめの学習方法も

NEW!
ノーベル物理学賞、本当は日本人研究者のもの? 甘利俊一の功績を忘れてはいけない【今井翔太コラム】
JOB BOARD編集部オススメ求人特集
タグ